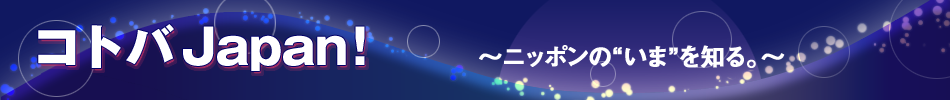11月16日に投開票された沖縄県知事選挙で現職の仲井真弘多(なかいま・ひろかず)氏(75)を10万票もの大差で破り当選した。64歳。父は真和志(まわし)市(現那覇市)の市長で兄は副知事を務めたこともある政治家一家。自身は那覇市議、県議、自民党県連幹事長を歴任。那覇市長を4期務めた。
前回仲井真氏が知事選に出馬したときは選対本部長を務めていた。普天間基地の県外移設を訴えていた仲井真氏が、安倍首相と会談して振興予算3400億円超をもらう代わりに名護市辺野古の埋め立てを受け入れたことに対し、「県民への裏切り」だと怨嗟の声が巻き起こり、翁長氏もこれを批判して袂を分かち、自民党を離党して出馬。「辺野古移設反対。この選挙に勝たなければ沖縄の未来はない」と訴え、選挙戦を戦った。
日米両政府が普天間返還に合意した1996年以降の5回の知事選挙で、はっきり辺野古移転反対を掲げた候補が勝利したのは初めてである。
翁長氏の勝利が与える影響は計り知れないが、なぜ翁長氏がこれほどの支持を受けたのか。だが週刊誌でこの知事選を取り扱ったところはほとんどない。そこで少し古くなるが『サンデー毎日』(10/5号、以下『毎日』)のジャーナリスト吉田敏浩氏のレポートを紹介しよう。
8月18日から辺野古で、米軍普天間飛行場の移設に向けた海底ボーリング調査が続いていると、吉田氏は書き始める。
しかし、沖縄の新基地反対への民意は根強い。こんな光景が日々見られるという。
「『海を壊すな!』『ボーリング調査やめて!』
口々に叫ぶのは、県内外から来てカヌーやモーターボートに乗り、新基地反対の抗議活動をする市民たちだ。しかし、海面に張りめぐらされた警戒区域の浮具(フロート)に近づくと、ヘルメットにウエットスーツ姿の海上保安官らを乗せた黒いゴムボートが全速力で白波を立てて集まり、行く手を阻む。拡声器で立ち入り禁止を警告し、退去を迫る。
安倍政権は抗議活動を閉め出すため、埋め立て予定の米海兵隊基地キャンプ・シュワブ沖に『臨時制限区域』を設定。基地内の海岸から50メートルだった常時立入禁止水域を、最大で沖合約2・3キロまで広げ、米軍施設・区域への侵入を取り締まる刑事特別法も適用するとした。海上保安庁は巡視船やゴムボートを全国から動員し、浮具の内外で連日、海上保安官らが海に飛び込み、カヌー操船者を引きずり出すなどして拘束している」(吉田氏)
新基地は単なる代替施設ではない。
「V字形の滑走路2本、垂直離着陸輸送機オスプレイと装甲車と兵員を運ぶ強襲揚陸艦なども接岸可能な岩壁、弾薬搭載施設などを備えた巨大基地だ。普天間飛行場移設とは、基地の負担軽減に名を借りた基地の新鋭化・強化にほかならない」(同)
しかも耐用年数は200年といわれている。沖縄では強硬な安倍政権への怒りが、県知事選に向けて高まっていた。
「前回の知事選で、普天間飛行場の県外移設を公約にして当選しながら、埋め立てを承認した仲井真知事の行為を、『沖縄振興予算のカネと引き換えに、沖縄の心を売った裏切り』と見る県民感情は浸透しており、自民党の独自調査でも仲井真氏苦戦が予想されている。
安倍政権のボーリング調査強行は、知事選の前に埋め立てに向けた既成事実づくりのイメージを広め、新基地反対の県民をあきらめさせ、翁長新知事が誕生した場合でも、新基地建設は後戻りできないと思わせるのが狙いだろう」(同)
元県議会議長で元自民党県連顧問の仲里利信さん(77)はこう語っている。
「安倍政権は軍拡路線に走り、尖閣諸島を巡って中国と対立を深め、沖縄で自衛隊増強も進めています。新基地ができれば自衛隊も使用し、米軍とともに沖縄を永久的に軍事要塞化するでしょう。沖縄が戦争に巻き込まれ、かつての沖縄戦のように本土防衛の捨て石にされる危険も高まる。しかし、それでは子や孫に申し訳が立たない。今回の知事選は、沖縄の将来を決する重大な選挙なのです」
これまでの知事選では基地反対か経済発展を優先するかが争点になってきたが、もはや沖縄経済にとって米軍基地は経済発展の阻害要因以外の何ものでもなくなっていると『毎日』はこう書いている。
「沖縄県の調査で、基地返還跡地の那覇新都心では、返還前と比べ従業員数が103倍、雇用者報酬が69倍に増えるなど、基地返還による経済波及効果の実績が証明された」
沖縄から基地がなくなれば生活が成り立たないなどと自民党連中が言っていることが根底から覆されてきているのである。
沖縄は歴史的に中国・韓国・東南アジア諸国との長い交易がある。こうした財産を生かしてアジアの観光・物流などの中心拠点を目指すのが沖縄経済発展の道だと考える沖縄財界人も増えてきている。
翁長氏は当選直後のインタビューでおおよそこう述べた。
「本土の0.6%の土地に74%の基地を69年もの間押しつけてきた日本の民主国家としてのあり方が問われた。この沖縄の民意を無視することは認められない。安全保障は日本国民全体で引き受けるべきだ。安倍首相のなかには沖縄が入っていない気がする」
これに対して政府は「知事選は基地問題に対する県民投票ではない」「過去の問題だ」と切り捨て、国が動き出し(仲井真)知事が承認したものを覆すことは法的にもできないと主張している。
たしかに辺野古移設を白紙に戻し県外移設を実現することは容易ではない。しかし今度の選挙ではっきりしたことは、基地を押しつけられ、切り捨てられ、忘れられ「屈辱のなかに生きてきた」沖縄の人々の怒りが沸点まで高まっているということである。
このことに鈍感で実感を欠いている本土の人間たちへの沖縄からの最後通牒である。私は常々「沖縄から日本が変わる」と言ってきた。沖縄の意思はひとつにまとまった。今度は本土の人間が意思を表明する番である。もちろんそれは、本当の意味で「戦後」を終わらせるために、これまで沖縄の人たちが味わった悲しみや怒りを我がこととすることであること、言うまでもない。
12月14日投開票の衆議院選では、沖縄の基地固定化を目論む安倍自民党へ本土の人間が「ノー」を突きつけるかどうかも問われるのである。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
週刊誌の大きな柱は、素朴な疑問に答えることと、疑惑の段階から追及していくことである。朝日新聞11月19日付朝刊にこういう記事が載った。
「京都府向日(むこう)市鶏冠井(かいで)町の民家で昨年12月、無職筧(かけひ)勇夫さん(当時75)が死亡し、体内から青酸化合物が検出される事件があり、京都府警は19日、妻の無職筧千佐子(ちさこ)容疑者(67)を殺人容疑で逮捕した。『逮捕された理由はよくわかっていますが、私は絶対に殺していません』と容疑を否認しているという」
これはかなり前から週刊誌で騒ぎになっていた事件である。こうした週刊誌の役割を示してくれた記事を3本紹介しよう。
第1位 「『交番SEX』にふけった美人婦警」(『週刊ポスト』11/28号)
第2位 「『安楽死』『尊厳死』あなたならどうする?」(『週刊文春』11/20号)
第3位 「羽生結弦『5回も転んで2位』」(『週刊現代』11/29号)
第3位。先日のフィギュアスケートで、練習中に大ケガを負った羽生結弦(はにゅう・ゆづる)がケガを押してフリーの演技をした姿には、私も感動して涙を流した。
しかし、たしかに5回も転倒したのに、終えた時点で「暫定1位」。あれっ、と思ったことも事実である。
現地で解説を担当したスケート解説者の佐野稔氏は「羽生選手の包帯姿が加点になった」としてこう語る。
「今シーズンの羽生選手のフリーの曲は『オペラ座の怪人』。あの曲は怪人の悲しみや愛の表現が求められますが、傷を負ったことで、怪人の心情を見せることができた。それがジャッジに反映されて、得点につながったんです。
もちろん、ルールとして『同情点』は禁じられています。ただ、それを厳しく守れる人がいるでしょうか」
表現力に与えられる「構成点」についてはこれまでも大きな議論を巻き起こしてきた。
きっかけは02年のソルトレイク五輪でのスキャンダルだったという。
「ペア部門でロシアが優勝に輝いたが、フランス人審判が『政治的な取引をし、ロシアに甘く採点した』と発言し、大問題になったのだ。結局この件は、問題の審判の判定を無効とし、2位だったカナダ人ペアにも金メダルが贈られ、決着を見た」(『現代』)
その反省から採点方式はより政治色や主観を排した厳密なものに変えられていったそうだが、やはりそれだけではないようだ。
スポーツライターの折山淑美(としみ)氏によれば、構成点は選手の「格」によって左右されるのだそうだ。
「たとえばソチ五輪銀メダリストのパトリック・チャン選手だったら10点満点で9点台後半がほぼ確実に出るとか、高橋大輔選手なら9点台は堅いとか、選手によってある程度は決まっています」
したがって羽生選手の場合、どんなに失敗しても7点台までは落としにくいというのだが、感動と演技の評価は別なのではないか。羽生があのとき低い得点でも、観客やテレビを見ているわれわれは惜しみない拍手を送ったはずである。
第2位。アメリカ人女性のブリタニー・メイナードさん(享年29)が11月1日(現地時間)、医者から処方された薬を飲んで自ら命を断ったことが話題になっている。
彼女は「愛する家族、友人よ、さようなら。世界は美しかった」とFacebookに書き残した。
『文春』によれば、ブリタニーさんは末期の脳腫瘍になり、今年4月に余命半年と宣告された。その後、自宅のあるカリフォルニア州から、医師の「自殺幇助(ほうじょ)」による「安楽死」が法的に認められているオレゴン州へと引っ越した。
若い彼女が安楽死を選択することをウェブ上で公にしたため、生前から全世界の関心を集めていた。
日本では終末期に「尊厳死」を選択するか否かは、本人の意思確認ができれば認められる場合があるが、「安楽死」は認められていない。
尼崎で開業医をしながら日本尊厳死協会の副理事長を務める長尾和宏医師が2つの違いをこう解説する。
「ブリタニーさんの死は、英語の『Death with dignity』を直訳して、『尊厳死』と一部のメディアで報じられました。しかし、これは医師が薬物を使って人工的に死期を早めるという、いわば医師による自殺幇助で、日本では『安楽死』と呼んでいます。
一方、日本での『尊厳死』とは患者の意思により、たとえばがんの終末期などに延命措置を行わない、または中止して自然死を待つことを意味します。
自然な経過に任せて最期を待つか待たないかが両者の違いと言えます」
『文春』はメルマガ会員1143人に尊厳死、安楽死について聞いたという。
すると「安楽死にも尊厳死にも賛成」という意見が全体の68.8%にもなった。理由としては身近な人の死を経験して「人間らしく生きる」ということについて考えたためという回答が多かったそうだ。
現在、難病と闘い切実な思いで病と向き合っている51歳の女性の言葉には胸打たれる。
「医師から、そう遠くない未来に全身が動かず寝たきりになり、失明し一切の光をも失うことを宣告されている。何も見えず、指先すら動かせない未来の自分の姿を考えると、ごく自然に『死』という選択肢が浮かぶ。自分の意思で身体が動かせない状況を受け止めながら生きることをなぜ他人に強要されなければならないのか。穏やかな表情や精神状態を保てるうちに、大切な人たちに落ち着いて『さようなら』と言える権利が私は欲しい。苦痛に歪む姿を家族に焼き付けたくない」
私には忘れられない思い出がある。親しくしていた有名ノンフィクション・ライターが、医者に行くカネもなくなり事務所で倒れ、担ぎ込まれた病院で末期がんと宣告された。
それからさほど経たないうちに激しい痛みが始まり、ベッドの中でのたうち回るようになった。小康状態の短い間は私と話ができるが、ほとんどは痛みのために苦しみ、モルヒネもあまり効かないようだった。
奥さんとは離婚状態で見舞いにも来てくれず、ベッドの上に「あなた頑張って」という奥さんからのFAXが一枚貼られていた。結局苦しみ抜いて数日後に亡くなったが、死をどう迎えるのかを私が真剣に考えるきっかけとなった。
必ず来るその日をどう迎えるのか。認知症にならないうちに「遺言」を書き始めようか。
第1位。11月17日の朝日新聞朝刊(デジタル版)にこんな記事が出た。
「勤務中、同僚女性にキスやセクハラ 警察官4人を処分
警視庁綾瀬署(東京都足立区)で女性警察官を勤務中の交番に泊まらせたり、セクハラ行為をしたりしたとして、署員の男女4人が内規上の処分を受け、今月までに辞職していたことが同庁への取材で分かった。同庁は『4人の行為はいずれも懲戒処分には当たらない』として公表していなかった。
同庁によると、同署地域課の男性巡査部長は今年に入って、勤務中に交番を訪ねてきた女性警察官とキスするなどした。同課の別の男性巡査は勤務する交番にこの女性警察官を泊まらせた。それぞれ女性警察官が承知のうえでのことで、交番勤務が1人態勢になる時間帯だった。さらに同署生活安全課の男性警部補はこの女性警察官に対して、セクハラ行為をしたという。
一連の問題は、女性警察官が警部補のセクハラ行為について相談したことをきっかけに発覚。懲戒処分にしなかった理由について、同庁幹部は『行為の性質や勤務に与えた影響を総合的に勘案した』と説明している」
「同庁への取材で分かった」と書いているが、これは『ポスト』の記事に出るとわかったから、あわてて取材したのではないのか。
『ポスト』は「身内の恥を晒すことになるだけでなく、地域安全の根幹を揺るがしかねない」と、厳重な箝口令が敷かれていたこのスキャンダルをスクープしたのだ。
『ポスト』ではどこの交番とは書いていないが、警視庁関係者の話を総合するとこうだ。
某日、若い男性警官が1人で勤務している某交番に20代前半とおぼしき女性Aが訪れたという。
手には菓子折か弁当か、手土産らしき包みを携えていたそうだ。男性警官とその女性は交番のバックヤードにある宿直用の休憩室へと消えていった。そして男女は、仮眠用の寝具が置かれた宿直室で、時を忘れて秘め事を楽しんだ──という。
Aは同じ警察署管内に勤務している20代前半の女性警察官。Aは自分が非番の時に、男性警察官のいる交番へ差し入れを持って訪れ、淫らな行為に及んでいたらしい。
「訪問した日時は把握していないが、複数勤務の時間帯にそんなことができるはずがない。だとすれば1人勤務が行なわれている白昼堂々ということになる。驚きを禁じ得ないが、調査をしている以上は恐らく事実なのだろう」(事情を知る警視庁関係者)
この一件は本庁の監察担当の知るところとなった。先の警視庁関係者が語る。
「宿直室はもともと居住用に作られていないために壁が薄く、行為の時に漏れた声に近隣住民が気づき、本庁にクレームの電話があったらしい」
だがそうではなかった。警視庁幹部がこう言ったという。
「どうやらAが先輩刑事からセクハラ被害にあったと訴え出ていたようです。それを監察が調査しているうちにこの問題が出てきた」
Aは上司からセクハラを受けていたことがあった一方で、複数の男性警察官と男女関係にあったことも疑われている。
近年警視庁では警察官同士の色恋沙汰にまつわるスキャンダルが少なくないと『ポスト』は書いている。
警察にも女性がいるといっても警視庁の女性警察官の割合は約8%にすぎない。男性中心の職場であることは間違いない。そこで少ない女性を取り合ったり、セクハラ、パワハラなどは日常茶飯事なのであろう。それにしても勤務中にSEXに励むなど言語道断である。
福島県警捜査二課で自殺者が相次いでいることが問題になっているが、この裏にも女性問題が絡んでいないのか。警察官こそ清廉性が求められるはずだ。
前回仲井真氏が知事選に出馬したときは選対本部長を務めていた。普天間基地の県外移設を訴えていた仲井真氏が、安倍首相と会談して振興予算3400億円超をもらう代わりに名護市辺野古の埋め立てを受け入れたことに対し、「県民への裏切り」だと怨嗟の声が巻き起こり、翁長氏もこれを批判して袂を分かち、自民党を離党して出馬。「辺野古移設反対。この選挙に勝たなければ沖縄の未来はない」と訴え、選挙戦を戦った。
日米両政府が普天間返還に合意した1996年以降の5回の知事選挙で、はっきり辺野古移転反対を掲げた候補が勝利したのは初めてである。
翁長氏の勝利が与える影響は計り知れないが、なぜ翁長氏がこれほどの支持を受けたのか。だが週刊誌でこの知事選を取り扱ったところはほとんどない。そこで少し古くなるが『サンデー毎日』(10/5号、以下『毎日』)のジャーナリスト吉田敏浩氏のレポートを紹介しよう。
8月18日から辺野古で、米軍普天間飛行場の移設に向けた海底ボーリング調査が続いていると、吉田氏は書き始める。
しかし、沖縄の新基地反対への民意は根強い。こんな光景が日々見られるという。
「『海を壊すな!』『ボーリング調査やめて!』
口々に叫ぶのは、県内外から来てカヌーやモーターボートに乗り、新基地反対の抗議活動をする市民たちだ。しかし、海面に張りめぐらされた警戒区域の浮具(フロート)に近づくと、ヘルメットにウエットスーツ姿の海上保安官らを乗せた黒いゴムボートが全速力で白波を立てて集まり、行く手を阻む。拡声器で立ち入り禁止を警告し、退去を迫る。
安倍政権は抗議活動を閉め出すため、埋め立て予定の米海兵隊基地キャンプ・シュワブ沖に『臨時制限区域』を設定。基地内の海岸から50メートルだった常時立入禁止水域を、最大で沖合約2・3キロまで広げ、米軍施設・区域への侵入を取り締まる刑事特別法も適用するとした。海上保安庁は巡視船やゴムボートを全国から動員し、浮具の内外で連日、海上保安官らが海に飛び込み、カヌー操船者を引きずり出すなどして拘束している」(吉田氏)
新基地は単なる代替施設ではない。
「V字形の滑走路2本、垂直離着陸輸送機オスプレイと装甲車と兵員を運ぶ強襲揚陸艦なども接岸可能な岩壁、弾薬搭載施設などを備えた巨大基地だ。普天間飛行場移設とは、基地の負担軽減に名を借りた基地の新鋭化・強化にほかならない」(同)
しかも耐用年数は200年といわれている。沖縄では強硬な安倍政権への怒りが、県知事選に向けて高まっていた。
「前回の知事選で、普天間飛行場の県外移設を公約にして当選しながら、埋め立てを承認した仲井真知事の行為を、『沖縄振興予算のカネと引き換えに、沖縄の心を売った裏切り』と見る県民感情は浸透しており、自民党の独自調査でも仲井真氏苦戦が予想されている。
安倍政権のボーリング調査強行は、知事選の前に埋め立てに向けた既成事実づくりのイメージを広め、新基地反対の県民をあきらめさせ、翁長新知事が誕生した場合でも、新基地建設は後戻りできないと思わせるのが狙いだろう」(同)
元県議会議長で元自民党県連顧問の仲里利信さん(77)はこう語っている。
「安倍政権は軍拡路線に走り、尖閣諸島を巡って中国と対立を深め、沖縄で自衛隊増強も進めています。新基地ができれば自衛隊も使用し、米軍とともに沖縄を永久的に軍事要塞化するでしょう。沖縄が戦争に巻き込まれ、かつての沖縄戦のように本土防衛の捨て石にされる危険も高まる。しかし、それでは子や孫に申し訳が立たない。今回の知事選は、沖縄の将来を決する重大な選挙なのです」
これまでの知事選では基地反対か経済発展を優先するかが争点になってきたが、もはや沖縄経済にとって米軍基地は経済発展の阻害要因以外の何ものでもなくなっていると『毎日』はこう書いている。
「沖縄県の調査で、基地返還跡地の那覇新都心では、返還前と比べ従業員数が103倍、雇用者報酬が69倍に増えるなど、基地返還による経済波及効果の実績が証明された」
沖縄から基地がなくなれば生活が成り立たないなどと自民党連中が言っていることが根底から覆されてきているのである。
沖縄は歴史的に中国・韓国・東南アジア諸国との長い交易がある。こうした財産を生かしてアジアの観光・物流などの中心拠点を目指すのが沖縄経済発展の道だと考える沖縄財界人も増えてきている。
翁長氏は当選直後のインタビューでおおよそこう述べた。
「本土の0.6%の土地に74%の基地を69年もの間押しつけてきた日本の民主国家としてのあり方が問われた。この沖縄の民意を無視することは認められない。安全保障は日本国民全体で引き受けるべきだ。安倍首相のなかには沖縄が入っていない気がする」
これに対して政府は「知事選は基地問題に対する県民投票ではない」「過去の問題だ」と切り捨て、国が動き出し(仲井真)知事が承認したものを覆すことは法的にもできないと主張している。
たしかに辺野古移設を白紙に戻し県外移設を実現することは容易ではない。しかし今度の選挙ではっきりしたことは、基地を押しつけられ、切り捨てられ、忘れられ「屈辱のなかに生きてきた」沖縄の人々の怒りが沸点まで高まっているということである。
このことに鈍感で実感を欠いている本土の人間たちへの沖縄からの最後通牒である。私は常々「沖縄から日本が変わる」と言ってきた。沖縄の意思はひとつにまとまった。今度は本土の人間が意思を表明する番である。もちろんそれは、本当の意味で「戦後」を終わらせるために、これまで沖縄の人たちが味わった悲しみや怒りを我がこととすることであること、言うまでもない。
12月14日投開票の衆議院選では、沖縄の基地固定化を目論む安倍自民党へ本土の人間が「ノー」を突きつけるかどうかも問われるのである。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
週刊誌の大きな柱は、素朴な疑問に答えることと、疑惑の段階から追及していくことである。朝日新聞11月19日付朝刊にこういう記事が載った。
「京都府向日(むこう)市鶏冠井(かいで)町の民家で昨年12月、無職筧(かけひ)勇夫さん(当時75)が死亡し、体内から青酸化合物が検出される事件があり、京都府警は19日、妻の無職筧千佐子(ちさこ)容疑者(67)を殺人容疑で逮捕した。『逮捕された理由はよくわかっていますが、私は絶対に殺していません』と容疑を否認しているという」
これはかなり前から週刊誌で騒ぎになっていた事件である。こうした週刊誌の役割を示してくれた記事を3本紹介しよう。
第1位 「『交番SEX』にふけった美人婦警」(『週刊ポスト』11/28号)
第2位 「『安楽死』『尊厳死』あなたならどうする?」(『週刊文春』11/20号)
第3位 「羽生結弦『5回も転んで2位』」(『週刊現代』11/29号)
第3位。先日のフィギュアスケートで、練習中に大ケガを負った羽生結弦(はにゅう・ゆづる)がケガを押してフリーの演技をした姿には、私も感動して涙を流した。
しかし、たしかに5回も転倒したのに、終えた時点で「暫定1位」。あれっ、と思ったことも事実である。
現地で解説を担当したスケート解説者の佐野稔氏は「羽生選手の包帯姿が加点になった」としてこう語る。
「今シーズンの羽生選手のフリーの曲は『オペラ座の怪人』。あの曲は怪人の悲しみや愛の表現が求められますが、傷を負ったことで、怪人の心情を見せることができた。それがジャッジに反映されて、得点につながったんです。
もちろん、ルールとして『同情点』は禁じられています。ただ、それを厳しく守れる人がいるでしょうか」
表現力に与えられる「構成点」についてはこれまでも大きな議論を巻き起こしてきた。
きっかけは02年のソルトレイク五輪でのスキャンダルだったという。
「ペア部門でロシアが優勝に輝いたが、フランス人審判が『政治的な取引をし、ロシアに甘く採点した』と発言し、大問題になったのだ。結局この件は、問題の審判の判定を無効とし、2位だったカナダ人ペアにも金メダルが贈られ、決着を見た」(『現代』)
その反省から採点方式はより政治色や主観を排した厳密なものに変えられていったそうだが、やはりそれだけではないようだ。
スポーツライターの折山淑美(としみ)氏によれば、構成点は選手の「格」によって左右されるのだそうだ。
「たとえばソチ五輪銀メダリストのパトリック・チャン選手だったら10点満点で9点台後半がほぼ確実に出るとか、高橋大輔選手なら9点台は堅いとか、選手によってある程度は決まっています」
したがって羽生選手の場合、どんなに失敗しても7点台までは落としにくいというのだが、感動と演技の評価は別なのではないか。羽生があのとき低い得点でも、観客やテレビを見ているわれわれは惜しみない拍手を送ったはずである。
第2位。アメリカ人女性のブリタニー・メイナードさん(享年29)が11月1日(現地時間)、医者から処方された薬を飲んで自ら命を断ったことが話題になっている。
彼女は「愛する家族、友人よ、さようなら。世界は美しかった」とFacebookに書き残した。
『文春』によれば、ブリタニーさんは末期の脳腫瘍になり、今年4月に余命半年と宣告された。その後、自宅のあるカリフォルニア州から、医師の「自殺幇助(ほうじょ)」による「安楽死」が法的に認められているオレゴン州へと引っ越した。
若い彼女が安楽死を選択することをウェブ上で公にしたため、生前から全世界の関心を集めていた。
日本では終末期に「尊厳死」を選択するか否かは、本人の意思確認ができれば認められる場合があるが、「安楽死」は認められていない。
尼崎で開業医をしながら日本尊厳死協会の副理事長を務める長尾和宏医師が2つの違いをこう解説する。
「ブリタニーさんの死は、英語の『Death with dignity』を直訳して、『尊厳死』と一部のメディアで報じられました。しかし、これは医師が薬物を使って人工的に死期を早めるという、いわば医師による自殺幇助で、日本では『安楽死』と呼んでいます。
一方、日本での『尊厳死』とは患者の意思により、たとえばがんの終末期などに延命措置を行わない、または中止して自然死を待つことを意味します。
自然な経過に任せて最期を待つか待たないかが両者の違いと言えます」
『文春』はメルマガ会員1143人に尊厳死、安楽死について聞いたという。
すると「安楽死にも尊厳死にも賛成」という意見が全体の68.8%にもなった。理由としては身近な人の死を経験して「人間らしく生きる」ということについて考えたためという回答が多かったそうだ。
現在、難病と闘い切実な思いで病と向き合っている51歳の女性の言葉には胸打たれる。
「医師から、そう遠くない未来に全身が動かず寝たきりになり、失明し一切の光をも失うことを宣告されている。何も見えず、指先すら動かせない未来の自分の姿を考えると、ごく自然に『死』という選択肢が浮かぶ。自分の意思で身体が動かせない状況を受け止めながら生きることをなぜ他人に強要されなければならないのか。穏やかな表情や精神状態を保てるうちに、大切な人たちに落ち着いて『さようなら』と言える権利が私は欲しい。苦痛に歪む姿を家族に焼き付けたくない」
私には忘れられない思い出がある。親しくしていた有名ノンフィクション・ライターが、医者に行くカネもなくなり事務所で倒れ、担ぎ込まれた病院で末期がんと宣告された。
それからさほど経たないうちに激しい痛みが始まり、ベッドの中でのたうち回るようになった。小康状態の短い間は私と話ができるが、ほとんどは痛みのために苦しみ、モルヒネもあまり効かないようだった。
奥さんとは離婚状態で見舞いにも来てくれず、ベッドの上に「あなた頑張って」という奥さんからのFAXが一枚貼られていた。結局苦しみ抜いて数日後に亡くなったが、死をどう迎えるのかを私が真剣に考えるきっかけとなった。
必ず来るその日をどう迎えるのか。認知症にならないうちに「遺言」を書き始めようか。
第1位。11月17日の朝日新聞朝刊(デジタル版)にこんな記事が出た。
「勤務中、同僚女性にキスやセクハラ 警察官4人を処分
警視庁綾瀬署(東京都足立区)で女性警察官を勤務中の交番に泊まらせたり、セクハラ行為をしたりしたとして、署員の男女4人が内規上の処分を受け、今月までに辞職していたことが同庁への取材で分かった。同庁は『4人の行為はいずれも懲戒処分には当たらない』として公表していなかった。
同庁によると、同署地域課の男性巡査部長は今年に入って、勤務中に交番を訪ねてきた女性警察官とキスするなどした。同課の別の男性巡査は勤務する交番にこの女性警察官を泊まらせた。それぞれ女性警察官が承知のうえでのことで、交番勤務が1人態勢になる時間帯だった。さらに同署生活安全課の男性警部補はこの女性警察官に対して、セクハラ行為をしたという。
一連の問題は、女性警察官が警部補のセクハラ行為について相談したことをきっかけに発覚。懲戒処分にしなかった理由について、同庁幹部は『行為の性質や勤務に与えた影響を総合的に勘案した』と説明している」
「同庁への取材で分かった」と書いているが、これは『ポスト』の記事に出るとわかったから、あわてて取材したのではないのか。
『ポスト』は「身内の恥を晒すことになるだけでなく、地域安全の根幹を揺るがしかねない」と、厳重な箝口令が敷かれていたこのスキャンダルをスクープしたのだ。
『ポスト』ではどこの交番とは書いていないが、警視庁関係者の話を総合するとこうだ。
某日、若い男性警官が1人で勤務している某交番に20代前半とおぼしき女性Aが訪れたという。
手には菓子折か弁当か、手土産らしき包みを携えていたそうだ。男性警官とその女性は交番のバックヤードにある宿直用の休憩室へと消えていった。そして男女は、仮眠用の寝具が置かれた宿直室で、時を忘れて秘め事を楽しんだ──という。
Aは同じ警察署管内に勤務している20代前半の女性警察官。Aは自分が非番の時に、男性警察官のいる交番へ差し入れを持って訪れ、淫らな行為に及んでいたらしい。
「訪問した日時は把握していないが、複数勤務の時間帯にそんなことができるはずがない。だとすれば1人勤務が行なわれている白昼堂々ということになる。驚きを禁じ得ないが、調査をしている以上は恐らく事実なのだろう」(事情を知る警視庁関係者)
この一件は本庁の監察担当の知るところとなった。先の警視庁関係者が語る。
「宿直室はもともと居住用に作られていないために壁が薄く、行為の時に漏れた声に近隣住民が気づき、本庁にクレームの電話があったらしい」
だがそうではなかった。警視庁幹部がこう言ったという。
「どうやらAが先輩刑事からセクハラ被害にあったと訴え出ていたようです。それを監察が調査しているうちにこの問題が出てきた」
Aは上司からセクハラを受けていたことがあった一方で、複数の男性警察官と男女関係にあったことも疑われている。
近年警視庁では警察官同士の色恋沙汰にまつわるスキャンダルが少なくないと『ポスト』は書いている。
警察にも女性がいるといっても警視庁の女性警察官の割合は約8%にすぎない。男性中心の職場であることは間違いない。そこで少ない女性を取り合ったり、セクハラ、パワハラなどは日常茶飯事なのであろう。それにしても勤務中にSEXに励むなど言語道断である。
福島県警捜査二課で自殺者が相次いでいることが問題になっているが、この裏にも女性問題が絡んでいないのか。警察官こそ清廉性が求められるはずだ。