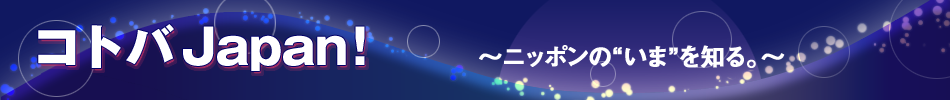春画がブームだそうである。『週刊文春』(10/8号、以下『文春』)までが「空前のブーム到来!」だと後半のカラーページまで使って特集した。
細川護煕(もりひろ)元首相&永青文庫理事長が所蔵しているものも含めた「春画」を公開した展覧会は盛況で、特に女性客が詰めかけているというのである。
「明治期の検閲がどのように人々の春画に対する意識を変えていったか」(石上阿希(いしがみ・あき)国際日本文化研究センター特任助教)をテーマにした銀座・永井画廊で開かれている「銀座『春画展』」も好評で、こちらも女性の姿が多いという。
作家の高橋克彦氏によれば、春画というのは中国が発祥で、「経験のない少女たちの教育用に寝室の壁に『春宮図(しゅんぐうず)』というセックスの絵を描かせた」ことが明代(1368~1644年)に流行し、日本にも入ってきて春画となったそうだ。
林真理子氏も連載の中で「銀座『春画展』」を見に行った様子を書いている。オープニングパーティーで春画の若い研究者がレクチャーをしたそうだが、「その方が今どきの美人なのである」(林氏)。一緒に行った作家の岩井志麻子氏が、なぜあんなに男性器を大きく描くのか、胸にはまるで興味がないのはなぜかという質問をしたそうだ。
答えは「古代からそうしたものは大きく描く風習があったと言うのだ。そして江戸の日本人は、胸にはさほど興味を持たない。色も塗られていないというのである」(林氏)
カラーページには、蛸が海女と交合している葛飾北斎の有名な「喜能会之故真通(きのえのこまつ)」、極彩色の色合いが絢爛豪華な歌川国貞の「艶紫娯拾余帖(えんしごじゅうよじょう)」、直接セックス描写をしているわけではないが、何ともエロチックな喜多川歌麿の「歌満くら(うたまくら)」の3点が見開きにドーンと載っている。なかなかの迫力である。
刑法175条のわいせつ基準は昔も今も何ら変わっていない。だが、今では『文春』までが春画をカラーで掲載しているのを見ると今昔の感である。
と感慨に耽っていたら、『文春』の編集長が3か月の間の休養を命じられたと新聞で報じられたのである。
聞くところによると、春画のグラビアを見た文藝春秋の社長が編集部に怒鳴り込んできたという。週刊誌に影響力を持つコンビニからも苦情が来たそうだ。今どき春画を載せたから編集長を処分するなんてと呆れ果てていたら、『週刊ポスト』(10/30号)が春画はわいせつか否かについて、識者たちの意見を聞いている。
鹿島茂氏(フランス文学者)「『週刊文春』の春画グラビアを問題にする必要は全然ないと思います」、小林節氏(憲法学者)「春画はあちこちで見ることができる。出版物も多数ある。ということは、社会通念上、春画は違法扱いされていない。よって、春画はすでにわいせつではない。そのように考えて問題はありません」
呉智英(くれ・ともふさ)氏(評論家)は「『ポスト』なら良いが『文春』なら問題だ」とし、性表現には「(学校の近くにラブホテルは建てられないというような)ゾーニング」が必要で、性表現は自由だが、見られる場所は制限があってしかるべきだと言う。
ロバート・キャンベル氏(日本文学者)も「雑誌はいつ誰が見るかわかりません。春画を掲載することで、不愉快に思う人もいると思います。その扱い方には、配慮が必要です」
批判派の意見は、私が『週刊現代』編集長時代にヘア・ヌードブームをつくり出した頃と変わっていない。「見られる場所を制限しろ」というのは良識派といわれる人がよく持ち出す論理だが、週刊誌の表紙に出ているわけでもない。電車の中で広げる人がいるのが迷惑だともよく言われたが、それはその人間のマナーが悪いので、雑誌の責任ではない。
そういう人は、ヘアが描いてある名画が教科書にも載せられなかった時代に逆戻りさせたいのだろうか。『ポスト』はいいが『文春』はいけないという「理屈」もさっぱりわからない。
気になるのは、『ポスト』がこう書いていることだ。
「警視庁は春画を『わいせつ図画』だとみなし、本誌を含め春画を掲載した週刊誌数誌を呼び出し、“指導”を行なっている。本誌編集長もこの1年の間に2回、呼び出しを受けた」(編集部注:朝日新聞(10月21日付朝刊)では、「警視庁が週刊誌4誌に「過激な内容を掲載しないよう配慮を求める」と口頭で指導したことが警視庁への取材でわかった。4誌は「週刊ポスト」(小学館)、「週刊現代」(講談社)、「週刊大衆」(双葉社)、「週刊アサヒ芸能」(徳間書店)」と報じている)
その際、以前から春画を掲載してきているのに呼び出しを受けなかったが、警視庁が方針を変更したのかと問うたところ、明確な返答はなかったという。
何ら明確な基準を示さず、思いつきのように呼びつけ恫喝(どうかつ)するやり方は戦前から何も変わっていない。
『文春』がジャ-ナリズム雑誌だというのならば(本当はそう思っていないのかもしれないが)、性表現の自由にも堂々と挑戦してお上と一戦交えてほしいものである。
作家の瀬戸内寂聴氏が永青文庫の春画展に触れ、小説家になってから外国で多くの春画を見てきたが、「その芸術性に圧倒された。それはわいせつ感などを圧倒するほどの芸術価値に輝いていた」と朝日新聞(10月9日付朝刊)に書いていることを紹介しておく。
ところでアメリカの雑誌『PLAYBOY』がヌードグラビアをやめるという。ネットなどで過激なヌードが出回っているからという理由だそうだ。われわれの青春時代、輸入された『PLAYBOY』のヌードのアソコに塗られた黒いインクを一生懸命消したものだった。
黒いインクも印刷されたもので、いくらこすっても消えはしなかったのだが。甘酸っぱいあの頃の思い出がなくなるようでチョッピリ残念な気がする。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
今週は私の大好きな田中邦衛(くにえ)の消息を『ポスト』が報じている。大学時代はテレビドラマ『若者たち』で融通のきかない長男役をやった。その頃から気になる役者ではあったが、好きではなかった。加山雄三の若大将シリーズの青大将も、加山を引き立てる脇役としてはよかったが、あのキザっぽさが鼻についた。やはり高倉健との『網走番外地』シリーズや『仁義なき戦い』あたりから存在感を増し、極めつけはテレビドラマ『北の国から』の五郎役が絶品だった。最初、五郎役は高倉健を予定していたそうだ。だが、スケジュールか何かで折り合わず田中に回ってきたそうだ。健さんだったらまったく違ったドラマになり、あれほど長く続くことはなかっただろう。今でもときどき『北の国から』のDVDを見ては五郎の姿に涙している。
第1位 「『下着ドロボー』が『大臣閣下』にご出世で『高木毅復興相』の資質」「『暴力団』事務所に出入りの過去がある株成金の『森山裕農水相』」(『週刊新潮』10/22号)
第2位 「アフリカ大陸を救った『大村智特別栄誉教授』の250億円人生」「宇宙創成の秘密に手を掛けた 京大不合格『梶田隆章教授』のニュートリノ」(『週刊新潮』10/22号)
第3位 「田中邦衛(82)『介護付き老人ホーム入居』で妻・娘と歩む『復帰への道』」(『週刊ポスト』10/30号)
第3位。私は田中邦衛(82)という役者が大好きだ。『北の国から』(フジテレビ系列)の黒板五郎役は絶品だったが、若大将シリーズの青大将や高倉健との網走番外地シリーズなど、名脇役という言葉がこれほど当てはまる人はいない。
もう40年近くになるだろうか、雑誌のグラビア撮影のために京都のイノダコーヒーで待ち合わせ、京の町をブラブラしながら一日話を聞いたことがある。ボソボソとした話し方、ときどき熱くなるとツバを飛ばしそうになるところはスクリーンそのまま。(高倉)健さんのことを語るときは優しい目が嬉しそうに大きく垂れ下がった。
多くの人間をインタビューしてきたが、このときほど暖かいものに包まれるような雰囲気の中で話を聞いた経験は、その後もない。
田中は麗澤(れいたく)短期大学卒業後、中学の代用教員を経て、俳優座養成所の試験に3度目で受かった。だが俳優としてスタートを切ってからは順風満帆そのものだった。
彼の姿を久々に見たのは12年8月、『北の国から』で共演した故・地井武男のお別れの会だった。
今年6月に『北の国から』のプロデューサーだった恩人の葬儀に参列しなかったことから、田中の健康不安説が再燃していた。
『ポスト』によれば「現在、田中は介護付き有料老人ホームに入居している。月額利用料は家賃に食費、管理費等を含めて20万円超と、その地域の相場を考えても一般的なもので、有名俳優が入居する施設としては決して豪華なものではない」
田中を知る関係者がこう話している。
「ホーム内では車椅子での移動が基本。部屋で過ごすことが大半ですが、食堂やホールに顔を出す時は介護士が付き添います。(中略)
やはりテレビで見かけた頃より痩せた印象は否めません。毛染めもやめているので白髪も目立ちます。ただ身体的に問題があるわけではありません。気懸かりなのは、最近はふさぎ込みがちなことだそうです」
田中の知人によれば、「地井さんが亡くなった時は本当に落ち込んで、余りの憔悴ぶりに(高倉)健さんが自宅に電話をかけて気遣ったほどでした。でも、その健さんも昨年11月に亡くなり、続けて親交のあった菅原文太さんまで逝ってしまった。最近の邦衛さんが、精神的にも肉体的にも相当参っているだろうことは容易に想像できました」
年齢的なものより精神的なもののほうが大きいのであろう。田中の奥さんは、本人はしっかり足を治してから帰ってくると言っていると話し、気弱になっているところは微塵もないと言うが、心配である。地井の葬儀のとき田中が呼びかけたように、こう言いたい。
「クニ兄、もう一度スクリーンで会いたいよ」
第2位。『新潮』がノーベル賞を受賞した日本人2人の人生と、その意義を特集している。
「アフリカ大陸を救った男」としてノーベル医学・生理学賞を受賞した大村智(さとし)・北里大特別栄誉教授(80)は、その功績はもちろんだが、テレビなどで伝えられる大村氏所有の豪邸、美術館、温泉、蕎麦屋が話題になっている。
なぜそのような資産が形成できたのか。大村氏の実家は山梨県韮山(にらやま)市で養蚕などを生業とする農家だった。山梨大学の学芸学部自然科学科を卒業した大村氏は、東京の夜間高校の理科教諭となり、後に研究者の道を歩み始める。
27歳のときにお見合いで、母親と同じ名前の文子(ふみこ)さんと結婚。これが大きな転機となったという。
氏と親交のある守家勤さんがこう説明する。
「彼は奥さんに頭が上がらなかった。というのも、彼女の実家は新潟県でデパートを経営していた資産家で、結婚してまだ間もない頃、奥さんの実家が、みすぼらしいところに住んではダメだと、家を買う資金としてポンと1500万円、援助したそうですから」
実家から援助してもらいながら研究者の道を歩み始め、71年に米国の大学に客員教授として赴任。帰国後の74年、北里研究所抗生物質室長時代に、米国の製薬会社「メルク社」とのイベルメクチン(寄生虫病の薬)の共同開発につながる細菌を、静岡県伊東市のゴルフ場近くの土壌から発見するのだ。
この薬が広まった背景には、メルク社が大村さんの同意を得て、80年代後半からWTO(世界保健機関)を通じ無償提供されたことが大きく関係しているという。
しかもこの薬を含む薬品の開発によって、大村さんはこれまで250億円もの特許料などを手にしている。
『新潮』は、大村さんを“類を見ない科学者”たらしめているのはその豪快さだという。250億円のうち220億円を北里研究所に寄付。残った30億円から税金を引いて手元に残った15億円の中から2億円を出して、小中高生が高名な研究者から講義を受けられる「山梨科学アカデミー」を設立した。しかし2000年に夫人を亡くしている。
「大村先生は奥さまを非常に大切にされていました。他界されたのがよほどショックだったのでしょう。彼女が亡くなられた後、先生は剃髪し、頭を丸められたんです。奥さまの存在がどれほど大きかったのか、改めて気づかされました」(東大医学部・北潔(きた・きよし)教授)
私もカミさんの実家から援助があれば、もっとましな編集者になっていたかもしれないが……。
先輩研究者から受け継がれてきたニュートリノの研究によって、ノーベル物理学賞を受賞したのは東大宇宙線研究所所長の梶田隆章教授(56)である。梶田氏は埼玉県東松山市の酪農家の生まれ。これほどの才能の人でも京都大学に不合格になり、二期校受験で埼玉大に行っている。
今回の受賞は2002年に同賞を受けた小柴昌俊東大名誉教授(当時)に続くもの。
「物質をどんどん細く切り刻んでいって最後に残る最小単位は何か。それを突き詰めていく学問です」(中畑雅行・東大宇宙線研究所教授)
だが、この説明では何のことやらさっぱりわからない。
湯川秀樹博士の弟子である坂東昌子・愛知大名誉教授がこう解説してくれる。
「核施設を内緒でつくった国があるとしましょう。そこから当然ニュートリノが出るのですが、これを捉えて分析すれば、“あそこにあるぞ”と出所がわかるといった利用法も考えられる」
地球物理学者の島村英紀氏がこう続ける。
「数年ほどのあいだに、火山の噴火予知に応用できるかもしれません。噴火というのは、火山の下にある『マグマ溜り』がどんどんせりあがってきて最終的に地上へ吹き出すもの。ニュートリノ観察によって、こういった特定の火山の下で起こっている動きを覗けるようになるのです」
ニュートリノで世界を透視できるというのだ。よくわからないが人類の平和に役立つ発明や発見のようである。
第1位。今週は『新潮』が頑張っている。第3次安倍改造内閣で入閣した2人にとんでもない「噂」があると報じているのだ。
一人は復興・原発事故再生担当大臣に就任した高木毅(つよし)代議士(59)。彼には「過去に女性の下着を盗んだことがある」という噂があるのだという。
高木氏は当選6回で、安倍首相の出身派閥の細田派に所属し、地盤が原発銀座といわれる福井県敦賀市ということで白羽の矢が立ったという。
だが初出馬当時から下着泥棒だという怪文書が出回っていたそうだ。
この噂を初めて記事にしたのは、地元で発行されている『財界北陸』。記者がこう語る。
「高木の“パンツ泥棒疑惑”について記事にしたのは、確か、96年の選挙の時だった。(中略)元々知り合いだった福井県警の警部補に、その噂が事実なのかどうか確認してみたんです。
すると、警部補は“敦賀署が高木毅を、下着の窃盗と住居侵入の疑いで取り調べたのは事実。犯行現場は敦賀市内。その後、事情は分からないが検挙には至らなかった”とほとんどの事実関係を認めた」
『新潮』は当該の被害にあった家を見つけた。敦賀市内の住宅街の一画にある。
近所に住む被害者の妹は「こちらが拍子抜けするほどあっさり事実関係を認めた」(『新潮』)そうである。
「被害者は私の姉です。近所のおばさんが、“家の斜め前に車を停めて中に入っていく人を見たけど、知り合いか?”って。通報したのは私だったかな。警察の人が来て、指紋とか取って。でも、教えてくれた近所のおばさんが車のナンバーを控えとってくれたんで、すぐにやったのは高木さんやと分かった。家に上がりこみ、姉の部屋で箪笥の中とかを物色し、帰って行ったようです」
今から30年ほど前。当時、下着を盗まれた女性は20代、高木氏は30歳前後だった。
だが、この「事件」がうやむやになったのは高木氏の父親の威光があったようである。高木氏の父、故・高木孝一氏は敦賀市議、県議、県会議長を務め、敦賀市長までした地元政界のドンだった。
被害者の妹によれば、当時、姉は福井銀行敦賀支店に勤めていて窓口業務をしていた。そこに高木が客として来て、姉を一方的に気に入ったという。
「だから、やったのが高木さんと分かると、姉は“いややわー。家まで来とったんやー”と言っていました」(妹)
合鍵まで勝手に作っていたともいう。
「高木氏の行為が犯罪であることは言うまでもないが、少なくともこの件は『立件』されていない」(『新潮』)
「姉が“騒がんといてくれ。勤め先にも迷惑かけたくない”って。父は“(高木氏の父親の)市長も頭下げてきた”“敦賀でお世話になっとるし”と言ってて、それで、示談っていうか……。それにしてもあんな人が大臣にまでなって、不思議やなーと思います」(妹)
もう一人は、安倍首相の「鬼門」である農水相になった森山裕(ひろし)代議士(70)。暴力団との関係が取り沙汰されているという。『新潮』の取材にはこう答えている。
「知らんかったとはいえ、暴力団の事務所に行ったことは軽率でした。ただ、個人的な付き合いは一切ありませんので……」
『新潮』によれば88年7月。
「事件現場は鹿児島最大の歓楽街・天文館からほど近い場所にある、指定暴力団の下部組織の事務所でした。暴力団幹部2人が、当時30代の男性を竹刀などで滅多打ちにしたことが分かり、翌年2月に逮捕された。(中略)暴行事件が発生した当夜、森山さんが組事務所1階の応接間に居合わせたことが明らかとなったからです」(地元記者)
このとき森山氏は鹿児島市議会議長の要職に就いていた。この件について森山氏は、当日は友達の社長に呼び出され、件の建物に連れて行かれただけだと釈明しているが、トラブルの話を付けたことは認めている。
森山氏は生粋の農水族議員で、
「TPP反対派のドンと目されていた。しかし、党のTPP対策委員長に任命されると、一転して反対派の説得に奔走。今回の入閣は大筋合意を受けての“論功行賞”に他なりません。とはいえ、そんな人事で安倍政権の“鬼門”とされてきた農水相が務まるのか、甚だ疑問です」(政治部記者)
下着泥棒に暴力団との付き合い。噂・疑惑だとしても下品窮まるではないか。第3次安倍内閣は出鼻をこっぴどく挫かれたようである。
細川護煕(もりひろ)元首相&永青文庫理事長が所蔵しているものも含めた「春画」を公開した展覧会は盛況で、特に女性客が詰めかけているというのである。
「明治期の検閲がどのように人々の春画に対する意識を変えていったか」(石上阿希(いしがみ・あき)国際日本文化研究センター特任助教)をテーマにした銀座・永井画廊で開かれている「銀座『春画展』」も好評で、こちらも女性の姿が多いという。
作家の高橋克彦氏によれば、春画というのは中国が発祥で、「経験のない少女たちの教育用に寝室の壁に『春宮図(しゅんぐうず)』というセックスの絵を描かせた」ことが明代(1368~1644年)に流行し、日本にも入ってきて春画となったそうだ。
林真理子氏も連載の中で「銀座『春画展』」を見に行った様子を書いている。オープニングパーティーで春画の若い研究者がレクチャーをしたそうだが、「その方が今どきの美人なのである」(林氏)。一緒に行った作家の岩井志麻子氏が、なぜあんなに男性器を大きく描くのか、胸にはまるで興味がないのはなぜかという質問をしたそうだ。
答えは「古代からそうしたものは大きく描く風習があったと言うのだ。そして江戸の日本人は、胸にはさほど興味を持たない。色も塗られていないというのである」(林氏)
カラーページには、蛸が海女と交合している葛飾北斎の有名な「喜能会之故真通(きのえのこまつ)」、極彩色の色合いが絢爛豪華な歌川国貞の「艶紫娯拾余帖(えんしごじゅうよじょう)」、直接セックス描写をしているわけではないが、何ともエロチックな喜多川歌麿の「歌満くら(うたまくら)」の3点が見開きにドーンと載っている。なかなかの迫力である。
刑法175条のわいせつ基準は昔も今も何ら変わっていない。だが、今では『文春』までが春画をカラーで掲載しているのを見ると今昔の感である。
と感慨に耽っていたら、『文春』の編集長が3か月の間の休養を命じられたと新聞で報じられたのである。
聞くところによると、春画のグラビアを見た文藝春秋の社長が編集部に怒鳴り込んできたという。週刊誌に影響力を持つコンビニからも苦情が来たそうだ。今どき春画を載せたから編集長を処分するなんてと呆れ果てていたら、『週刊ポスト』(10/30号)が春画はわいせつか否かについて、識者たちの意見を聞いている。
鹿島茂氏(フランス文学者)「『週刊文春』の春画グラビアを問題にする必要は全然ないと思います」、小林節氏(憲法学者)「春画はあちこちで見ることができる。出版物も多数ある。ということは、社会通念上、春画は違法扱いされていない。よって、春画はすでにわいせつではない。そのように考えて問題はありません」
呉智英(くれ・ともふさ)氏(評論家)は「『ポスト』なら良いが『文春』なら問題だ」とし、性表現には「(学校の近くにラブホテルは建てられないというような)ゾーニング」が必要で、性表現は自由だが、見られる場所は制限があってしかるべきだと言う。
ロバート・キャンベル氏(日本文学者)も「雑誌はいつ誰が見るかわかりません。春画を掲載することで、不愉快に思う人もいると思います。その扱い方には、配慮が必要です」
批判派の意見は、私が『週刊現代』編集長時代にヘア・ヌードブームをつくり出した頃と変わっていない。「見られる場所を制限しろ」というのは良識派といわれる人がよく持ち出す論理だが、週刊誌の表紙に出ているわけでもない。電車の中で広げる人がいるのが迷惑だともよく言われたが、それはその人間のマナーが悪いので、雑誌の責任ではない。
そういう人は、ヘアが描いてある名画が教科書にも載せられなかった時代に逆戻りさせたいのだろうか。『ポスト』はいいが『文春』はいけないという「理屈」もさっぱりわからない。
気になるのは、『ポスト』がこう書いていることだ。
「警視庁は春画を『わいせつ図画』だとみなし、本誌を含め春画を掲載した週刊誌数誌を呼び出し、“指導”を行なっている。本誌編集長もこの1年の間に2回、呼び出しを受けた」(編集部注:朝日新聞(10月21日付朝刊)では、「警視庁が週刊誌4誌に「過激な内容を掲載しないよう配慮を求める」と口頭で指導したことが警視庁への取材でわかった。4誌は「週刊ポスト」(小学館)、「週刊現代」(講談社)、「週刊大衆」(双葉社)、「週刊アサヒ芸能」(徳間書店)」と報じている)
その際、以前から春画を掲載してきているのに呼び出しを受けなかったが、警視庁が方針を変更したのかと問うたところ、明確な返答はなかったという。
何ら明確な基準を示さず、思いつきのように呼びつけ恫喝(どうかつ)するやり方は戦前から何も変わっていない。
『文春』がジャ-ナリズム雑誌だというのならば(本当はそう思っていないのかもしれないが)、性表現の自由にも堂々と挑戦してお上と一戦交えてほしいものである。
作家の瀬戸内寂聴氏が永青文庫の春画展に触れ、小説家になってから外国で多くの春画を見てきたが、「その芸術性に圧倒された。それはわいせつ感などを圧倒するほどの芸術価値に輝いていた」と朝日新聞(10月9日付朝刊)に書いていることを紹介しておく。
ところでアメリカの雑誌『PLAYBOY』がヌードグラビアをやめるという。ネットなどで過激なヌードが出回っているからという理由だそうだ。われわれの青春時代、輸入された『PLAYBOY』のヌードのアソコに塗られた黒いインクを一生懸命消したものだった。
黒いインクも印刷されたもので、いくらこすっても消えはしなかったのだが。甘酸っぱいあの頃の思い出がなくなるようでチョッピリ残念な気がする。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
今週は私の大好きな田中邦衛(くにえ)の消息を『ポスト』が報じている。大学時代はテレビドラマ『若者たち』で融通のきかない長男役をやった。その頃から気になる役者ではあったが、好きではなかった。加山雄三の若大将シリーズの青大将も、加山を引き立てる脇役としてはよかったが、あのキザっぽさが鼻についた。やはり高倉健との『網走番外地』シリーズや『仁義なき戦い』あたりから存在感を増し、極めつけはテレビドラマ『北の国から』の五郎役が絶品だった。最初、五郎役は高倉健を予定していたそうだ。だが、スケジュールか何かで折り合わず田中に回ってきたそうだ。健さんだったらまったく違ったドラマになり、あれほど長く続くことはなかっただろう。今でもときどき『北の国から』のDVDを見ては五郎の姿に涙している。
第1位 「『下着ドロボー』が『大臣閣下』にご出世で『高木毅復興相』の資質」「『暴力団』事務所に出入りの過去がある株成金の『森山裕農水相』」(『週刊新潮』10/22号)
第2位 「アフリカ大陸を救った『大村智特別栄誉教授』の250億円人生」「宇宙創成の秘密に手を掛けた 京大不合格『梶田隆章教授』のニュートリノ」(『週刊新潮』10/22号)
第3位 「田中邦衛(82)『介護付き老人ホーム入居』で妻・娘と歩む『復帰への道』」(『週刊ポスト』10/30号)
第3位。私は田中邦衛(82)という役者が大好きだ。『北の国から』(フジテレビ系列)の黒板五郎役は絶品だったが、若大将シリーズの青大将や高倉健との網走番外地シリーズなど、名脇役という言葉がこれほど当てはまる人はいない。
もう40年近くになるだろうか、雑誌のグラビア撮影のために京都のイノダコーヒーで待ち合わせ、京の町をブラブラしながら一日話を聞いたことがある。ボソボソとした話し方、ときどき熱くなるとツバを飛ばしそうになるところはスクリーンそのまま。(高倉)健さんのことを語るときは優しい目が嬉しそうに大きく垂れ下がった。
多くの人間をインタビューしてきたが、このときほど暖かいものに包まれるような雰囲気の中で話を聞いた経験は、その後もない。
田中は麗澤(れいたく)短期大学卒業後、中学の代用教員を経て、俳優座養成所の試験に3度目で受かった。だが俳優としてスタートを切ってからは順風満帆そのものだった。
彼の姿を久々に見たのは12年8月、『北の国から』で共演した故・地井武男のお別れの会だった。
今年6月に『北の国から』のプロデューサーだった恩人の葬儀に参列しなかったことから、田中の健康不安説が再燃していた。
『ポスト』によれば「現在、田中は介護付き有料老人ホームに入居している。月額利用料は家賃に食費、管理費等を含めて20万円超と、その地域の相場を考えても一般的なもので、有名俳優が入居する施設としては決して豪華なものではない」
田中を知る関係者がこう話している。
「ホーム内では車椅子での移動が基本。部屋で過ごすことが大半ですが、食堂やホールに顔を出す時は介護士が付き添います。(中略)
やはりテレビで見かけた頃より痩せた印象は否めません。毛染めもやめているので白髪も目立ちます。ただ身体的に問題があるわけではありません。気懸かりなのは、最近はふさぎ込みがちなことだそうです」
田中の知人によれば、「地井さんが亡くなった時は本当に落ち込んで、余りの憔悴ぶりに(高倉)健さんが自宅に電話をかけて気遣ったほどでした。でも、その健さんも昨年11月に亡くなり、続けて親交のあった菅原文太さんまで逝ってしまった。最近の邦衛さんが、精神的にも肉体的にも相当参っているだろうことは容易に想像できました」
年齢的なものより精神的なもののほうが大きいのであろう。田中の奥さんは、本人はしっかり足を治してから帰ってくると言っていると話し、気弱になっているところは微塵もないと言うが、心配である。地井の葬儀のとき田中が呼びかけたように、こう言いたい。
「クニ兄、もう一度スクリーンで会いたいよ」
第2位。『新潮』がノーベル賞を受賞した日本人2人の人生と、その意義を特集している。
「アフリカ大陸を救った男」としてノーベル医学・生理学賞を受賞した大村智(さとし)・北里大特別栄誉教授(80)は、その功績はもちろんだが、テレビなどで伝えられる大村氏所有の豪邸、美術館、温泉、蕎麦屋が話題になっている。
なぜそのような資産が形成できたのか。大村氏の実家は山梨県韮山(にらやま)市で養蚕などを生業とする農家だった。山梨大学の学芸学部自然科学科を卒業した大村氏は、東京の夜間高校の理科教諭となり、後に研究者の道を歩み始める。
27歳のときにお見合いで、母親と同じ名前の文子(ふみこ)さんと結婚。これが大きな転機となったという。
氏と親交のある守家勤さんがこう説明する。
「彼は奥さんに頭が上がらなかった。というのも、彼女の実家は新潟県でデパートを経営していた資産家で、結婚してまだ間もない頃、奥さんの実家が、みすぼらしいところに住んではダメだと、家を買う資金としてポンと1500万円、援助したそうですから」
実家から援助してもらいながら研究者の道を歩み始め、71年に米国の大学に客員教授として赴任。帰国後の74年、北里研究所抗生物質室長時代に、米国の製薬会社「メルク社」とのイベルメクチン(寄生虫病の薬)の共同開発につながる細菌を、静岡県伊東市のゴルフ場近くの土壌から発見するのだ。
この薬が広まった背景には、メルク社が大村さんの同意を得て、80年代後半からWTO(世界保健機関)を通じ無償提供されたことが大きく関係しているという。
しかもこの薬を含む薬品の開発によって、大村さんはこれまで250億円もの特許料などを手にしている。
『新潮』は、大村さんを“類を見ない科学者”たらしめているのはその豪快さだという。250億円のうち220億円を北里研究所に寄付。残った30億円から税金を引いて手元に残った15億円の中から2億円を出して、小中高生が高名な研究者から講義を受けられる「山梨科学アカデミー」を設立した。しかし2000年に夫人を亡くしている。
「大村先生は奥さまを非常に大切にされていました。他界されたのがよほどショックだったのでしょう。彼女が亡くなられた後、先生は剃髪し、頭を丸められたんです。奥さまの存在がどれほど大きかったのか、改めて気づかされました」(東大医学部・北潔(きた・きよし)教授)
私もカミさんの実家から援助があれば、もっとましな編集者になっていたかもしれないが……。
先輩研究者から受け継がれてきたニュートリノの研究によって、ノーベル物理学賞を受賞したのは東大宇宙線研究所所長の梶田隆章教授(56)である。梶田氏は埼玉県東松山市の酪農家の生まれ。これほどの才能の人でも京都大学に不合格になり、二期校受験で埼玉大に行っている。
今回の受賞は2002年に同賞を受けた小柴昌俊東大名誉教授(当時)に続くもの。
「物質をどんどん細く切り刻んでいって最後に残る最小単位は何か。それを突き詰めていく学問です」(中畑雅行・東大宇宙線研究所教授)
だが、この説明では何のことやらさっぱりわからない。
湯川秀樹博士の弟子である坂東昌子・愛知大名誉教授がこう解説してくれる。
「核施設を内緒でつくった国があるとしましょう。そこから当然ニュートリノが出るのですが、これを捉えて分析すれば、“あそこにあるぞ”と出所がわかるといった利用法も考えられる」
地球物理学者の島村英紀氏がこう続ける。
「数年ほどのあいだに、火山の噴火予知に応用できるかもしれません。噴火というのは、火山の下にある『マグマ溜り』がどんどんせりあがってきて最終的に地上へ吹き出すもの。ニュートリノ観察によって、こういった特定の火山の下で起こっている動きを覗けるようになるのです」
ニュートリノで世界を透視できるというのだ。よくわからないが人類の平和に役立つ発明や発見のようである。
第1位。今週は『新潮』が頑張っている。第3次安倍改造内閣で入閣した2人にとんでもない「噂」があると報じているのだ。
一人は復興・原発事故再生担当大臣に就任した高木毅(つよし)代議士(59)。彼には「過去に女性の下着を盗んだことがある」という噂があるのだという。
高木氏は当選6回で、安倍首相の出身派閥の細田派に所属し、地盤が原発銀座といわれる福井県敦賀市ということで白羽の矢が立ったという。
だが初出馬当時から下着泥棒だという怪文書が出回っていたそうだ。
この噂を初めて記事にしたのは、地元で発行されている『財界北陸』。記者がこう語る。
「高木の“パンツ泥棒疑惑”について記事にしたのは、確か、96年の選挙の時だった。(中略)元々知り合いだった福井県警の警部補に、その噂が事実なのかどうか確認してみたんです。
すると、警部補は“敦賀署が高木毅を、下着の窃盗と住居侵入の疑いで取り調べたのは事実。犯行現場は敦賀市内。その後、事情は分からないが検挙には至らなかった”とほとんどの事実関係を認めた」
『新潮』は当該の被害にあった家を見つけた。敦賀市内の住宅街の一画にある。
近所に住む被害者の妹は「こちらが拍子抜けするほどあっさり事実関係を認めた」(『新潮』)そうである。
「被害者は私の姉です。近所のおばさんが、“家の斜め前に車を停めて中に入っていく人を見たけど、知り合いか?”って。通報したのは私だったかな。警察の人が来て、指紋とか取って。でも、教えてくれた近所のおばさんが車のナンバーを控えとってくれたんで、すぐにやったのは高木さんやと分かった。家に上がりこみ、姉の部屋で箪笥の中とかを物色し、帰って行ったようです」
今から30年ほど前。当時、下着を盗まれた女性は20代、高木氏は30歳前後だった。
だが、この「事件」がうやむやになったのは高木氏の父親の威光があったようである。高木氏の父、故・高木孝一氏は敦賀市議、県議、県会議長を務め、敦賀市長までした地元政界のドンだった。
被害者の妹によれば、当時、姉は福井銀行敦賀支店に勤めていて窓口業務をしていた。そこに高木が客として来て、姉を一方的に気に入ったという。
「だから、やったのが高木さんと分かると、姉は“いややわー。家まで来とったんやー”と言っていました」(妹)
合鍵まで勝手に作っていたともいう。
「高木氏の行為が犯罪であることは言うまでもないが、少なくともこの件は『立件』されていない」(『新潮』)
「姉が“騒がんといてくれ。勤め先にも迷惑かけたくない”って。父は“(高木氏の父親の)市長も頭下げてきた”“敦賀でお世話になっとるし”と言ってて、それで、示談っていうか……。それにしてもあんな人が大臣にまでなって、不思議やなーと思います」(妹)
もう一人は、安倍首相の「鬼門」である農水相になった森山裕(ひろし)代議士(70)。暴力団との関係が取り沙汰されているという。『新潮』の取材にはこう答えている。
「知らんかったとはいえ、暴力団の事務所に行ったことは軽率でした。ただ、個人的な付き合いは一切ありませんので……」
『新潮』によれば88年7月。
「事件現場は鹿児島最大の歓楽街・天文館からほど近い場所にある、指定暴力団の下部組織の事務所でした。暴力団幹部2人が、当時30代の男性を竹刀などで滅多打ちにしたことが分かり、翌年2月に逮捕された。(中略)暴行事件が発生した当夜、森山さんが組事務所1階の応接間に居合わせたことが明らかとなったからです」(地元記者)
このとき森山氏は鹿児島市議会議長の要職に就いていた。この件について森山氏は、当日は友達の社長に呼び出され、件の建物に連れて行かれただけだと釈明しているが、トラブルの話を付けたことは認めている。
森山氏は生粋の農水族議員で、
「TPP反対派のドンと目されていた。しかし、党のTPP対策委員長に任命されると、一転して反対派の説得に奔走。今回の入閣は大筋合意を受けての“論功行賞”に他なりません。とはいえ、そんな人事で安倍政権の“鬼門”とされてきた農水相が務まるのか、甚だ疑問です」(政治部記者)
下着泥棒に暴力団との付き合い。噂・疑惑だとしても下品窮まるではないか。第3次安倍内閣は出鼻をこっぴどく挫かれたようである。