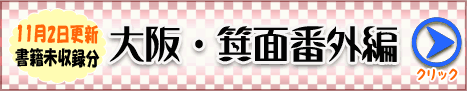シンガポール編
二十五日 昧爽、シンガポール着。頗る熱き処と覚悟せしに非常に涼しくして、東京の九月末位なり。尤も曇天なり。土人丸木をくりたる舟に乗りて船側を徘徊す。船客銭を海中に投ずれば海中に躍入ってこれを拾う。
土人にて日本語を操る者、日本旅館松尾某の引札を持して至る。命じて馬車二台を二円五十銭ずつにて雇わしめ、植物園に至る。熱帯地方の植物、青々として頗る美事なり。また、虎・蛇・鰐魚を看る。Conservatoryあり。それより博物館を見る。余り立派ならず。帰途、松島に至り午飯を喫す。此処、日本町と見えて醜業婦街上を徘徊す。
妙な風なり。午後三時、再び馬車を駆って船に帰る。三時半なり。
土人にて日本語を操る者、日本旅館松尾某の引札を持して至る。命じて馬車二台を二円五十銭ずつにて雇わしめ、植物園に至る。熱帯地方の植物、青々として頗る美事なり。また、虎・蛇・鰐魚を看る。Conservatoryあり。それより博物館を見る。余り立派ならず。帰途、松島に至り午飯を喫す。此処、日本町と見えて醜業婦街上を徘徊す。
妙な風なり。午後三時、再び馬車を駆って船に帰る。三時半なり。

夏目漱石は1900年9月8日、横浜から汽船プロイセン号に乗船、はるばるロンドン留学に旅立った。プロイセン号は順調に東シナ海を南下、上海、香港を経て、25日、シンガポールに着いた。漱石は同行の留学生仲間数人とともに下船、半日、シンガポールを見物する。
漱石が最初にみた
|
 |
私は内外の漱石の足跡を追って旅し、ジャパンナレッジ「漱石右往左往」を連載、それらをもとに、2011年に『旅する漱石先生』(小学館)を上梓したが、漱石が歩いた土地で私がまだ足を踏み入れていないところが多くある。シンガポールもそのひとつだ。シンガポールは漱石にとって、留学途上の、わずか半日の滞在にすぎないが、私は自分の目で、100年後を確かめてみたかった。数日の休暇を得て、当地へ向かった。

今のシンガポールを象徴する統合型リゾート・マリーナ・ベイ・サンズ。
カジノが併設され、物議をかもしている。
シンガポールはアジアの金融センター、エネルギッシュな都市国家として知られる。東京23区ほどの狭い島に、550万の人口を有し、一人当たりの国民総生産は5万ドルを超え、日本より豊かだ。シンガポールを富裕国に引き上げた政治家、リー・クアン・ユーが、私の出発する数日前に死去し、大きく報道された。
4月半ば、日本列島を桜前線が移動中というのに、東京では雪が舞うという寒い日、ジャケットの下にセ-ターを着込んで成田を出発した。7時間後、到着した深夜のシンガポールではセーターを捨てたくなった。昼は34℃になるという、むっとする暑さである。
漱石は9月末、案外涼しい朝、シンガポール港に着いた。そこで、珍しい光景に出合った。汽船の近くに小舟が来て、船べりから小銭を海に投げ入れると、船の現地人が飛び込んで銭を拾うのだ。客は面白がってコインを次々に投げこみ、そのたびに褐色の人が海中に潜る。植民地の現実、リアルなアジアの姿を、漱石ははやくも見知ったことだろう。
漱石とともにプロイセン号に乗船した留学生仲間のひとりに、芳賀矢一という国文学者がいた。ドイツに留学する芳賀は、漱石以上に筆まめな男で、詳細な渡航日記『留学日誌』を残している。これにも、この光景が記されている。
朝6時に甲板から新嘉坡(シンガポール)市街を見るが、その遠景は「品川湾より高輪辺を望むが如し」だった。2隻の独木舟(木をくりぬいた小舟)が汽船に接近、「これ旅客より銭を乞わんとするものにて、旅客若し銭を海中に投入すれば、舟人は直に水中に飛入りて之を拾い来るなり。その巧妙なること亦一種の芸術というべし」。
それから13年後の1913年、洋行途上の作家島崎藤村も、この地で同様の光景に接し、わざわざ紀行文に記している。「港に停泊するわれわれの船をめがけてカノオを漕ぎ寄せる土人もあった。不思議な声を出して手を挙げて見せるのは、銭を海に投げて呉れ、という合図だった。旅のつれづれに高い甲板の上から銭を投げ入れるものがあれば、土人は直ぐに水の中を潜っていって拾い出して見せた。こんなあさましい慰みも、初めて見る眼にはめづらしかった」(「海へ」)

今のシンガポールを象徴する統合型リゾート・マリーナ・ベイ・サンズ。
カジノが併設され、物議をかもしている。
4月半ば、日本列島を桜前線が移動中というのに、東京では雪が舞うという寒い日、ジャケットの下にセ-ターを着込んで成田を出発した。7時間後、到着した深夜のシンガポールではセーターを捨てたくなった。昼は34℃になるという、むっとする暑さである。
漱石は9月末、案外涼しい朝、シンガポール港に着いた。そこで、珍しい光景に出合った。汽船の近くに小舟が来て、船べりから小銭を海に投げ入れると、船の現地人が飛び込んで銭を拾うのだ。客は面白がってコインを次々に投げこみ、そのたびに褐色の人が海中に潜る。植民地の現実、リアルなアジアの姿を、漱石ははやくも見知ったことだろう。
漱石とともにプロイセン号に乗船した留学生仲間のひとりに、芳賀矢一という国文学者がいた。ドイツに留学する芳賀は、漱石以上に筆まめな男で、詳細な渡航日記『留学日誌』を残している。これにも、この光景が記されている。
朝6時に甲板から新嘉坡(シンガポール)市街を見るが、その遠景は「品川湾より高輪辺を望むが如し」だった。2隻の独木舟(木をくりぬいた小舟)が汽船に接近、「これ旅客より銭を乞わんとするものにて、旅客若し銭を海中に投入すれば、舟人は直に水中に飛入りて之を拾い来るなり。その巧妙なること亦一種の芸術というべし」。
それから13年後の1913年、洋行途上の作家島崎藤村も、この地で同様の光景に接し、わざわざ紀行文に記している。「港に停泊するわれわれの船をめがけてカノオを漕ぎ寄せる土人もあった。不思議な声を出して手を挙げて見せるのは、銭を海に投げて呉れ、という合図だった。旅のつれづれに高い甲板の上から銭を投げ入れるものがあれば、土人は直ぐに水の中を潜っていって拾い出して見せた。こんなあさましい慰みも、初めて見る眼にはめづらしかった」(「海へ」)
シンガポールを“つくった”
|
 |
さて、漱石は上陸すると、日本旅館の引き札(ちらし、ビラの類)を持った男に案内され、馬車で植物園に行く。このシンガポール植物園は、シンガポールを「建設」したとされる、ラッフルズが発案してできた、由緒ある植物園だ。
イギリス東インド会社の現地幹部で植民地行政官、トーマス・ラッフルズ(1781~1826)が、マレー半島南端のほとんど無住の島、シンガポールに注目し、現地王国の内紛に乗じて手に入れたのは、1819年のことだった。以降、イギリスは同地を、オランダ東インド会社を牽制する地政学上の意味だけでなく、関税をとらない自由貿易港として育成し、同地は大英帝国の東の窓口に発展した。働き場を求める中国人、インド人が続々移住し、19世紀初頭に150人程度だった人口はみるみる大膨張し、東南アジア有数の都市に変貌した。
ラッフルズは単なる行政官ではなかった。動物学、植物学、歴史学などに造詣が深く、ジャワ歴史書も書いている。シンガポールに植物園開園を発案したのもラッフルズだった。学問上のためだけでなく、当時、コショウやガンビル(染料や薬草)などの植物栽培品が主要な貿易品であり、その栽培研究、品種改良などの目的もあった。
上陸した漱石が、まず植物園に案内されたということは、当時、観光客に見せる施設はほかになかったのだろう。漱石が記すとおり、当時はトラやワニなど動物も飼っていた。
私も、馬車ではないが最新の地下鉄で、植物園に行った。都心部から少し離れたところに、広大なボタニック・ガーデンがあった。入場無料の入り口から入ると、幹が細く、傘のように枝が広がる熱帯の林が迎えてくれる。遊歩道が縦横に延び、池があり、芝生が広がり、一周するには数時間かかるという。しかし、5分も歩くと熱帯の暑さにどっと汗が出て、とても遠くまで行く気になれない。高い枝先から、うーうーと不機嫌そうに鳴くセミの声も、蒸し暑さを増す。中央にあるランの庭園まで歩くのが精いっぱいだった。漱石の当時は、園内に馬車も入れたというから、馬車で回ったのだろう。例の芳賀日誌には「我大学の植物園に似たり、但しその異木花卉の多きは他に類なきところという」などと記されている。

シンガポール植物園の入り口。かつては馬車や車でも入れたという。
この植物園はロンドンのキュー植物園の傘下にあったという。漱石はロンドン留学中、キューに行ったはずだ。ラッフルズはインドネシア・ボゴールの植物園の設立にも関係した。数年前、ボゴール植物園を訪れた際、園内にラッフルズ夫人のお墓があったのを思い出した。夫人と子どもたちは、灼熱の熱帯で健康を害し、次々と病死したのだった。
漱石は植物園のあと、日本人町にある松尾旅館で昼ご飯を食べた。活字化された漱石日記では「帰途、松島に至り、午飯を喫す」となっている。芳賀日誌では「松尾兼松の旅館」とあるので、「松島」は「松尾」の間違い、漱石の原文を活字化したとき、崩し字を読み違えたのだろうと思った。
そこで東北大学漱石文庫のデータベースをウェブで開き、当該箇所を原文であたってみた。すると「松島」は「松嶌」とかなりはっきり書かれていた。漱石の勘違いだったようだ。ここでタイのさしみ、照り焼きなどを食べた。コメはインド米で甘かった。
イギリス東インド会社の現地幹部で植民地行政官、トーマス・ラッフルズ(1781~1826)が、マレー半島南端のほとんど無住の島、シンガポールに注目し、現地王国の内紛に乗じて手に入れたのは、1819年のことだった。以降、イギリスは同地を、オランダ東インド会社を牽制する地政学上の意味だけでなく、関税をとらない自由貿易港として育成し、同地は大英帝国の東の窓口に発展した。働き場を求める中国人、インド人が続々移住し、19世紀初頭に150人程度だった人口はみるみる大膨張し、東南アジア有数の都市に変貌した。
ラッフルズは単なる行政官ではなかった。動物学、植物学、歴史学などに造詣が深く、ジャワ歴史書も書いている。シンガポールに植物園開園を発案したのもラッフルズだった。学問上のためだけでなく、当時、コショウやガンビル(染料や薬草)などの植物栽培品が主要な貿易品であり、その栽培研究、品種改良などの目的もあった。
上陸した漱石が、まず植物園に案内されたということは、当時、観光客に見せる施設はほかになかったのだろう。漱石が記すとおり、当時はトラやワニなど動物も飼っていた。
私も、馬車ではないが最新の地下鉄で、植物園に行った。都心部から少し離れたところに、広大なボタニック・ガーデンがあった。入場無料の入り口から入ると、幹が細く、傘のように枝が広がる熱帯の林が迎えてくれる。遊歩道が縦横に延び、池があり、芝生が広がり、一周するには数時間かかるという。しかし、5分も歩くと熱帯の暑さにどっと汗が出て、とても遠くまで行く気になれない。高い枝先から、うーうーと不機嫌そうに鳴くセミの声も、蒸し暑さを増す。中央にあるランの庭園まで歩くのが精いっぱいだった。漱石の当時は、園内に馬車も入れたというから、馬車で回ったのだろう。例の芳賀日誌には「我大学の植物園に似たり、但しその異木花卉の多きは他に類なきところという」などと記されている。

シンガポール植物園の入り口。かつては馬車や車でも入れたという。
漱石は植物園のあと、日本人町にある松尾旅館で昼ご飯を食べた。活字化された漱石日記では「帰途、松島に至り、午飯を喫す」となっている。芳賀日誌では「松尾兼松の旅館」とあるので、「松島」は「松尾」の間違い、漱石の原文を活字化したとき、崩し字を読み違えたのだろうと思った。
そこで東北大学漱石文庫のデータベースをウェブで開き、当該箇所を原文であたってみた。すると「松島」は「松嶌」とかなりはっきり書かれていた。漱石の勘違いだったようだ。ここでタイのさしみ、照り焼きなどを食べた。コメはインド米で甘かった。
“からゆきさん”にみる
|
 |
漱石は日本人町に売春婦が多いことに驚いているが、シンガポールはいわゆる「からゆきさん」が東南アジアで最も多い街だった。19世紀後半、同地にはアジア各地から単身の出稼ぎ労働者が集まってきた。また交易が盛んになるにつれ、多くの船が寄港し、船員が上陸。こうして売春業が発展した。日本からも九州、とくに島原半島や天草地方などから、多くのからゆきさんがやってきた。シンガポールのからゆきさんは、1877年にはわずか14人だったが、1903年には585人に達し、在シンガポール日本人の多くを占めたという(『物語 シンガポールの歴史』岩崎育夫著、中公新書)。コインを海中から拾う男たちや、多くのからゆきさんの姿に接した漱石は、貧困や植民地化というアジアの現実を目の当たりにし、日本の近代化について、何かしら感じるところがあっただろう。

19世紀半ばに作られたカベナ橋。漱石も目にしたはずだ。
私はかつて日本人町だったといわれるあたりにも、行ってみた。だがシンガポールはいたるところ、再開発中であり、日本人町の面影はまったくなかった。都心に近く、ビルが立ち並んでいたが、どこかしら場末感が感じられた通りだった。
シンガポールでもっとも有名なホテルは、ラッフルズの名を冠した(もっともただ名前を借りただけだが)ラッフルズ・ホテルだ。そこのバーの売り物、シンガポール・スリングというカクテルは、酒好きにはよく知られる。ものはためしと私も夕刻、その超高級ホテルのバーに行き、くだんのカクテルを頼んだ。このロング・バーというバーは、ホテル本体の隣にあり、宿泊客ではなく私のような外の観光客らしき客で混んでいた。きっとシンガポール・スリング目あてだろう。
見るからにトロピカルなこのカクテルは、ジンベースでオレンジジュースなどが交じり、イチゴ(チェリー)が載る、甘い酒だった。一口、口にするとジュースのようだが、ジンがベースだけに、飲みほすと結構アルコールが入った、という感じになる。バーテーブルの各所に置いてある、小さな麻袋に入った落花生をつまんで食べるのが、粋らしく、私も真似てぽりぽりやってみた。でも肝心の落花生は小さくてすぐ砕け、茨城や千葉産の剛直な落花生に、はるかに及ばなかった。

19世紀半ばに作られたカベナ橋。漱石も目にしたはずだ。
シンガポールでもっとも有名なホテルは、ラッフルズの名を冠した(もっともただ名前を借りただけだが)ラッフルズ・ホテルだ。そこのバーの売り物、シンガポール・スリングというカクテルは、酒好きにはよく知られる。ものはためしと私も夕刻、その超高級ホテルのバーに行き、くだんのカクテルを頼んだ。このロング・バーというバーは、ホテル本体の隣にあり、宿泊客ではなく私のような外の観光客らしき客で混んでいた。きっとシンガポール・スリング目あてだろう。
見るからにトロピカルなこのカクテルは、ジンベースでオレンジジュースなどが交じり、イチゴ(チェリー)が載る、甘い酒だった。一口、口にするとジュースのようだが、ジンがベースだけに、飲みほすと結構アルコールが入った、という感じになる。バーテーブルの各所に置いてある、小さな麻袋に入った落花生をつまんで食べるのが、粋らしく、私も真似てぽりぽりやってみた。でも肝心の落花生は小さくてすぐ砕け、茨城や千葉産の剛直な落花生に、はるかに及ばなかった。

漱石右往左往~文豪・夏目漱石の足跡をたずねて~
2015年5月 15日
2015年5月 15日