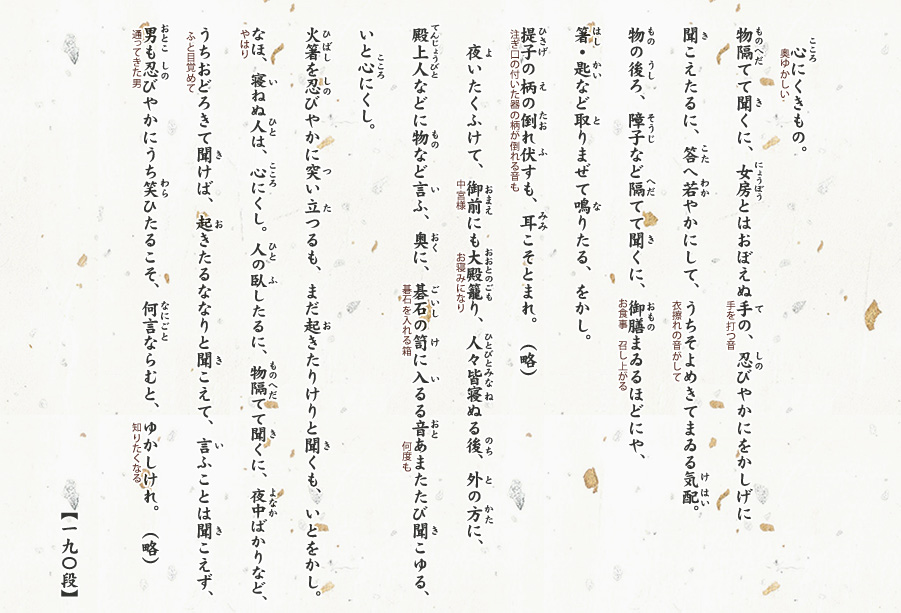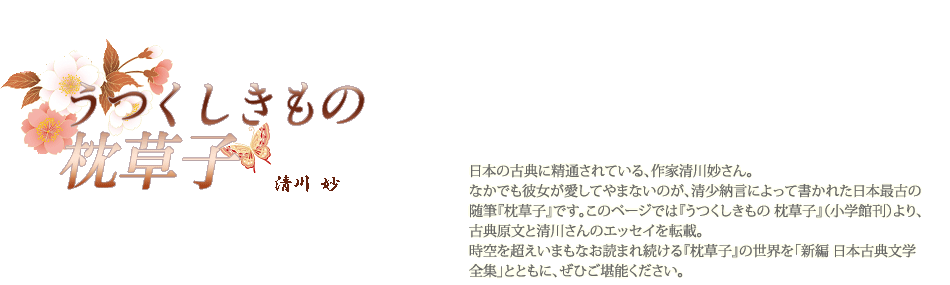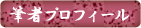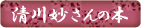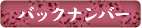「心にくし」とは、あらわには示されていない相手の人柄、態度、センスなどに、上品な深みを感じて、心ひかれることで、現代語で言えば、「奥ゆかしい」ということになる。
「物隔てて聞くに」ではじまるこの段は、間接的にあることを知って、その向こうにあるものを想像してときめかす心が語られる。じかに見たり聞いたりするよりも、秘密のベールに隠されて、より魅力的なのである。
抄出部分は聴覚の世界である。
屏風や几帳を隔てて聞いていると、相当の身分と思われる女性の、人を呼ぶときの、ひっそりと品のいい手の音がする。と、うてば響くように、「はい」と若々しい声が受けて、衣ずれの音をさやさやとかすかにたてて伺候するけはいも奥ゆかしい。センスのいい女主人と、それにふさわしい若い女房。若い女房が主人を大切に思っていることも汲みとれる。すてきな主従なのである
なにかのうしろか、襖障子などを隔てて聴くと、向こうでは、身分ある方がお食事をなさっているのだろうか、箸、匙などの音が交錯して鳴っている。コトッと音がする。あっ、いま、提子の柄が倒れたな。そんな小さな音までが聴きとめられる。
ほかの段で、清女は言っている。女房の局に訪ねてくる男が、女の部屋で食事なんかするのは、ほんとうにみっともない。私は、男が酔っぱらって夜更けにやってきて泊まっても、白湯漬けごはんだって出さないわ、と。むき出しの食事風景は、彼女の美的恋愛センスからすると、ごめんなのである。
もののうしろ、襖などを隔てて聴くからこそ、思い描く食事風景はなにか愉しく、物語めいて感じられるのであろう。しかも、貴い方のお食事ではあるし。
中宮様ももうおやすみになった夜更け、誰かが外のほうに向かって、訪ねてきた殿上人となにか話す声がしたり、奥のほうでは、誰かが碁の対局をしているらしく、碁石を碁笥にザラザラと入れる音が何度も聞こえるのも、奥ゆかしい。
誰かが、そっと火箸を突きさす音がする。まだ起きているのかしら、なにか物思いでもしているのかしら、と興味をそそられる。夜中に寝ないでいる人って、すてきだな。その人がなにか秘密の――それも知的な世界を持っている気さえして。
そういう自分は、いつかトロトロと眠ってしまって、真夜中にふっと目が覚めて、几帳越しに聞くともなしに聞くと、お隣には、誰か男の人が来ているらしい。何の話だか、話の中身はわからないが、なにやらひそひそ話だけ聞こえ、男がひっそり笑い声をたてる。好奇心を抑えがたい。ここはかなりなまめかしい場面である。
宮様御寝の後の、女房たちの夜の生態は、ひそかな音だけを通して、息づかいも聞こえるように、なつかしく語られる。あんな夜もあった、こんな夜もあった。清女は思い出の夜々を心に浮かべては、回想の筆を進めていったにちがいない。
* * *
この段の原文の、省略した部分には、視覚や嗅覚の世界の奥ゆかしさも記されている。
完璧に飾り付けられた中宮様の御殿が舞台である。日は暮れたが、まだ燭台に灯はともされず、ただ長火鉢に、炭火がいっぱいおこしてある。その火の光だけがあたりを照らしているとき、宮様の御座所にかかる御帳の飾り紐がつややかに光っている奥ゆかしさを、なんと言おう。炭火に光るものは、まだある。御簾を巻き揚げたときに留める鉤が、その鉤かくしの絹紐の飾りの端から、キラッと光る。ああ、ここは宮。そして、宮仕えの私の目がそれを見ている。誇りやかな自己満足を添えて、清女は光る紐や鉤を、奥ゆかしいとみつめるのだ。
清女はまた、丸火鉢の中も見つめる。極上の丸火鉢だ。掃き目も美しい灰の中におこされた火。その光に、内側に描かれた絵まで見えるのもおもしろく、光る火箸を二本そろえてすっきりと斜めにさしてあるのも、優雅でゆかしい。
限定された条件の中で見えるものは、ここでも、想像力を添えることによって、魅力が増すのだ。
火鉢の内側の絵をさしのぞく眼は、透垣の羅文の蜘蛛の巣にかかる露を見つめる、あの眼である。
さて、この段の最後には、「袖の几帳」でおなじみの斉信の中将が登場する。
「薫物の香、いと心にくし」ではじまるこの場面では、中宮のお部屋の簾に寄りかかった斉信の、衣にたきしめた香りのすばらしさが語られる。彼が立ち去ったあと、その翌日まで、香りは御簾に染みこんでいて、若い女房たちが大さわぎした。若くない女房の清女も胸をときめかして、「ことわりなりや――さわぐのもあたりまえだわ」と言っている。
平安の昔は、男のおしゃれも奥ゆかしかった。