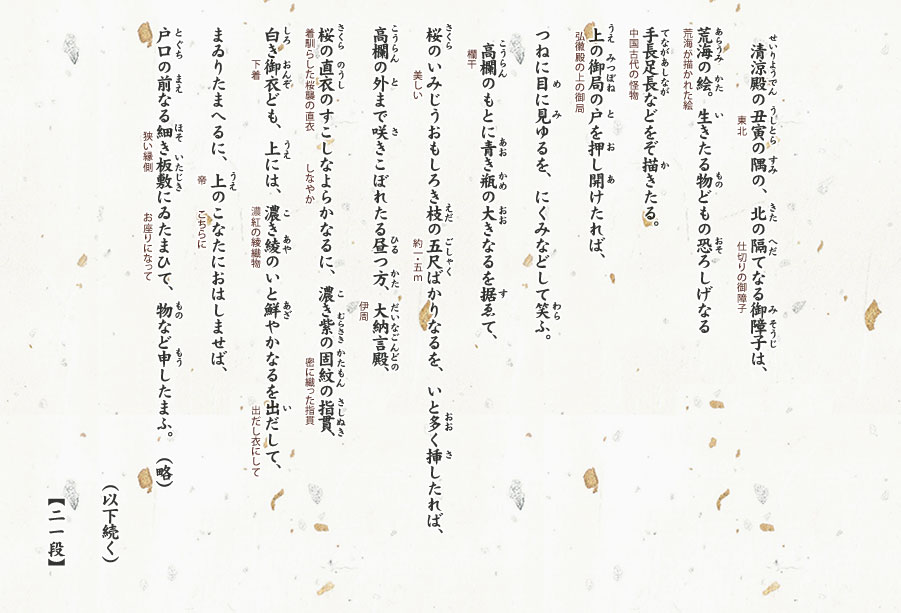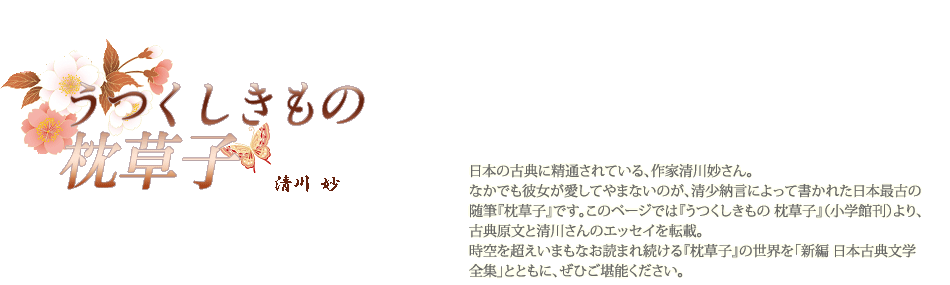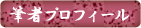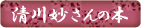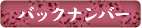ただもう恥ずかしいばかりだった初宮仕えの年も明け、清女はすこしずつ定子の宮に馴れてきた。美貌と教養とやさしい人柄と――。レディーとしての条件を完璧に充たした中宮定子の侍女として、才覚あることを示したいという野望めいた思いは、胸にたたまれたままだった。
だが、生来、明るく闊達な彼女である。新参者として、まだ、ことあるごとに驚きながらも、宮仕えの水に次第に馴れていく自分に喜びを感じていたにちがいない。
「清涼殿の丑寅の隅の」と書き出されたこの段は、そんな彼女が、言ってみれば最高の晴れの舞台で演じてみせた、最初の味な演技の記録である。
なにしろ、清涼殿。そこは、帝の常の御座所。プライベートハウスである。宮仕え以前には思ってもみなかった夢の場所である。定子様にお仕えしたおかげで、一地方官の娘にすぎない自分も、華のなかの華の場所に足を踏み入れることができたのだ。
この段のひとつ前は、「家は」という段である。その家のトップは、「九重の御門」――つまり、帝の御所である。
くどいけれど、もういちど言おう。「清涼殿の丑寅の隅の」と書き出した、このことばの裏には、「今日の私の話は、九重の御門の中の、そのまた秘密の場所の、清涼殿での話なのよ。その東北の隅っこの荒海の障子だって、私たちはしょっちゅう見てるのよ」という気合いやら、自慢やらのまじった気分がある。
荒海の絵のついたてぶすまに描かれているのは、鬼門の魔除けとしての手長足長である。「こわくて、にくったらしくて、でも、滑稽なヤツたちよね」なんて、清女ももう宮仕え仲間の中に溶けこんで、その異形の手長足長とも友達感覚で付き合っているのだ。
さて、清涼殿は春のまっさかり。「高欄のもとに青き瓶の大きなるを据ゑて」にはじまる桜の描写の美しいこと。ここを読むたびに、私には、陶酔に充ちた清女のまなざしが見えるような気がする。
花瓶は舶来の青磁の、しかも特大の超高級品。それに桜の晴れやかな枝ぶりのものを選んで、長さもなんと一メートル半ばかりのを、たっぷり。惜しげもなく豪勢に活けてある。桜のはなびらのピンクも花瓶の青も、日ざしの中にふっくらと光をこもらせ、わが世の春をうたいあげているよう。
咲き充ちた花は高欄の外まで枝を伸ばし、ひとひら、ふたひら、はなびらは、これも光りながら、散りこぼれる。
おあつらえ向きの舞台装置なのだ。そこへ、しずしずと登場するのは、ここでもまた、定子中宮の兄上、伊周。若さあふれる二十一歳。
「桜の直衣のすこしなよらかなるに、濃き紫の固紋の指貫、白き御衣ども、上には、濃き綾のいと鮮やかなるを出だして、まゐりたまへるに……」
桜の直衣とは、表が白、裏が赤(紫という説も)の、貴族のふだん着。「すこしなよらかなるに」とは、ちょっと着馴らしてやわらかにしているのだ。芸がこまかいのである。濃紫の指貫袴は、糸を固くしめて模様を沈めて織り出したもの。白い小袖の上に着た濃い紅の袿を直衣の下からのぞかせた当世風の出だし衣。とり集めて胸がすくようなおしゃれ感覚だ。
ああ、物語の中の主人公みたい、と清女はここでもためいきをついている。御簾のなかからまじまじと見つめている清女の目になって、伊周登場のここの文章は、どうか声に出して読んでいただきたい。清女の酔いはあなたにも伝わるはずだ。
清女は伊周の目鼻立ちなど、克明には書かない。初宮仕えの日の定子を描いた筆の「さし出でさせたまへる御手のはつかに……薄紅梅なるは」と、おなじ手法なのだ。伊周のいでたちの場面は声に出して読んだあと、目をつぶって、その色と光を、まぶたの裏にもう一度思い浮かべていただきたい。
なまじの目鼻立ちなど書かれるよりも、花のもとに伺候した貴公子の風貌は、想像力をかきたてて、この世ならぬ美しさにかがやくはずだ。これも、清女の筆の魔術なのである。
清女は、先輩女房たちと共に、弘徽殿の上の御局と呼ばれる部屋の御簾のなかにすわっている。
この部屋は、中宮が帝に召されたときには、いつも御座所にされるところで、今日はここに帝もおいでになっているので、伊周はご遠慮して、縁側にすわっているのである。
帝はお食事のために、しばらく御局をお出になったが、すぐにお立ち帰りになった。