シリーズ 26 「漢語をめぐって 」目次
- 1. 今野真二:漢語に注目することの意義 2023年09月20日
- 2. 今野真二:漢語なのか、漢語風なのか? 2023年10月04日
- 3. 今野真二:情報強化で得られる「気づき」とは? 2023年10月18日
- 4. 佐藤宏:漢語は「泥沼」か? 2023年11月01日
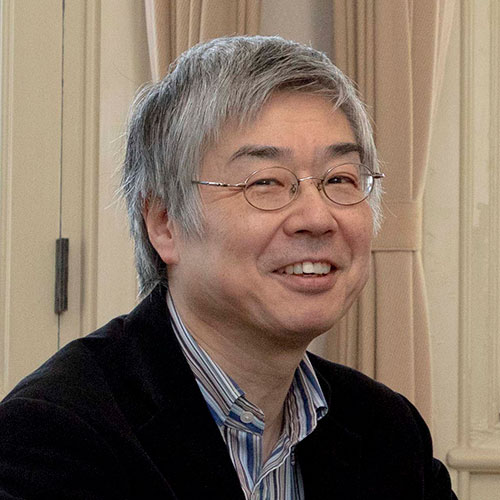
漢語をめぐって
Series26-1
漢語に注目することの意義
日本は中国と早くから接触をし、それは深く、長く続いた。「日本」と表現したが、「日本」をもう少し具体的に「日本文化」といってもよいし、「日本語」といってもよい。
夏目漱石の作品を、男性の登場人物ではなく、女性の登場人物の立場から読み直すということが行なわれることがある。「ジェンダー」という枠組みを設定し、男性の立場から(おそらくはつくられ)よまれてきた文学作品を、女性の立場からよみ、これまでの「よみ」を相対化するという試みといってよい。
日本語を「語種」という観点からとらえれば、日本語は「和語」「漢語」「外来語」から成っているととらえることができる。「漢語」はもともとは中国語として使われていた語で、日本語の語彙体系内で使われるようになった語、「外来語」は中国語以外の外国語(すなわち非日本語)が日本語の語彙体系内で使われるようになった語、とごく簡略に定義することができるだろう。
この定義でいいとすれば、「漢語」と「外来語」とを分けていることがすでに特殊であるともいえよう。日本語以外の外来語という枠組みではなく、その「日本語以外の外来語」の中で、「中国語」だけを別にしているのは、先に述べたように、日本語と中国語との接触が深く、長いために、他の外国語よりも借用されている語の数としても多く、そして語彙体系内への「入り込みの度合い」もつよいためと思われる。
さて、上では「漢語」を「もともとは中国語として使われていた語で、日本語の語彙体系内で使われるようになった語」と定義した。そうすると、ある語を漢語と認める場合には、「中国語としての使用」「日本語としての使用」の両方を確認する必要があることになる。
『新潮国語辞典』第2版(1995年)の「凡例」の「見出し語」の一には「見出し語はアンチック体とし、平仮名と片仮名とを用いた。平仮名は和語(固有の日本語)であることを、片仮名は漢語(字音語)または外来語およびそれに準ずるものであることを示す」とあって、「和語」の見出しを平仮名で、「漢語」と「外来語」の見出しを片仮名で表示していることを謳う。『新潮国語辞典』は語種に気配りをした辞書といえるだろう。「外来語」を片仮名で表示する辞書は小型の国語辞書を含めて少なくないが、「漢語」を「和語」と区別できるようにしている辞書は多くはない。『日本国語大辞典』の「凡例」「見出しについて」の「二 見出しの文字」には「和語・漢語はひらがなで示し、外来語はかたかなで示す」とある。『新潮国語辞典』の「対立軸」は「和語:漢語・外来語」で、『日本国語大辞典』の「対立軸」は「和語・漢語:外来語」であることになる。
現代日本語を使うということからすれば、すでに日本語の語彙体系内に位置を占めている漢語が、もともとは中国語であったことを知る必要はないともいえよう。それでも外来語は区別するというのが、現代日本語使用者の「心性」であろう。それはそれでもちろんいい。しかし、「日本語の歴史」を意識するのであれば、現在は区別をしない、あるいはできなくなってきている「漢語」を認識しておくことに一定の意義はあると考える。そして、『日本国語大辞典』が「日本語のアーカイブ」を目指す、あるいは結果としてそういう位置づけになるのであれば、「漢語」について、情報を加えたり、整えたりすることを、考えてよいだろう。「漢語」に注目することは、日本語全体を相対化することに何ほどかつながるはずだ。そしてそれは『日本国語大辞典』全体の強化にもつながることは疑いない。
いせい【威勢】
〔名〕
(1)(─する)人を威圧する力。はげしいいきおい。また、権力をふるって威圧すること。
*百座法談〔1110〕六月一九日「王、輪法の威勢にて、鉄のあみをすき、いくさをおこして、海にむかひて龍王をせめ給に」
*色葉字類抄〔1177~81〕「威勢 ヰセイ」
*平家物語〔13C前〕八・征夷将軍院宣「平家頼朝が威勢におそれて宮こを落ち」
*玉塵抄〔1563〕二八「桓温が政をとっていせいして殷を尚書の官にして用のことにつかわうと思て状をかいてやったぞ」
*浄瑠璃・嫗山姥〔1712頃〕一「姉女院のゐせいをかって中なごんの右大将にへあがり」
*管子‐明法解「人主之所三以制二臣下一者威勢也」
(2)(多く「威勢がよい(ある)」などの形で用いる)意気のさかんなようす。活気のあるさま。元気。
*勝山記‐永正八年〔1511〕「此年長尾伊賢、此郡を武州へとをり威勢を取らるる也」
*滑稽本・浮世風呂〔1809~13〕前・下「石段の立(たて)は威勢(イセヘ)が能(いい)っちゃアねへヨ」
*土〔1910〕〈長塚節〉一「『おっかあか』と直(すぐ)におつぎの返辞が威勢(ヰセイ)よく聞えた」
漢語「イセイ」を例としてみよう。語義は(1)(2)に分けて説明されている。語義(1)の末尾に『管子』における使用例があげられている。『管子』の成立年代は特定されていないが、中国の戦国時代から秦、漢にかけての成立とみなされている。いずれにしても、古代中国語とみることができるだろう。『大漢和辞典』には『韓非子』の使用例もあげられている。
『色葉字類抄』が見出しとしているということは、一つの目安になりそうで、そのことのみから判断するのは粗いが、『色葉字類抄』が成った十二世紀末ぐらいまでに、広義の日本語において使われていたとひとまずは推測することができるだろう。時期としてみれば、『平家物語』、『玉塵抄』、そして浄瑠璃に使用が確認でき、日本語の中でずっと使われていたことが推測できる。また語義(2)は「イセイがよい」「イセイがある」という、どちらかといえば「はなしことば」的ないいまわしにおける「イセイ」の使用で、『浮世風呂』にそうした使用が確認できることは、江戸期には「はなしことば」においても使われていたことを窺わせる。後に「はなしことば」においても使われるようになる漢語が必ず早くから「かきことば」内で使われていた漢語ではないだろうが、「かきことば」で使われ定着し、それが「はなしことば」でも使われるようになる、というのは一つの「みちすじ」であろうから、「イセイ」は日本語の語彙体系内で、そのように使われていったという「歴史」が推測できる。
「イセイ」に関しては、中国語としての使用が確認でき、日本語の語彙体系内での使用も確認できた。つまり、『日本国語大辞典』が示している「情報」によって「イセイ」が漢語であることがはっきりと確認できる。『日本国語大辞典』が示している「情報」から何をよみとることができるかということであるが、それは逆側からいえば、こういう「情報」があれば、もっとよみとりの幅がひろがるということの気づきにもなる。
▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は10月4日(水)、清泉女子大学教授今野真二さんの担当です。
ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典
“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった
筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ
1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし
1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。
最新10件
- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える
佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?
今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?
今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」
今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』
今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?
佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?
今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?
今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義
今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される
佐藤宏 2023/09/06
『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!
会員登録をしてぜひ投稿してみてください。
『日本国語大辞典』をよむ
辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。







