シリーズ 18 「使い方動画をつくってみて考えたこと 」目次
- 1. 今野真二:編集者側とユーザー側 2022年04月06日
- 2. 今野真二:非対面授業の良さ 2022年04月20日
- 3. 今野真二:マニュアルの大切さ 2022年05月06日
- 4. 佐藤宏:メディアとしての国語辞書 2022年05月18日
使い方動画をつくってみて考えたこと
Series18-4
メディアとしての国語辞書
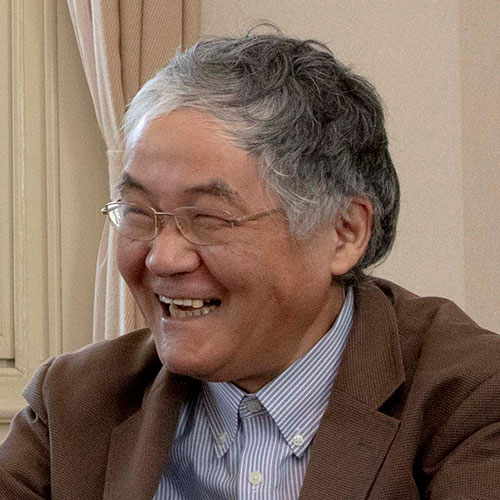
1.国語辞典・一冊本の歴史
大槻文彦の『言海』が近代的な国語辞書の嚆矢とされる所以は、見出し語を五十音順に並べそれぞれの「発音・語別(品詞)・語原・語釈・出典」を示すという辞典の構成を確立したところにあります[1]。また、普通語すなわち日常生活で普通に用いられることばを収録するという点でも画期的なものでした。それまでは、庶民が手紙などを書くときに読みからその漢字を調べるために用いた節用集や、役人や学者が部首から漢字を調べるために用いた倭玉篇などのほかに、雅語、俗語、方言など個別に編まれた字引はあったのですが、一般の人が日常的に使っていることばに語釈などを施しそれを引きやすい順番に並べて一書にまとめた辞書は『言海』が初めてだったのです。その収録語数は約3万9000語ですが、現代では主に生活語彙を収める6万〜9万語の小型辞典[2]がそれを引き継いでいると見ることもできるでしょう。
一方、明治から大正、昭和へと、社会が高度化、複雑化するにともない、さまざまな分野のことばも増えてきます。新聞・雑誌や書籍などによって新しいことばが次々に生まれてくると、普通語にそれらの百科語も加えて10万語以上を一冊に収めるようになり、『ことばの泉』[3]『広辞林』[4]『辞苑』[5]などが登場します。戦後になると、昭和30年(1955)に『辞苑』を大幅に増補改訂して20万語以上を一冊に収めた『広辞苑』が岩波書店から刊行され、このクラスでは唯一の辞典として人気がありました。それに対して昭和56年(1981)に小学館から25万語の『国語大辞典』[6]が出て話題を呼び、昭和63年(1988)には22万語の『大辞林』(三省堂)、その翌年に17万5000語(1995年刊の第二版で、約20万語)の『日本語大辞典』(講談社)が相次いで刊行されて国語辞典ブームが起きます。「一家に一冊」ということばが見えるようになるのは、まさに、この時期です[7]。
ちょうどその頃に『広辞苑』のCD-ROM版(1987)が出て、デジタル辞書の可能性もさまざまに模索され始めますが、1995年以降インターネットが普及するようになり、さらに2000年代には検索エンジンのGoogleの利用が破竹の勢いで広がります。また、カシオなどから専用の電子辞書も登場して売り上げを伸ばし、スマートフォンのアプリとしても販売されるなど、デジタル媒体が普及するにつれて、紙の辞書の売れ行きは落ち込むようになります。主に学校などで使われる学習辞典や小型辞典は健闘していますが、それでも今はアプリ辞書などとの共存を迫られているのが実情かと思われます。一般には、なんでもネット検索で済ませてしまいがちなこのご時世に、ありきたりの検索では得られない国語辞典ならではの特徴[8]を備えた情報をどのように提供していくのかが今まさに問われています。
2.インターネットと辞典
現代ではネット上で、たとえばWikipedia(ウィキペディア)のように、「集合知」[9]を活かした百科事典が生成しつつあることも確かです。時間に余裕のある人がそれぞれの趣味や専門の知識を持ち寄ることで、いくらでも広く深い内容になっていくのかもしれません。とはいえ、仮に情報が常に更新され、形式処理についてはAI(人工知能)が活用されるようになるとしても、それを使うのが人間である限り、当然ながら、それに形を与えるのも人間でなければならないでしょう。誰でも無償で引くことができ執筆にも参加できるとはいえ、実際にはWikipediaも寄付金に支えられたスタッフがいて内容を管理していることも事実です。これが国語辞典の執筆・編集ともなれば、ことばを分野ごとの事柄としてではなく分野を超えた言語として扱い、わかりやすく説明するという専門性は、これからも求められ続けるのではないでしょうか。
特に、学習用あるいは事務用などの用途に合わせて編集される小型辞典は、どのような項目を収めるかがその辞典の性格を大きく左右することに変わりはないでしょう。紙の制約を抜きにしても、8万なら8万の語彙を集めてその中で体系的にわかりやすく解説するという点にこそ、国語辞典の個性を発揮する余地があります。その個性によって多様なニーズに応えるとともに、ことばがその辞典に載っているか載っていないかがこれまで以上に意味を持つようになるのかもしれません[10]。一方、ネット上では、新しい情報や知見があればその都度付け加えたり、古くなった情報に上書きしたりと常時更新することは可能でしょう。しかし、その場合、情報は常に現在を優先することによって過去の痕跡は消され、変化が見えにくくなる恐れがあります。履歴をこまめに残しそれが誰にもわかるようにするか、あるいは、体系的に見直す作業を適宜入れてバージョン管理し、旧版は旧版として保存(アーカイブ化)していくことでことばの歴史性を担保する必要があると考えます。
3.辞典を使う人と作る人
いずれにしても、国語辞典を作る側は「充実した内容をいかに簡潔に収めるか」といった課題を抱え、それに対して使う側は「このことばがない、意味・用法がない、解説がわかりにくい」といった感想を持つのもある意味では当然のことと言えましょう。それぞれの見方や意見を出し合うことによって、より深い辞典像のようなものも浮かび上がってくるのではないか。この往復書簡の企画をご提案いただいたときには、『日本国語大辞典』をもとに、それを国語辞典一般にも通じるテーマとして議論できるのではないかという期待もありました。今回、今野先生のゼミの学生さんたちがジャパンナレッジの『日本国語大辞典』を存分に利用し、それを『大漢和辞典』や『新編日本古典文学全集』にまで裾野を広げて追究している様子を拝見しては嬉しくなり、さらにことばごとに古辞書や用例の資料を集めるための「ゴシゴシカルテ」を作るに至っては、次世代の辞典編集者もかくあるべしと思わされました[11]。
国語辞典を引いて、単にわからないことばの意味と書き方を調べて済ますのではなく、それ以上の情報が詰め込まれていることを知って味わう、つまりよく引くことがいかに面白く実り豊かなことであるかを知ることが大事なのだと思います。山田忠雄先生が西洋の諺として引かれている「その著述を最も良く利用したる者は、最大の批評者たる資格を有す」は誠にその通りで、辞典についていえば、批評者に加えて「編纂者」を添えてもいいような気がしました。実際、山田先生は『新明解国語辞典』の編集主幹をなさっていたということもありますが、辞書を単に引くだけではなく、よく引くためには辞書を批評すること、すなわち長短合わせてよく理解することが求められ、その域に達するということは、とりも直さず、よき編纂者すなわち作り手でもあり得るということがいえるのではないでしょうか。
さて、作家の井上ひさしは、世界に一冊しかない『広辞苑』を持っていたという話があります。どういうことかと言いますと、彼はことばの意味を調べたり確認したりするだけでなく、調べてもわからないことがあると、他の辞典や書籍にあたって自らその項目の余白にそれを書き込んでいたというのです。
自分は愛用する『広辞苑・第二版補訂版机上版』の余白部分に、他の辞典で見つけたすぐれた語釈や、新聞・雑誌記事からの抜粋や用語例を思いつくたび書き込んで、自分用の『私家版広辞苑』を作っている
〔井上ひさし『本の枕草紙』p128「理想の辞書」〕[12]
たとえば、(注: 広辞苑の) 531ページの「きず」という項目を見てみよう。世の中に氾濫する広辞苑には、
きず 〔傷・疵・瑕〕①切ったり打ったりして膚や肉の損ずること。また、その箇所。けが。②物のこわれ損じた所。われめ。さけめ。③不完全な所。非難すべき所。欠点。「玉に─」④転じて、恥辱。不名誉。平家11「ながき御方(みかた)の弓矢の御―にて候ふべし」
としか記載がないが、わたしのはちがう、さらに次の如き説明が付記されているのだ。
瑕(宝石の場合にこの字を用いる)
疵(物の表面にあって不完全だと思われる部分)
傷(体の表面にあって不完全だと思われる部分)
創(物や身体の表面にあって、刀や刃物で切りつけられたものに用いる)〔同上p27-28「世界に一冊しかない本」〕
引用したのは漢字表記の例ですが、これは武部良明著『漢字の用法』(角川書店)から転写しています。ほかにも、例えば「つとめ〔勤・務〕」に語源がなかったので、大野晋ほか編『岩波古語辞典』から〈ツトニ(夙)のツトと同根。早朝から事を行なう意〉を転写しており、こうして新たな情報が書き込まれた『広辞苑』はまさに世界に一冊しかない本といえるでしょう。そしてこのような作業こそが、実は、辞典編集者の日常であるともいえます。
4.節用集とインターネット
ここから連想されるのは、室町時代に写本で伝えられた「節用集」のことです。江戸時代になってからは板本が流布するようになりますが、それまでは元本を手で写していました。そのときに、余白を利用して新たに情報を書き加えるということもあったわけで、それは書き込まれた段階ではまさに『私家版節用集』ともいうべきものだったと思います。しかし、その書き加えられた情報がまた次の人に選ばれてさらに伝われば、その情報は公共性を帯びてきます。
『節用集』は「増刊を繰り返す動的なテキスト/可変箇所を内包したテキスト」で、複数の「顔」をもつ「複合体テキスト」であり、「漢字列を類聚する」という意志によって書写を繰り返されてきた
〔今野真二『『節用集』研究入門』p39-40〕[13]
江戸時代になって板本が一般になるとこのような伝わり方は少なくなり、近代以降、活版印刷が主流となるに及んで個別の書き込みは「私家版」以上のものでは無くなってしまいます。さらに時代が降ってインターネットの時代になっても、初期には企業や役所がこれまでの刊行物や案内と同じように一方向的に発信するホームページを設けるのが主流で、従来の出版文化と基本的には同じ構造でした。しかし、2000年代以降になると、Web2.0と喧伝されたデジタルの双方向性が注目され、さまざまなサービス、ブログやSNSなどが広まります。このときに生まれたユーザー参加型の百科事典Wikipediaなどを見て、使う人が作る人にもなりうる節用集的な〈増刊を繰り返す動的なテキスト〉としての国語辞典が可能になるかもしれない、とナイーブに思ったことを覚えています[14]。
5.来たるべき辞書の形を求めて
ブログやSNSの投稿とコメントのやり取りに着目するだけでも、辞典の記述を初発の投稿と見立てれば、それに思い思いのコメントを付けてもらい蓄積することは可能だろう。そうすれば来たるべきときに辞典本文に生かせるのではないかと考えました。実は「日国友の会」もそのような期待のなかで、『日本国語大辞典 第二版』(全13巻)が完結した直後の2002年に生まれたサイトでした。「友の会」では、日国本文に対して、適切な用例があれば教えてもらい、それを広範囲の読者と共有するようにしています。もちろん、『日本国語大辞典』は用例に基づく実証を編集の基本としますから、語釈を補ったり訂正したりしたいものがあればその根拠となる用例も示し、新しい項目が欲しい場合もその用例を必ず添えるという原則を設けています。
このような用例は、見つけた読者が個別に教えてくださっていたのですが、それからは直接サイトに書き込んでいただき、それを公開することによって重複は避けられ、さらにさかのぼる用例や、より適切な文献が見つかるかもしれないという期待もありました。『日本国語大辞典』の場合、用例採集という意味では、Webを活用していると言えますが、それでは、その内容を盛る本体はどのような形にすべきなのか。辞典一般に目を転じれば、今のところ紙版をもとにしたアプリが売られ、無料サイトにも有償で提供されることはありますが、まだまだデジタルだけではコストを埋められないのが実情です。仮にデジタルで改版を重ねていくとしても、どうのようにすれば持続可能な編集態勢を構築できるのか。これはもちろん技術革新とも密接にかかわる問題ですが、編集サイドの「来たるべき辞書」の当面の課題の一つであると言えるでしょう。
- [1] 大槻文彦著『言海』(1889-91)「本書編纂の大意」。
- [2] 『例解国語辞典』(中教出版)『明解国語辞典』(三省堂)を経て、『三省堂国語辞典』『岩波国語辞典』『新選国語辞典』(小学館)『新明解国語辞典』(三省堂)『明鏡国語辞典』(大修館書店)等々が、それぞれの時代における日常語の意味と用法をビビッドに捉えており、普通語・通用語の系譜を引き継いでいると考えられる。
- [3] 『ことばの泉』は落合直文著で約13万語を収める。明治31年(1898)から和装5分冊で上梓され始め、翌年に揃ったところで洋装本一冊として大倉書店から刊行された。
- [4] 『広辞林』は金沢庄三郎編で約10万語を収め、大正14年(1925)に三省堂から刊行された。同じ編者と版元による『辞林』(1907、約8万語)を増補改訂したもの。
- [5] 『辞苑』は新村出編で約16万語を収め、昭和10年(1935)に博文館から刊行された。『広辞苑』(岩波書店)はその後身。
- [6] 小学館『国語大辞典』は、『日本国語大辞典』(初版)を抄録したもので、項目数もさることながら用例も相応に残し一冊に収めて評判になった。後に、マイクロソフト社のCD-ROMブックシェルフに収められ、ワープロソフトの「Word」にもバンドルされた。小学館が満を持して刊行した中型辞典の『大辞泉』の初版は1995年だが、程なくCD-ROM版がリリースされると、他社に先駆けてさまざまな電子媒体に進出するようになった。
- [7] 『北海道新聞』1989年12月20日付け夕刊に、「一冊六、七千円する大型国語辞典の売れ行きが絶好調だ。三省堂の「大辞林」(松村明編)、講談社のカラー版「日本語大辞典」(金田一春彦ほか編)など、首都圏では入荷待ちの書店が出るほど在庫が払底し、道内の書店でも「売れない日はない」というブーム」とあり、「購読者層がこれまでの五、六十歳代中心から年齢的に平均化してきたのも最近の傾向で「一家に一冊」の時代を迎えたよう」とある。〔新聞・雑誌記事横断検索@niftyにおける初出例〕
- [8] そのことばの意味と用法、あるいは位相や歴史をわかりやすく簡潔に示すことを基本にし、類語との対比や関連語の参照を添えるなど、紙・デジタルそれぞれの特性に合わせて工夫する余地はまだまだある。
- [9] アマチュアのものであれプロのものであれ、多様な見方や知識が大量に集まることで形成されるより高度な知。集団的知性。狭義には、専門知に対して用いられることが多い。
- [10] これまでは、新語が載っているかどうかが注目され、できるだけ多く載っているほうが価値があると思われてきたが、それぞれの辞典のコンセプトに照らせば敢えて載せないという価値判断もこれからは意味を持つようになる。
- [12] 井上ひさし『本の枕草紙』(文藝春秋、1982)。1988年に文庫化されている。
- [13] 今野真二『日本語学講座第5巻 『節用集』研究入門』(清文堂出版、2012)
- [14] たとえば、糸井重里『インターネット的』(PHP新書、2001。のち加筆増補して2014年に文庫本として刊行)でも触れられていた、コンピュータソフトのとりあえずの製品(αバージョン)を無料で配って有志にバグを修正してもらうβバージョンの利便性はそれとして、それをどこでフィックスするのかという問題は残る。つまり、テキストがいつでも変更可能になり更新されるのはいいとして、それでは、何を以て完成品とするのかという問題が、これまでの出版文化そのものの再考を迫る射程を持っている。
▶︎清泉女子大学今野ゼミのみなさんが作ったジャパンナレッジ「日本国語大辞典」の使い方動画第2弾「【清泉女子大学】学びを深めるデジタルコンテンツ」が清泉女子大学の公式YouTubeチャンネルで配信中。ぜひご覧ください。
▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は6月1日(水)、新シリーズがスタートします。今野教授の担当です。
ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典
“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった
筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ
1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし
1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。
最新10件
- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える
佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?
今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?
今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」
今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』
今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?
佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?
今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?
今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義
今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される
佐藤宏 2023/09/06
『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!
会員登録をしてぜひ投稿してみてください。
『日本国語大辞典』をよむ
辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。







