前口上
- 1. 佐藤宏:いま、できることはなにか? 2019年04月03日
- 2. 今野真二:推測・憶測・妄想 2019年04月03日
いま、できることはなにか?
昨年の9月に、『『日本国語大辞典』をよむ』を三省堂から刊行された日本語学者の今野真二先生をお迎えして、往復書簡というかたちでお話をうかがうことになりました。この書は、『日本国語大辞典 第二版』(全13巻、2000-02)について初めてなされた本格的な批評の書です。実は、一昨年、三省堂のウェブサイト[1]で著書の元になった連載が始まったときに、関係者の間では因縁めいた空気を感じた人も少なくなかったと思います。というのも、『日本国語大辞典』の初版(1972-76)が刊行された際に、先生の伯父にあたる山田忠雄先生[2]が『近代国語辞書の歩み』(三省堂、1981)という浩瀚な書を著された中で批判を加えられ、それに対して松井栄一先生[3]が反論したという経緯があったからです。
もちろん、今野先生のこれまでの著書『百年前の日本語』『辞書をよむ』『辞書からみた日本語の歴史』『「言海」を読む』等々の読者であれば、先生が『日本国語大辞典』を参照しながら、バランスのとれた公平な観点から論攷を進めていらっしゃるのを熟知していたはずで、同じように客観的な目で『日本国語大辞典』が読まれたらどのようになるか、いよいよ本丸かという期待のようなものすらあったかも知れません。私自身、第二版の刊行時に編集長としてかかわり、本組みになる直前の棒組みゲラ(三校)と、責了時に曲がりなりにも通して読んだ者として、まな板の鯉であるのは致し方がないとしても、敢えて、五十音順に頭から読んでいただけるということ自体、ありがたいことだと思ったものです。
『日本国語大辞典 第二版』を通読するに際しては、1日に25ページぐらいのペースで読まれたといいます。総ページ数が約20,000ページですから、単純に計算しても800日はかかる勘定になります。それを「無謀」と思いながらも2年で読み終わると、読んでよかったという「感覚」が残った、というお話は、なによりも心に響きました。そして今、実際に2度目の通読を試みてもいらっしゃるわけですが、どのような「感覚」だったかというと、日本語のバランスがよくなったことだといいます。
〈自然な読書や自然な言語生活でふれる文献や語は案外と限られているのではないだろうか。『日本国語大辞典』は、そうした「自然な読書や自然な言語生活」でふれることのできない文献があることを教えてくれ、そうした文献を読むことを促し、そうした文献に「足跡」を残している語の存在を教えてくれるという「役割」をはたしてくれた、と思う。〉〔『『日本国語大辞典』をよむ』、p376-377〕
本書で特に面白かったのは、先生は通読しながら、折にふれてジャパンナレッジ搭載のオンライン版『日本国語大辞典』をも縦横に検索なさっていることです。そのことによって言葉と言葉の横のつながりが可視化され、用例から用例へと渡り歩き、まさに言葉の海を自在に泳ぎ回っている風でした。たとえば、全文検索で語釈に「語源未詳」とある言葉を調べてみたり、あるいは、「辞書」欄の組み合わせの傾向から、『和名類聚抄』『色葉字類抄』『類聚名義抄』『言海』に一貫した流れをよみとり、『日本国語大辞典』もその辞書の連鎖のなかにあることを跡づけてみたりするくだりは、オンライン版を利用しなければなかなか見えにくい部分でしょう。さらに、
〈『日本国語大辞典』をよみ進めていると、必要があって読んでいる文献や文学作品で、少し珍しそうな語に出会うと、「これは『日本国語大辞典』で見出しになっているだろうか」と思うようになった。さいわいなことに、オンライン版はこういう時にうってつけだ。〉〔同、p385〕
とおっしゃるわけです。著書の巻末に「『日本国語大辞典』にない見出し」227語を用例と作品名と刊行年などのデータ付きで示されたのは、まさしくその実践です。まさに我が意を得たりでした。というのも、私たちは、『日本国語大辞典』の読者が折にふれ、「これは見出しになっているだろうか」と思い、あるいは見出し項目に「用例があるだろうか」、現行のものよりも「古い例ではないか」などと思ったときに、いつでもそれを投稿できるようなサイト『日国友の会』[4]を設けていたからです。全13巻が完結した翌2002年に開設したもので、2019年1月現在で、総投稿数約13万件、うち仮に公開している用例が10万件を超えています。一部は、2005年から2006年にかけて刊行された『精選版 日本国語大辞典』(全三巻)に反映されましたが、以後、第三版に向けて運営を続けています。
さて、今野先生に初めてお目にかかったのは、昨年の11月に「語彙・辞書研究会」に登壇されたときでした。ネットアドバンスの方も何人か居合わせて話が弾み、12月にはこの「来たるべき辞書のために」というタイトルの連載が企画されたのでした。タイトル名は今野先生のご提案でしたが、第三版への期待が込められていると同時に、フランスの文芸批評家、モーリス・ブランショの『来(きた)るべき書物』を踏まえているようにも思えました[5]。それ自体としては未だ存在しているわけではないが、それを志向するときにのみ存在する書物といったような意味合いでしょうか。『日本国語大辞典 第二版』の「あとがき」にはこうありました。
〈第三版がどのような媒体で実現するかは全く予想がつかない。しかし、いかなる媒体によるにせよ、大型の国語辞典の性質が、ある時期までの国語の集大成であり、その後数十年のことばのパラダイムを提供することにあるとすれば、書籍版と同じように時間をかけた語彙と用例の採集、電子化をふまえた、より正確で体系的な語義・用法の説明、さらに従来にも増して地道かつ綿密な検証作業等が求められることに変わりはない。〉〔『日本国語大辞典 第二版』第13巻、p1420-21〕
そのために、今できることは何か。増殖し続ける各種データベースともリンクが可能になったこの時代において、あり得べき「国語辞書」とは何かを、一緒に考えさせていただきます。先生には、今回は初版も視野に入れながら、引き続き『日本国語大辞典 第二版』の分析を深めていただき、書簡による質疑応答を通じて、『日本国語大辞典』の仕組みをできるだけ明るみに出し、使い方だけではなく作り方についても考えをめぐらせて、その可能性の中心を探りたいと思います。次世代の編集者に引き継げるような分かりやすい内容をめざし、結果、第三版へ向けて生産的な議論になればこれに勝る喜びはありません。
- [1] “Word-Wise Web”「ことばのコラム」
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column - [2] 国語学者。三省堂『新明解国語辞典』の編集主幹を務めた。国語学者の山田孝雄は父、山田俊雄は弟。(1916-1996)
- [3] 国語学者。小学館『日本国語大辞典』の初版と第二版の編集委員を務めた。『大日本国語辞典』の編者・松井簡治の孫。(1926-2018)
- [4] 『日本国語大辞典』の用例投稿サイト。
https://japanknowledge.com/tomonokai/ - [5] 「作品とは作品に対する期待である。この期待のなかにのみ、言語という本来的空間を手段とし場所とする非人称的な注意が集中するのだ。『骰子一擲』は、来るべき書物である。」〔モーリス・ブランショ著/粟津則雄訳『来るべき書物』ちくま学芸文庫2013、p496〕
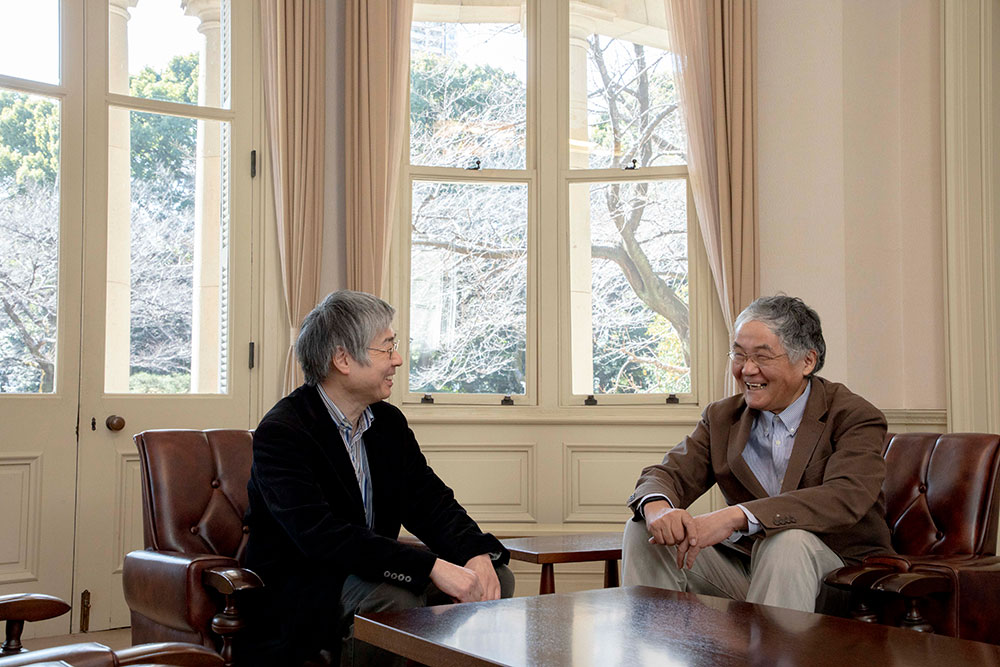
推測・憶測・妄想
2018年11月10日に新宿NSビル3階で開催された第54回の語彙・辞書研究会の研究発表会は「近代辞書の歩みとこれから―明治150年の辞書世界―」というタイトルのシンポジウムだった。そのシンポジウムで筆者が「『日本国語大辞典』と明治の辞書」というタイトルで話をしたことが今回の往復書簡のきっかけとなった。
筆者が「『日本国語大辞典』と明治の辞書」というタイトルで話をしたことには少し「経緯」のようなものがあった。初めに発表をしないかとお話をいただいた時に、教え子である小野春菜さんとの共著『言海の研究』(2018年、武蔵野書院)が出版されたばかりであったことから、『言海』について話したいと打診したところ、『言海』についてはすでに発表者が決まっているということだった。他にもう一つ打診したのだが、結局それも実現せず、筆者側から、それではこういうのはどうでしょう、と提案したのが「『日本国語大辞典』と明治の辞書」だった。
なぜ、そういうタイトルを提案したかといえば、話は『辞書をよむ』(2014年、平凡社新書)まで遡る。詳しくはこの本を読んでいただきたいが、この本の終章で「平安時代に成立した『和名類聚抄』が日本の辞書に大きな影響を与えてきた。そしてそのことに現代の辞書編集者はあまり気づいていないかもしれないが、結果として、現代の辞書も何らかのかたちで『和名類聚抄』の影響を受けている」(180~181ページ)と述べた。それが、辞書には「具体的な系譜的なつながり」の他に、「少し大きな系譜的なつながり」もある、ということを(事実として)確認し、自身の「感覚」としてはっきりと感じることができた初めての時であったといってよいだろう。「自身の「感覚」」というと、「感じかあ」と受けとられやすいが、この「自身の「感覚」」はもう少し「自身の認識」にちかい。
さて、話を戻せば、佐藤宏さんもふれてくださっているが、筆者は『『日本国語大辞典』をよむ』(2018年、三省堂)という本を出版していただいた。書名をあらわす二重鉤括弧がついている書名で、引用すると二重鉤括弧の中に二重鉤括弧が入ることになってしまう。ちなみにいえば、「読む」ではなく「よむ」という書き方を選んだのは、通常の本を読むという場合の「ヨム」よりも、『日本国語大辞典』に埋め込まれている「情報」をくまなくよむということで、「よむ」とした。こういうところにもどちらかといえば、気を使う。「X駅からだったら、こっちのパン屋さんのほうが近い」という時は具体的な距離だから「近い」と書く。「Pさんの考え方はQさんよりもむしろRさんにちかい」という時は、抽象的な意味合いでの「距離」だから「ちかい」と書く、というような感じだ。しかし原稿に「近い」と「ちかい」が混在しているから、どちらかに統一してくださいと出版社から言われることが多い。黙って赤字が入ることもある。あるいは両方使うなら「基準」を示してくれと言われる。「基準」は上に述べたようなことであるが、まあどちらともいえないような場合もないではない。それを「不統一」とみるか、そのくらい「許容」するか、「そもそも気にしない」か。
言語に関しては、その言語を使っている人々の間で共有されていることがらがある。その一方で、共有されていないこともある。だから実際に使用されている言語をある観点から観察すると、すべてが同じ方向に動いているようにはみえない。それを「例外」と名づけるかどうか、そこはまた考える必要がありそうだが、とにかくそういうものだ。
だいぶ寄り道をしたので、「『日本国語大辞典』と明治の辞書」の話に戻ろう。『和名類聚抄』が影響力の強い辞書だということはわかってきた。同じように『言海』も『言海』以降に編まれた辞書については影響力がありそうだ、というのが次に得た「感覚」だった。『日本国語大辞典』初版には「古辞書」欄があったが、第二版ではそれを「辞書」欄として、17世紀初頭の『日葡辞書』、明治期の『和英語林集成(再版)』と『言海』とを加えている。明治期の辞書が加わったことによって、歴史的展開についての概観がしやすくなった。『言海』を分析するようになってからは、この「辞書」欄に『言海』が入っているかどうかが気になるようになった。そして、『日本国語大辞典』全巻をよみ始めてからは、見出しの用例と「辞書」欄と両方に目がいくようになってきた。そしてオンライン版を使って検索をよくするようになった。そうしているうちに、中国の文献に使用されている漢語で、江戸時代までの文献での使用例が示されておらず、明治期に刊行された漢語辞書では見出しになっている語があることに気づいた。「これはなんなんだろう」と思った。中国の文献で使用されているのだから、奈良時代ではなくてもいずれかの時代に日本語の中に入ってきて、日本語の語彙体系内で使われていてもよさそうなのに、そうした使用が(少なくとも)『日本国語大辞典』では確認できず、しかし明治期に刊行された漢語辞書では見出しになっている。
それがどういうことなのか、という問いについてのはっきりとした答えはまだ出ていない。シンポジウムの時もそういう話をした。そのシンポジウムを佐藤宏さんや小学館で『日本国語大辞典』の編集に関わった方々、『日本国語大辞典』のオンライン版に関わっている方々がきいてくださり、そこからこの「往復書簡」連載の話が進んでいったことは、佐藤宏さんの「前口上」に記されているとおりだ。
『『日本国語大辞典』をよむ』は三省堂から出版されている。辞書を扱う三省堂は小学館から出版されている『日本国語大辞典』についての書物を出版するにあたって、細心の注意を払ってくれた。筆者もそうしたことを強く感じたので、表現などにはできるだけ気を配った。しかし、この「往復書簡」は『日本国語大辞典』第2版の編集長であった佐藤宏さんとの「往復書簡」であり、ジャパンナレッジのサイトに掲載される。戦争では人の命が奪われる。それは人としてはもっとも避けなければならないことの一つだろう。だから戦争にかかわる比喩表現はできるだけ使わないようにしているが、ちょっとだけ使わせていただくとすれば、今回はいわば一人で「本丸」に切り込むといった体だ。あまり分がいいとはいえない。軽く「討ち死に」ということになるかもしれない。それでも、この「往復書簡」の企画が成立したということには大きな意義がある。この「往復書簡」がどれだけ続くかわからない。先日佐藤宏さんとお話した時は即座に「死ぬまでやるよ」とおっしゃった。筆者も即座に「私もやりますよ」と応じた。それはもちろんわからないけれども、筆者も佐藤宏さんもいわば「本気」だ。このあたりは「(笑)」をつけてぼかしておくところかもしれないが、とにかく「本気」だ。そしてこういう企画である以上、「蟷螂の斧」にしても「隆車」(りゅうしゃ:立派な車)に立ち向かっていかなければならない。だから噛みつくのが筆者の役目だと心得ている。『日本国語大辞典』にはファンが多い。そういう方は、「何をしょうもない細かいことをカマキリごときがごちゃごちゃと言っているのだ」と思われるかもしれないが、それは『日本国語大辞典』の次の版のため、そしてひいては、「来たるべき辞書」のためと思って、どうか寛容な気持ちでお読みいただければと思う。
筆者が述べていることは「しょうもないこと」かもしれない。しかし、その「しょうもないこと」にも筆者の中では「段階」がある。おおまかにいえば、そう述べるにあたって、「ある程度根拠があること」、「根拠を示すことはできないけれども、筆者のこれまでの感覚からすればそう感じること」、「思い切って突飛なこと」という三段階だ。実際はこの三つの間ということもあるが、まずはこんなところだ。これを「~と推測する」「~と憶測している」「これは妄想だが」というような表現と結びつけている。これまで書いてきたものでもおおよそそういう感じで「推測・憶測・妄想」という表現を使っている。読者の方々もそのあたりをちょっと頭の片隅にでも入れておいていただき、「またカマキリが妄想を語っているな」というように流していただければさいわいだ。もちろん基本的にはきちんとした「筋」を通して述べていくつもりだが、言語にかかわる話は「ああでもない、こうでもない」となることが多い。つまりつきつめていくと辛気くさくなる。そういう時に気分転換に思い切った「妄想」を語る、ということだ。『日本国語大辞典』の「次の版」のために、そして「来たるべき辞書」のために、「本気で」しかし「楽しく」語り合うという「往復書簡」にしていきたい。佐藤宏さん、どうぞお手柔らかにお願いします。
ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典
“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった
筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ
1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし
1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。
最新10件
- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える
佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?
今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?
今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」
今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』
今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?
佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?
今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?
今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義
今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される
佐藤宏 2023/09/06
『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!
会員登録をしてぜひ投稿してみてください。
『日本国語大辞典』をよむ
辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。







