景気とは、経済活動の多くの分野(生産、雇用、価格など)が同じように上昇したり、下降したりする動向・現象をさすが、この景気の波をとらえるために、内閣府が毎月算出し、公表しているのが景気動向指数である。景気の波そのものを表すため現状把握に利用できる「一致指数」、一致指数を先読みするための「先行指数」、景気の広がりを事後に確認するための「遅行指数」の3種類が存在する。現行では、一致指数は生産指数(鉱工業)、鉱工業用生産財出荷指数、耐久消費財出荷指数、輸出数量指数など10系列、先行指数は最終需要財在庫率指数、鉱工業用生産財在庫率指数、新規求人数(除く学卒)など11系列、遅行指数は第3次産業活動指数(対事業所サービス業)、常用雇用指数(調査産業計)など9系列の経済データを合成している。
合成の方法としては、CI(コンポジット・インデックスcomposite index)、DI(ディフュージョン・インデックスdiffusion index)の2種類が存在する。日本を含めて多くの国ではCIを基本とし、DIを参考指標として示している。
CIでは、各データの量的な大きさを統合しているため、算出方法は複雑である。まずは以下の式で対称変化率を算出する。
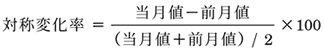
次に、対称変化率の四分位範囲(過去上位25%の値から下位25%の値を差し引いたもの)を算出するとともに、対称変化率のトレンド(当月を含む過去60か月間を平均したもの)を求める。そのうえで、下記の式で基準化変化率を算出する。
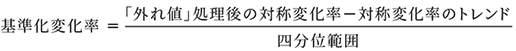
以上のように、各データの対称変化率を過去の平均的な動きと比較した変動の大きさ(量感)にそろえ、合成している。
CIが上昇しているときには、景気は拡張局面、下降しているときは後退局面と考えられる。なお、基準化変化率の算出過程では、異常値(外れ値(はずれち))を取り除く作業も行うが、それによる弊害もあるため、内閣府では外れ値処理を行ったものと、行っていないものの2系列のCIを算出・公表している。
一方、DIの算出方法はシンプルである。各採用系列について3か月前の値と比較して上昇(景気がよくなると統計数字が低下する逆サイクル系列の場合は下降)した拡張系列の数を採用全系列の数で割って100倍する。この際、系列指標が3か月前の数字と変わらなかった系列については分子の数に0.5の値を入れて計算する。DIは0~100の値をとり、50を超えているときは景気拡張局面と判断する。
日本の景気動向指数は1960年(昭和35)8月から算出が始まった。当時は、一致指数と先行指数は7、遅行指数は6の経済データが算出に用いられた。そこから、経済構造の変化を反映して採用系列の改定は2021年(令和3)までに13回行われたが、一致指数のなかで一貫して使用されてきたのは生産指数(鉱工業。ただし1965年までは製造業)のみである。近年の動きとしては、2020年6月分(2020年8月公表)から一致指数に輸出数量指数が追加され、2021年1月分(2021年3月公表)からは、従来、一致指数に採用されていた所定外労働時間指数(調査産業計)が労働投入量指数(調査産業計)に、先行指数に採用されていた消費者態度指数(総世帯、原数値)が消費者態度指数(2人以上世帯、季節調整値)に変更されるなどした。なお、労働投入量指数(調査産業計)は、総実労働時間指数(調査産業計、事業所規模30人以上)に雇用者数(非農林業)を乗じて算出している。
経済データの変動を合成する方法は長らくDI中心であったが、2008年(平成20)4月からCI中心に移行した。諸外国がCI中心であることや、景気変動の大きさやテンポを測定できるためである。
また、2011年には、「外れ値」の処理について改善するとともに、「外れ値」処理を行わないCIの公表も始めた。従来の「外れ値」処理の手法では、世界金融危機や東日本大震災のようなマクロショックが発生し、多くの系列にその影響が同時に発現する場合でも、こうした「共通循環変動」を「外れ値」と認識し、結果的に景気変動を過小評価してしまう問題があったためである。新しい手法では、系列の変動を個別のデータの変動と共通変動に分け、個別のデータの変動のみを「外れ値」処理の対象とした。
なお、経済の動向を一つの数字で把握する景気指数の作成作業は、第二次世界大戦前にアメリカで開発されたハーバード景気指数とよばれるものが最初とされている。DI、CIとも戦後まもなく開発された計算手法である。このため、新しい景気動向指数の算出方法も模索が始まっている。たとえば、数百といった数多くの統計データの共通変動成分を統計的な手法で取り出すことなどである。
内閣府は2022年8月から「景気を把握する新しい指数(一致指数)」を参考指標として公表を開始した。従来の景気動向指数の一致指数が製造業中心であるとの批判を踏まえ、非製造業のデータも加えて算出されている。具体的には、鉱工業生産指数(最終需要財)、建設出来高(民間及び公共)など財関連の9指標と、第3次産業活動指数(広義対個人サービス)、無形固定資産(ソフトウエア投資)などサービス関連の8指標の合計17指標を合成している。ただし、この指標に対しては景気指数の専門家から、現行の景気動向指数の一致指数に比べ、相対的に振幅が小さく、今後、景気の転換点が明瞭(めいりょう)にならない局面が出てくる懸念があるなどの問題点も指摘されている。