シリーズ 12 「「歴史的仮名遣い」をどう扱うべきか? 」目次
- 1. 今野真二:方言に歴史的仮名遣いは必要? 2021年03月03日
- 2. 今野真二:[あはれっ‥]でいいのか? 2021年03月17日
- 3. 今野真二:漢語の歴史的仮名遣いについて 2021年04月07日
- 4. 佐藤宏:歴史的仮名遣いと辞典の形式 2021年04月21日
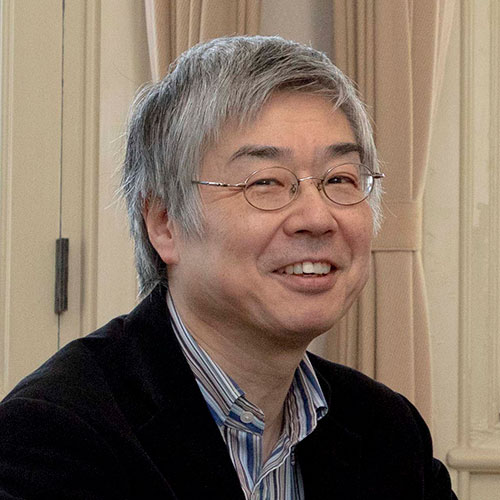
「歴史的仮名遣い」をどう扱うべきか?
Series12-1
方言に歴史的仮名遣いは必要?
「歴史的仮名遣い」を正確に説明することもなかなか難しいし、筆者としては、「古典かなづかい」という概念を認め、「古典かなづかい」と「歴史的仮名遣い」とを区別して話を進めたいが、かえって話がややこしくなるという懸念もあるので、今ここでは措く。機会があれば、改めて採りあげるということにしたい。よろしければ、拙書『かなづかいの歴史』(中公新書、2014年)をご参照ください。
さて、『日本国語大辞典』の「凡例」の「編集方針」の「歴史的仮名遣いについて」は1~6の箇条書きとなっている。今回の話題にかかわる条のみをあげてみよう。
1 歴史的仮名遣いが見出しの仮名遣いと異なるものについては、見出しのあとの[ ]の中に、その歴史的仮名遣いを示す。
4 和語はひらがな、漢語(字音語)はかたかなで示す。ただし、その区別の決めにくい語のうち、漢字の慣用的表記のあるものは、その漢字の歴史的仮名遣いに従う場合もある。
5 字音語のうち、音変化をきたして今日のかたちになっている語、「観音(クヮンオン→クヮンノン→カンノン)」の類、「天皇(テンワウ→テンノウ)」の類、および、「学校(ガクカウ→ガッコウ)」の類は、便宜上それぞれもとのかたちの「クヮンオン・テンワウ・ガクカウ」を、歴史的仮名遣いとして示す。
6 方言・固有名詞などでは、歴史的仮名遣いの注記を省略するものもある。
6について筆者がまず気にするのは「省略するものもある」という文言で、ということは「省略しないものもある」はずで、どういう場合には省略し、どういう場合には省略しないのかということを知りたくなる。そのことが気になる。
「『歴史的仮名遣い』を正確に説明すること」は難しいと述べたが、どういう概念としてとらえるか、ということだ。「かなづかい」は「かなづかい」というくらいだから、「仮名の使い方」にかかわる概念であることはいうまでもない。つまり、ある語を仮名だけで文字化する、あるいは漢字と仮名とで文字化する場合にのみ「かなづかい」を考える必要がある。もっとも「どう書いてもいい」と開き直ってしまえば、「かなづかい」を考える必要はなくなる。「タマウ(給)」と発音している語を全部仮名で書く時に「たまふ」と書くのか「たまう」と書くのかということが「かなづかい」であるし、漢字も使って書く時に「給ふ」と書くのか「給う」と書くのかということが「かなづかい」である。漢字一字で「給」と書けば「かなづかい」を考える必要はなくなる。
「かなづかい」ということの根柢には、日本語の音韻変化の結果、かつて存在していた音韻(音素)がなくなるということがある。「イ」という発音があり、「ヰ」という発音があった。しかし「ヰ」という発音がなくなって「イ」のみになったという時に、かつて「ヰ」という発音に対応していた仮名「ゐ・ヰ」をどうするか、ということが「かなづかい」の根柢にある。音韻(音素)がなくなったのだから、それに対応していた仮名を使うのをやめましょう、ということにすれば、「かなづかい」を考える必要がなくなる。音韻(音素)が減るたびに、使う仮名も減らしていけば、つねに音韻(音素)と仮名とが1対1(にちかい)対応状態を保つことになる。音韻(音素)と仮名とが1対1の対応をしているのであれば、表音的に書けばよい。
現代日本語でいえば、仮名「を/ヲ」にかつて対応していた発音[wo]は使わない。だから、仮名「を/ヲ」を使うのをやめて、[o]と発音するところにはすべて「お/オ」を書くことにすることもできる。しかし、そうはしないで、(原則としては)助詞の「ヲ」に限って、仮名の「を/ヲ」を使うことにしている。これは「かつてそう書いていた」ということにかかわる。「かなづかい」は「かつてどう書いていたか」を顧慮するという「心性」によって支えられている面が確実にある。いろいろと音韻変化した後の「今」ではなく、そういう音韻変化が起こる前の「かつて」はどう書いていたのか。その時のように書きたい、という「心性」といってもよいかもしれない。音韻変化を「乱れ」のようにとらえると、音韻変化前は「乱れていない頃」ということになり、それを「正しい」とか「あるべき姿」ととらえることもあるだろう。契沖の著した『和字正濫鈔(わじしょうらんしょう)』は「歴史的仮名遣い」を前面に打ち出した「かなづかい書」と考えられ、説明されることが多いが、「かつての日本語の文字化」「日本語のそもそものかたち」を探り求めた結果を示した書とみることもできる、と考える。そうだとすると、『和字正濫鈔』は単なる「かなづかい書」ではないことになる。
そこで、やっと6であるが、「方言」が「はなしことば」に限られるということではないだろうが、それでもどちらかといえば「はなしことば」であろう。とすると、「方言」が文字化されることは「書きことば」に比べればかなり少ないはずだ。つまり「方言」は「仮名書きされた経験」があまりない。その「方言」の「歴史的仮名遣い」を探ることはそもそも難しいだろう。固有名詞に関していえば、人名、地名などは(仮名で書かれることもある、仮名書きの人名・地名もあるけれども)多くは漢字で書かれてきただろう。そうなるとこれまた「仮名書きされた経験」が乏しいということになる。
筆者の結論としては、方言・固有名詞には「歴史的仮名遣い」を示さないということでいいのではないかということだ。1・4・5については次回の後編で述べることにしよう。
▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は3月17日(水)、今野真二さんの担当です。
ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典
“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった
筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ
1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし
1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。
最新10件
- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える
佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?
今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?
今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」
今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』
今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?
佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?
今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?
今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義
今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される
佐藤宏 2023/09/06
『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!
会員登録をしてぜひ投稿してみてください。
『日本国語大辞典』をよむ
辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。







