シリーズ 11 「「栽培品種」というメタ言語 」目次
- 1. 今野真二:アマザクロは甘いと言い切れるのか? 2021年01月06日
- 2. 今野真二:なぜ「栽培品種」が見出し語にならないのか? 2021年01月20日
- 3. 今野真二:遠隔授業だからこそ見えた辞書のこれから 2021年02月03日
- 4. 佐藤宏:「日本語の言語宇宙」と百科語 2021年02月17日
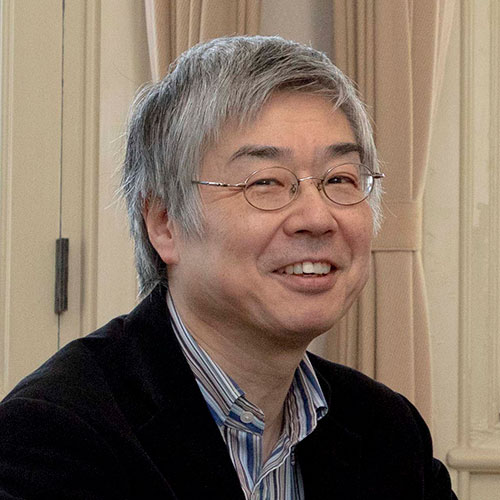
「栽培品種」というメタ言語
Series11-2
なぜ「栽培品種」が見出し語にならないのか?
前回は語釈に使われている「栽培品種」という語をきっかけとして、「日本語の言語宇宙にある語」と「現実世界にあるモノ」とについて考えてみた。『日本国語大辞典』の語釈中で、両者がはっきりと区別されていない場合がないだろうか、という問題提起だ。
もちろん両者は基本的に区別されていると思うし、そもそも両者は一体化することもある。それでもなお、両者をはっきりと区別することによって、得られることは少なくないと思う。
さて、再度、ジャパンナレッジで「栽培品種」に検索をしてみよう。「全文(見出し+本文)」に検索をかけると、233件がヒットする。この中に見出し「栽培品種」が含まれているだろうと思っていたが、それは……なかった。つまり『日本国語大辞典』は語釈中で、200回以上使用している「栽培品種」という語を見出しにしていない。『日本国語大辞典』が「栽培品種」という語をどのような定義で使っているかが、『日本国語大辞典』では確認できないことになる。
明治24(1891)年に印刷出版を終えた『言海』は、「凡例」の(五十四)において「凡ソ、此篇中ノ文章ニ見ハレタル程ノ語ハ、即チ、此辞書ニテ引キ得ルヤウナラデハ不都合ナリ、因テ、務メテ其等ノ脱漏齟齬ナキヤウニハシタリ、然レトモ、凡ソ万有ノ言語ノ、此篇ニ漏レタルモ、固ヨリ多カラム」と述べ、『言海』内で使われた語を務めて見出しにしたことを述べるが、それも徹底しなかったことを反省的に記している。
辞書内で使われているすべての語を見出しにすることは辞書がバランスのとれた「小宇宙」であることの具現といってよい。そこには語と語とのつながりが完全なかたちで提示されていることになる。こう述べると、そうなっていない辞書は完全ではない、と述べているように聞こえてしまうかもしれないが、こうした意味合いでの「完全なかたち」は理想形ではあろうが、実現が難しいことも容易に想像できる。だから、それを求めているわけではない。
しかし、その一方で、200回以上語釈で使っている「メタ言語」(言語を説明するための言語)については、できれば見出しにして、こういう語義であるいは定義で、「栽培品種」という語を使っているということを示してあると親切ではないだろうか。
「栽培品種」は「栽培」であるから、植物に関しての用語ということになる。筆者が「栽培品種」に注目するのは、植物(生物)という具体的な(いわば)モノを分類するということは、言語のありかたと深くかかわると思うからに他ならない。言語によってモノを分類するのだから、それは当然といえようが、分類学的観点によって斉整と分類されている生物のありかたをきちんと辞書内にとりこむことによって、言語のありかたがうかびあがってくるのではないだろうか。「界・門・綱・目・科・属・種」という分類を使うと、「インゲンマメ」は「植物界」「マメ目」「マメ科」「インゲンマメ属」の「インゲンマメ」という「種」ということになる。「門」「綱」は「階級なし」。この場合は、言語側では「マメ」と「インゲンマメ」しか使われていないが、「ミヤマクワガタ」だと違う。
「ミヤマクワガタ」は「動物界」「節足動物門」「昆虫綱」「甲虫目」「カブトムシ亜目」「コガネムシ上科」「クワガタムシ科」「クワガタムシ亜科」「ミヤマクワガタ属」の「ミヤマクワガタ」という「種」である。この場合は、「動物」の中に「節足動物」がいて、その中に「昆虫」がいて、その「昆虫」の中に「甲虫」がいて、「甲虫」の中に「カブトムシ」がいて、その中に「コガネムシ」「クワガタムシ」がいて、「クワガタムシ」の中に「ミヤマクワガタ」がいるという「階層」がはっきりとわかる。
言語においては、「連合関係」のような、語同士のつながりが大事であるが、語同士は「横につながっている」だけではなく、「階層」をもって「縦にもつながっている」。「上位語(hyperonym)」「下位語(hyponym)」と呼ばれることもある。
『広辞苑』も「栽培品種」を見出しにしていない。調べてみると、「栽培品種」は「分類階級」や「タクソン」=分類群ではなく、学名とは結びつかないということで、つまりは定義がしにくそうに思われる。このあたりが見出しになっていない理由であろうか。
きんときまめ【金時豆】
〔名〕
インゲンマメの栽培品種。豆は赤紫色で、甘納豆、煮豆に用いられる。金時。
うずらまめ【鶉豆】
〔名〕
インゲンマメの栽培品種。晩生つる性。花は桃色。さやは淡緑色に褐色の斑点がある。種子に、淡褐色地に赤褐色の斑点があるので、この名がある。煮豆、甘納豆などに用いる。うずらいんげん。
*大和本草〔1709〕四「大豆〈略〉うづら豆。黒大豆より少大にして円し。まはりは黒くして両方にうづらの文あり」
前回の末尾で、「「日本語の言語宇宙」に存在している語と、「現実世界」にある「具体的なモノ」とが、『日本国語大辞典』の見出し中で「同居」していないだろうか」と述べた。それには、まずは両者の違いをはっきりさせることで、「言語」の記述をより徹底できないだろうか、という気持ちがあった。
「うずらまめ」には「種子に、淡褐色地に赤褐色の斑点がある」とある。欲をいえば、「うずらのように」が入っているとさらによい。「きんときまめ」の語釈には「赤紫色」の豆を「金時」と名づけている(文化的な)理由が記されていない。これはもちろん坂田公時(金時)の赤ら顔に由来しているわけだが、それこそが「国語辞典」が記述することではないだろうか。「キントキマメ」は「kidney beans」であるが、英語では形に注目した命名(kidneyは「腎臓」)であることになり、言語文化の違いがより明確になってくる。
▶「来たるべき辞書のために」は月2回(第1、3水曜日)の更新です。次回は2月3日(水)、今野真二さんの担当です。
ジャパンナレッジの「日国」の使い方を今野ゼミの学生たちが【動画】で配信中!

日本国語大辞典
“国語辞典の最高峰”といわれる、国語辞典のうちでも収録語数および用例数が最も多く、ことばの意味・用法等の解説も詳細な総合辞典。1972年~76年に刊行した初版は45万項目、75万用例で、日本語研究には欠かせないものに。そして初版の企画以来40年を経た2000年~02年には第二版が刊行。50万項目、100万用例を収録した大改訂版となった
筆者プロフィール

今野真二こんの・しんじ
1958年、神奈川県生まれ。早稲田大学大学院博士課程後期退学。清泉女子大学教授。専攻は日本語学。『仮名表記論攷』(清文堂出版)で第30回金田一京助博士記念賞受賞。著書は『辞書をよむ』(平凡社新書)、『百年前の日本語』(岩波新書)、『図説 日本語の歴史』(河出書房新社)、『かなづかいの歴史』(中公新書)、『振仮名の歴史』(集英社新書)、『「言海」を読む』(角川選書)など多数。

佐藤 宏さとう・ひろし
1953年、宮城県生まれ。東北大学文学部卒業。小学館に入社後、尚学図書の国語教科書編集部を経て辞書編集部に移り、『現代国語例解辞典』『現代漢語例解辞典』『色の手帖』『文様の手帖』などを手がける。1990年から日本国語大辞典の改訂作業に専念。『日本国語大辞典第二版』の編集長。元小学館取締役。
最新10件
- 慣用的な漢字表記 :国語辞書の漢字欄の役割について考える
佐藤宏 2024/02/07 - 慣用的な漢字表記 :「慣用的」とは何か?
今野真二 2024/01/17 - 慣用的な漢字表記 :いつから「天晴」なのか?
今野真二 2023/12/20 - 慣用的な漢字表記 :「熱灰」と「煨」
今野真二 2023/12/06 - 特別篇:中村正直と『西国立志編』
今野真二 2023/11/15 - 漢語をめぐって:漢語は「泥沼」か?
佐藤宏 2023/11/01 - 漢語をめぐって:情報強化で得られる「気づき」とは?
今野真二 2023/10/18 - 漢語をめぐって:漢語なのか、漢語風なのか?
今野真二 2023/10/04 - 漢語をめぐって:漢語に注目することの意義
今野真二 2023/09/20 - 使用例:日本国語大辞典は用例によって作られ、用例によって訂正される
佐藤宏 2023/09/06
『日国』に未収録の用例・新項目を募集中!
会員登録をしてぜひ投稿してみてください。
『日本国語大辞典』をよむ
辞書・日本語のすぐれた著書を刊行する著者が、日本最大の国語辞典『日本国語大辞典第二版』全13巻を巻頭から巻末まで精読。この巨大辞典の解剖学的な分析、辞書や日本語の様々な話題や批評を展開。







