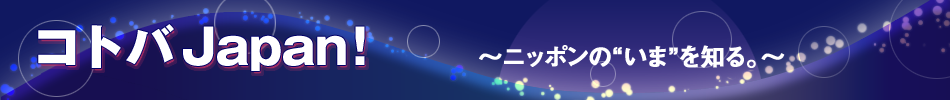何のために解散したのかほとんどの国民が理解できなかった衆議院選挙があっという間に終わった。予想通りだったのは自民党が勝つということと投票率の低さだ。50%を少し超えた
戦後最低の投票率。国民の半数近くを無関心にさせた責任はひとえに安倍首相にあるといっていいはずだ。
『週刊ポスト』(12/19号、以下『ポスト』)は選挙前から「総選挙の終盤情勢はどうやら自民党の『不戦勝』の様相を見せてきた」と報じていた。
『ポスト』は、この選挙を何が何でも勝つために安倍自民党はメディア、特にテレビを規制し、いつもなら党首が出席して質問に答える「外国特派員協会」にも嫌がって出席しなかったのは、
安倍首相の器の小ささだと難じているが、その通りである。
「官邸はメディアに圧力をかけて政権批判を封じて選挙をつまらなくし、メディアはその片棒を担いだ。
その工作の第一弾が『萩生田(はぎうだ)文書』である。衆院解散前日(11月20日)、安倍首相の側近中の側近で、『親衛隊長』の異名をとる萩生田光一・自民党総裁特別補佐が在京民放キー局の自民党記者クラブキャップを個別に呼び出し、各局の『編成局長』『報道局長』に宛てた文書を手渡した。
受け取ったキー局側は、そうした報道圧力を受けたことをひた隠しにして、文書の存在を自ら明らかにしようとはしなかった。
『選挙時期における報道の公平中立ならびに公正の確保についてのお願い』と題するその文書は、
〈衆議院選挙は短期間であり、報道の内容が選挙の帰趨に大きく影響しかねない〉
と警告したうえで、具体的に〈出演者の発言回数〉〈ゲスト等出演者の選定〉に注文をつけ、さらに〈特定政党出演者への意見の集中がないよう〉〈街角インタビュー、資料映像等で一方的な意見に偏る、あるいは特定の政治的立場が強調されることのないよう〉と細かく指示して〈特段の配慮〉を求めている」(『ポスト』)
何が何でも安倍批判は許さないという恫喝(どうかつ)である。だが情けないことに政府に「放送免許」という生殺与奪の権を握られているテレビ局は、ひたすら
恭順の意を見せ土下座してしまうのである。
政治ジャーナリストの鈴木哲夫氏がこう批判する。
「これまでもテレビ局に対して『公平中立な報道を』という要請はあったが、ここまで細かい注文をつけるのは異例です。
公平中立な報道かどうかはメディアが自主的に判断すべきで、そのために放送倫理・番組向上機構という組織がある。権力側、それも一政治団体でしかない自民党が公平中立の中身をどうだと決めるのはおかしい。テレビ局側も
一意見として処理すればいいだけの話です」
案の定、この文書の効力が表面化したのだ。テレビ朝日「朝まで生テレビ!」(11月29日放送)のゲスト出演拒否事件が起きた。
選挙をテーマに討論するはずだったが、当局は出演予定だった評論家の荻上(おぎうえ)チキ氏と小島慶子氏らのゲストに「質問が特定の党に偏る可能性などがある」と伝えてキャンセルしてしまったのだ。
「言論を封殺した安倍親衛隊の行動は
民主主義の否定であり、権力の圧力に屈したテレビ局も
国民を裏切ったことになる」(同)
安倍首相は批判を封じておきながら各局に単独出演して「アベノミクスで賃金は上がっている」と嘘を並べ自己アピールに努めたが、萩生田文書に従うなら、各局は
他党の党首も同じだけ出演させなければならないはずではないか。自分の主張だけ言いたい放題で、批判は封じ込めるのでは「言論ファッショ」だと『ポスト』が指弾するが、まったくその通りである。
なぜなら安倍首相がいかに雇用と賃金が上昇して経済がいい循環になってきたと力説しようと、経済指標は7~9月期のGDP速報値が年率マイナス1.6%と2期連続で大きく落ち込み、景気上昇を「実感していない」が84.2%(共同通信調査)に達しているからだ。
アベノミクスの破綻は今や国民の多くが知っている。
なり振り構わず言論を封殺し、アベノミクスがバラ色の未来をもたらすと言い募るのは、この選挙に勝って、安倍の悲願である
「憲法改正」をやりたいからである。
選挙動向に詳しい政治ジャーナリストの野上忠興(ただおき)氏がこう指摘する。
「前回総選挙の自民党の総得票数(小選挙区)は約2560万票。全有権者のわずか4分の1の票で294議席を得た。今回、投票率がさらに10ポイント程度下がれば、たとえ国民の8割がアベノミクス失敗と思っていても、2割程度の自民党支持層が投票すれば大勝という現象が起きます」
事実、安倍の思惑通りそうなってしまった。
安倍首相の言論統制はそれだけではない。彼の
フェイスブック(FB)でも同様のことが行なわれているというのだ。
「衆院解散後、〈特定秘密保護法、集団的自衛権、原発、派遣法につき、安倍さんは間違っていると思う〉〈選挙の争点は有権者である国民が決める〉という内容の書き込みをしたある有権者は、突然、書き込みが
ブロックされた。
別の有権者は、FBのコメント欄のヘイトスピーチについて指摘したところ、その後、『あなたには閲覧する権限がないため、表示できません』と表示され書き込みも閲覧もできなくなった。一方の
ヘイトスピーチは削除されずに残っている。
首相のFBは国民(外国人も)が直接、トップに意見を伝えることができる『目安箱』といえる。批判の声があれば正対するのが『首相の器』だろう。
それを自分に都合がいい意見に酔い、批判を門前払いするやり方はこの政治家の器の小ささだけでなく、危険な暴君になりつつあることを物語っている」(同)
今週は、私が言いたいことを『ポスト』がみな言ってくれている。何も付け加えることはない。
安倍のやり方は北朝鮮や中国の一党独裁政権がやっていることと同じではないか。
さらに自民党側は投票日前に外国特派員協会の会見には出ないと拒否していたのだ。フランスの通信社AFPは
「厳しい質問におじけづいたとの批判に火が付いている」と世界に配信(11月28日)した。
ジャーナリスト出身の政治学者で、同協会元会長のカレル・ヴァン・ウォルフレン氏(アムステルダム大学教授)がこう語る。
「自民党は野党の力が衰えて一強支配政治になると、その影響力をメディアコントロールに及ぼそうとしている。日本のテレビ局の番組内容にまで踏み込んで規制する文書を見ると、一党支配の驕りが明らかです。(中略)
もっと問題なのは、NHKや日本の大メディアがそれに抵抗せず、自民党政権の意図に従っていることだ。メディアのそうした姿勢は、
国民の知る権利を奪い、有権者の目を曇らせることになる。政権の言いなりになった
報道機関の役割放棄こそ、日本にとって非常にシリアスな問題です」
安倍自民党を大勝させてしまった
ツケは全部の国民に回ってくるのだ。暗澹たる気持ちにならざるを得ないが、こういうときこそ
ガンジーの言葉を思い出そうではないか。
「われわれのやっていることは無意味かもしれないが、それをするのは世界を変えるためではなく、世界によって自分が変えられないようにするためだ」
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
亡くなったやしきたかじんの奥さん・さくらさんと実の娘との争いは、週刊誌を巻き込んでさらに激しさを増している。
百田尚樹(ひゃくた・なおき)が書いた『殉愛』というノンフィクションが、あまりにもさくらさん側に寄り添いすぎていて、一方的だという批判もある。今週は
たかじんをめぐる週刊誌報道をまとめてお見せしよう。あなたはどちらの言い分が正しいと思うだろうか。
【大論争】「やしきたかじん」の妻をめぐる報道合戦 真実はどっちだ!
「故やしきたかじん『遺族と関係者』泥沼の真相」(『週刊新潮』12/18号)
「『林真理子さんの疑問にお答えします』百田尚樹」(『週刊文春』12/18号)
「百田尚樹さん、事実は違う。なぜ、私に取材しなかったのか」(『週刊朝日』12/19号)
「袋とじ 家鋪さくら独占手記『重婚疑惑』『直筆メモ捏造疑惑』すべてに答えます」(『フライデー』12/26号)
「書かれなかった『殉愛』妻(33)の裏面」(『女性自身』12/30号)
先週、林真理子が『週刊文春』で、やしきたかじんの妻・さくらさんが献身的に看護したことを取り上げたノンフィクション『殉愛』についての「騒動」をどこも報じないのはおかしいと書いた。
その“剣幕”に驚いたのであろう、『文春』は著者である百田尚樹に弁明させ、『週刊新潮』は5ページも割いて「遺族と関係者の泥沼の真相」と題した特集を組んでいる。
『週刊朝日』はたかじんの最初の妻との間にできた唯一の娘H子さん(41)のインタビューを掲載。
重婚、たかじんのメモの筆跡が違うのではないか、カネ目当ての結婚ではないのかという「疑惑」は一掃されたのか。娘と妻の言い分はどちらが正しいのか、読み比べてみた。
『文春』で百田は「林真理子さんの疑問にお答えします」で、
重婚の事実はないと言っている。さくらさんはイタリア人と結婚していたが2012年の3月に離婚し、たかじんと入籍したのは2013年10月。これは戸籍を見て確認しているという。ちなみにたかじんが亡くなったのは入籍からわずか4か月足らずである。
ほかにも彼女には離婚歴があるが、彼女の過去を問題にして「悪女」にしようという世間の悪意は理解できない、たかじんの最後の2年間を献身的に支えたのは紛れもない事実だと突っぱねる。
だが、後述するように遺産を巡って不可解なことが起きているため、「もちろん人の心の奥底に何が潜んでいるか、見えないところはあるでしょう。しかし私は、自分の目に曇りがあったとはとても思えないのです」と予防線を張った結び方をしている。
『新潮』では、メモの疑惑は「あるサイト」(どこかは書いていない)の求めに応じた日本筆跡鑑定協会指定鑑定人の藤田晃一氏が鑑定した結果、
「あのメモはたかじん氏の真筆」だという。
問題を複雑にしているのは、百田が本でも書いている、たかじんとさくらさん対H子さんのこじれた関係である。
さくらさん側は、たかじんは娘を嫌っており、彼が食道がんだとマスコミで報じられたとき、H子さんから「なんや食道ガンかいな。自業自得やな」というメールが来て、たかじんが激怒したことや、見舞いに一度も来なかったことをあげて娘の不実を言い募っている。
H子さんは
『朝日』で、離れて暮らしてはいたがクリスマスにはプレゼントを買ってもらったり、大人になってからも年に1、2回は会っていて、
決して仲の悪い親子ではなかったと反論している。
また、「やしきたかじんを偲ぶ会」でさくらさんが挨拶した際、H子さんが大きな声で野次を飛ばしていたと本で書かれたが、そんな声は出していないと言っている。H子さんの弁護団は、その会の進行を記録した録音を確認したが、野次は聞き取れなかったとしている。
両者の言い分はまったく違っているが、ここで私が疑問に思うのは、百田はノンフィクションと銘打っているのに
H子さんに一度も取材をしていないことである。看護の話だから数メートル四方だけのことさえわかればいいというのかもしれないが、たかじんは女性関係も含めて極めて複雑な人生を抱え、死と向き合っていたはずである。
そうしたノンフィクションを書く場合、最終的には取り上げないかもしれないが、たかじんの唯一の娘の話は聞いておくのが
常道である。
百田の得意な「ノンフィクション・ノベル」という不思議なジャンルのものを書くなら、そうしたことは必要ないのかもしれないが。
さくらと実娘の間で一番こじれているのはたかじんの遺産を巡る問題である。
遺産は総額で約8億から9億円とも言われているそうである。遺言には「6億円程度を大阪市などに寄付し、娘H子には相続させない」と書かれているという。
そのほかにも金庫に2億8000万円のおカネがあったというが、そのうち1億8000万円は、さくらさんがたかじんと「業務委託契約を交わし、毎月、一定額の支払いを受ける約束になっていた」(『新潮』)から、彼女のものだと主張している。
夫婦なのに業務委託契約を結んでいた? 仕事内容は「セクレタリー業務」となっていると『新潮』は書いている。
そのほかにもさくらさんは、元マネージャーに対して使途不明金の返還請求訴訟を起こすことを考えているそうだ。
失礼だが、こうしたことが事実なら、このさくらという人物、カネに恬淡(てんたん)とした女性ではないようである。
『朝日』は「Hさんに取材せずに作品を世に出したことに問題はなかったのか。幻冬舎と百田氏に見解を尋ねたが、
≪現在係争中であり一切の回答を差し控えさせていただきます≫」と書いている。
ちなみにH子さん側の弁護士は私と旧知の講談社の顧問もやっている人間である。
『フライデー』にはさくらさんの「告白手記」とたかじんの「遺言書」がご丁寧に袋とじになって載っている。
売りは丸ごとさくらさん側の言い分と、遺言書にある「(大阪市などへの寄付以外の=筆者注)その余の全ての現金は妻・家鋪さくらに相続させる。遺言者は、子である家鋪(旧姓)(実名)には、遺言者の財産を相続させない」と書かれてある部分であろう。
『文春』は百田尚樹の弁明。『新潮』はさくらさん寄りの記事の作り方。『フライデー』は100%さくらさん側。娘の言い分をそのまま載せているのは
『朝日』だけ。これを見るとメディアに対する百田の「圧力」が強いことがよくわかるが、ここに
『女性自身』が参戦した。
「これまで本誌は3年近くにわたり、たかじんさんの親族へ取材を重ねてきた。そこで彼らが語っていたのは、ぶっきらぼうながらも親族への愛情を忘れない彼の姿だった」
H子さん側に頼もしい助っ人が現れた。
『自身』は、さくらさんがたかじんと出会った当初、彼女は彼を知らなかったと証言しているところを衝いている。
彼女は兵庫県明石市に育ち、地元の商業高校を卒業している。彼女の同級生がこう語る。
「彼女は幼いころから明石に住んでいましたよ。たかじんさんは、当時からかなりの人気者でしたから。この辺で彼を知らないのは、
東京でタモリさんや北野武さんを知らないと言っているようなものです。ありえないでしょう?」
重婚疑惑についてもこう指摘する。
「さくら氏は12年3月に日本国内での離婚が成立したと疑惑を否定。だが、行政書士の荒木康宏氏はこう語る。
『原則的に国際結婚や離婚は双方の国で書類を提出しなければなりません。イタリアで離婚届を提出していた場合、離婚するにはまず別居の申し立てが必要です。そこから
3年後を待って裁判所へ申請をし、離婚が成立するのです』
さくら氏は『離婚に向けての話し合いを始めたのは11年5月』と語っている。イタリアで結婚届を提出していれば、離婚が成立するのは、どんなに早くても14年5月以降となる。日本国内で“重婚”とはならないため違法性はないが、彼女が主張するように“正統な結婚・離婚だった”と言えるのだろうか」
と疑問を呈している。
たかじんが2度目の結婚&離婚した女性がいる。本の中では、たかじんが、彼女がヨリを戻したいと言ってきているが、その気はないと言い、彼女が葬儀でさくらさんに「グロイよ」と言ったと書かれている。彼女の親族は憤りを隠さずこう語っている。
「本が出て、すぐ彼女から怒りのメールが来ました。『そんなことは絶対に言っていない』と言っていました。それに、
ヨリを戻したいと言っていたのは逆。たかじんさんは彼女にずっとラブコールを送っていましたから。彼女は別の男性と結婚しています。それでもたかじんさんは諦めきれず、私にも『なんとか(前妻との)仲を取り持ってほしい』と言ってきたんです」
『自身』も、前の妻へのたかじんさんの思いについては、生前の彼を知る複数の人が同様の証言をしていると書いている。親族が、闘病中もたかじんから連絡があって、細かく検査の数値や治療法などを知らせてきて、何度も復縁したいと伝え、ついには彼女に最期を看取ってほしいとも言っていたそうだ。
最期の頃にはたかじんからの彼女への連絡は途絶えたが、それはたかじんの携帯に登録されていた
彼女の電話番号が変わっていたからだとわかったという。
H子さんはこう話す。
「さくらさんに、父との間を取り持ってもらいたかった、とは思いません。ただ、もし彼女が本当に父を愛していたならば、たとえ父が何と言おうと、最期は家族と会わせようとするのではないでしょうか。そして父が亡くなった後、その家族をおとしめるような本などは
決して書かせないと思います」
彼女が提訴したのは、百田が『殉愛』に書いた自分に対する記述が
「プライバシー侵害と名誉毀損に当たる」ということである。
この著者は、2002年に最高裁判所が柳美里(ゆう・みり)著『石に泳ぐ魚』(新潮社)について、モデルとされた原告の主張どおり「この小説はモデルの女性のプライバシーを侵害している」と認定し、出版差止めと慰謝料の支払いを命じたことを知らないわけではあるまい。この場合、モデルの女性には事前に書くことを伝えてあったはずだ。
ましてやこの本はノンフィクションである。にもかかわらず実娘側の取材や了解を取っていないのだから、個人的には、この裁判は百田側に
厳しいものになると思う。
そこのところを
出版社系週刊誌はどう考えているのだろうか。見解を聞かせてほしいものだ。
わたしは東京に住んでいるから「やしきたかじん」という人がどれほどの人気があるのかわからない。本音でズバズバものを言うキャラクターでカリスマだったらしいが、もし生きていたらこの騒動に対して何と言うのであろうか。
ここまで騒動が広がったのも、作家がものを書くときに欠いてはならない関係者への「配慮」を怠ったことからである。