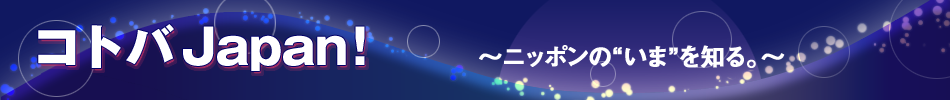『週刊新潮』(以下、『新潮』)が
創刊60周年を迎えた。2月22日には『別冊週刊新潮 60周年記念創刊号復活』を発売した。「60年史」によれば、創刊は1956年2月6日。B5判、本文64頁、グラビア16頁、誌価30円で表紙絵は谷内六郎。30万部程度の発行部数ではなかったか。だが、その年の11月12日号は早くも発行部数50万部を超えたと記している。
ここにも書いてあるように「新聞社系でなければ出せないといわれた週刊誌の創刊に挑戦し、販売、広告、取材の課題を克服。ユニークな編集方針と、文芸出版社の伝統を生かした連載小説」を武器に週刊誌市場へ切り込んだのである。
巻頭の特集は「オー・マイ・パパに背くもの─父と子のモラル戦後版─」、ほかには「ブラジルの子等天理に帰る」「私生活が決した勝敗」などがあり、ワイド特集「週間新潮欄」の1本には『新潮』らしく「不思議な憲法改正反対論」というのがある。
だが売り物は谷崎潤一郎の「鴨東綺譚(おうとうきたん)」、五味康祐「柳生武芸帳」、大佛次郎「おかしな奴」。それに石坂洋次郎「青い芽」とサラリーマン小説で人気だった中村武志の「目白三平の逃亡」が並んでいる。
当時は新聞社系の『週刊朝日』と『サンデー毎日』が100万部といわれ、週刊誌は情報力、取材力のある
新聞社でなければ無理だと言われていた。出版社の出す週刊誌では編集部員はせいぜい20~30人程度、しかも取材経験もほとんどない。アンカーマンといわれる記事のまとめは作家崩れに頼むとしても、情報収集は、取材の方法は、と難題が山積していた。
創刊時ではなかったが、少し後に『新潮』編集部に入った年上の友人からこんな話を聞いたことがある。大阪や名古屋などに取材に行くときは一等車に乗れ、と先輩から言い渡されたそうだ。当時はまだ三等車があった時代である。なぜ一等車か? 一等車は今のグリーン車というよりも飛行機のファーストクラスと言ったほうがいいだろう。そこには各界の名士や一流企業の社長たちが乗っている。目的地に着くまでにそこで『新潮』の名刺を配り、知り合いを何人か作れというのである。それが編集部の財産になる。だから
『新潮』編集部の人間の多くは、定年まで他の編集部に異動しない。
しかし、新聞社系と伍して闘うには小説と人脈作りだけでは武器が足りない。そこで『新潮』や3年後に創刊された『週刊現代』や『週刊文春』などが模索した結果、新聞社系には絶対出来ない「武器」を発見したのである。
それが
「メディア批判とスキャンダル」である。当時メディアといえば大新聞のこと。今もそうだが当時は新聞が他紙を批判することなどほとんどなかった。だが出版社系なら遠慮なくできる。それにツンとお高くとまっている新聞社系はスキャンダルなどには関心もなかっただろう。だが出版社系には
「他人の不幸は蜜の味」である。
メディア批判とスキャンダルを選択し、少ない人数と取材をそこに集中したことによって、出版社系週刊誌は飛躍的に伸びたのである。
私が『週刊現代』編集部に配属されたのは1973年だった。事件ものの取材に地方へ行くと、『新潮』の強さをまざまざと見せつけられたものだった。現地に着くとまず地方新聞社や警察署に行って基本的な情報を取るのだが、どこへ行っても先に『新潮』の記者が来ていた。
われわれはタクシーをその都度つかまえるが、『新潮』は一日チャーターするのだ。それに警察への食い込みがすごい。『新潮』の取材には警察署長が出てくるが、われわれの取材には下っ端の警察官しか対応してくれないことが何度かあった。
『新潮』の強みはそれだけではない。ものの見方、ある事象の切り口、タイトルのつけ方のうまさに、われわれ他の週刊誌は唸ったものだ。それは長きにわたって『新潮』を“支配”してきた
齋藤十一(さいとう・じゅういち)という人間がいたからである。
「この憎しみで何と書く──やがて江川『快投乱麻』の日」「気をつけろ『佐川君』が歩いてる」などの
名タイトルを生み、「キミは殺人者の顔が見たくないか」という発想で
写真週刊誌『FOCUS』をつくった男である。
『新潮』には
数多くのスクープがある。この別冊にも載っている「三億円事件敗退記 平塚八兵衛」「テルアビブまでの旅 岡本公三」。最近では鴻池(こうのいけ)官房副長官(当時)と愛人の温泉旅行をスクープし、自民党下野へのきっかけとなった。
私が一番覚えているのは1978年の1月12日号から3回にわたって連載された、日本共産党副委員長・袴田里見(はかまだ・さとみ)の手記だった。宮本顕治委員長に対する批判だが、日共を散々叩いてきた『新潮』に、当の日共幹部がトップを批判して除名される経緯を赤裸々に書いたというので、われわれ雑誌はもちろん、大新聞もあわてて後追いしたものだった。
もう1本は「暴露された『鳩山由紀夫』と『室蘭の愛人』十年の葛藤」という記事だ。愛妻家といわれていた鳩山氏が初当選から官房副長官になった頃まで続いていた現地女性との“艶談”である。
同じ頃、『現代』もこの話を取材していた。女性の話もとれて次の月曜日発売で掲載しようと準備していたところ、木曜日発売の『新潮』に出し抜かれてしまったというほろ苦い思い出である。
60年史には2009年に起きた
朝日新聞阪神支局襲撃犯の告白という「大誤報」が載っていないのが私には残念だが、『新潮』がジャ-ナリズムで果たしてきた大きな足跡は、いまさらながらたいしたものだったと思う。
今年に入って『文春』のスクープが次々に大きな話題を呼んでいる。それに比べ老舗の『新潮』や『現代』、『ポスト』の存在感が薄くなってきている。それは『新潮』や他の週刊誌が原点である
「新聞、テレビに出来ないことをやる」ということを忘れがちだからではないのかと、私は考える。
昔のような大部数は望めず、取材費や原稿料を削られ、事件取材をやらない週刊誌も多くなってきている。ノンフィクション・ライターが腕を振るう場も少なくなり、取材力やそのジャンルを扱える編集者の劣化が言われて久しい。
こういうときこそ、創刊時の
「選択と集中」を思い出すべきである。少ない人材と取材費をどのターゲットに向けるのかを真剣に議論して体勢を立て直さない限り、週刊誌は生き残れはしない。『新潮』60周年にあたって、週刊誌に携わるみんなに考えてほしいものである。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
今週は力作が集まった。『文春』がスクープを連発するのに「危機感」を感じたのではないか。『現代』を除いて、
スキャンダル・ラッシュとなっている。いいことだ。週刊誌の原点を忘れなければまだまだ生き残れる。新聞やテレビが政権の“ポチ”になってしまっている現状を打破できる底力はまだまだ週刊誌にはある。そう思わせてくれるものを3本選んでみた。
第1位 「自民党目玉候補SPEED今井絵理子同棲相手は『女子中学生をフーゾク店』で逮捕されていた」(『週刊ポスト』3/4号)
第2位 「永田町の黒幕を埋めた『死刑囚』の告白」(『週刊新潮』2/25号)
第3位 「元少年Aを直撃!『命がけで来てんだろ? お前、顔覚えたぞ!』」(『週刊文春』2/25号)
第3位。週刊誌にこれほど注目が集まるのは久しぶりだ。年明けから連続してスクープを放ち続ける『文春』の力によるところ大であるが、今週は
「元少年Aを直撃」が巻頭特集である。
元少年A(33)は1997年に神戸市須磨区で起きた連続児童殺傷事件の加害者で、当時14歳。この事件で少年法が大幅改正されるなど、社会に与えた衝撃は大きかった。
Aは約7年間医療少年院で治療を受け、2004年に仮退院し翌年に本退院が認可され、社会復帰している。
Aが再び注目を浴びたのは昨年6月に手記
『絶歌』(太田出版)を出版したことだった。反響は大きく発行部数は25万部に達しているという。だが、手記に対する批判も大きかった。出版が被害者の遺族の了解をとっていなかったことや、贖罪意識に疑問を感じさせる記述が反発を呼び、当時小学6年生だった土師淳(はせ・じゅん)くんを殺された父親は「淳はこれによって二度殺されたようなもの」だと不快感を露わにした。
『文春』は手記が出された頃からAを追い続け、モノクログラビアではAが自宅を出てバス停へ走る姿や、電車内で携帯電話に見入っているAの姿を掲載している。目隠しは入っているが、顔の輪郭から着ている服、スニーカーがはっきり写っている。実名は書いていない。『文春』は、Aを取材し続けた理由をこう書いている。
「医療少年院を退院したとはいえ、彼は出版物を自ら世に問い、ベストセラーの著者となった人物である。彼の著書に影響を受ける“信者”も少なくない。
もちろん素顔や現在の名前をさらす記事が許されるべきではないが、一方で純粋な私人であるとは、とても言えないのではないか。
そう考えた取材班は、昨年六月の『絶歌』刊行から半年以上、彼の取材を続けてきた」
そして1月26日、東京都内でAを直撃している。『文春』の取材に対して「なんのことか分からない」「違います。まったく別人」だと否定し続けるA。
改めてインタビューをさせてもらえないかと記者が、その旨を書いた手紙と名刺を渡そうとすると、Aの口調が一変し、記者ににじり寄りこう言い放ったという。
「命がけで来てんだろ、なあ。命がけで来てんだよな、お前。そうだろ!」
身の危険を感じた記者が走り出すと、興奮したAは記者を全力で追いかけてきた。この直撃の数日後にAは東京を離れたという。
『文春』によれば、98年以降17年連続で少年犯罪の再犯者率が上昇していて、15年上半期は37%と過去最高だそうである。
また、土師淳くんの父親の言うように「重大な非行に対しては現行の少年法でも甘すぎる」という批判も頷ける。
だが、と、これを読みながら考え込んでしまう。匿名という隠れ蓑に隠れ、被害者に対して心から反省しているとは思えない手記を書いて金儲けをする中年男への怒りは、私にもある。
そうした社会の怒りを背景に『文春』がAを追いかけ回し、写真を公表することが、Aの再犯を抑止することになるのだろうか。かえって彼を追い詰め、自暴自棄にして再び犯罪を起こさせてしまわないだろうか。
私も関わった『元少年Aの殺意は消えたのか』(イースト・プレス)の著者・草薙厚子(くさなぎ・あつこ)氏は、
Aは社会的不適合を起こしやすい広汎性発達障害ではないかと推測している。広汎性発達障害は「生得的な脳機能の異変が精神の発達に影響をおよぼした結果、幼少期から成長を通じて日常生活上のハンディキャップを生じている状態」(京都大学医学部の十一元三(といち・もとみ)教授)だそうである。
もしAがそうだとしたらという前提だが、草薙氏は「再犯防止の意味でも、いまとなってはいちばん重要である家族が中心となり、連携して支援システムを構築することが必要なのではないだろうか。そして遺族に手記の出版に対する謝罪と、今後一生をかけて償っていく具体的な内容を早急に示すべきである」としている。
ジャ-ナリズムの役割は、ここにこんな危険なヤツがいると鉦や太鼓で囃し立てることではないはずだ。
その人間が二度と過ちを犯さないために何ができるのかを提示することも大切だと思う。
たしか、少年Aの母親の手記『「少年A」この子を生んで……』は文藝春秋で出したはずだ。Aと両親とを会わせる努力を『文春』はしたのだろうか。
第2位。『新潮』が
「永田町の黒幕を埋めた『死刑囚』の告白」を掲載している。死刑囚から届いた一通の手紙という書き出しを見て、あの大誤報を思い出した。
朝日新聞阪神支局を襲った真犯人のスクープ手記と大々的に謳ったが、結局、真っ赤なウソだとわかって、大きな批判を受けた。
今度は大丈夫なのだろうか? そう思いながら読み進めた。
手紙の主は東京拘置所在監の暴力団組長、矢野治死刑囚(67)。死刑判決をうけた事件は、03年に発生した暴力団同士の抗争。矢野の指示を受けた組員がスナックで飲んでいた相手方のナンバー2を射殺するために銃を乱射し、一般人たちまで殺してしまったため、共謀共同正犯で逮捕され、極刑を言い渡されたのである。
その矢野が、斎藤衛氏殺害を告白したというのだ。斎藤が
「オレンジ共済事件」で、国会で証人喚問されたとき、私も週刊誌の編集長だったのでよく覚えている。この事件は、国会議員を目指していた友部達夫が92年に「オレンジ共済組合」を設立、高配当を謳った金融商品を売り出した。100億円近い資金を集めたが資金は友部の私的流用に消え、配当は続かず組合は倒産、彼は詐欺容疑で逮捕された。
だがその間の95年、彼は参議院選に新進党から出馬して当選している。その際、比例名簿順位を上げてもらおうと政治ブローカーを使い、工作資金約5億円が新進党に流れたと言われる。
そのブローカーが斎藤氏であった。
斎藤氏は暴力団の企業舎弟で、その頃矢野と知り合ったと言う。このオレンジ共済事件は結局、未解決となり、斎藤氏は政界の「黒幕」と言われたが、
その後姿を消してしまったのだ。
家族から捜索願が出されたが杳として行方が知れず、手がかりもなかった。矢野死刑囚が言うには、斎藤との間で金銭トラブルがあり、それがこじれて殺したというのだ。
死体を始末した人間の名前まで書いているが、以前のことで懲りているのであろう、『新潮』は、
「矢野の証言は極めて具体的だった。もっとも、彼の告白の目的が、新たな事件の立件化による死刑執行の先送りにあるのも間違いないだろう。毎日新聞の記事(斎藤氏が行方不明になっているというもの=筆者注)や、業界の話で斎藤の失踪を知り、架空の殺人事件をでっち上げている可能性も完全には否定できまい」
と“慎重”なのである。それに同様の手紙を警視庁目白警察署にも送っているのだ。目白署の刑事が東京拘置所で矢野に対する事情聴取を行なったが、その後警察は動いていないという。
そこで『新潮』は、死体遺棄役とされた矢野の組の元構成員を探し出すのである。このあたりは『新潮』の取材力に脱帽である。そして固い口をこじ開け、その人間から全容を聞き出すことに成功するのである。
このあたりは良質のミステリーを読むが如くである。だが死体は一つではなく二つ出ると矢野は言っていたという。二つ目の死体とは何か? 次号をお楽しみにである。
なぜ警察は動かなかったのか。95年以降の殺人事件には時効が廃止されたから、死体遺棄役が死体の埋まっている場所に案内すれば、逮捕されることはないのか。いくつかの疑問はあるが、なかなか読み応えのある記事である。
第1位。今週の第1位は久々に『ポスト』に輝いた。自民党の目玉候補として立候補を早々と表明した
今井絵理子氏(32)についてのちょっとおかしな話である。彼女は人気音楽グループSPEEDのボーカルとして活躍する一方、聴覚障害のある長男(11)を持つシングルマザーとしても知られている。
だが『ポスト』によれば、彼女はシングルマザーという触れ込みではあるが、実は交際相手がいるというのである。
地元・沖縄の同級生で、1年半ほどの交際の末に現在は半同棲しているという男性A氏。俳優の徳重聡(とくしげ・さとし)似のイケメンと評されているそうだ。
今井氏もそのことは認めていて、「私には将来を見据えて交際している男性がいます。この方は、障がい児童デイサービスで働く一般男性です」と言っている。
実はA氏、地元沖縄では、この報道とはまるで正反対の人間だと受け取られているようなのだ。
彼はこの地でほんの1年前まで風俗店を経営していたのだ。同じ那覇市の歓楽街・松山で飲食店を経営する古い友人がこう語る。
「今井さんはAが風俗店をしているのが嫌で、『自分と一緒に本土で暮らそう』といっていたらしく、頻繁に内地に行っては、働き先として福祉施設を紹介されたりしたらしい」
しかし、今井氏と付き合って以降もA氏は風俗店の経営から手を引くことはなかった。そして彼がその世界と縁を切り、本土へ移るきっかけとなったのは、皮肉にも彼の逮捕だったという。
2015年3月、中学生を含む少女3人にみだらな行為をさせたとして、店員の男性と2人で
風営法・児童福祉法違反の容疑で那覇警察署に逮捕されたのだ。
『ポスト』の取材に那覇署はA氏を逮捕・送検した事実を認めたが、その後、検察による起訴には至っておらず、A氏はひと月もたたずに釈放されているという。
釈放されたA氏は直ちに風俗店をたたんで本土へ行った。
そして今井氏と東京で暮らし始めたA氏は1年後、今度は好青年のイケメン彼氏としてメディアに取り上げられるようになった。
だがA氏は沖縄で風俗店のほかに飲食店や貸金業にも手を出しており、そのために方々から金を集めていたそうだ。その借金はいまだに返されていないという。
「そもそも自民党は、この“目玉候補”の交際関係について、しっかり身体検査したのだろうか。スキャンダル続出でイメージ回復に躍起になり、
『SPEED出馬』させたのが裏目に出たということだ」(『ポスト』)
これから参議院選に出馬する有名候補が次々出てくるだろうが、週刊誌で「身体検査」をきっちりやってほしいものである。