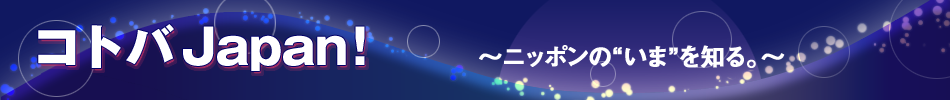[暮らし]
まだ寒さを残す余寒のころ、春の訪れを告げる和菓子といえば、うぐいす餅。こし餡(あん)を餅や求肥(ぎゅうひ)に包み、青大豆でつくった淡緑色の青きな粉を表面にまぶして色づけてある。菓子の両端の部分を少しだけつまんでとがらせ、うぐいすをかたどっている。
都市と山里が近接する京都は、桃のつぼみが膨らみ始めるころ、春を象徴するうぐいすがいたるところで「ホーホケキョ、ピチュピチュピチュ」と、愛らしくさえずり出す。越冬した山中を下りてきたばかりのうぐいすは、青きな粉よりもっと黄色っぽく、きな粉そのもののような色合いをしている。それが山の芽吹きの色へと合わせるように、徐々に緑褐色を強めていく。
うぐいす餅の発祥は、豊臣秀長が兄の秀吉を天正年間(1573-92年)に郡山城(奈良県大和郡山市)に招いて開いた茶会のための「珍菓」だと伝わっている。秀長の「珍菓をつくれ」という命を受け、御用菓子司であった菊屋治兵衛が献上したのがうぐいす餅の発祥である。秀吉はこの餅菓子が気に入り、「うぐいす餅」と名づけたといわれている。城跡の入り口付近に現在もある本家菊屋では、「お城の口餅」という菓銘で、いまもうぐいす餅を作り続けている。