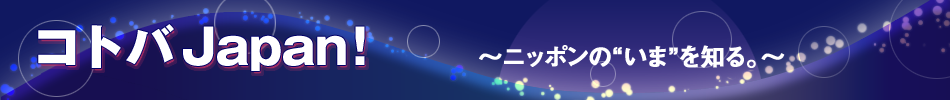[暮らし]
おつゆにゆれながら、ほどけてなくなっていきそうな湯葉を、掬うようにして口に含む。すると、思いのほか厚みを感じさせる歯ごたえがあり、大豆特有の濃厚な風味を残して、するりと喉の奥に消えてなくなる。湯葉は鎌倉期に禅僧が製法を伝え、京都の精進料理や京料理に欠かせない材料の一つになっている。大豆を原料とする加工食品のため、タンパク質が豊富で栄養価が高い。滑らかで柔らかいので、病中や病後の食事にも向いている。これがおいしいと思えるようになったのは、味覚が肥えて、少々齢を重ねてからのことであった。
お椀の中の様子そのままのように、湯の葉と書いて「ゆば」と読む。通常、乾燥させたものを戻して食べるのが「干し湯葉」で、干さずに生のまま食べるものを「生湯葉」という。京都では、どちらの湯葉も普通の食品スーパーで手に入るが、ほとんどは機械製である。手づくりのものは流通量が少なく、特に保存の利かない生湯葉は高級品である。作りたてを食べる生湯葉は、中に百合根などの具を入れた種類もあり、これがおいしい。一方、干し湯葉には濃縮された独特の風味があり、加工方法によって厚みや大きさ、形などで種類が多く、懐石料理からおばんざいまで幅広く使われている。
京都で湯葉を手づくりしている湯葉専門店を初めて見たとき、なにをつくっているのかわからなかった。たいていの店は大きな窓のある町家造りで、土間には細長い四角のお鍋がたくさん火にかけてある。手づくりの湯葉は、豆乳を加熱して表面にできる膜をめくること、7回か8回ほどだろうか。職人さんは、湯気のあがる鍋の中から薄い布巾でも竹串にかけて取り出すようにしながら、頭上の桟に重ならないように丁寧に干していく。
鍋の表面に張った薄膜がゆらゆら波がたつようなので、「湯波(ゆば)」とも。また、豆腐の上物(うわもの)という意味から「上(うは)」が変化し「うば」となり、あるいは表面にしわがよっているため「豆腐の姥(うば)」を略して「うば」となり、「ゆば」と呼ばれたなどとされる。京都の家庭では「おゆば」と、親しみを込めて呼ばれている。

湯葉の工場(昭和30年代)。
お椀の中の様子そのままのように、湯の葉と書いて「ゆば」と読む。通常、乾燥させたものを戻して食べるのが「干し湯葉」で、干さずに生のまま食べるものを「生湯葉」という。京都では、どちらの湯葉も普通の食品スーパーで手に入るが、ほとんどは機械製である。手づくりのものは流通量が少なく、特に保存の利かない生湯葉は高級品である。作りたてを食べる生湯葉は、中に百合根などの具を入れた種類もあり、これがおいしい。一方、干し湯葉には濃縮された独特の風味があり、加工方法によって厚みや大きさ、形などで種類が多く、懐石料理からおばんざいまで幅広く使われている。
京都で湯葉を手づくりしている湯葉専門店を初めて見たとき、なにをつくっているのかわからなかった。たいていの店は大きな窓のある町家造りで、土間には細長い四角のお鍋がたくさん火にかけてある。手づくりの湯葉は、豆乳を加熱して表面にできる膜をめくること、7回か8回ほどだろうか。職人さんは、湯気のあがる鍋の中から薄い布巾でも竹串にかけて取り出すようにしながら、頭上の桟に重ならないように丁寧に干していく。
鍋の表面に張った薄膜がゆらゆら波がたつようなので、「湯波(ゆば)」とも。また、豆腐の上物(うわもの)という意味から「上(うは)」が変化し「うば」となり、あるいは表面にしわがよっているため「豆腐の姥(うば)」を略して「うば」となり、「ゆば」と呼ばれたなどとされる。京都の家庭では「おゆば」と、親しみを込めて呼ばれている。

湯葉の工場(昭和30年代)。