「学問」カテゴリの記事一覧
オンライン辞書・事典サービス「ジャパンナレッジ」の「学問」のカテゴリ別サンプルページです。
ジャパンナレッジは日本最大級のオンライン辞書・事典サービスです。
「国史大辞典」「日本古典文学全集」「日本国語大辞典」「世界大百科事典」「日本大百科全書」など80種類以上の辞書・事典をパソコン、タブレット、スマートフォンで利用できます。
「国史大辞典」「日本古典文学全集」「日本国語大辞典」「世界大百科事典」「日本大百科全書」など80種類以上の辞書・事典をパソコン、タブレット、スマートフォンで利用できます。

歴史学(国史大辞典)
歴史学すなわち学問としての歴史研究は、現代の日本では、本項目の以下の区分のように、国史学・東洋史学・西洋史学の三つの分野に分けられるのが、普通である。このうち国史学は、日本文学の研究が国文学とよばれているのと同様に、自国の歴史を対象とする意味の名称であるが

社会学(国史大辞典)
人間の社会的行為を最も基本的単位とする社会の構造や変動を、地位・役割、関係、集団・組織、階級・階層、制度、体制などの概念を用いながら、理論的、実証的に分析し、社会を構成する一定の法則性の発見をめざすとともに、諸社会問題の解決に貢献するという応用的領域をも含んだ
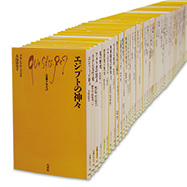
ファッションの社会学 ――流行のメカニズムとイメージ(文庫クセジュ ベストセレクション)
ファッションの社会学――流行のメカニズムとイメージ 文庫クセジュ933 F・モネイロン著/北浦 春香訳 社会科学 はじめに 「ファッション」という言葉は、捉え方もさまざまで、定義も一つではない。そして、多くの定義があるという事実そのものが

すなわち(日本国語大辞典・全文全訳古語辞典)
【一】〔名〕(1)(多く連体修飾語を受けて)ある動作の終わったその時。途端。*万葉集〔8C後〕八・一五〇五「霍公鳥(ほととぎす)鳴きし登時(すなはち)君が家に行けと追ひしは至りけむかも〈大神女郎〉」*竹取物語〔9C末~10C初〕

よし 【由・因・縁】(日本国語大辞典)
〔名〕(「寄(よ)す」と同根で、物事に関係づけていくことの意)(1)物事の起こった理由。由来。わけ。いわれ。*日本書紀〔720〕推古一一年二月(岩崎本平安中期訓)「故、猪手連の孫を娑婆連と曰ふ。其れ是の縁(ヨシ)なり」*万葉集〔8C後〕

地政学(日本大百科全書・世界大百科事典・日本国語大辞典)
スウェーデンの政治学者チェレーンRudolfKjellén(1864―1922)によって第一次世界大戦直前につくられた用語で、政治地理学が世界の政治現象を静態的に研究するのに対し、地政学はこれを動態的に把握し、権力政治の観点にたって、その理論を国家の
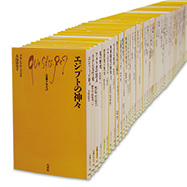
現象学(文庫クセジュ・集英社世界文学大事典・世界大百科事典)
第一部フッセル(1)A形相的なものI心理主義的懐疑論フッセルは心理主義と戦った。心理主義が、認識の主観と心理学的な主観とを、同一視するからである。心理主義の主張によれば、《この壁は黄色である》という判断は、この判断を言い表わしこの壁を知覚する私から
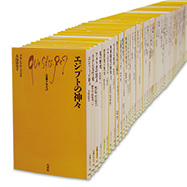
ヘーゲル哲学(文庫クセジュ・日本大百科全書)
緒論一はじめにかつて、ヘーゲルは近代のアリストテレスであると言われた。じじつ彼の学説は、かつてひとりの哲学者によって構想された哲学体系のなかで、最も完結したものであり、そしておそらく最も深遠なものであろう。それは知の諸領域を一つのこらず網羅し


