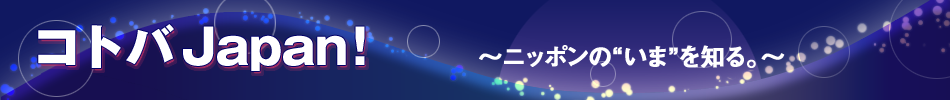5月5日と13日に起きた首都圏地震が大きな話題を呼んでいる。なかでも5日に伊豆大島近海で発生した地震は東京・千代田区で震度5弱を記録した。
『週刊現代』(5/31号、以下『現代』)によれば、地震の規模より発生した場所と160kmという震源の深さが専門家を驚かせているという。
「この地域で、こんなに深い震源でのM6級の地震というものは、気象庁の観測開始以来、初めてのことだと思います。やはり3・11以来、日本列島の地震活動が変わってきている可能性がある」(東海大学教授長尾年恭(としやす)氏)
ここから週刊誌では“お約束”の地震予知の専門家が登場し、危ないのはいついつと予言する。今回は立命館大学歴史都市防災研究所の高橋学教授が、気象庁の地震記録データを精査してみたら、以下のことがわかったと話す。
「(1)それまで滅多に地震の起こっていない場所で地震が発生し、(2)約2週間、静かな期間が続き、(3)また周辺で地震が発生し始めると、(4)1~2日後に地下の力のバランス上、関係する地点でM7級以上の地震が発生する」
これを5月5日の地震に当てはめると、5月末にも大地震が来るかもしれないというのである。
『週刊ポスト』(5/23号、以下『ポスト』)によると、地震調査研究関連の予算は毎年100億円単位で投じられているのに、いつまでたってもこれといった成果が上がっていないという。
そんななか、地震研究の中枢からは大きく距離を置いているが、昨年からズバズバと地震予測を的中させている人物がいると報じている。
東京大学名誉教授で92~96年まで国際写真測量・リモートセンシング学会会長を務めた「測量学の世界的権威」である村井俊治氏だ。
村井氏が顧問を務める民間会社JESEA(地震科学探査機構)が週一回配信する『週刊MEGA地震予測』で、4月9日号から3週にわたって、首都圏での地震発生の可能性を示していたというのである。
村井氏の手法は測量技術の応用だという。国土地理院は95年の阪神・淡路大震災を機に、各地のGPSデータを測定する「電子基準点」を全国約1300か所に配備している。これを使うそうだ。
「これほどのGPS網が張り巡らされている国は、世界でも日本だけです。このデータが02年から利用できるようになった。我々が00~07年に起きたマグニチュード6以上の地震162件全てのGPSデータの追跡調査を行なったところ、地震の前に何らかの前兆現象が見られることに気がついたのです」(村井氏)
こうした分析に基づいて、昨年4月、淡路島で震度6弱の地震が発生したときも、その直後の4月17日に起こった三宅島地震(震度5強)も地震の可能性を指摘していた。東日本大震災の前にもその前兆をつかんでいたが「パニックになることを恐れて注意喚起ができなかった」そうだ。
「その結果、1万8000人もの人々が亡くなられたのです。これは学者としての恥です。ですから名誉を失っても、恥をかいても、今後は自分の理論において異常なら異常と公表する、と決断した」(同)
村井氏が指摘した今後注意すべき地域はゴールデンウィーク中に群発地震が起きていた岐阜県だという。
「春先から飛騨・高山中心に20か所くらいの電子基準点で大幅な上下動が観測されている。もっとも大きく動いているのは高山です」
『ポスト』は次の号(5/30号)でも「首都圏直撃地震からわずか8日後の5月13日午前8時35分、再び首都圏を地震が襲った。埼玉県南部や神奈川県東部で震度4を記録。東京都でも震度3を記録した」が、それも村井氏はメルマガで「可能性を予測」していたと報じている。
そのうえ、村井氏はこうも警告している。
「現時点で注意が必要なのは、北海道の函館の周辺です。今、全国的に基準点の短期の動きはほとんど目立たないのですが、今週届いた記録では函館にだけ動きが確認されました。(中略)函館だけではなく道南の広い地域で警戒が必要です」
津軽海峡を隔てた青森でも注意が必要だと村井氏は語っているが、これが発売された月曜日(5月19日)の夜(21時2分頃)、青森県東方沖でM4.2の地震が起きている。
あなたはこうした地震予知を信じますか?
ここで私の体験談を話させていただこう。阪神・淡路大震災は1995(平成7)年1月17日火曜日早朝に発生したことをご記憶だろうか。
当時『週刊現代』編集長だった私は、徹夜仕事を終えて家に帰るタクシーの中で地震のニュースを聞いた。だが、それほどの大地震とは思わず、そのまま寝てしまったのだから編集長失格である。編集部員の何度目かの電話で起きてテレビをつけ、呆然とした。部員に取材指示を出し慌てて出社すると、新聞社から私を取材したいという依頼が殺到していた。
地震前日の月曜日に発売した『現代』に「関西方面に地震が起きる」という予測記事を掲載していたのである。
「なぜ『現代』は地震を予知できたのか」聞きたいというのである。関西方面では雑誌が手に入らないのでコピーが回し読みされているという。余震は来ないか、来るとすればどれぐらいの規模なのか。被災した人たちは何でもいいから情報が欲しいという心境だったのだろう。
確たる根拠があるわけでもない記事を貪るように読んでいる被災者たちの気持ちを思うと、暗澹たる気分になったことを今でも覚えている。週刊誌の地震予測記事は、あくまでも「警告」であって、外れるのが当たり前なのだが、私のような万に一つのケースもあるので、頭の片隅に置いておく程度でいいと思う。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
今週は何といっても覚醒剤で逮捕されたASKAの記事が中心だ。昨年この問題をスクープした『週刊文春』は当然ながら内容が充実しているが、警察筋に強い『週刊新潮』が肉薄しているのがすごい!
第1位 「ASKA逮捕!」(『週刊文春』5/29号)
第2位 「家族に密告された覚醒剤常習『ASKA』禁断の乱用履歴」(『週刊新潮』5/29号)
第3位 「ASKAが溺れた『キメセク』そのあまりに危険な快楽」(『週刊ポスト』6/6号)
第3位。『ポスト』は控えめな記事づくりだが、芸能界には「麻薬逮捕者の互助会」があるというのが興味深い。
逮捕された芸能人が警察の取り調べに口を割らなければ、芸能界への復帰ができ、ミュージシャン仲間やテレビ局関係者、プロデューサーなどが「恩義」を感じて尽力してくれてヒットが出せるのだという。ほんとかね。
第2位。さて『新潮』はこう報じている。
「もう捕まえてください……。
『警視庁組織犯罪対策5課』捜査員の間を、その言葉が駆け巡っていた。
行動確認を続けていた彼らは、ASKAが覚醒剤を日常的に使用しているという確証を得て、洋子さん(ASKAの妻=筆者注)に接触。そして、そのやりとりの中で飛び出したのが、先に記した台詞なのだ。
さる捜査関係者は、
『ASKAが栩内(とちない=筆者注)の部屋を訪れる日の特定、自宅に覚醒剤やMDMAがあるという具体的な証言。これらについては、内部からの情報が不可欠だった』
と、逮捕には洋子さんの協力があったことを匂わせる。
『人の出入りは普段あまりない』(近所の住民)という目黒区のASKA邸だが、逮捕前日は打って変わって、
『関係者が続々訪れ、深夜まで部屋の明かりが消えることがなかった。翌朝のASKA逮捕を前提に、その後について、“作戦会議”をしていたようです』(芸能関係者)」
5月17日、午前7時30分。東京港区南青山の高級マンションからASKAが出てきたところを逮捕された。しかも、冒頭に引用した『新潮』によれば、ASKAの年上の妻が、もうこれ以上堪えられないから捕まえてくれと、捜査員に漏らしたというのである。これと同じ内容を翌日のスポーツ紙が後追いしていたが、これはスクープだ。
第1位。人気デュオ「CHAGE and ASKA」のASKA(本名・宮崎重明・56)の逮捕は『週刊文春』(2013年8月8日号)がスクープした「シャブ&飛鳥の衝撃」が発端である。
『文春』によると、捜査員はASKAが週末に栩内香澄美(37)の自宅に通ってシャブをやり朝帰りするというパターンを把握していた。
女の自宅から出たゴミの中からも薬物反応が出ているという。そのブツとはティッシュペーパーで、ASKAと栩内の性行為で使用されたため精液が付着していたという。
ASKA逮捕で俄然クローズアップされた栩内という女性だが、一体どんな女性なのだろうか。彼女は逮捕当時、パソナグループの中のメンタルヘルスケアを業務とする「セーフティネット」の社員だった。
彼女の友人によれば、青森県生まれで、上京後はカメラマンのアシスタント、ネイリストなど職を転々とし、20代前半に教育関連会社に勤めた後、人材派遣の大手・パソナグループ経営コンサルティング会社「I」に就職。以来、パソナグループの会社を渡り歩いて、現在に至っているという。
彼女が以前在籍していたパソナグループの元同僚は、「パソナグループ代表南部(靖之、62)さんの“お気に入り”として有名」だったと『文春』に話している。
同誌で、以前彼女と一緒に働いていた女性はこう語る。
「栩内さんは、異例の厚遇をされていました。今住んでいる南青山のマンションは家賃二十万円超とも言われますが、会社が借り上げてくれたものです。立場は“秘書”ということになっていましたが、タイムカードは押さなくていいし、幽霊社員のようなもの。よく見ると持ち物はブランド品ばかりでしたし、グループ内の別会社からお手当てが出てるのではないかと言われてました」
南部代表は元麻布に政財界のVIPを接待するための迎賓館「仁風林(にんぷうりん)」をもっているそうだ。そこで頻繁にパーティを催し、政界や芸能人なども多く訪れていたという。
ASKAは南部代表のお抱えアーティストで「仁風林」のパーティで2人は知り合ったといわれる。謎めいた女性の登場で、この事件の奥がますます深いことがわかる。
『週刊現代』(5/31号、以下『現代』)によれば、地震の規模より発生した場所と160kmという震源の深さが専門家を驚かせているという。
「この地域で、こんなに深い震源でのM6級の地震というものは、気象庁の観測開始以来、初めてのことだと思います。やはり3・11以来、日本列島の地震活動が変わってきている可能性がある」(東海大学教授長尾年恭(としやす)氏)
ここから週刊誌では“お約束”の地震予知の専門家が登場し、危ないのはいついつと予言する。今回は立命館大学歴史都市防災研究所の高橋学教授が、気象庁の地震記録データを精査してみたら、以下のことがわかったと話す。
「(1)それまで滅多に地震の起こっていない場所で地震が発生し、(2)約2週間、静かな期間が続き、(3)また周辺で地震が発生し始めると、(4)1~2日後に地下の力のバランス上、関係する地点でM7級以上の地震が発生する」
これを5月5日の地震に当てはめると、5月末にも大地震が来るかもしれないというのである。
『週刊ポスト』(5/23号、以下『ポスト』)によると、地震調査研究関連の予算は毎年100億円単位で投じられているのに、いつまでたってもこれといった成果が上がっていないという。
そんななか、地震研究の中枢からは大きく距離を置いているが、昨年からズバズバと地震予測を的中させている人物がいると報じている。
東京大学名誉教授で92~96年まで国際写真測量・リモートセンシング学会会長を務めた「測量学の世界的権威」である村井俊治氏だ。
村井氏が顧問を務める民間会社JESEA(地震科学探査機構)が週一回配信する『週刊MEGA地震予測』で、4月9日号から3週にわたって、首都圏での地震発生の可能性を示していたというのである。
村井氏の手法は測量技術の応用だという。国土地理院は95年の阪神・淡路大震災を機に、各地のGPSデータを測定する「電子基準点」を全国約1300か所に配備している。これを使うそうだ。
「これほどのGPS網が張り巡らされている国は、世界でも日本だけです。このデータが02年から利用できるようになった。我々が00~07年に起きたマグニチュード6以上の地震162件全てのGPSデータの追跡調査を行なったところ、地震の前に何らかの前兆現象が見られることに気がついたのです」(村井氏)
こうした分析に基づいて、昨年4月、淡路島で震度6弱の地震が発生したときも、その直後の4月17日に起こった三宅島地震(震度5強)も地震の可能性を指摘していた。東日本大震災の前にもその前兆をつかんでいたが「パニックになることを恐れて注意喚起ができなかった」そうだ。
「その結果、1万8000人もの人々が亡くなられたのです。これは学者としての恥です。ですから名誉を失っても、恥をかいても、今後は自分の理論において異常なら異常と公表する、と決断した」(同)
村井氏が指摘した今後注意すべき地域はゴールデンウィーク中に群発地震が起きていた岐阜県だという。
「春先から飛騨・高山中心に20か所くらいの電子基準点で大幅な上下動が観測されている。もっとも大きく動いているのは高山です」
『ポスト』は次の号(5/30号)でも「首都圏直撃地震からわずか8日後の5月13日午前8時35分、再び首都圏を地震が襲った。埼玉県南部や神奈川県東部で震度4を記録。東京都でも震度3を記録した」が、それも村井氏はメルマガで「可能性を予測」していたと報じている。
そのうえ、村井氏はこうも警告している。
「現時点で注意が必要なのは、北海道の函館の周辺です。今、全国的に基準点の短期の動きはほとんど目立たないのですが、今週届いた記録では函館にだけ動きが確認されました。(中略)函館だけではなく道南の広い地域で警戒が必要です」
津軽海峡を隔てた青森でも注意が必要だと村井氏は語っているが、これが発売された月曜日(5月19日)の夜(21時2分頃)、青森県東方沖でM4.2の地震が起きている。
あなたはこうした地震予知を信じますか?
ここで私の体験談を話させていただこう。阪神・淡路大震災は1995(平成7)年1月17日火曜日早朝に発生したことをご記憶だろうか。
当時『週刊現代』編集長だった私は、徹夜仕事を終えて家に帰るタクシーの中で地震のニュースを聞いた。だが、それほどの大地震とは思わず、そのまま寝てしまったのだから編集長失格である。編集部員の何度目かの電話で起きてテレビをつけ、呆然とした。部員に取材指示を出し慌てて出社すると、新聞社から私を取材したいという依頼が殺到していた。
地震前日の月曜日に発売した『現代』に「関西方面に地震が起きる」という予測記事を掲載していたのである。
「なぜ『現代』は地震を予知できたのか」聞きたいというのである。関西方面では雑誌が手に入らないのでコピーが回し読みされているという。余震は来ないか、来るとすればどれぐらいの規模なのか。被災した人たちは何でもいいから情報が欲しいという心境だったのだろう。
確たる根拠があるわけでもない記事を貪るように読んでいる被災者たちの気持ちを思うと、暗澹たる気分になったことを今でも覚えている。週刊誌の地震予測記事は、あくまでも「警告」であって、外れるのが当たり前なのだが、私のような万に一つのケースもあるので、頭の片隅に置いておく程度でいいと思う。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
今週は何といっても覚醒剤で逮捕されたASKAの記事が中心だ。昨年この問題をスクープした『週刊文春』は当然ながら内容が充実しているが、警察筋に強い『週刊新潮』が肉薄しているのがすごい!
第1位 「ASKA逮捕!」(『週刊文春』5/29号)
第2位 「家族に密告された覚醒剤常習『ASKA』禁断の乱用履歴」(『週刊新潮』5/29号)
第3位 「ASKAが溺れた『キメセク』そのあまりに危険な快楽」(『週刊ポスト』6/6号)
第3位。『ポスト』は控えめな記事づくりだが、芸能界には「麻薬逮捕者の互助会」があるというのが興味深い。
逮捕された芸能人が警察の取り調べに口を割らなければ、芸能界への復帰ができ、ミュージシャン仲間やテレビ局関係者、プロデューサーなどが「恩義」を感じて尽力してくれてヒットが出せるのだという。ほんとかね。
第2位。さて『新潮』はこう報じている。
「もう捕まえてください……。
『警視庁組織犯罪対策5課』捜査員の間を、その言葉が駆け巡っていた。
行動確認を続けていた彼らは、ASKAが覚醒剤を日常的に使用しているという確証を得て、洋子さん(ASKAの妻=筆者注)に接触。そして、そのやりとりの中で飛び出したのが、先に記した台詞なのだ。
さる捜査関係者は、
『ASKAが栩内(とちない=筆者注)の部屋を訪れる日の特定、自宅に覚醒剤やMDMAがあるという具体的な証言。これらについては、内部からの情報が不可欠だった』
と、逮捕には洋子さんの協力があったことを匂わせる。
『人の出入りは普段あまりない』(近所の住民)という目黒区のASKA邸だが、逮捕前日は打って変わって、
『関係者が続々訪れ、深夜まで部屋の明かりが消えることがなかった。翌朝のASKA逮捕を前提に、その後について、“作戦会議”をしていたようです』(芸能関係者)」
5月17日、午前7時30分。東京港区南青山の高級マンションからASKAが出てきたところを逮捕された。しかも、冒頭に引用した『新潮』によれば、ASKAの年上の妻が、もうこれ以上堪えられないから捕まえてくれと、捜査員に漏らしたというのである。これと同じ内容を翌日のスポーツ紙が後追いしていたが、これはスクープだ。
第1位。人気デュオ「CHAGE and ASKA」のASKA(本名・宮崎重明・56)の逮捕は『週刊文春』(2013年8月8日号)がスクープした「シャブ&飛鳥の衝撃」が発端である。
『文春』によると、捜査員はASKAが週末に栩内香澄美(37)の自宅に通ってシャブをやり朝帰りするというパターンを把握していた。
女の自宅から出たゴミの中からも薬物反応が出ているという。そのブツとはティッシュペーパーで、ASKAと栩内の性行為で使用されたため精液が付着していたという。
ASKA逮捕で俄然クローズアップされた栩内という女性だが、一体どんな女性なのだろうか。彼女は逮捕当時、パソナグループの中のメンタルヘルスケアを業務とする「セーフティネット」の社員だった。
彼女の友人によれば、青森県生まれで、上京後はカメラマンのアシスタント、ネイリストなど職を転々とし、20代前半に教育関連会社に勤めた後、人材派遣の大手・パソナグループ経営コンサルティング会社「I」に就職。以来、パソナグループの会社を渡り歩いて、現在に至っているという。
彼女が以前在籍していたパソナグループの元同僚は、「パソナグループ代表南部(靖之、62)さんの“お気に入り”として有名」だったと『文春』に話している。
同誌で、以前彼女と一緒に働いていた女性はこう語る。
「栩内さんは、異例の厚遇をされていました。今住んでいる南青山のマンションは家賃二十万円超とも言われますが、会社が借り上げてくれたものです。立場は“秘書”ということになっていましたが、タイムカードは押さなくていいし、幽霊社員のようなもの。よく見ると持ち物はブランド品ばかりでしたし、グループ内の別会社からお手当てが出てるのではないかと言われてました」
南部代表は元麻布に政財界のVIPを接待するための迎賓館「仁風林(にんぷうりん)」をもっているそうだ。そこで頻繁にパーティを催し、政界や芸能人なども多く訪れていたという。
ASKAは南部代表のお抱えアーティストで「仁風林」のパーティで2人は知り合ったといわれる。謎めいた女性の登場で、この事件の奥がますます深いことがわかる。