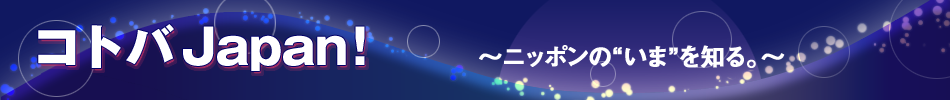[社会]
1月15日から始まった芦田愛菜(あしだ・まな、9)主演の児童養護施設を舞台にした日本テレビ系ドラマ。『高校教師』『人間・失格』『聖者の行進』などのドラマで、タブーをテレビドラマに持ち込むことで知られている脚本家の野島伸司氏(50)が脚本監修を務めている。
『週刊文春』(1/30号)によれば、第1話では、鈍器で恋人を殴る傷害事件を起こした母親に見捨てられ、グループホームにやってきた少女が、施設でリーダー的存在の「ポスト」(芦田)に出会う。
赤ちゃんポストに預けられ、親を知らないまま育っているためについたあだ名だ。新参者に付けられたあだ名は「ドンキ(鈍器)」。
その施設で“魔王”と呼ばれる冷酷非情な施設長から、朝ごはんの食卓を囲む子どもたちに、
「お前たちはペットショップの犬と同じだ」「犬だってお手ぐらいはできる。わかったら泣け。泣いたヤツから食っていい」
などと罵倒される。こうした扇情的な描写が功を奏したのか、初回視聴率は14%という好成績だったという。
だが、放送開始直後から施設関係者を傷つける恐れがあるなどとして「こうのとりのゆりかご」(赤ちゃんポスト)を設置する熊本市の慈恵病院のほか全国児童養護施設協議会、全国里親会が放送中止や表現の改善を求める抗議をし、慈恵病院は22日、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会に審議を求める申立書を送付した。
これを受けて番組のスポンサー全8社がCMを見合わせるという異常事態となり、2月4日、日テレ側は「放送の打ち切りや脚本を一から変えるような変更はしないが、改善する」と協議会側に伝え、文書で謝罪した。
朝日新聞(2/4付)では施設にいた経験のある20代女性が、いま施設にいる子を傷つけている現実がある以上内容は修正すべきだとしながら、こう語っている。
「私自身は、ドラマが描く子どもの心情に共感している。(中略)『親に捨てられたんじゃない、捨てたんだ』という主人公のせりふには、救われる思いがした」
自らも里親として二人を養育している喜連川智敬氏は『里親制度の何が問題なのか』(eBookJapanで2/14(金)発売)で、乳児院や児童養護施設などで暮らしている9割は、生みの親の病気や経済的事情・虐待などといった理由があって、同居できなくなっている子どもたちだと指摘し、施設出身者がこのドラマに“賛成”するのには、根深い問題があると書いている。
「施設出身者の現在が必ずしも幸福ではなかった場合、その原因を自分たちが育った施設に求めたとしてもなんら不思議はない。施設がドラマによって真実を歪められていると主張するのであれば、それを否定することで自らのアイデンティティを確認し、心理的な満足感を得られるということになるというわけだ。
一種の倒錯した心理で大なり小なり誰にでも見られるものだが、自分の居場所が不安定な『要保護児童』はこの傾向が顕著に現れる場合が多い。もちろん、それは養育する施設や里親のやり方にも問題があるからなのだが、こういった現象が『要保護児童』の養育を難しくしていることは間違いない」
現在「要保護児童」は全国で約4万7千人(2011年のデータ)いるといわれるが、そのうち里親に委託されている子どもは4000人余りに過ぎない。喜連川氏のいうように「なんらかの理由で不幸にして生みの親に育ててもらえない『要保護児童』だからといって、幸せに生きる権利が阻害されることがあってはならない」はずである。
このドラマがそうしたことを考え、里親制度を含めた制度改革をするきっかけになればいいのだが、抗議する側も日テレ側も議論を深めず、臭いものには蓋では、単なる視聴率稼ぎの番組づくりといわれても仕方あるまい。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
今週は週刊誌だからいえる記事を3本選んでみた。ご覧あれ!
第3位 「専門家が警告 糖質制限ダイエットで『寝たきり』が続出!」(『週刊現代』2/15号)
今流行の炭水化物ダイエットだが、これは危険だと警鐘を鳴らす記事。糖尿病の世界的権威、関西電力病院院長の清野裕(せいの・ゆたか)医師がこう解説する。
「人間には一日170gの糖が必要とされています。そのうちの120~130gは脳で消費され、30gは全身に酸素などを運ぶ赤血球のエネルギー源として消費されます。糖質は、生命を維持するために欠かせない栄養素なのです。
糖質を制限してしまうと、代わりにタンパク質を構成しているアミノ酸を、肝臓が糖に作り変えるというシステムが働き始めます。タンパク質を糖に変えられるなら、肉を食べれば問題ないのではないかと思う方もいるでしょう。しかし、人体の維持に必要なエネルギーをタンパク質や脂質でまかなおうと思ったら、毎日大量の肉を食べなければなりません。数kgもの肉を毎日食べ続けることは現実的に不可能です。糖エネルギーが不足すると、それを補うために、体は自分の筋肉を分解してアミノ酸に変えていきます。結果、筋肉量がどんどん減っていってしまうのです」
寝たきりの原因ナンバー1の脳卒中の危険性も増すという。それでもあなたは炭水化物ダイエットを続けますか?
第2位 「小林よしのり『脱・靖国論 安倍総理は靖国に行くな』」(『週刊ポスト』2/14号)
安倍首相のいう「靖国にヒーローはいない」「不戦の誓い」は靖国に対して失礼だと、ウルトラ保守の小林氏が叱っているが、頷ける指摘である。
第1位 「農薬混入事件で分かった『非正規』の深い恨み」(『AERA』2/10号)
マルハニチロの冷凍食品に農薬「マラチオン」を混入させた容疑で阿部利樹容疑者(49)が逮捕されたが、阿部容疑者は妻と子どもの3人暮らしで年収は約200万円。
元同僚は阿部容疑者に同情を感じるとまで言っている。
「会社の幹部が記者会見で、『従業員からの不満はなかった』と話すのを聞いた時は、怒りが込み上げてきた。表向きは会社が被害者なのだろうが、待遇を考えると、引き起こした遠因は会社にもあるのでは、と思わざるを得ない。他の人が事件を起こしていたかもしれない」
したがって「今も現場に不平不満の種は残り続けている。セキュリティー強化が根本的な解決になるのだろうか」とAERAは疑問を呈している。
こうした視点の記事が週刊誌にはもっとあってほしいものだ。
読んだ気になる!週刊誌 / 元木昌彦 [社会]