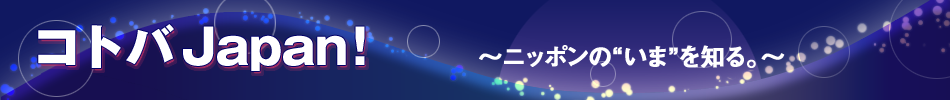『失楽園』『ひとひらの雪』『鈍感力』など数多くのベストセラーを生み出した作家。享年80。
1933年北海道空知郡砂川町(現・上砂川町)に生まれる。札幌医大医学部卒業。33歳で同医学部の整形外科学教室講師に着任。『死化粧』が芥川賞候補になる。
36歳の時、札幌医大・和田寿郎(じゅろう)教授による心臓移植事件を題材にした小説を発表し、同大学の講師を辞任して上京。
翌年、戦場で腕に銃創を負った二人の兵士の人生の明暗を描いた『光と影』で直木賞受賞。1983年、日経新聞に連載した不倫小説『ひとひらの雪』が評判になり、日経の部数が伸びたといわれ「ひとひら族」という言葉も生まれた。
W不倫を描いた『うたかた』で「うたかた族」。『失楽園』は1997年の流行語大賞を受賞した。79歳で上梓した『愛ふたたび』では男性の性的不能がテーマだったように、男女の愛と官能のあり方を生涯追及し続けた作家だった。
中国でも「言情大師(叙情の巨匠)」という異名で知られ、村上春樹と並んで人気作家となっている。
多くの週刊誌が追悼特集を組んでいるが、『週刊文春』(5/22号)によれば、次回は「少女の美しさを書きたい」といっていて、実際に10代の女の子と母親公認のもとでメールをやりとりしたり、食事をともにしていたという。
私が渡辺さんと親しく付き合ったのは『週刊現代』編集長時代だった。銀座のバー、料亭遊び、ゴルフなどを一緒にやり、大人の遊び方を教えてもらった。
あるとき、ゴルフが終わってクラブハウスで渡辺さんと話し込んでいるところへ川島なお美が駆けつけてきたことなど、懐かしい思い出である。
20数年前になるが、私がいた『月刊現代』で、渡辺さんと女優岸惠子さんの対談をお願いしたことがある。
テーマは忘れたが、対談中の渡辺さんが岸さんを視る眼のなんと優しかったことか。終わって、渡辺さんが誘って銀座のバーに行くのを見送った。遠慮したのは、明らかに渡辺さんが岸さんを口説こうとしている気配が色濃く漂っていたからである。その後の進展具合は残念ながら聞いていない。
私は渡辺さんの小説としては、スキャンダラスな面ばかりがクローズアップされる作品より、初期の作品『死化粧』『無影燈』や高校生の頃の恋人の死について書いた『阿寒に果つ』のほうが好きだ。
バイアグラが日本で発売された頃、私に熱心にその効用と使い方について話してくれたことがあった。
先に触れたように、近年は老いて性愛ができなくなった男の“女の愛し方”をテーマにした小説を書いていた。
そんな渡辺さんが『週刊ポスト』(以下『ポスト』)の「死ぬまでSEX」特集を叱ったことがある。
「死ぬまでセックス? そんなことできるわけがありません。人体というもの、雄というものが、何にもわかっていない。『ポスト』を作っているのは30~40代か、せいぜい50代の男性でしょう? 70、80の男の何がわかるのかね?(中略)
男性は勃起と射精に囚われすぎています。もちろん自分のペニスを女性の中に挿入したいと思う、これは男本来の願望でしょう。挿入して、射精しないかぎり満たされないと考える、人間の雄とはそういう生き物です。しかし、だからといって『死ぬまでセックスしたい』なんていうのは完全に間違っています。勃起して射精するというのは、大変なエネルギーと労力、そして気力が必要で、そんなことを死ぬ直前までできるわけがありません」(『ポスト』8/2号)
渡辺氏は年をとったらセックスより、優しく声をかけたり肌を愛撫することのほうが重要だと語る。
私がビジネス情報誌『エルネオス』(2010年3月号)で渡辺さんと対談したとき、男女についてこんなことを話してくれた。
渡辺 俺が思うには、創造主の神は、人間っていうものをつくるときに、性格も根本体力も弱い男を、一見、外見だけは大きく逞しく、瞬間暴力を強く創りたもうたんだ。これに対して女は、性格が強くフィジカル面も強いから、そのまま創るとバランスが取れない。だから小ぶりで愛らしく創りたもうた。これは素晴らしい創造主の叡智だね。
そして恋愛のすばらしさについてもこう語ってくれた。
渡辺 俺が『愛の流刑地』で、女って、好きな男によって、こんなにエクスタシーを感じて変貌するんだって書けたのは、たくさん恋愛をしてきたからわかる。あの女は、こんな感じかなって決めていたのが、恋愛してみると変わる。とんでもないものを食う人だったり、素晴らしい感性の持ち主だったりと、思いがけない発見がいっぱいある。そこが恋愛の凄みで、恋愛は実学の最たるものなんだ。だから、どんないい大学でも恋愛学って講座は持てない。
元木 文学の世界ですからね。
渡辺 まさしく文学だ。自分の中に潜んでいる未知の領域を、恋愛をして知ってほしい。俺って、こんなに好色なんだとか、女のこんなとこに惹かれるんだとか気がつくことがいっぱいある。
老いて未だ恋愛のなんたるかを知らず。渡辺さんの1000分の1でも恋愛をしていれば、女性についてもう少し知り得たのかもしれないな。渡辺さん、ありがとうございました。ゆっくりお休みください。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
週刊誌は読者の素朴な疑問に答えるのが王道である。もっと知りたい、なぜこうなるの、おかしいよ、これって。そんな疑問に答えている記事を3本選んでみた。
第1位 「91歳の認知症夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令 実名と素顔を公開 この裁判官はおかしい」(『週刊現代』5/24号)
第2位 「札幌連続ボンベ爆発事件 北海道警『誤認逮捕』疑惑」(『週刊朝日』5/23号)
第3位 「スクープ! 人間ドック学会理事長がついに告白『高血圧なんて、本当は気にしなくていい』」(『週刊現代』5/24号)
日本人間ドック学会と健康保険組合連合会が4月初旬に発表した「新たな健診の基本検査の基準範囲」が大きな話題になっている。
この欄でも書いたが、そこに記されていた健康の基準値が現行の値とは大きく異なっていたためである。例えば高血圧の場合、従来の正常の上限値である129よりも大幅に緩い147という新基準値が示されたのだ。
今週の『週刊現代』は渦中の人間ドック学会理事長・奈良昌治氏(83)の直撃に成功している。奈良氏によれば「高血圧なんて気にしなくていい」んだそうだ。
「確かに以前は、高血圧は怖かったですよ。われわれが医者になった60年前は、日本人には脳出血が非常に多かった。ところが、今では栄養状態がよくなって血管が丈夫になり、血圧が上がってもそう簡単に血管は破れなくなった。むしろ血圧が下がったときのほうが危ないこともあるのです。(中略)
特に人間は脳が心臓よりも高いので、脳に血液がいかなくなると深刻ですよ。駆け出しの医者が『血圧が高い、大変だ』ということでおじいさんにたくさん降圧剤を出すでしょう。すると脳に血がまわらず、あっという間にボケてしまう」
ちょっと血圧が高いと「クスリを飲みましょう」という医者は信用してはいけないそうだ。
2位は『週刊朝日』の記事。
「札幌市北区の商業施設や警察関連施設でカセットコンロ用ガスボンベによる爆発が相次いだ事件で、北海道警が道警官舎への爆発物破裂容疑で逮捕した無職・名須川早苗容疑者(51)の勾留理由開示の法廷が5月9日、札幌簡裁で開かれた。名須川容疑者の主張がはじまると、その“爆弾発言”に法廷は凍りついた。
『取り調べを受けていました』」(『朝日』)
札幌北署の駐車場で爆発が起きたのが1月27日朝だった。名須川容疑者は別の窃盗事件の事情聴取のため、同署の取調室にいたと明かしたのだ。「4月までの5件の爆発事件は同一犯としていた道警の主張が大きく揺らいだ瞬間だった」(同)
報じられているように、北海道内では名須川容疑者が逮捕されてからも、5月4日朝に道警の駐在所、6日には大型書店でガスボンベの爆発事件が発生している。
道警はこれについては模倣犯によるものと説明しているが疑問は残る。“冤罪”の二文字が浮かんでは消える。
第1位。91歳の認知症の夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令が出た名古屋高裁の判決を取り上げ、『現代』は、この裁判官はおかしいと怒り、地裁、高裁の裁判官の実名と素顔を公開している。
事故が起きたのは2007年12月7日の夕方。愛知県大府市に住むAさんは2000年から認知症の症状が出始め、この頃には要介護4と認定されるほど症状は進んでいた。
自分の名前も年齢もわからず自宅がどこなのかも認識できない。昼夜を問わず「生まれ育った場所に帰りたい」と家を出てしまう。
それでも家族はAさんを必死に介護した。長男は月に数度、週末を利用して横浜から大府にやってきた。長男の嫁は単身、大府に転居し、妻と一緒に介護に当たったという。
それでも悲劇は起こった。奥さんがウトウトした隙にAさんは家を出てJR東海の線路に入り込み、快速列車にはねられてしまった。JR東海側は損害賠償を求めた。
そして長門(ながと)栄吉名古屋高裁裁判長は360万円の支払いを妻に求めたのだ。長門裁判長は判決文の中でこう言っている。
「配偶者の一方が徘徊等により自傷又は他害のおそれを来すようになったりした場合には、他方配偶者は、それが自らの生活の一部であるかのように、見守りや介護等を行う身上監護の義務があるというべきである」
私も、この判決を聞いたとき、それはないだろうと叫んだ。
だが、昨年8月の名古屋地裁の判決はもっとひどかったのだ。上田哲(さとし)裁判長は、別居の長男にも720万円の賠償命令を下し、妻にも注意義務を怠ったと同額の支払いを命じたのである。
これからますます増える老老介護だが、こんな判決が出るのでは、認知症になった伴侶を殺して自分も死ぬしかないと思う老人が増えるはずだ。
1933年北海道空知郡砂川町(現・上砂川町)に生まれる。札幌医大医学部卒業。33歳で同医学部の整形外科学教室講師に着任。『死化粧』が芥川賞候補になる。
36歳の時、札幌医大・和田寿郎(じゅろう)教授による心臓移植事件を題材にした小説を発表し、同大学の講師を辞任して上京。
翌年、戦場で腕に銃創を負った二人の兵士の人生の明暗を描いた『光と影』で直木賞受賞。1983年、日経新聞に連載した不倫小説『ひとひらの雪』が評判になり、日経の部数が伸びたといわれ「ひとひら族」という言葉も生まれた。
W不倫を描いた『うたかた』で「うたかた族」。『失楽園』は1997年の流行語大賞を受賞した。79歳で上梓した『愛ふたたび』では男性の性的不能がテーマだったように、男女の愛と官能のあり方を生涯追及し続けた作家だった。
中国でも「言情大師(叙情の巨匠)」という異名で知られ、村上春樹と並んで人気作家となっている。
多くの週刊誌が追悼特集を組んでいるが、『週刊文春』(5/22号)によれば、次回は「少女の美しさを書きたい」といっていて、実際に10代の女の子と母親公認のもとでメールをやりとりしたり、食事をともにしていたという。
私が渡辺さんと親しく付き合ったのは『週刊現代』編集長時代だった。銀座のバー、料亭遊び、ゴルフなどを一緒にやり、大人の遊び方を教えてもらった。
あるとき、ゴルフが終わってクラブハウスで渡辺さんと話し込んでいるところへ川島なお美が駆けつけてきたことなど、懐かしい思い出である。
20数年前になるが、私がいた『月刊現代』で、渡辺さんと女優岸惠子さんの対談をお願いしたことがある。
テーマは忘れたが、対談中の渡辺さんが岸さんを視る眼のなんと優しかったことか。終わって、渡辺さんが誘って銀座のバーに行くのを見送った。遠慮したのは、明らかに渡辺さんが岸さんを口説こうとしている気配が色濃く漂っていたからである。その後の進展具合は残念ながら聞いていない。
私は渡辺さんの小説としては、スキャンダラスな面ばかりがクローズアップされる作品より、初期の作品『死化粧』『無影燈』や高校生の頃の恋人の死について書いた『阿寒に果つ』のほうが好きだ。
バイアグラが日本で発売された頃、私に熱心にその効用と使い方について話してくれたことがあった。
先に触れたように、近年は老いて性愛ができなくなった男の“女の愛し方”をテーマにした小説を書いていた。
そんな渡辺さんが『週刊ポスト』(以下『ポスト』)の「死ぬまでSEX」特集を叱ったことがある。
「死ぬまでセックス? そんなことできるわけがありません。人体というもの、雄というものが、何にもわかっていない。『ポスト』を作っているのは30~40代か、せいぜい50代の男性でしょう? 70、80の男の何がわかるのかね?(中略)
男性は勃起と射精に囚われすぎています。もちろん自分のペニスを女性の中に挿入したいと思う、これは男本来の願望でしょう。挿入して、射精しないかぎり満たされないと考える、人間の雄とはそういう生き物です。しかし、だからといって『死ぬまでセックスしたい』なんていうのは完全に間違っています。勃起して射精するというのは、大変なエネルギーと労力、そして気力が必要で、そんなことを死ぬ直前までできるわけがありません」(『ポスト』8/2号)
渡辺氏は年をとったらセックスより、優しく声をかけたり肌を愛撫することのほうが重要だと語る。
私がビジネス情報誌『エルネオス』(2010年3月号)で渡辺さんと対談したとき、男女についてこんなことを話してくれた。
渡辺 俺が思うには、創造主の神は、人間っていうものをつくるときに、性格も根本体力も弱い男を、一見、外見だけは大きく逞しく、瞬間暴力を強く創りたもうたんだ。これに対して女は、性格が強くフィジカル面も強いから、そのまま創るとバランスが取れない。だから小ぶりで愛らしく創りたもうた。これは素晴らしい創造主の叡智だね。
そして恋愛のすばらしさについてもこう語ってくれた。
渡辺 俺が『愛の流刑地』で、女って、好きな男によって、こんなにエクスタシーを感じて変貌するんだって書けたのは、たくさん恋愛をしてきたからわかる。あの女は、こんな感じかなって決めていたのが、恋愛してみると変わる。とんでもないものを食う人だったり、素晴らしい感性の持ち主だったりと、思いがけない発見がいっぱいある。そこが恋愛の凄みで、恋愛は実学の最たるものなんだ。だから、どんないい大学でも恋愛学って講座は持てない。
元木 文学の世界ですからね。
渡辺 まさしく文学だ。自分の中に潜んでいる未知の領域を、恋愛をして知ってほしい。俺って、こんなに好色なんだとか、女のこんなとこに惹かれるんだとか気がつくことがいっぱいある。
老いて未だ恋愛のなんたるかを知らず。渡辺さんの1000分の1でも恋愛をしていれば、女性についてもう少し知り得たのかもしれないな。渡辺さん、ありがとうございました。ゆっくりお休みください。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
週刊誌は読者の素朴な疑問に答えるのが王道である。もっと知りたい、なぜこうなるの、おかしいよ、これって。そんな疑問に答えている記事を3本選んでみた。
第1位 「91歳の認知症夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令 実名と素顔を公開 この裁判官はおかしい」(『週刊現代』5/24号)
第2位 「札幌連続ボンベ爆発事件 北海道警『誤認逮捕』疑惑」(『週刊朝日』5/23号)
第3位 「スクープ! 人間ドック学会理事長がついに告白『高血圧なんて、本当は気にしなくていい』」(『週刊現代』5/24号)
日本人間ドック学会と健康保険組合連合会が4月初旬に発表した「新たな健診の基本検査の基準範囲」が大きな話題になっている。
この欄でも書いたが、そこに記されていた健康の基準値が現行の値とは大きく異なっていたためである。例えば高血圧の場合、従来の正常の上限値である129よりも大幅に緩い147という新基準値が示されたのだ。
今週の『週刊現代』は渦中の人間ドック学会理事長・奈良昌治氏(83)の直撃に成功している。奈良氏によれば「高血圧なんて気にしなくていい」んだそうだ。
「確かに以前は、高血圧は怖かったですよ。われわれが医者になった60年前は、日本人には脳出血が非常に多かった。ところが、今では栄養状態がよくなって血管が丈夫になり、血圧が上がってもそう簡単に血管は破れなくなった。むしろ血圧が下がったときのほうが危ないこともあるのです。(中略)
特に人間は脳が心臓よりも高いので、脳に血液がいかなくなると深刻ですよ。駆け出しの医者が『血圧が高い、大変だ』ということでおじいさんにたくさん降圧剤を出すでしょう。すると脳に血がまわらず、あっという間にボケてしまう」
ちょっと血圧が高いと「クスリを飲みましょう」という医者は信用してはいけないそうだ。
2位は『週刊朝日』の記事。
「札幌市北区の商業施設や警察関連施設でカセットコンロ用ガスボンベによる爆発が相次いだ事件で、北海道警が道警官舎への爆発物破裂容疑で逮捕した無職・名須川早苗容疑者(51)の勾留理由開示の法廷が5月9日、札幌簡裁で開かれた。名須川容疑者の主張がはじまると、その“爆弾発言”に法廷は凍りついた。
『取り調べを受けていました』」(『朝日』)
札幌北署の駐車場で爆発が起きたのが1月27日朝だった。名須川容疑者は別の窃盗事件の事情聴取のため、同署の取調室にいたと明かしたのだ。「4月までの5件の爆発事件は同一犯としていた道警の主張が大きく揺らいだ瞬間だった」(同)
報じられているように、北海道内では名須川容疑者が逮捕されてからも、5月4日朝に道警の駐在所、6日には大型書店でガスボンベの爆発事件が発生している。
道警はこれについては模倣犯によるものと説明しているが疑問は残る。“冤罪”の二文字が浮かんでは消える。
第1位。91歳の認知症の夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令が出た名古屋高裁の判決を取り上げ、『現代』は、この裁判官はおかしいと怒り、地裁、高裁の裁判官の実名と素顔を公開している。
事故が起きたのは2007年12月7日の夕方。愛知県大府市に住むAさんは2000年から認知症の症状が出始め、この頃には要介護4と認定されるほど症状は進んでいた。
自分の名前も年齢もわからず自宅がどこなのかも認識できない。昼夜を問わず「生まれ育った場所に帰りたい」と家を出てしまう。
それでも家族はAさんを必死に介護した。長男は月に数度、週末を利用して横浜から大府にやってきた。長男の嫁は単身、大府に転居し、妻と一緒に介護に当たったという。
それでも悲劇は起こった。奥さんがウトウトした隙にAさんは家を出てJR東海の線路に入り込み、快速列車にはねられてしまった。JR東海側は損害賠償を求めた。
そして長門(ながと)栄吉名古屋高裁裁判長は360万円の支払いを妻に求めたのだ。長門裁判長は判決文の中でこう言っている。
「配偶者の一方が徘徊等により自傷又は他害のおそれを来すようになったりした場合には、他方配偶者は、それが自らの生活の一部であるかのように、見守りや介護等を行う身上監護の義務があるというべきである」
私も、この判決を聞いたとき、それはないだろうと叫んだ。
だが、昨年8月の名古屋地裁の判決はもっとひどかったのだ。上田哲(さとし)裁判長は、別居の長男にも720万円の賠償命令を下し、妻にも注意義務を怠ったと同額の支払いを命じたのである。
これからますます増える老老介護だが、こんな判決が出るのでは、認知症になった伴侶を殺して自分も死ぬしかないと思う老人が増えるはずだ。