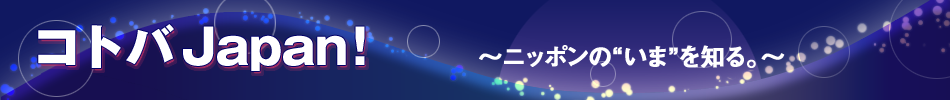"
第3回WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)準決勝でプエルトリコに敗れ,、侍JAPANの3連覇の夢が破れた。野村克也元監督の名言に「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」というのがあるが、敗退はWBC開幕前から決まっていたという見方が多い。かくいう私もそう思っていた。
開催前からケチがついた。収益金の分配や出場選手の報酬、待遇の格差を巡って日本選手会が参加拒否も辞さないという騒動に発展したのだ。結局、なし崩し的に出場が決まったものの全面解決にはほど遠く、WBCはMLB(メジャー・リーグ・ベースボール)の金儲け興行だというイメージが定着してしまった。
それはチケットの高さにも表れ、1次リーグの日本での試合は、一番いい席が1万4000円、外野席でも4000円もしたため、対中国戦では約36%しか席が埋まらなかった。
決定的な敗因の原因は二つある。一つは中心になる選手がいなかったことだ。第1回では王貞治監督、第2回ではイチローがチームを引っ張ったが、今回、それほどカリスマ性のある選手や監督はいない。
おまけに『フライデー』(3/22号)でメンバーの杉内俊哉と涌井(わくい)秀章が女性とのツーショットを撮られるなど、選手たちの緊張感の欠如も心配されていた。
いま一つの心配は山本浩二監督の采配にあった。広島監督時代は10シーズンでリーグ優勝は1度だけ、Bクラスが7度。それに加えて現役を退いてから長いための「現場勘」のなさだったが、その心配が現実のものとなった。
オランダ戦に勝った後「準決勝も前田健太でいく」と宣言してしまったことだった。『週刊新潮』(3/21号)でスポーツジャーナリストが、ブラジル戦で苦しんだのは相手投手の配球を知らなかったためなのに、「相手を知らずに苦い思いをしたという教訓をまったく活かさず、相手に先発を知らせて研究する余地を与えてしまっています」と呆れていた。
案の定、大リーグナンバーワンの捕手、プエルトリコのY・モリーナは研究し尽くした見事な投手リードで日本打線を翻弄した。
さらに2点をリードされた日本が8回に1点を返し、なおも1死1、2塁で4番・主砲阿部慎之助の打席に采配ミスが起きた。左バッターだから捕手は3塁に投げやすい。だから2塁走者は動かないと野球ファンなら誰しも考えるところである。だが、山本監督から「ダブルスチールにいってもいい」という信じられない曖昧なサインが出されるのだ。
2塁走者の井端弘和が走ったのを見た1塁走者の内川聖一は猛然と走り始める。だが井端はモリーナの強肩を恐れて2塁へ戻ってしまって、内川は2塁手前で憤死する。試合後内川は涙に暮れたが、野球をよく知る人間なら誰もが彼に同情するはずだ。
『日刊スポーツ』(3/19)は「大ざっぱで、曖昧で、ギャンブルだった。(中略)選手がすべてを背負い込んでしまうような采配だった」と厳しく批判している。
シーズン開幕を控え大物大リーガーが次々に出場辞退したアメリカは準決勝にも進めず、盛り上がりに欠ける大会だった。私見だが、公式シーズン前のこの時期にやるのを止めて、アメリカではワールドシリーズ、日本では日本シリーズが終わった後、真の世界一を決める大会として衣替えしてはどうか。
そうすればサッカーのW杯同様、WBCが世界の関心を集める一大イベントになるのは間違いない。
"