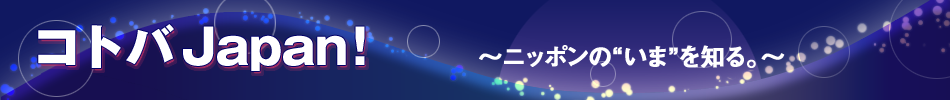[政治]
参院で野党が多数を占める「ねじれ国会」の下、永田町では手詰まり感が漂うが、新聞の政治面で頻出するのが「話し合い解散」という言葉である。文字通り、事前に与野党が話し合って衆院解散を行なうものだ。
新しい言葉ではない。戦後政治史では、1958(昭和33)年の解散が知られている。当時の岸信介首相(自民党総裁)と社会党委員長の鈴木茂三郎(もさぶろう)が会談し、解散の日取りや「社会党が内閣不信任決議案を上程し、採決直前に解散する」といった国会運営まで話し合った。「死んだふり解散」(1986年)、「郵政解散」(2005年)など、メディアは解散に通称を付けるが、この1958年の解散は「話し合い解散」と呼ばれている。
さて今回だが、野田佳彦(よしひこ)首相は、野党から特例国債法案成立への協力を得る代わりに衆院解散を迫られている。
解散権は首相の「伝家の宝刀」とされる。本来は、政権を維持するうえで最も都合のよいタイミングを見計らって首相が行使するものだ。だが、「ねじれ」のせいで、重要法案の成立がままならず、いま、野田首相は、法案を人質に解散権を自民党など野党側になかば奪われた格好だ。
その意味で、今回は「追い込まれ解散」という側面もある。