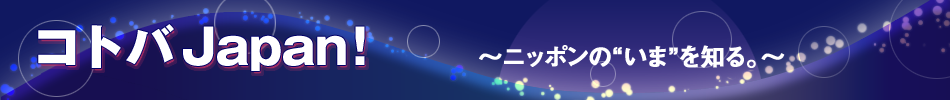布団のど真ん中に陣取る乳幼児の寝相。ときに驚くほどアクロバティックなポーズもあって、あどけない寝顔とともに、子育て疲れの親を癒してくれる。そんな睡眠中の姿を生かし、タオル・おもちゃなどで「背景」をつくり、絵本のような世界を演出して撮る写真が密かなブームを呼んでいるという。火付け役は主婦業と漫画家を両立させている小出真朱(こいで・まみ)氏。夜、仕事中の夫に娘の画像を送るために始めたそうだ。あくまで子どもの安眠を優先させるのが鉄則、とか。
その「作品」群はネット上で注目を集め、写真集『ねぞうアートの本―寝ている間にHAPPY赤ちゃん写真』(ぶんか社)も出版された。版元と出版取次トーハンによって「ねぞうアートコンテスト」も開催され、同好の士(母?)も増えているようだ。乳幼児の子育ては孤独感に陥りやすいもの。遊び心がアートに昇華したアイデアは、なかなか秀逸である。