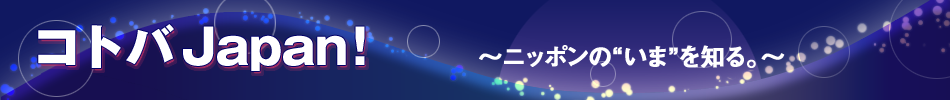私はアパレルとファッションとは違うものだと思っていたが、同じもののようだ。
だから、『週刊現代』(9/2号、以下『現代』)が
「誰がアパレルを殺したか」で、女性の消費行動が変わり、彼女たちが「働いたり、普段の生活をするための服しか買わなくなった。ビジネスカジュアルならZARA、パート勤務ならH&Mでいい」(小島ファッションマーケティング・小島健輔代表)となったから、アパレル業界がだめになったというのは少しおかしいのではないか。
ユニクロもしまむらもZARAも同じアパレルだからだ。だからアパレル大手4社、オンワードHD、三陽商会、TSIホールディングス、ワールドの15年度の売り上げが約8000億円で、前年に比べ1割も低下しているから、
アパレル業界が「死に向かっている」(『現代』)といういい方もおかしいことになる。
ユニクロやしまむらなどはまだまだ成長しているからである。
と、『現代』の特集にケチをつけても仕方ないが、デパートなどで売っている高いブランド女性洋品や男物のスーツなどが売れなくなったので、渋谷などのセレクトショップには若い女性が押しかけている。
また、ファッション通販大手の「ZOZOTOWN」などは上場以来増収増益を続けており、「営業利益ではすでに
三越伊勢丹ホールディングスを抜くほどになっている」(『現代』)ようである。
要は、時代のニーズに合わない古臭いものを大量生産しているアパレルメーカーに女性たちが手を出さなくなっているので、それは
どこの業界でも同じであろう。
もう40年以上前になるが、1週間ほどパリに取材で行ったことがある。私はファッションにはとんと興味のない人間だが、シャンゼリゼ通りの小粋なカフェでコーヒーを飲みながら、行き交う女性たちのファッションセンスの良さにため息を漏らしたものであった。
パリジャンに聞いてみると、そのほとんどがノーブランドか手製であるというのだ。高いブランド品を着ていれば素敵に見えるという妄想を抱いていた私は、これではいつまでたっても日本の女性のファッションセンスは磨かれないだろうと思った。
案の定、日本にもバブルが来て、ディオールやエルメスで着飾る女性たちが輩出したが、サルがブランドを着て歩くがごときで、センスが磨かれることはなかった。
私事で恐縮だが、当時、私もアルマーニというブランドが好きで、背広はもちろんワイシャツ、ネクタイ、バッグに至るまで全身アルマーニだった時代があった。
背広一着が30万、50万。アルマーニを着ていることで自分がリチャード・ギアになったつもりで銀座の夜を闊歩していた。
私が思うに、そんな日本人のブランド志向を完膚なきまでに叩き壊した「偉人」が二人いた。
ビートたけしと泉ピン子である。
たけしがアルマーニの背広でテレビや映画に出てきたときは衝撃的だった。黒のバカ高い背広だろうが、まるで羽織袴を引きずっているかのようで、見るに堪えなかった。
やはり、アルマーニはイタリア男のように背は低くてもがっしりした体形でなくては似合わない。たけしの不格好な姿を見てすぐに、持っていたアルマーニの背広を燃えるゴミに出してしまった。
もっとブランド側にショックだったのはピン子が全身シャネラーとして人前に現れた時であった。「シャネルを着た悪魔」。これは“事件”だったといってもいいのではないか。
シャネルはファッション雑誌にとって死ぬほど欲しいナショナルブランドである。だが、雑誌の女性編集長に聞いたところによると、シャネルほど広告や記事に注文を付けてくる、うるさいブランドはないと嘆いていた。
それほどまでにブランドを守り、世界中の映画スターたちに自社ブランドを着せてきたシャネルだったが、そんなシャネルにもできないことが一つあった。
着る女性を選べないことである。私がシャネルの広報だったら、飛んで行って、ピン子に「何億でも払うからうちのブランドを着て外を歩くのだけはやめてください」と土下座したであろう。
私の知り合いにも資産数百億円というシャネラーがいる。シャネラーというのは、すべて同じブランドで統一しなくてはいけないそうだ。
彼女ももちろんそうであった。あるときゴルフに誘った。ゴルフ場で会った時、目を見張った。ゴルフウェアーも全身シャネルだったのである。違うのはクラブとボールだけ。キャディもゴルフの腕前にではなく、ファッションにうっとりしていた。だが、彼女はシャネラーの資格のある美人だった。
だが、たけしとピン子の2人の姿は言葉では形容できないほど無残であった。それまで培ってきた2つのブランドの幻想を完膚なきまでに地に叩き落とし、破壊したのだ。
その結果、借金してまでブランド品を追い求め、買いあさっていた女性たちの目を覚まさせたのである。
ある程度のブランド力を持っていた先のアパレル大手4社は、この時、気が付かなければいけなかったのだ。だが、バブルが弾け、ファストファッションが台頭する中で、
「アパレル各社は目先の売り上げを立てようと、生産拠点を中国に移し、大量生産でコストカットを図ってきました。国内のマーケットは縮小しているにもかかわらず、製品の品質には目をつぶり、
過剰に製品を供給することで生き延びようとしたのです」(
『誰がアパレルを殺すのか』の著者の一人・杉原淳一氏)
そしてユニクロが出てくれば、これからは低価格路線だとコストカットに躍起になり、品質は低下し、社内で肩で風を切って歩いていたデザイナーやパタンナーが
次々に辞めていった。
その人たちが独立して、低価格のブランドのデザインを請け負うようになったというから皮肉なものである。
そこへ先ほど触れた
通販サイトができて、膨大な量の衣服を一覧できる。昔は手を出さなかったセコハン洋品にも、今の女性は抵抗がない。
気に入ったものはセレクトショップという流れの中で、
それに棹さしたのが一冊の本だったと思う。
大ベストセラーになった
『フランス人は10着しか服を持たない~パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘訣』(ジェニファー・L・スコット著・大和書房)である。
「間食はせず、食事を存分に楽しむ。上質なものを少しだけ持ち、大切に使う。日常の中に、ささやかな喜びを見つける。情熱的に、お金をかけずに、生活を心から楽しむ方法が満載」(アマゾンの本の紹介から)
ミニマリズムの流行もその流れの中にあるはずだ。
『現代』は、その一方でエルメスが売り上げを伸ばしていると書いているが、いつの時代でもブランドにカネをつぎ込む金持ちはいるのだから、そういう人間だけを相手にするブランドは昔ほどではないが、まだ生き延びるのだろう。
だが、ボストンバッグのような数百万もするバーキンとかいう重たいバッグが小柄な日本人に似合うはずがないではないか。
私も今、ミニマリズムというか断捨離に凝っていて、本、CD、DVD、背広からブレザー、昔の資料などをどんどん捨てている。
たしかにこれは癖になる。捨てられなかった名刺の山をエイヤと捨てた時の快感は、なかなかいいものだった。ブランド品はいらない。一人2万円もするフレンチや和食を食べるより、京成立石の居酒屋で飲むほうがいい。
人生の敗者の遠吠えかもしれないが、身の丈に合った生活がいいとようやく思えるようになった。
最後に、『現代』の
「ZOZOTOWN社長の『異形の履歴書』」という記事にも触れておこう。この社長、前澤友作という。41歳。この「ZOZOTOWN」を運営する会社スタートトゥデイの本社は千葉・海浜幕張。200人以上の社員が仕切りのない大部屋にいて、基本給とボーナスは従業員一律。違うのは役職給だけ。
6時間労働制で、9時出社だと15時退社になる。2007年に東証マザーズに上場した時の時価は366億円だったが、
今夏は1兆円を超えたという。
この社長、早稲田実業学校高等部卒だという。千葉の鎌ヶ谷出身で、千葉への愛情が半端でないらしい。現在建てている100億円の新居も千葉市内。
高校を出てインディーズバンドをやったりしているうちに、海外のCDやレコードのカタログ販売に手を付け、カタログ通販で年商1億円に。そこから現在のような会社をつくって成功したらしい。
アート作品へのカネのつぎ込み方も尋常ではないという。まあ、これだけカネがあれば何でもできるだろうが。
ネット通販はこれからも雨後の筍のように出てくるだろうが、よほどの差別化を図らない限り、生き残るのは大変だろう。10年後、「ZOZOTOWN」がどうなっているのか、楽しみではある。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
ノンフィクション・ライターというのは哀れである。若いうちは文章が下手でも体を動かせばそれなりに稼げる。だが、長い時間をかけて本を書いても初版は数千、重版はなし。出版社はすぐに絶版にしてしまう。書く媒体はどんどんなくなり、老後は暗澹たるものになる。出版社はノンフィクションに冷たすぎる。これでは優れたノンフィクション・ライターなど出てくるわけはない。
「ノンフィクション・ライター死んだ。出版社も死ね」そう叫びたくなるこのごろである。
第1位 「75歳まで働かされるニッポン」(『週刊ポスト』9/1号)
第2位 「山田太一、83歳。『私はもう原稿が書けない、ドラマを観る気力すらない』」(『週刊ポスト』9/1号)
第3位 「米朝開戦」(『週刊現代』9/2号)
第3位。『現代』が
「米朝開戦」かと、ドでかい特集を巻頭で組んでいるが、残念ながらというべきか幸いなことに、その危機は今のところなさそうである。
トランプ米大統領も金正恩もそこまでバカではないということだ。騒いでいるのは週刊誌と、支持率を上げるためには北朝鮮危機が起こればいいと内心考えている安倍首相ぐらいではないか。
トランプの側近中の側近だったバノン大統領首席戦略官が突然、首を切られたが、彼のようなウルトラ右派でさえ、こう言っているのだ。
「北朝鮮問題は余興に過ぎない。軍事的解決などあり得ない。忘れてよい」
ロシアンゲートだけではなく、人種差別問題でも非難を浴びているトランプには、北朝鮮から飛んでくるICBMなどよりも、国内から飛んでくる非難の礫のほうが怖いというのが本音であろう。
それに側近といわれた人間が次々に離れ、今や自分の身内しかいなくなってしまったトランプに、軍隊を動かせる力はない。
中国がせせら笑っているはずだ。
第2位。
山田太一という脚本家は天才だと思う。『岸辺のアルバム』『ふぞろいの林檎たち』、中でも鶴田浩二主演の『男たちの旅路』は素晴らしいドラマだった。
その山田も83歳になり、今年1月、自宅を出たところで倒れ、意識不明のまま救急車で搬送されたという。
脳出血で、倒れてから3日間の記憶が全くないという。
退院したのは6月で、言語機能は回復しつつあるが、
脚本を執筆する状態ではないようだ。
テレビも観る気力がわかず、ひとりで散歩に出ることもかなわないという。
次の作品を書いて、それから仕事を辞め、遊ぼうと思っていたが、「人生、なかなか思い通りにならないですね」(山田)
山田はこう語っている。
「人生は自分の意思でどうにかなることは少ないと、つくづく思います。生も、老いも。そもそも人は、生まれたときからひとりひとり違う限界を抱えている。性別も親も容姿も、それに生まれてくる時代も選ぶことができません。生きていくということは限界を受け入れることであり、諦めを知ることでもあると思います。でも、それはネガティブなことではありません。
諦めるということは自分が“明らかになる”ことでもあります。良いことも悪いことも引き受けて、その限界の中で、どう生きていくかが大切なのだと思います」
山田のような高名な脚本家は、つらいだろうが、書けなくなっても生活に困ることはないだろう。じっくり養生して、書きたいものがあったら口述でもできるかもしれない。
だが、ノンフィクション・ライターはそうはいかない。
松田賢弥という優れた記者がいる。小沢一郎を追いかけて、私が『週刊現代』編集長時代に小沢批判キャンペーンを続け、その後、『週刊文春』で小沢の妻からの「離縁状」をスクープした男である。
野中広務に食い込み、彼のインタビューをもとに数々のスクープをものにもした。
小沢と同じ岩手県の出身で、東北人らしく黙々と地を這うような地道な取材をする。原稿は足で書く、を実践してきた今ではまれな記者である。
その彼が3月初め、2度目の脳梗塞で倒れた。虎の門病院に入院して手術をしたが、左手に後遺症が残った。
現在、リハビリを続けているが、言葉もスムーズには出てこない。時々ふっと記憶を失うことがあるという。
私が見る限り、もう一度物書きとして再起できるかというと、かなり難しいかもしれない。
残念なことに、彼には再婚した妻との間に子どもがいるが、脳梗塞になる前に離婚していた。
離婚に至る夫婦の間には、いろいろなことがあったのであろう。子どもに会いたいと彼はいうが、離婚後、一度も会ってはいないそうだ。元妻もほとんど顔を出さない。
地元には90歳を超える母親がいるが、もはや彼が身を寄せられる場所ではない。
あまり人付き合いのいいほうではなかった。親族との付き合いも疎遠であった。『現代』や『文春』の編集者たちは退院後もカンパしてくれたりと、何かと面倒を見てくれてはいるが、60をいくつか過ぎた松田の老後は、大変であろうと思わざるを得ない。
それでなくともノンフィクション・ライターの老後は生きがたい。私は、そうしたケースをいやというほど見てきている。
若い時は花形ライターとしてもてはやされ、稼ぎもかなりのものがあった。
しかし、当然ながらこの仕事には退職金もなければ、年を食ったからといって原稿料が上がるわけでもない。
有名なノンフィクション賞をとり、何冊も本を出したが、そのほとんどが絶版になっているから、印税もない。
出版社は、ノンフィクションは売れないからと言って、そうしたライターたちの支えになる雑誌まで潰してしまった。
長い時間をかけて資料を漁り、読みこみ、取材してまとめても、初版はせいぜい数千部。重版されることは稀である。
本田靖春さんのことを少し書いておこう。ノンフィクション作家として一時代を築いた本田さんだったが、50代半ばから重い糖尿を患い、60になるあたりから執筆できなくなっていた。
だが、糖尿のためのインシュリンは毎週打たなければいけない。今はたしか保険が適用されるが、その頃はかなりの額を払わなければならない。行き帰りにはタクシーを使うとかなりの物入りになった。
私は『週刊現代』の編集長で、本田さんに連載を書いてもらっていたが、中断していた。私の一存で、休載中も本田さんに毎週原稿料を払い続けた。
それは、彼のような優れたノンフィクションを書く作家が苦しんでいるのに、出版社が救わなくていいわけはない。たとえ、背信行為、横領だといわれようと、俺は本田さんのためにできることをやるという思いからだった。
私が編集長を辞めるまでの3年以上に渡って、本田さんに払い続けた。残念ながら、連載を再開することはなかったが。
本田さんからは、君のおかげで生き延びることができたといわれたが、編集者として当然のことをやったまでだ。
本田さんはその後、『月刊現代』で「我、拗ね者として生涯を閉ず」を亡くなる直前まで連載してくれた。編集者冥利に尽きるというものである。
今のままではノンフィクションなどを書く人間はいなくなってしまう。それでもいいと出版社はいうだろう。しかし、70年代初めに起きたノンフィクション勃興期を知っている世代は、今の惨状を少しでもよくするために何ができるか、出版社はもちろんのこと、現場の編集者たちにも真剣に考えてほしいと思う。
出版社は、執筆する人間がいて成り立つこと、今さら言うまでもないが、忘れているアホな経営陣がいることは間違いない。
松田のような人間一人助けられなくて、出版社社員だとか編集者だとかいうな。彼を病室に送りながら、松田の背中にそう吠えたくなった。
第1位は、『ポスト』の
安倍政権の考えていることは75歳まで働けということだと喝破している巻頭特集。
要は、年金・医療・介護を合わせた社会保障制度を「革命的」に悪くさせようというものだということである。
『ポスト』の小見出しを見ただけで、よくわかる。
「高齢者は働いて社会保障の“支え手”になれ」
「楽隠居は認めない。死ぬまで働け」
「健康なうちは年金を支給しない」
「自己責任で老後資金を捻出せよ」
「90歳になるまで医療費は3割負担で」
「高齢者は介護施設から出てってくれ」
「でも、子供や孫世代からも搾取します」
『ポスト』はこう結ぶ。
「安倍首相が『成長戦略』を話し合う未来投資会議で介護や医療の論議をしていること自体、社会保障を高齢者のためでも子孫のためでもなく、
金儲けの種としか考えていない証拠なのだ」
何も付け加えることはない。『ポスト』のいうとおりである。