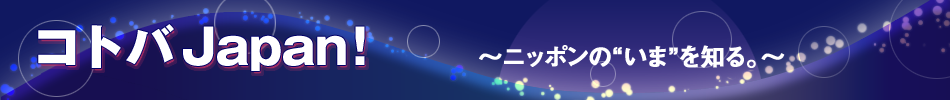高速増殖炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)は三人寄れば
「文殊」の知恵からきているが、バカが何千人寄り集まってもバカはバカ、知恵など出て来なかった。
「もんじゅ」は、原発から出る使用済み核燃料(ゴミ)をリサイクルして新しい核燃料につくりかえ、それを高速増殖炉で使えば、ウランなどを輸入してこなくてもいいという
“夢みたいな”計画からつくられた。
だが夢は夢のまま
ゴミになる可能性が高いようだ。この構想ができたのは1960年代で施設をつくりだしたのは1980年代。ようやく動きだしたのは1990年代である。
核燃料サイクルに必要な再処理工場を
青森県・六ヶ所村につくったが、こちらも未だ失敗続きで見込みはまったく立たない。
『週刊現代』(以下『現代』)は10/8号で「血税1兆2000億円がパー『もんじゅ』の責任、誰が取るのか」という特集をやっているが、
目次の中でも小さくて目立たない。『現代』のこの扱いが日本人のこの問題に対する
「無関心」を象徴している。
だが、この「もんじゅ」の廃炉が検討されているというニュースは、日本中が政府に対して怨嗟の声を上げなければならない
重大な問題であるはずだ。
厚顔無恥な安倍首相が推し進めている
「原発再稼働」政策を根底から覆すことになるからである。
昨年末に、国の原子力規制委員会は「もんじゅ」で重要な機器の点検漏れなどが相次いでいることから、法律に基づく施設の使用停止命令を出す方向で調査を進めていると、各メディアが報じた。
『現代』によれば、8月末に、菅義偉官房長官のチームの下で
「もんじゅ」廃炉を視野に入れながら今後検討していくということが発覚したという。
「政府は、現行計画でもんじゅを運転しようとすると、約6000億円の追加支出が必要だという試算を出しました。
その額があまりに大きいため、廃炉の可能性も考慮し始めたようです」(全国紙政治部記者)
9月16日には茂木敏充自民党政調会長までがこう言った。
「もんじゅは運転停止が6年間続き、この22年間で運転した期間はわずか250日にとどまっています。昨年11月には原子力規制委員会が運営主体の変更を勧告しましたが、新たな運営主体も決まらない状況。廃炉以外の選択肢はないとまでは言わないが、私の想像力を超えています」
安倍の側近たちが本当に「原発再稼働」の最大の障害になる「もんじゅ」廃炉に本気で取り組むのか、私ははなはだ疑問だが、この役立たずのカネ食い虫は、日本政府の重荷になっていることは間違いない。
トイレのないマンションといわれる原発だが、持って行き場のない使用済み核燃料という危険極まりない便が原発の中に溜まり続けている。だが、それがあふれ出てくるのをただ手を拱(こまね)いて待っているだけで、手のうちようがないのだ。
このままいけば使用済み核燃料は確実に
日本中を覆い尽くし、すべてを死滅させる。
高速増殖炉をやっていたアメリカ、イギリス、ドイツなどはすでに中止している。フランスだけはまだ未練を持ち、日本に研究させて、もしうまくいけば自国でもと考えているようだが、これも日本の失敗で諦めざるを得ないだろう。
さすがの安倍首相も、停止中でも「もんじゅ」を維持するために、原子炉を冷却するナトリウムの管理、放射線量のチェック、部品の点検などに
年間約200億円が注ぎ込まれている巨大なでくの坊に、我慢ならなくなったのであろうか。
しかし廃炉にするにしても3000億円はかかるといわれる。それにこれまでにかかった費用はなんと1兆2000億円。
しかしながら歴代政府、文科省、原子力発電を推進する経済産業省、予算をつけてきた財務省などからは
「『反省』の声は聞こえてこない」(『現代』)。
「国策として始まったもんじゅは、着地点を見出さずに計画がスタートしたため、当初数百億円だった建設費が、1600億円、4000億円、5900億円とどんどん膨れ上がっていきました。一度予算がつくとそれに慣れてしまい、やめられなくなる。まさに日本の官僚機構の宿痾(しゃくあ)です」(「もんじゅ」に関する市民検討委員会委員の福武公子弁護士)
その上「もんじゅ」は95年に大惨事寸前の大事故を起こすのである。
「燃料冷却用の液体ナトリウムが漏れ出し、空気に触れて火災が起きたのです。その後、事故の隠蔽なども問題となりました。そもそもナトリウムは空気に触れると火が出る危険なもの。また、ほかの原発と違って、トラブルが起きても、原子炉に『不活性ガス』という特殊なガスが入っているので、蓋も簡単に開けることができない。非常にリスクが高い原発なのです」(元東芝の原子炉技術者・後藤政志氏)
運営主体の原研機構(日本原子力研究開発機構)にも湯水のように研究費が投じられてきた。
地元・福井の自治体の首長や議員たちは、当然ながら廃炉については反対、継続を望むと言うが、地元の利益だけしか考えず、
日本全体の安心・安全を考えていないと言われても致し方あるまい。
だが、「もんじゅ」は高い代償を払って廃炉にするとしても、「もんじゅ」を見捨てるということは
「原発政策もろとも否定することになる」(原発差し止め訴訟などに関わる河合弘之弁護士)のだ。さて、安倍政権はどうするのか。
「側近に廃炉を示唆させ、一方で閣僚には原発推進政策を吹聴させる。『もんじゅの廃炉はするが、かわりに原発を稼働させる』と、
アメとムチの巧妙な支持率対策をしているように見えます」(全国紙政治部記者)
バカも休み休み言え。核燃料サイクル計画が破綻したのだから、これ以上核の便を貯めないためにも即刻、全原発を停止し廃炉にするべきである。
バカな安倍たちの思い通りにしていたら、日本だけではなく、世界中を放射能の死の灰が覆うことになる。
もんじゅ廃炉は、日本の原発政策が間違っていたことの証左なのだから、安倍を含めた連中のおかしな言い分を聞くことはない。こんなことは10歳の子どもでもわかる。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
矢部宏治氏が書いた『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』(ともに集英社インターナショナル)がすこぶるおもしろい。2冊とも結論は、
日本は未だにアメリカの占領状態が続いているからだというものだが、これまでの類書と違うところは、その事実をこれまで明らかになっている公文書で実証していることである。
安倍首相の発言のほとんどが、アメリカの意向で「言わされている」ことがよくわかる。戦後70年以上の長きにわたって日本人は占領軍の「洗脳」から解き放たれていないのだ。嗚呼!
第1位 「『甲状腺検査は必要ない』の仰天! 福島母たち 届けられた県通達への憤怨」(『女性自身』10/4号)
第2位 「意味不明が多すぎる『豊洲のパンドラ』20の疑問」(『週刊新潮』9/29号)/「豊洲の『戦犯』石原慎太郎とドン内田」(『週刊文春』9/29号)
第3位 「若大将 加山雄三にゴーストライターがいた!」(『週刊文春』9/29号)
第3位。『文春』が、
加山雄三に「ゴーストライターがいた」と報じている。それも初期の頃の「恋は紅いバラ(Dedicated)」や「ブーメラン・ベイビー」「マイ・ジプシー・ダンス」などの英語の歌詞を書いたというのだ。
きっかけは1本の留守番電話に吹き込まれた以下のような加山の音声であった。
「僕の名前と君の名前では値打ちが違うからね。(報酬が支払われたら)お金を送るように努力するよ。それでいいかい? だから君はこれまでと同じように僕のゴーストライターでいてくれないといけないんだ」(原文は英語)
この相手は、加山の妹と結婚し、離婚した元米軍厚木基地にいたマイケル・ルノー氏。
ルノー氏は、60年代に加山のために作った11曲と、15年に発表された「I Simple Say」の作詞のおカネを合わせて払ってくれと加山に要求していたのだが、いつまでも払われないので、米国と日本で訴訟を起こす準備を始めていると、加山側に通告したそうである。
さあ加山はどう答えるのか。
加山は「I Simple Say」についてはルノー氏の作詞だと認めたが、それだけでは足りないので、自分で足して書いたから「僕の作詞」だと言う。
これはやや苦しい言い訳だが、昔の曲については、その当時親しかったルノー氏に、英語の表現がおかしくないかを修正してもらっただけだというのだから、これは頷ける。
どうやらここまで話がこじれたのには、加山の吝嗇(りんしょく)が原因であるらしい。ルノー氏と加山の妹は70年代に離婚しているのだが、「加山さん自身、亮子さん(妹=筆者注)とは、お金をめぐるトラブルが原因で
十数年前に絶縁していて、彼女は以前住んでいた港区内の高級マンションを出て、現在はお子さん二人と困窮されていると聞きます」(当時の二人を知る人物)
ゴーストライター問題よりも、このほうが加山にとっては大きなイメージダウンになると思うが。
加山には
「ぼくの妹に」といういい曲があるが、あの歌を歌う加山の笑顔の裏に骨肉の争いがあるとすれば、素直に聴くことができなくなるからだ。
第2位。本来単純だった話が、時間を追うごとに複雑になっていくのは、当事者たちが自分に
火の粉が降りかかるのを怖れたり、責任逃れをするからである。
豊洲市場移転問題がその典型であろう。都議会のドンといわれ、都政を我が物顔に牛耳ってきた内田茂都議の「悪行」については『文春』をはじめ様々な週刊誌が書き立ててきた。だが、舛添要一前都知事を遙かに超える額の税金を湯水のように使って毎晩のように料亭、高級レストランで散財し、その上、新銀行東京なるバカなものを立ち上げ1400億円もの巨費をドブに投げ捨てた
「巨悪」石原慎太郎元都知事については、メディアは忘れ去ったかのように見えた。
豊洲の盛り土問題について石原の証言が二転三転していくことで、ようやく、この男のデタラメな都政運営が明らかになろうとしているのは、私は大歓迎である。
『文春』によると、石原が都知事になった99年当時、都が推し進めてきた臨海副都心開発が失敗に終わり累積5000億円超もの赤字を抱えていた。
そこで石原は、「黒字の羽田沖埋立事業会計などと統合させ、赤字を見えにくくした。そして、築地市場を豊洲に移転させて、超一等地の市場跡地を民間に高値で売却し、赤字削減と臨海再開発の
一挙両得を狙ったのです」(元都庁幹部)
目をつけた東京ガスの跡地は当初交渉が難航していたが、石原の腹心の浜渦副知事を交渉担当として、東京のきれいな土地と、様々な危険物質で汚染されている東京ガスの土地を等価交換するなど、不可解な契約までして、手に入れるのである。
「通常、土壌が汚染されたような土地を買う場合、価格を割り引くのが当たり前。が、都は、売買価格を算出する際、財産価格審議会に“現在は汚染物質は存在していない”として通常価格で計算させている。なぜこのような経緯になったのか。都は一連の交渉過程を公開すべきです」(この問題に詳しいルポライターの永尾俊彦氏、『新潮』)
ベンゼン、シアンが環境基準の何百倍、何千倍も検出されている土地のため、土壌汚染対策を徹底的にやると当時の市場長が言っていたのに、石原は
「時間もかかる。カネもかかる。そこまでやることないだろ」と言い出し、会見でコンクリ箱を作れば安くて早いと言ったのだ。
石原が言い出しっぺだったのに、はじめは関知しないと逃れようとした。だが、数々の事実や都庁内からの批判が出てきて観念したのか、9月21日に文書を発表した。
そこには冒頭、自分の知事在任中のことで大きな混乱と懸念を生じさせたことを詫びている。この件は専門家の意見を聞いて進めたもので、「私が土壌汚染を無視して予算と完成時期だけにこだわり強引に今回問題になっている構造にさせたといった指摘がなされているようですが、そのような事実は断じてありません」と型通りに否定している。
誰も、知事一人でやったと言ってはいない。最大の権力者が、自分の腹心と、息のかかった都庁の人間にやらせたのであろう。
石原は「都は伏魔殿だ」と言ったが、その伏魔殿を牛耳り、やりたい放題やったのが石原と内田である。
『新潮』は、盛り土が全体に行なわれていなかったと騒ぐが、専門家は、盛り土の上に建物を建てると
「豆腐の上に家を建てるようなもの」(一級建築士の田岡照良氏)で、「地下部分に空間を作らず盛り土の上に直接建物を作る場合と、コンクリートの『地下ピット』を作った今回の場合。両者を比較すると後者の方が衛生的かつ安全であると言えます」(藤井聡京大大学院工学研究科教授)というコメントを紹介する。
その後、都は08年に環境調査をしているが、「ベンゼンは土壌の1ヵ所から環境基準値の4万3000倍の濃度が検出されるなど、地上で35ヵ所、地下水では561ヵ所で基準値超え」(永尾氏)。シアンも1か所から基準の860倍の高濃度で検出されるなど、地上で90か所、地下水では966か所で基準値を上回っていた。
そうした結果を受けて、都は土壌汚染対策に858億円を費やしてきたと『新潮』は書いているが、それで完全にそうした危険が取り払われたのか、要再調査である。
ネズミの大群が潜む築地、土壌の安全性が完全に確保されていない豊洲。どちらも都民の食を脅かす存在だが、小池都知事はどういう判断を下すのか。
第1位。早くも風化しつつある福島第一原発事故だが、『女性自身』(以下、『自身』)が
「福島県が、甲状腺検査は必要ないと言わんばかりの通達を出した」と報じている。
子どものことだからということもあるが、
男性週刊誌がこの問題に触れることがほとんどなくなってしまったのは、おかしくないか。
『自身』によれば、福島県の小児科医会は、「いっせいに検査することで、放置しておいても健康や命に影響のない“潜在がん”を見つけているにすぎない。甲状腺検査をすることで、子供に負担をかける」として、
甲状腺検査の規模を縮小するよう8月に県に要望書を提出したのだという。
福島では原発事故後2巡目の検査までに174人の子どもの甲状腺がん(悪性の疑いを含む)が見つかり135人が手術を受けている。1巡目の数字で比較すると通常の約200倍の発生率になると『自身』は書いている。
たしかに精密検査することで、これまでなら発見できなかった命に別状のないがんを見つけることはあるだろう。だが、あのすさまじい放射能を浴びた子どもたちを、放っておいていいと言わんばかりの言い草は、医者として恥ずかしくはないのか。
医者も県も、この程度の認識だから、県民の不安は消えず、自分の家に帰ろうという気持ちにならないのだ。万が一のことがないように万全を期すのが、これだけの大事故を起こした東電や県、医療関係者のあり方だと思う。