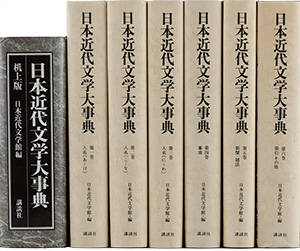1. 源義経
日本大百科全書
平安末~鎌倉初期の武将。源義朝(よしとも)の九男、源頼朝(よりとも)の弟。幼名牛若(うしわか)丸、遮那(しゃな)王丸、九郎。検非違使(けびいし)に任ぜられて九郎 ...
2. 源義経
世界大百科事典
1159-89(平治1-文治5) 平安末期~鎌倉初期の武将。源義朝の末子,頼朝の異母弟。母は九条院の雑仕女(ぞうしめ)常盤(ときわ)。幼名牛若,九郎と称す。平治 ...
3. みなもと‐の‐よしつね【源義経】
日本国語大辞典
平安末期から鎌倉初期の武将。義朝の九子。母は常盤。幼名牛若。平治の乱で平氏に捕えられ鞍馬寺に入れられたが、ひそかに陸奥藤原秀衡の下におもむいて庇護をうけた。治承 ...
4. みなもとのよしつね【源義経】
全文全訳古語辞典
[人名]平安末期の武将。一一五九年(平治元)~一一八九年(文治五)。義朝の九男で、頼朝の弟。俗に九郎判官とも。幼名は牛若。平治の乱で父を失い、幼くして鞍馬寺(= ...
5. みなもとのよしつね【源義経】画像
国史大辞典
』四ノ二 文治五年閏四月三十日条、数江教一『源義経―義経伝と伝説―』(『アテネ新書』五八)、渡辺保『源義経』(『人物叢書』一三三)、安田元久『源義経』(『日本の ...
6. 源義経
日本史年表
8・6 義経 ,検非違使・左衛門少尉となる(山槐記・吾)。 1187年〈文治3 丁未〉 2・‐ 源義経 ,陸奥国の藤原秀衡のもとに逃れる(吾)。 1189年〈文 ...
7. みなもとの-よしつね【源義経】
日本人名大辞典
1159−1189 平安後期-鎌倉時代の武将。平治(へいじ)元年生まれ。源義朝の9男。母は常盤御前(ときわごぜん)。平治の乱での義朝の敗死後,捕らえられて京都の ...
8. みなもとのよしつね【源義経】
日本架空伝承人名事典
平安末期~鎌倉初期の武将。源義朝の末子、頼朝の異母弟。母は九条院の雑仕女(ぞうしめ)常盤(ときわ)。幼名牛若、九郎と称す。平治の乱(一一五九)で父義朝が敗死した ...
9. 源義経[文献目録]
日本人物文献目録
精一『源義経』大森金五郎『源義経』桜木史郎『源義経』重野安繹『源義経 義経記』山下宏明『源義経の偽文書』坂本正典『源義経の最後を陳べて安徳天皇及び豊臣秀頼の最後 ...
10. 源義經一谷戰 (見出し語:源義經)
古事類苑
兵事部 洋巻 第1巻 644ページ ...
11. 源義經元服 (見出し語:源義經)
古事類苑
神祇部 洋巻 第4巻 351ページ ...
12. 源義經兵法 (見出し語:源義經)
古事類苑
兵事部 洋巻 第1巻 4ページ ...
13. 源義經北國落 (見出し語:源義經)
古事類苑
宗教部 洋巻 第1巻 1094ページ ...
14. 源義經善二劍術一 (見出し語:源義經)
古事類苑
武技部 洋巻 第1巻 27ページ ...
15. 源義經屋島戰 (見出し語:源義經)
古事類苑
兵事部 洋巻 第1巻 1209ページ ...
16. 源義經幼時居二鞍馬寺一 (見出し語:源義經)
古事類苑
宗教部 洋巻 第3巻 734ページ ...
17. 源義經忍耐 (見出し語:源義經)
古事類苑
人部 洋巻 第2巻 142ページ ...
18. 源義經於二相州腰越一上二款状於源賴朝一 (見出し語:源義經)
古事類苑
政治部 洋巻 第3巻 188ページ ...
19. 源義經等通二過三口關一 (見出し語:源義經)
古事類苑
地部 洋巻 第3巻 672ページ ...
20. 源義経(一)花押[図版]画像
国史大辞典
(c)Yoshikawa kobunkan Inc. ...
21. 源義経将棊経(著作ID:505317)
新日本古典籍データベース
みなもとのよしつねしょうぎきょう 義経将棊経 近松門左衛門(ちかまつもんざえもん) 浄瑠璃/義太夫 宝永三初演 ...
22. 源義経拝賀次第(著作ID:1021461)
新日本古典籍データベース
みなもとよしつねはいがしだい 記録 ...
23. 文貨古状揃(著作ID:1679578)
新日本古典籍データベース
ぶんかこじょうそろえ 源義経腰越状 往来物 ...
24. 靜(しずか)[源義経妾]
古事類苑
人部 洋巻 第1巻 1129ページ ...
25. 靜〈源義経妾〉 (見出し語:靜[源義経妾])
古事類苑
人部 洋巻 第2巻 859ページ ...
26. あいあげむら【相上村】埼玉県:大里郡/大里村地図
日本歴史地名大系
井の井戸があり、明治初年までは方四尺ばかりの一枚石に丸い穴をあけて水をくんでいた。この井戸は源義経が亀井六郎清重に命じて掘らせたものといわれ、この水に浴すると病 ...
27. 愛知(県)画像
日本大百科全書
救った地蔵といわれている。岡崎市は徳川家康の生誕地であるだけにゆかりの伝説が多い。また、世に知られているのは源義経(よしつね)と浄瑠璃姫(じょうるりひめ)の悲恋 ...
28. あおがさき【青崎】石川県:金沢市/旧石川郡地区/粟崎村
日本歴史地名大系
関連の絵図も作成されている。室町期の流通ルートを反映した「義経記」巻七の記述では、井上左衛門の配下が源義経主従に教えた逃走経路として「加賀国宮腰に出でて、大野の ...
29. あおもりし【青森市】青森県
日本歴史地名大系
虫と久栗坂の間の善知鳥崎であるとする説もあるが、詳しいことは不明である。藤原氏滅亡に関連する源義経北行伝説が、野内の鈴森にある貴船神社その他にある。源頼朝のいわ ...
30. あかいわどうくつ【赤岩洞窟】北海道:後志支庁/小樽市/祝津村
日本歴史地名大系
長の娘が立向かい、退治した。その祟りを恐れる者により洞窟に白竜大権現を祀ったという。あるいは源義経を慕ったアイヌ首長の娘がその悲恋を嘆き、海に身を投げ、時を経て ...
31. あかさきじんじゃ【赤崎神社】山口県:吉敷郡/秋穂町/大海村
日本歴史地名大系
祭神は田心姫命・湍津姫命・市杵島姫命。旧村社。社伝は神亀四年(七二七)の鎮座といい、寿永四年(一一八五)源義経が平家追討の時、この浦に着船し、当社に詣でて朝敵退 ...
32. あき-さねみつ【安芸実光】
日本人名大辞典
平安時代後期の武士。土佐(高知県)安芸郷の人。三十人力であったとつたえられる。壇ノ浦の戦いに源義経にしたがって出陣。元暦(げんりゃく)2年3月24日平教経(のり ...
33. あきし【安芸市】高知県
日本歴史地名大系
地で、地割東端の玉造と上中村の地域で土師器・須恵器が出土している。平安時代の末期、源平の戦で源義経の下に戦った者に安芸太郎実光と次郎実俊がいる(平家物語)。この ...
34. あげわしんでん【上輪新田】新潟県:柏崎市
日本歴史地名大系
半路の普請を行っている。鎮守神明社と応安元年(一三六八)日翁の開基という日蓮宗妙泉寺がある。源義経の北の方と伝える亀御前が出産した場所という亀割坂には茶屋が二軒 ...
35. あさかわむら【浅川村】山形県:米沢市
日本歴史地名大系
山・野銭・掛銭など三貫二一六文余・漆木役四六五文。溜井・切樋など普請所があった。本山修験宗大学院は、源義経に仕えた亀井六郎に縁ある修験坊慶元が開山と伝える。亀井 ...
36. あさがけ の 釜(かま)の焦(こ)げ
日本国語大辞典
物事の容易であることのたとえ。*浄瑠璃・源義経将棊経〔1711頃〕四「明朝錦戸が何万騎にてよする共、あさかけのかまのこげ、このむ所ぞ弁慶がゆの子共思はぬ」 ...
37. 朝駆(あさが)けの釜(かま)の焦(こ)げ
故事俗信ことわざ大辞典
物事の容易であることのたとえ。「駆け」と「焦げ」の語呂合わせ。 浄瑠璃・源義経将棊経(1711頃)四「明朝錦戸が何万騎にてよする共、あさかけのかまのこげ、このむ ...
38. あさひのしんめいぐうあと【朝日神明宮跡】大阪府:大阪市/東区/松山町地図
日本歴史地名大系
当社は逆櫓社とも通称された。「平家物語」巻一一(逆櫓)には、元暦二年(一一八五)二月一六日平家追討に向かう源義経軍が摂津渡辺で船揃えの際、義経と梶原景時が船を後 ...
39. あしおじんじゃ【足尾神社】茨城県:新治郡/八郷町/小屋村
日本歴史地名大系
れたとき当社に祈願したところ平癒したので、勅額を賜るという。また文治年間(一一八五―九〇)に源義経の家臣常陸坊海尊が度々参詣して武運長久を祈願したともいい、修験 ...
40. あしざきむら【芦崎村】秋田県:山本郡/八竜町
日本歴史地名大系
男鹿街道の夫伝馬などの負担が浜田・大口・芦崎三ヵ村の高割で割り当てられた。菅江真澄の「男鹿の秋風」には、芦崎に源義経と鞍馬山でともに修行した鈴木宗因がおり、義経 ...
41. あすかいまさつね【飛鳥井雅経】
国史大辞典
母は大納言源顕雅女。侍従・左中将・右兵衛督などを経て、建保六年(一二一八)正月非参議従三位。父頼経は源義経に同心の科で文治五年(一一八九)伊豆に配流され、兄宗長 ...
42. あすかい-まさつね【飛鳥井雅経】
日本人名大辞典
れ。藤原頼経(よりつね)の次男。母は源顕雅の娘。飛鳥井家の祖。蹴鞠(けまり)にすぐれる。父は源義経にくみし流罪となるが,雅経は蹴鞠をこのむ将軍源頼家(よりいえ) ...
43. 安宅
世界大百科事典
能の曲名。四番目物。現在物。観世信光作。シテは武蔵坊弁慶。安宅関の関守富樫(とがし)(ワキ)は,源義経捕縛の命を受けている。兄頼朝に追われている義経は,家来の弁 ...
44. あたか【安宅】
国史大辞典
、「作者不分明能」に分類されており、作者不詳。寛正六年(一四六五)観世大夫演能の記録がある。源義経(子方)は頼朝と不和になり、弁慶(シテ)その他の郎等(ツレ)を ...
45. あたか【安宅】
国史大辞典
勝家がこれを焼くまで、しばしば戦場となった記録がある。能楽の「安宅」は、『義経記』に描かれた源義経一行の受難の場面を、一幕に集めたもので、すでに幸若にその原型が ...
46. あたか【安宅】石川県:小松市/旧能美郡地区/安宅町
日本歴史地名大系
「阿多賀」などを焼払っている。室町時代成立の「義経記」巻七(平泉寺御見物の事)によれば、北陸を逃避行中の源義経は「斎藤別当実盛が手塚の太郎光盛に討たれけるあいの ...
47. あたか【安宅】[能曲名]
能・狂言事典
喜多 不明(観世信光とも) 四番目物・侍物・大小物 シテ・武蔵坊弁慶・[山伏出立]子方・源義経・[山伏出立]ツレ(立衆)・随行の郎等・[山伏出立]ワキ・富樫 ...
48. あたかまち【安宅町】石川県:小松市/旧能美郡地区
日本歴史地名大系
空珍坊円金が蓮如に帰依し、文明一七年(一四八五)安宅に寺を建立、一時兵火にかかり越後に移っていた。源義経一行を供応して贈られたと伝える法螺貝、蓮如親筆の背負名号 ...
49. あだち-きよつね【安達清経】
日本人名大辞典
?−? 鎌倉時代の雑色(ぞうしき)。源頼朝につかえ,御家人監視や源義経の探索などにあたる。文治(ぶんじ)2年(1186)静御前の子をすてる使いや押領(おうりょう ...
50. あっぱれ【天晴・遖】
日本国語大辞典
懸「あ(っ)ぱれ剛の者かな。是をこそ一人当千の兵ともいふべけれ」*謡曲・八島〔1430頃〕「源義経と名のり給ひしおん骨柄、あっぱれ大将やと見えし」*三体詩素隠抄 ...
 一谷へおとさんと思ふはいかに」。「ゆめ
一谷へおとさんと思ふはいかに」。「ゆめ
 かなひ候まじ。卅丈の谷、十五丈の岩さきなンど申ところは、人のかよふべき様候はず。まして御馬なンどは思ひもより候はず」。「さてさ様の所は鹿はかよふか」。「鹿はかよひ候。世間だにもあたゝかになり候へば、草のふかいにふさうどて、播磨の鹿は丹波へこえ、世間だにさむうなり候へば、雪のあさきにはまうどて、丹波の鹿は播磨のゐなみ野へかよひ候」と申。御曹司「さては馬場ごさむなれ。鹿のかよはう所を馬のかよはぬ様やある。やがてなんぢ案内者仕つれ」とぞの給ける。此身は年老てかなうまじゐよしを申す。
かなひ候まじ。卅丈の谷、十五丈の岩さきなンど申ところは、人のかよふべき様候はず。まして御馬なンどは思ひもより候はず」。「さてさ様の所は鹿はかよふか」。「鹿はかよひ候。世間だにもあたゝかになり候へば、草のふかいにふさうどて、播磨の鹿は丹波へこえ、世間だにさむうなり候へば、雪のあさきにはまうどて、丹波の鹿は播磨のゐなみ野へかよひ候」と申。御曹司「さては馬場ごさむなれ。鹿のかよはう所を馬のかよはぬ様やある。やがてなんぢ案内者仕つれ」とぞの給ける。此身は年老てかなうまじゐよしを申す。
 しける程に、いかゞしたりけん、判官弓をかけおとされぬ。うつぶしで、鞭をもツてかきよせて、とらうとらうどし給へば、兵ども「たゞすてさせ給へ」と申けれども、つゐにとツて、わらうてぞかへられける。おとなどもつまはじきをして、「口惜き御事候かな、たとひ千疋万疋にかへさせ給べき御たらしなりとも、争か御命にかへさせ給べき」と申せば、判官「弓のおしさにとらばこそ。義経が弓といはば、二人してもはり、
しける程に、いかゞしたりけん、判官弓をかけおとされぬ。うつぶしで、鞭をもツてかきよせて、とらうとらうどし給へば、兵ども「たゞすてさせ給へ」と申けれども、つゐにとツて、わらうてぞかへられける。おとなどもつまはじきをして、「口惜き御事候かな、たとひ千疋万疋にかへさせ給べき御たらしなりとも、争か御命にかへさせ給べき」と申せば、判官「弓のおしさにとらばこそ。義経が弓といはば、二人してもはり、
 、もとゆひはらひすみぞめの衣川の波ときえし、らうじうの跡とひ教信と号すいにしへを、語れば今更に忍びて落るなみだ哉。(シテ)かくて上人滅後にいたり、はだのまもりをひらきて見れば、けいづたゞしき義経と、人々やがて注集す。
、もとゆひはらひすみぞめの衣川の波ときえし、らうじうの跡とひ教信と号すいにしへを、語れば今更に忍びて落るなみだ哉。(シテ)かくて上人滅後にいたり、はだのまもりをひらきて見れば、けいづたゞしき義経と、人々やがて注集す。 さてもやしまのひよどりごへに、こゝにのこりしいちのたに、むさしぼにべんけいをさきとして、なかによしつねきよろ
さてもやしまのひよどりごへに、こゝにのこりしいちのたに、むさしぼにべんけいをさきとして、なかによしつねきよろ
 と、けんれいもんいんをちよいととこへしなだれかかれば、うしろからまおとこみつけたとのりつねが、こへにびつくりぎやうてんし、かけいだしなんのくもなくちよい
と、けんれいもんいんをちよいととこへしなだれかかれば、うしろからまおとこみつけたとのりつねが、こへにびつくりぎやうてんし、かけいだしなんのくもなくちよい
 と、みがるのはやわざはつそふとんで、よふ
と、みがるのはやわざはつそふとんで、よふ
 こゝろがおちついた
こゝろがおちついた
 としてぞゐられける。
としてぞゐられける。
 し
し
 )忍,覚円坊阿闍梨円乗とも)のもとにあずけられ,遮那王(しやなおう)と呼ばれた。自分の素姓を知った牛若は,平家打倒を心に秘め,昼は学問を修め,夜は鞍馬の奥僧正ヶ谷(涯とも)で武芸に励んだ。このとき,山の大天狗が憐れんで師弟の約を結び,兵法を授け,小天狗らと立ち合わせて腕を磨かせたとする伝説もある(《平治物語》《太平記》,能《鞍馬天狗》,幸若舞《未来記》など)。たまたま山に登った黄金商人(こがねあきんど)の金売吉次を説いて鞍馬を脱出し,藤原秀衡を頼って奥州に向かう。途中,近江国の鏡の宿で強盗に襲われるが,その頭目,由利太郎,藤沢入道らの首を取り賊を撃退する。異伝では鏡の宿が美濃の国の青墓宿,赤坂宿,垂井宿などともなり,賊の頭目も熊坂長範らとなることがある(能《烏帽子折》《熊坂》《現在熊坂》,幸若舞《烏帽子折》など)。尾張の熱田(あつた)では前大宮司を烏帽子親として元服し,九郎義経と名のる。この東下りの途中にも,無礼を働いた関原与市を牛若が切る伝説があり,場所は京の粟田口,美濃の不破,山中などともされる(《異本義経記》,能《関原与市》,幸若舞《鞍馬出》など)。三河国矢矧(やはぎ)宿では牛若丸は宿の長老の娘浄瑠璃姫と恋に陥る伝説(《浄瑠璃物語》など)などもある。駿河国では兄の阿濃禅師(今若)と会い,下野国では鞍馬で知り合った陵兵衛(みささぎのひようえ)を訪ねて,その冷遇を怒って館を焼き払い,上野国板鼻では伊勢三郎と会って家来とする。ついに奥州に入って吉次の手引きで秀衡に対面する。翌年,義経は単身で東山道を経て京に帰り,一条堀川(今出川とも)に住む陰陽師で兵法家の鬼一法眼(きいちほうげん)の娘幸寿前の手引きで,その秘伝の六韜(りくとう)兵法一巻の書を学びとる。鬼一法眼伝説は他に御伽草子《判官都話》(一名,《鬼一法眼》),《皆鶴》,能の《湛海》にも伝え,法眼の娘の名を皆鶴姫とするなど,異伝を含んでいる。これに似た伝説に御曹子島渡り伝説があり,奥州滞在中に義経は千島とも蝦夷(えぞ)ガ島とも称される島に渡り,鬼の大王の秘蔵する〈大日の法〉と名づけた兵法を大王の娘の手引きで盗み出すというものである(御伽草子《御曹子島渡り》)。この伝説の島が地獄となると牛若丸地獄巡り伝説となるが,これは牛若丸が鞍馬の毘沙門(びしやもん)に祈って,大天狗の内裏に至り,懇願して地獄を巡り,今は大日如来となっている亡父義朝に会うというものである。この時期で特筆すべき伝説は義経と武蔵坊弁慶との出会いを伝えるもので,《義経記》では五条天神と清水寺でのこととなっているが,五条橋での二人の対戦を描くいわゆる橋弁慶伝説は特に有名である(御伽草子《橋弁慶》《弁慶物語》,能《橋弁慶》など)。この伝説では,ふつう太刀1000本を奪う悲願を立てるのが弁慶で,義経と対戦して敗れ家来となることになっているが,1000本の太刀を奪うのが義経となっているものもある(《武蔵坊弁慶絵巻》など)。
)忍,覚円坊阿闍梨円乗とも)のもとにあずけられ,遮那王(しやなおう)と呼ばれた。自分の素姓を知った牛若は,平家打倒を心に秘め,昼は学問を修め,夜は鞍馬の奥僧正ヶ谷(涯とも)で武芸に励んだ。このとき,山の大天狗が憐れんで師弟の約を結び,兵法を授け,小天狗らと立ち合わせて腕を磨かせたとする伝説もある(《平治物語》《太平記》,能《鞍馬天狗》,幸若舞《未来記》など)。たまたま山に登った黄金商人(こがねあきんど)の金売吉次を説いて鞍馬を脱出し,藤原秀衡を頼って奥州に向かう。途中,近江国の鏡の宿で強盗に襲われるが,その頭目,由利太郎,藤沢入道らの首を取り賊を撃退する。異伝では鏡の宿が美濃の国の青墓宿,赤坂宿,垂井宿などともなり,賊の頭目も熊坂長範らとなることがある(能《烏帽子折》《熊坂》《現在熊坂》,幸若舞《烏帽子折》など)。尾張の熱田(あつた)では前大宮司を烏帽子親として元服し,九郎義経と名のる。この東下りの途中にも,無礼を働いた関原与市を牛若が切る伝説があり,場所は京の粟田口,美濃の不破,山中などともされる(《異本義経記》,能《関原与市》,幸若舞《鞍馬出》など)。三河国矢矧(やはぎ)宿では牛若丸は宿の長老の娘浄瑠璃姫と恋に陥る伝説(《浄瑠璃物語》など)などもある。駿河国では兄の阿濃禅師(今若)と会い,下野国では鞍馬で知り合った陵兵衛(みささぎのひようえ)を訪ねて,その冷遇を怒って館を焼き払い,上野国板鼻では伊勢三郎と会って家来とする。ついに奥州に入って吉次の手引きで秀衡に対面する。翌年,義経は単身で東山道を経て京に帰り,一条堀川(今出川とも)に住む陰陽師で兵法家の鬼一法眼(きいちほうげん)の娘幸寿前の手引きで,その秘伝の六韜(りくとう)兵法一巻の書を学びとる。鬼一法眼伝説は他に御伽草子《判官都話》(一名,《鬼一法眼》),《皆鶴》,能の《湛海》にも伝え,法眼の娘の名を皆鶴姫とするなど,異伝を含んでいる。これに似た伝説に御曹子島渡り伝説があり,奥州滞在中に義経は千島とも蝦夷(えぞ)ガ島とも称される島に渡り,鬼の大王の秘蔵する〈大日の法〉と名づけた兵法を大王の娘の手引きで盗み出すというものである(御伽草子《御曹子島渡り》)。この伝説の島が地獄となると牛若丸地獄巡り伝説となるが,これは牛若丸が鞍馬の毘沙門(びしやもん)に祈って,大天狗の内裏に至り,懇願して地獄を巡り,今は大日如来となっている亡父義朝に会うというものである。この時期で特筆すべき伝説は義経と武蔵坊弁慶との出会いを伝えるもので,《義経記》では五条天神と清水寺でのこととなっているが,五条橋での二人の対戦を描くいわゆる橋弁慶伝説は特に有名である(御伽草子《橋弁慶》《弁慶物語》,能《橋弁慶》など)。この伝説では,ふつう太刀1000本を奪う悲願を立てるのが弁慶で,義経と対戦して敗れ家来となることになっているが,1000本の太刀を奪うのが義経となっているものもある(《武蔵坊弁慶絵巻》など)。