「歴史」カテゴリの記事一覧
オンライン辞書・事典サービス「ジャパンナレッジ」の「歴史」のカテゴリ別サンプルページです。
ジャパンナレッジは日本最大級のオンライン辞書・事典サービスです。
「国史大辞典」「日本古典文学全集」「日本国語大辞典」「世界大百科事典」「日本大百科全書」など80種類以上の辞書・事典をパソコン、タブレット、スマートフォンで利用できます。
「国史大辞典」「日本古典文学全集」「日本国語大辞典」「世界大百科事典」「日本大百科全書」など80種類以上の辞書・事典をパソコン、タブレット、スマートフォンで利用できます。

真田幸村(真田信繁)(国史大辞典・日本大百科全書・日本架空伝承人名事典)
一五六七 - 一六一五 安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将。幼名御弁丸、のち源次郎。左衛門佐と称す。名は信繁。幸村の名で有名であるが、この称の確実な史料はない。高野山蟄居中に剃髪して好白と号した。永禄十年(一五六七)信濃国上田城主真田昌幸の次男

上杉景勝(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)
一五五五 - 一六二三 安土桃山・江戸時代前期の大名。越後春日山城・会津若松城主、出羽国米沢藩主。幼名を卯松、喜平次と称し、はじめ顕景と名乗った。弘治元年(一五五五)十一月二十七日に生まれる。父は越後国魚沼郡上田荘坂戸(新潟県南魚沼郡六日町)

茶臼山(日本歴史地名大系)
[現]天王寺区茶臼山町 四天王寺南西、天王寺公園のなかにある比高約八メートルほどの小丘。茶磨山(摂陽群談)・茶磑山(摂津名所図会大成)とも書く。東面して三段築成された前方後円墳とみられ、西側から南側にかけてめぐる河底かわぞこ池は周濠の遺構と推定されている。全長約二〇〇メートルで

真田昌幸(国史大辞典)
安土桃山時代の武将。初代上田城主。幼名源五郎、通称喜兵衛。安房守。真田弾正幸隆の第三子として天文十六年(一五四七)信濃国に生まれる。信之・幸村の父。武田信玄・勝頼父子に仕えて足軽大将を勤め、甲斐の名族武藤家をついだが、兄信綱・昌輝が天正三年(一五七五)に

真田信之(真田信幸)(国史大辞典)
安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将。初代松代藩主。幼名は源三郎。はじめ信幸、のち信之と改めた。号は一当斎。真田安房守昌幸の嫡男として永禄九年(一五六六)生まれた。母は菊亭(今出川)晴季の娘。幸村の兄。昌幸が徳川家康に属したため

本多正信(国史大辞典)
戦国時代から江戸時代前期にかけて徳川家康に仕えた吏僚的武将。その側近にあり謀臣として著名。通称は弥八郎。諱ははじめ正保、正行。佐渡守。天文七年(一五三八)三河国に生まれる。父は本多弥八郎俊正。母は不詳であるが松平清康の侍女だったという。徳川家康に仕え

大谷吉継(国史大辞典)
安土桃山時代の武将。永禄二年(一五五九)に生まれる。父は豊後の国主大友宗麟の家臣大谷盛治であるといわれている。はじめ紀之介と称し、のち吉継と改めた。豊臣秀吉に近侍して信任を受け、天正十三年(一五八五)七月、従五位下刑部少輔に叙任された。賤ヶ岳の戦に軍功をあらわし

高台院(北政所・寧々)(国史大辞典)
豊臣秀吉の夫人。北政所といわれた。天文十八年(一五四九)生まれる。尾張の杉原助左衛門定利の次女で、幼名はねね(禰々)。のち一時吉子と称したこともあるが、『(備中足守)木下家譜』その他の文書には寧子とある。叔母の嫁ぎ先である尾張津島の浅野又右衛門尉長勝に養われ

淀殿(淀・茶々)(国史大辞典・改訂新版 世界大百科事典)
豊臣秀吉の側室、秀頼の母。父は近江浅井郡小谷城主浅井長政。母は織田信長の妹お市の方。長女として小谷城で生まれた。幼名はお茶々。正確な生年月日は不明であるが、『翁草』によって生年を永禄十年(一五六七)とする説がある。天正元年(一五七三)信長に包囲された小谷城から母に伴われて

本多忠勝(国史大辞典)
戦国時代から江戸時代前期にかけて徳川家康に仕えた武将。江戸時代前期の有力譜代大名。幼名は鍋之助。通称平八郎。中務大輔。天文十七年(一五四八)三河国に生まれる。父は岡崎城主松平広忠の家臣本多平八郎忠高、母は植村新六郎氏義の娘。父忠高が天文十八年安城の城攻めで討死したため

大坂の陣(国史大辞典・世界大百科事典・日本国語大辞典)
関ヶ原の戦の戦勝により、政治の主導権を獲得し、かつ戦勝者として大名の支配を可能にした徳川氏にとっては、中央政権を樹立し、その支配権を正当化し確立することが今後の課題となった。そのため戦後一門・譜代大名の創出とその要衝配置、ならびに豊臣秀吉恩顧の大名をはじめとする外様大名

豊臣秀次(国史大辞典)
安土桃山時代の武将。孫七郎。中納言、内大臣、関白、左大臣。号高厳寺(瑞泉院・善正寺)。永禄十一年(一五六八)生まれる。父は豊臣秀吉の近臣三好吉房、母は秀吉の実姉日秀で秀吉の甥にあたる。天正十二年(一五八四)の小牧・長久手の戦には八千人を率いて出陣したが、有力家臣を失い

吉野太夫(国史大辞典)
江戸時代初期の京都の代表的な遊女。文化九年(一八一二)の序文のある『吉野伝』には、天正から寛文・延宝ごろまでに、吉野を名乗った遊女が十人あったと記している。しかし二代目以外はほとんどその実体がよくわからない。二代目の吉野太夫は、『色道大鏡』の

酒井忠次(国史大辞典)
戦国・安土桃山時代の武将。大永七年(一五二七)三河国に生まれる。小平次・小五郎と称す。左衛門尉酒井家の系譜では、忠次は第二代とされており、徳川宗家との姻戚関係に加えて、譜代大名の中では最古参の譜代の一人であった。忠次の妻は碓井姫といい

福島正則(国史大辞典)
安土桃山・江戸時代前期の武将。安芸国広島藩主。尾張の住人福島市兵衛正信の長男。母は豊臣秀吉の伯母木下氏と伝えられている。永禄四年(一五六一)尾張海東郡二寺邑(愛知県海部郡美和町)に生まれる。幼時より秀吉に仕え、市松と称した。はじめ知行二百石を領し、天正六年(一五七八)
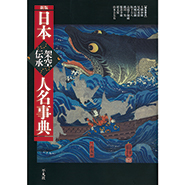
猿飛佐助(新版 日本架空伝承人名事典)
甲賀流忍術の名人とされる伝説上の人物。玉田玉秀斎による創作講談『忍術名人猿飛佐助』の主人公であるが、一九一一年に刊行された「立川文庫」により大衆のあいだに定着した。戸沢白雲斎に忍術をならい、真田幸村につかえ、いわゆる真田十勇士の一人として活躍するが
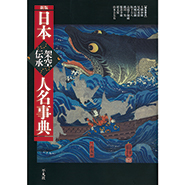
真田十勇士(日本架空伝承人名事典・日本大百科全書・世界大百科事典)
安土桃山時代の武将真田幸村につかえて、武勇をあらわしたという一〇人の勇士の総称。猿飛佐助、霧隠才蔵、三好清海入道、三好伊三いさ入道、穴山小介、海野うんの六郎、筧かけい十蔵、根津甚八、望月六郎、由利鎌之助の一〇人だが、三好清海入道と伊三入道は兄弟とされている

細川ガラシャ(国史大辞典)
安土桃山時代の代表的なキリシタン女性。細川忠興夫人。永禄六年(一五六三)明智光秀の次女として生まれる。本名玉子、ガラシャGraciaは霊名。諡は秀林院。天正六年(一五七八)織田信長の媒酌により細川藤孝の息忠興と結婚し、細川氏の居城山城勝竜寺城(京都府長岡京市)に輿入れ

徳川秀忠(国史大辞典)
江戸幕府第二代将軍。一六〇五―二三在職。法号台徳院殿。徳川家康の三男。母は家康の側室西郷氏於愛の方(宝台院)。天正七年(一五七九)四月七日遠江浜松城に生まれた。童名長松君、のちに竹千代と改めた。長兄信康が自害、次兄秀康が羽柴(豊臣)秀吉の養子になったため

大坂城跡(日本歴史地名大系)
日本歴史地名大系/平凡社/[現]東区大阪城。東区の北東の一角にある城跡で、本丸と二ノ丸のほぼ全域七三万平方メートルが国の特別史跡。城跡にもと玉造定番屋敷・同与力同心屋敷の一部を加えた約一〇三万平方メートルが大阪城公園となっている。

興福寺(国史大辞典)
奈良市登大路町にある法相宗大本山。南都七大寺の一つ。寺伝では「こうぶくじ」という。縁起によると、天智天皇八年(六六九)藤原鎌足の死去に際し、妻の鏡女王が鎌足の念持仏の釈迦丈六像などを祀る伽藍をその山階(山科)邸に設けたのに始まり(山階寺)、その子不比等によって藤原京の厩坂に移遷(厩坂寺)

東大寺(国史大辞典)
奈良市雑司町にある華厳宗の総本山。大華厳寺・金光明四天王護国寺・総国分寺などの別称がある。南都七大寺・十三大寺・十五大寺の一つ。東大寺の寺号は平城京の東方にある大寺を意味し、『正倉院文書』の天平二十年(七四八)五月の「東大寺写経所解案」に初見するが

沙汰(日本国語大辞典・全文全訳古語辞典・国史大辞典)
焼いた薩摩芋。《季・冬》*評判記・秘伝書〔1655頃〕下ほんの事「やきぐり、やきいもは、いきくさくなる也」*俳諧・骨書〔1787〕上「朝の月狩の竹鑓手束弓〈青蘿〉 来かかるものが焼芋を喰ふ〈樗良〉」

舎人親王(日本大百科全書(ニッポニカ))
天武天皇の第三皇子。母は天智天皇の娘新田部皇女。知太政官事穂積親王の亡きあとは皇親の長老として重んぜられ、新田部親王とともに皇太子首親王(聖武天皇)を輔翼する責務を負った

藤原不比等(国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
六五九-七二〇奈良時代の政治家。鎌足の第二子。史とも書く。母を車持国子の女与志古娘とし、不比等を天智天皇の皇胤とする説があるが、信用しがたい。斉明天皇五年(六五九)生まれる。幼時山科の田辺史大隅の家に養われたといわれ

皇位継承(改訂新版・世界大百科事典)
7世紀末までの皇位継承を《古事記》《日本書紀》によってみると,16代の仁徳天皇まではほとんどが父子間の直系相続であり,仁徳以後持統までは,父子間相続6,母子間1,兄弟間10,姉弟間2,叔父・甥間1,夫婦間2,三親等以上をへだてた相続3の計25例で

光格天皇(国史大辞典・世界大百科事典)
一七七一-一八四〇 一七七九―一八一七在位。明和八年(一七七一)八月十五日東山天皇の皇孫である閑院宮典仁親王の第六王子として誕生。生母は贈従一位岩室磐代である。幼称は祐宮、諱は初め師仁、ついで兼仁と改められた。誕生の翌年聖護院宮忠誉入道親王の附弟となり、将来出家して聖護院門跡を継ぐ予定であったが

推古天皇(国史大辞典)
五九二―六二八在位。和風諡号は豊御食炊屋姫尊。諱は額田部。欽明天皇の皇女で、母は大臣蘇我稲目の娘堅塩媛。用明天皇の同母妹。崇峻天皇の異母姉。五五四年生まれる。七一年皇太子(敏達天皇)妃となり、七六年、前皇后広姫死没の後をうけて異母兄敏達天皇の皇后に立てられた。時に二十三歳。

豊臣秀頼(国史大辞典・日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典)
一五九三-一六一五。豊臣秀吉の第二子。文禄二年(一五九三)八月三日大坂城内に生まれた。母は側室浅井氏(茶々、淀殿)。秀吉は実子に恵まれず、浅井氏との間に鶴松を得たが三歳にして死別した。このため秀頼誕生の喜びは大きく、みずから肥前名護屋の陣中より正室北政所に書状を送り

孝謙天皇(称徳天皇)(国史大辞典)
七一八-七〇。七四九―五八在位。のち重祚して称徳天皇となり、七六四―七〇在位。養老二年(七一八)聖武天皇の第一皇女として誕生。母は光明皇后。諱を阿倍といい、天平宝字二年(七五八)上台宝字称徳孝謙皇帝の尊号を上られ、また高野姫尊・高野天皇とも称された。


