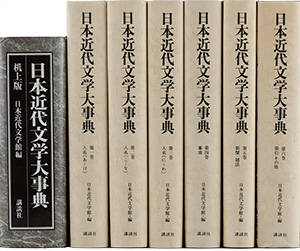1. 大隈重信画像
日本大百科全書
明治・大正期の政治家。天保(てんぽう)9年2月16日肥前国(ひぜんのくに)佐賀会所小路に、佐賀藩砲術長の父信保(のぶやす)、母三井子(みいこ)の長男として生まれ ...
2. 大隈重信[百科マルチメディア]画像
日本大百科全書
©小学館ライブラリー ...
3. 大隈重信
世界大百科事典
1838-1922(天保9-大正11) 明治維新から大正期にかけて,財政・外交にすぐれた手腕を発揮した政治家。佐賀藩の上級士族の家に生まれ,幼少から藩校弘道館で ...
4. おおくま‐しげのぶ【大隈重信】
日本国語大辞典
政治家。侯爵。名は八太郎。佐賀藩出身。参議、大蔵卿を経て明治一五年(一八八二)立憲改進党を結成して自由民権運動に参加。同年東京専門学校(早稲田大学の前身)を創立 ...
5. おおくましげのぶ【大隈重信】
国史大辞典
編『大隈侯八十五年史』、渡辺幾治郎『大隈重信』、同『文書より観たる大隈重信侯』、中村尚美『大隈重信』(『人物叢書』七六)、柳田泉『明治文明史における大隈重信』 ...
6. おおくま-しげのぶ【大隈重信】画像
日本人名大辞典
1838−1922 明治-大正時代の政治家。天保(てんぽう)9年2月16日生まれ。肥前佐賀藩士大隈信保の長男。長崎でフルベッキに英学をまなぶ。維新後,明治政府の ...
7. 大隈重信[文献目録]
日本人物文献目録
村尚美『大隈重信』安部勝弘『大隈重信』中村尚美『大隈重信』中村尚美『大隈重信』服部之総『大隈重信』山本茂『大隈重信侯の民主主義』馬場恒吾『大隈重信自叙伝の再検討 ...
8. おおくましげのぶあんさつみすいじけん【大隈重信暗殺未遂事件】
国史大辞典
大隈重信はその生涯に二度暗殺計画に遭遇している。その最初は、明治二十二年(一八八九)十月外相として条約改正に取りくんでいたときである。十月十八日午後四時過ぎ、 ...
9. おおくましげのぶかんけいもんじょ【大隈重信関係文書】
国史大辞典
大隈家旧蔵、現在早稲田大学図書館所蔵の『大隈文書』の中の公私の書翰のうちから、特に史料的価値の高いと思われるもの千二百八十七点を選び、これを時代順に配列し、参 ...
10. 『大隈重信関係文書』
日本史年表
1932年〈昭和7 壬申〉 この年 渡辺幾次郎編 『大隈重信関係文書』 刊(~昭和10年)。 ...
11. おおくましげのぶきゅうたく【大隈重信旧宅】佐賀県:佐賀市/佐賀城下/片田江七小路
日本歴史地名大系
路の、最も南の会所小路の中ほどにある。参議・大蔵卿・外相、そして二度にわたり総理大臣を務めた大隈重信(幼名八太郎)は、天保九年(一八三八)佐賀藩士大隈重伴(知行 ...
12. 大隈重信銅像[百科マルチメディア]画像
日本大百科全書
早稲田(わせだ)大学構内にあるアカデミック・ガウン姿の銅像。1932年(昭和7)、大学創立50周年記念祭と大隈(おおくま)の十回忌をかねてつくられた。制作者は彫 ...
13. 大隈重信内閣画像
日本大百科全書
明治後期・大正初期、大隈重信を首班として組織された第一次、二次の内閣。第一次(1898.6.30~11.8 明治31)隈板内閣(わいはんないかく)ともいう。第三 ...
14. 大隈重信内閣(第一次)[百科マルチメディア]画像
日本大百科全書
※(兼)は兼任を。一つの職名に複数の人名がある場合は順次後任を示す ©Shogakukan ...
15. 大隈重信内閣(第二次)[百科マルチメディア]画像
日本大百科全書
※(兼)は兼任。一つの職名に複数の人名がある場合は順次後任を示し、同一人名がある場合は再任を示す ©Shogakukan ...
16. 青木周蔵画像
日本大百科全書
んさん)委員に任命された。1889年には第一次山県有朋(やまがたありとも)内閣の外相に就任、大隈重信(おおくましげのぶ)前外相が激しい反対運動のため失敗した後を ...
17. 青木周蔵自伝 27ページ
東洋文庫
行の海外旅行免許状第一 号であった。帰国ののち、順天堂(現在の順天堂医科大学)を創立、大隈重信が霞が関事件で、 李鴻章が下関で遭難した際、治療に当っ ...
18. 青木周蔵自伝 67ページ
東洋文庫
4 帝号大日本政典、尾佐竹猛氏著「日本憲政史」所収、七篇九十五ヵ条 5 帝号大日本国政典、大隈重信文書、七篇九十五ヵ条 がある。 四 「大日本政規(原稿 ...
19. 青木周蔵自伝 78ページ
東洋文庫
であった。明治政府は不平等条約改正を国家的課題として、歴代外務 卿・外相(寺島宗則・井上馨・大隈重信・青木周蔵・榎本武揚ら)が改正交渉を行なったが、 いずれも失 ...
20. 青木周蔵自伝 303ページ
東洋文庫
無制限にドイツ領事裁判権の継続を許 すなどの条約に調印したため政治問題となり、明治三十年九月一日、大隈重信外相(第二次松 方内閣)により帰朝を命ぜられた。 ...
21. 青木周蔵自伝 347ページ
東洋文庫
駐米大使召還事情、十四年~十八年に至る井上外務卿へのアドバイス、ドイツ人お雇い外人の採用、万国郵便連盟加盟、大隈重信・森有礼の評価、第二次山県内閣瓦解事情、北清 ...
22. 青木周蔵自伝 361ページ
東洋文庫
藤博文、兼摂外相となる七月、那須青木開墾内に別荘建築十月五日、自治制研究会に入る・二月一日、大隈重信、外相となる・四月、黒田清隆内閣十一月一日、外相代理となる十 ...
23. アカデミー
日本大百科全書
った。民間では福沢諭吉の慶応義塾(1858)、新島襄(にいじまじょう)の同志社(1875)、大隈重信(おおくましげのぶ)の東京専門学校(1882。早稲田大学の前 ...
24. あさひなちせん【朝比奈知泉】
国史大辞典
中退した。大学でラートゲンから学んだ国法学を立論の基礎として政党否定・議会攻撃の論説を書いた。大隈重信の条約改正に反対し、三度発行停止となった。同二十四年、伊東 ...
25. 安達謙蔵
世界大百科事典
13年桂太郎の立憲同志会創立に参加し,以後憲政会,立憲民政党に属す。この間,国権党時代の選挙指導の経験を生かし大隈重信内閣下の15年総選挙で同志会の大勝に重要な ...
26. あぶらやまち【油屋町】長崎県:長崎市/長崎町
日本歴史地名大系
安政三年(一八五六)イギリス商人オルトから大量の注文を受け、茶の輸出が増大していった。これで富を得た慶は大隈重信・松方正義・陸奥宗光らに経済支援を行った。その屋 ...
27. あまのためゆき【天野為之】
国史大辞典
り、同二十三年衆議院議員に当選、二十五年第二回総選挙に落選し以後政界を退く。他方卒業とともに大隈重信創立の東京専門学校教師となり、大正六年(一九一七)十月早稲田 ...
28. あめみやけいじろう【雨宮敬次郎】
国史大辞典
し、石油・蚕種取引をつづけ十三年より東京府下南葛飾郡深川に製粉工場を経営などするうち、大蔵卿大隈重信の内意により大阪商法会議所会頭五代友厚をたすけて紙幣下落防止 ...
29. アメリカ彦蔵自伝 2 191ページ
東洋文庫
辞するまでは彼のところで働き、さらに一八七四年の初頭、願いによって解職になるまで新大臣〔大蔵卿、大隈重信〕のところで働いた。井上氏に仕えていた間ずっと、この上も ...
30. アメリカ彦蔵自伝 2 208ページ
東洋文庫
いるかについては、人によって大いに意見の分かれるところであった。 五月十日付の官報は、直ちに大隈重信が大蔵省の政務を指揮するよう命ぜられたことを発表した。さらに ...
31. アメリカ彦蔵自伝 2 223ページ
東洋文庫
もって買取った。こうした法外の利得を三菱が得たというのも、岩崎が政府部内に深く食い入り、とくに大蔵卿大隈重信と密接に結びついていたためであった。 一 五 ...
32. アメリカ彦蔵自伝 2 269ページ
東洋文庫
いっぽう民衆が銅貨であげた賽銭は六百円に達し、俵八俵に一ばいとなった。 大隈重信の遭難 十月十八日。この日の午後四時頃、外務大臣の ...
33. アメリカ彦蔵自伝 2 291ページ
東洋文庫
〈二六( 八美 ○家康の江戸入府三百年祭。 〈柔バ 一2八〇外相大隈重信の遭難。 〈一蓉 一八九〇 一一一.三 〇榊原道 ...
34. アーネスト・サトウ 神道論 263ページ
東洋文庫
政府の蒸気船タボール号が、同国南部海岸に建つ灯台を巡る視察の航行中、鳥羽の港に入った折、参議大隈重信氏および工部大輔山尾庸三氏の大変柔軟な計らいにより、同船した ...
35. アーネスト・サトウ 神道論 271ページ
東洋文庫
(明治五年)冬に日本政府の参議大隈重信と工部大輔山尾庸三が実施した、日本南部海岸に建設された灯台を巡る視察に同行し、同年一一月二九日に蒸気船タボール号に乗り込み ...
36. アーネスト・サトウ伝 186ページ
東洋文庫
を飾っている。(5) ドイツ主義憲法への傾斜 佐賀出身で長崎でフルペッキから英学を教えられた大隈重信は、イギリス式の議会政治の導入に熱心であったが、岩倉具視、伊 ...
37. いいだまちいつちようめ【飯田町一丁目】東京都:千代田区/旧麹町区地区地図
日本歴史地名大系
った(元治元年改正尾張屋版切絵図など)。明治維新後は華族などの邸宅地となり、もとの御厩の地は大隈重信邸となった(明治一六年東京図測量原図)。明治九年雉子橋から北 ...
38. いけだ-しげのり【池田林儀】
日本人名大辞典
大正-昭和時代のジャーナリスト。明治25年1月11日生まれ。大日本雄弁会講談社から報知新聞社にうつる。大隈重信の専属記者をへてベルリン特派員。昭和8年京城日報に ...
39. 石井菊次郎
日本大百科全書
石井邦猷(くにみち)の養子となる。通商局長、次官、駐仏大使を歴任後、1915年(大正4)第二次大隈重信(おおくましげのぶ)内閣の外相に就任、日露協約の締結に尽力 ...
40. 石井菊次郎
世界大百科事典
次西園寺公望内閣の林董外相のもとで次官,さらに1912年駐仏大使となる。第1次大戦中の14年大隈重信内閣の外相に就任し,日露協約締結など戦時外交に苦心する。17 ...
41. 伊集院彦吉[文献目録]
日本人物文献目録
【図書】:1件 【逐次刊行物】:2件 『伊集院彦吉男・青木宣純将軍追悼録』追悼会発起人『伊集院公使論』大隈重信等『伊集院彦吉先生』信夫淳平 ...
42. 板垣退助
世界大百科事典
にむかえられた。98年6月自由・進歩両党の合同により憲政党が結成され,同党を基礎として第1次大隈重信内閣が成立すると,これに内務大臣として入閣した(隈板内閣)。 ...
43. いたがきたいすけ【板垣退助】
国史大辞典
臣となった。三十一年六月自由党が進歩党と合同して憲政党となり、第三次伊藤内閣が総辞職すると、大隈重信・板垣退助に組閣の大命が下り、同月三十日隈板内閣が成立し、板 ...
44. 板垣退助[文献目録]
日本人物文献目録
近代政治家伝』阿部真之助『板垣退助抄伝』松川譲児『板垣退助小論』深谷博治『板垣退助と大隈重信』井上清『板垣退助と大隈重信』徳富猪一郎『板垣退助と谷干城の一代華族 ...
45. 一木喜徳郎
日本大百科全書
1900年(明治33)貴族院議員に勅選され、法制局長官、内務次官などを歴任。1914年(大正3)第二次大隈重信(おおくましげのぶ)内閣の文部大臣、翌年内務大臣と ...
46. 一木喜徳郎
世界大百科事典
第1次桂太郎内閣の法制局長官,第2次桂内閣で内務次官に就任。この間貴族院勅選議員。その後,第2次大隈重信内閣の文相,内相を歴任し,17年から枢密顧問官。日本の地 ...
47. いちしまけんきち【市島謙吉】
国史大辞典
十六歳で上京、東京英語学校を経て東京大学文学部に進んだ。大学卒業の一年前の明治十四年(一八八一)、参議大隈重信の追放とひきかえに国会開設の勅諭が下りると、大学を ...
48. 市島春城
日本大百科全書
ばら)(現、阿賀野(あがの)市)に生まれる。本名謙吉。1881年(明治14)東京大学を中退、大隈重信(おおくましげのぶ)の傘下に入り、改進党や東京専門学校(早稲 ...
49. いとうないかく【伊藤内閣】画像
国史大辞典
年来の懸案たる地租増徴をもはや不可避とする情勢にあった。ここに伊藤首相は議会対策の上から、板垣退助と大隈重信の入閣による自由・改進両党の支持、挙国態勢の構築を試 ...
50. いとうないかく【伊藤内閣】 : 伊藤内閣/〔第二次〕
国史大辞典
年来の懸案たる地租増徴をもはや不可避とする情勢にあった。ここに伊藤首相は議会対策の上から、板垣退助と大隈重信の入閣による自由・改進両党の支持、挙国態勢の構築を試 ...