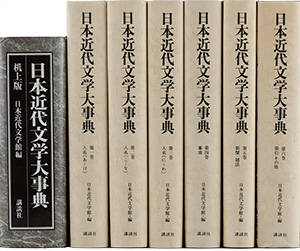江戸前期の俳人。日本近世文学の最盛期をなす元禄 (げんろく)期(1688~1704)に活躍した井原西鶴 (いはらさいかく)、近松門左衛門 (ちかまつもんざえもん)、芭蕉は、それぞれ小説、浄瑠璃 (じょうるり)、俳諧 (はいかい)の分野を代表する三大文豪として評価されている。さらに詩歌部門に限っていえば、和歌文学の頂上に位置する万葉の柿本人麻呂 (かきのもとのひとまろ)に対して、俳諧文学の頂上として芭蕉が対峙 (たいじ)し、中間の新古今時代を西行 (さいぎょう)と藤原定家 (ていか)とが世の評価を二分している。しかも芭蕉自身は、己がつながる伝統を先人のうえに数え上げて、「西行の和歌における、宗祇 (そうぎ)の連歌 (れんが)における、雪舟の絵における、利休が茶における、其 (その)貫道する物は一 (いつ)なり」(『笈の小文 (おいのこぶみ)』)といいきり、文学のみならず、絵や茶も視野のうちにとらえて、風雅全般の伝統の継承者として、自分を任じていた。
生い立ち・故郷
芭蕉は寛永 (かんえい)21年伊賀上野 (いがうえの)の赤坂農人町(三重県伊賀市上野赤坂町)に、松尾与左衛門の子として生まれた。兄半左衛門のほかに、4人の姉妹があり、家格は無足人 (むそくにん)級(一種の郷士・地侍級の農民)であった。藤堂 (とうどう)藩の侍大将であった、食禄5000石の藤堂新七郎良精 (よしきよ)の嗣子 (しし)、良忠 (よしただ)に子小姓として出仕、時に19歳。2歳年長の良忠(俳号蝉吟 (せんぎん))とともに、貞門の北村季吟 (きぎん)系の俳諧を学び、宗房 (むねふさ)の名のりを音読して号に用いたらしい。作品の初出は1662年(寛文2)だが、まだいうに足りない。66年4月、良忠は病没、やがて致仕して兄の家に戻った。
漂泊の詩人といわれた芭蕉が、いつも帰ろうと思えば迎えてくれる母郷の家をもっていたことを重視したい。芭蕉の帰郷は生涯10回にも及んでいて、滞在はおおかた2~3か月の長期にわたり、旅のついでに立ち寄ったという程度をはるかに超えている。これは「郷愁の詩人」(萩原朔太郎 (はぎわらさくたろう))といわれた蕪村 (ぶそん)の郷愁が、慈母の懐袍 (ふところ)のように、いまは存在しない毛馬 (けま)村の生まれ故郷を恋うた、浪漫 (ろうまん)的なものでしかなかったのと、まるで違う。芭蕉における故郷は現在に存在する故郷であり、彼は意外に土着的発想が強い。彼が故郷をいうとき、山家・山中・山里などといつも山ということを強調するが、芭蕉にとっては上野そのものが「山家ノケシキ」であり、とくに半左衛門の家をさすことが多い。懐かしいとともに貧しく寒々として悲しい故郷の様相ということだった。
江戸へ赴く
1672年正月、宗房の名で伊賀上野の産土 (うぶすな)神、天満宮に、三十番句合 (くあわせ)を編んで奉納(『貝おほひ』の題で翌年刊)。菅公 (かんこう)七百七十年忌にあたり、発句 (ほっく)の作者はすべて伊賀の住人、芭蕉の生涯での唯一の著述である。そのころ行われていた小唄 (こうた)や奴詞 (やっこことば)(六方詞)や流行語などを縦横に駆使した判詞が珍しく、あたかも胎動期にあった談林 (だんりん)流の無頼ぶりに一歩先んじている。この年の春、「雲とへだつ友かや雁 (かり)のいきわかれ」の留別吟を残して、江戸へ赴いた。落ち着き先は日本橋界隈 (かいわい)で、卜尺 (ぼくせき)あるいは杉風 (さんぷう)方。おりから東下した宗因 (そういん)が談林の新風の気勢をあげたのに呼応する形で、同じ志の素堂 (そどう)と、自分は桃青 (とうせい)と号して、新風合流の意図をあらわにした「両吟二百韻」を興行した。大名俳人内藤風虎 (ふうこ)らの後援を得、東下した言水 (ごんすい)、才麿 (さいまろ)、信徳 (しんとく)らとも交流し、門弟にも杉風らのほか、其角 (きかく)、嵐雪 (らんせつ)のような若い俊秀が集まり、独吟歌仙や句合を催し、立机披露 (りっきひろう)の万句興行もやったらしい。神田 (かんだ)川上水の普請に水役として、生活の資も得ていた。
1679年(延宝7)ごろから芭蕉は老荘思想や、杜甫 (とほ)、蘇東坡 (そとうば)、黄山谷 (こうさんこく)、白楽天、寒山などの漢詩風に関心をみせ始め、作風も晦渋奇矯 (かいじゅうききょう)な句風に転換しだした。それも談林風の雑駁 (ざっぱく)を脱する一時の方途であり、80年冬には芭蕉は市井雑踏の地を離れ、閑寂の地を求めて、深川六間堀の魚商杉風の生け簀 (いけす)の番小屋に移り、門下から一株の芭蕉を贈られて芭蕉庵 (あん)とよび、芭蕉翁と尊称され、しばしば「はせを」と自署した。漢詩調はしだいに格調の高さを増し、其角撰 (せん)の『虚栗 (みなしぐり)』で頂点に達する。「芭蕉野分して盥 (たらひ)に雨を聞く夜かな」「枯枝に烏 (からす)のとまりたるや秋の暮」「世 (よ)にふるはさらに宗祇のやどり哉 (かな)」など、延宝 (えんぽう)末から天和 (てんな)にかけ、徐々に純化の度は深まってゆく。
漂泊時代・蕉風確立
1684年(貞享1)の『野ざらし紀行』の旅から、本格的な漂泊時代が始まる。ときに芭蕉41歳、生涯余すところわずか11年にすぎない。だがこのわずかの期間が、芭蕉を同時代の言水、才麿、来山 (らいざん)、鬼貫 (おにつら)らを決定的に超えさせる。「野ざらしを心に風のしむ身哉」の一句に旅への決意を秘めながら、名古屋では待ち受けていた荷兮 (かけい)、野水 (やすい)、杜国 (とこく)らの面々と打てば響くような五歌仙を巻いて、それが荷兮の手で刊行され、「芭蕉七部集」の第一冊『冬の日』となる。続いて86年、同じ尾張 (おわり)の連衆によって『春の日』が出され、その三歌仙に芭蕉は加わっていないが、発句「古池や蛙 (かはづ)飛こむ水のをと」がみえ、七部集第二冊とされる。87年の旅には、3年前の悲壮な決意と違って「旅人と我 (わが)名よばれん初しぐれ」との留別吟に心の余裕がみられる。この紀行は『笈の小文』と称されるが、やはり荷兮によってこのときの収穫をも含めて、七部集第三集『阿羅野 (あらの)』が89年(元禄2)に刊行される。だが、芭蕉の遊意は一刻も止 (や)まず、その年3月末には門弟曽良 (そら)を伴って『おくのほそ道』の旅に出立する。芭蕉の紀行文の傑作であり、その定稿が完成したのは93、4年かと推定される。曽良は忠実に『随行日記』『俳諧書留』をつけていて、紀行の本文との間にいくつかの虚実がみられ、芭蕉が文に打ち込んだ志のほどをほのみせている。この旅は、西行、能因 (のういん)の跡を訪 (と)いながらの、歌枕 (うたまくら)巡りの観をも呈したが、裏日本へ越えてから歌枕的意識は薄まり、直截 (ちょくせつ)の感動が句中に打ち出されるようになる。「閑 (しづか)さや岩にしみ入 (いる)蝉 (せみ)の声」「さみだれを集て早し最上 (もがみ)川」「荒海や佐渡によこたふ天河 (あまのがは)」など。旅中の昂揚 (こうよう)した詩心がそのまま上方 (かみがた)滞在中に持ち越され、90年には珍碩 (ちんせき)(洒堂 (しゃどう))ら湖南連衆を相手に『ひさご』刊、七部集第四冊となり、91年には京の去来、凡兆 (ぼんちょう)を直接指導して『猿蓑 (さるみの)』刊、七部集第五冊として、華実兼備の蕉風 (しょうふう)俳諧の頂点に位置した。そのことは「初しぐれ猿も小蓑 (こみの)をほしげ也 (なり)」以下の発句についていえるが、去来、凡兆らを相手に心を込めて捌 (さば)いた歌仙についても妥当する。「発句は門人にも作者あり。附合 (つけあい)は老吟のほね」(『三冊子 (さんぞうし)』)とは、芭蕉の強い自負であった。
軽み・最後の旅
「不易流行」や「さび、しをり、細み」など俳諧常住の心構えは、「ほそ道」の旅中に胚胎 (はいたい)し、上方滞在中、門人との問答のうちに漏らされたもので、『去来抄』『三冊子』など、そのような意味で芭蕉の俳論の精髄であった。それだけに、支考 (しこう)、許六 (きょりく)らがあげつらったこちたき議論より、よほど含意が深く、読む者によって受け取り方も多岐に分かれやすい。1691年冬、江戸へ帰還後は、旅中の心労その他が重なって、老衰を意識し、門戸を閉じて保養に努めたが、やがて野坡 (やば)ら町人俳人を相手に「軽み」の新風を唱導し、「浅き砂川を見るごとく、句の形、付心ともに軽き」(『別座鋪 (べつざしき)』序)を志向した。心の粘りや甘みや渋滞を去って、三尺の童子の無私の態度に倣おうとした。いわば大自然に身をゆだねる随順の態度だが、それは「軽み」の具現とされる七部集第六冊『炭俵 (すみだわら)』の撰者野坡たちにも、平板な庶民性、通俗性と受け取られる傾きがあった。
1694年5月、最後の旅へ出、その終わりに近く、芭蕉自身「軽み」の神髄ともいうべき作風に到達する。「此 (この)道や行人 (ゆくひと)なしに秋の暮」「此秋は何で年よる雲に鳥」「秋深き隣は何をする人ぞ」など、芭蕉の理念の昇華して至った句境であろう。10月12日、大坂の旅舎花屋で生涯を閉じた。病中吟、「旅に病んで夢は枯野をかけ廻 (めぐ)る」。粟津(滋賀県大津市)義仲寺に葬られた。七部集最後の『続猿蓑』は98年に刊行された。伊賀市に芭蕉翁記念館がある。