「文学」カテゴリの記事一覧
オンライン辞書・事典サービス「ジャパンナレッジ」の「文学」のカテゴリ別サンプルページです。
ジャパンナレッジは日本最大級のオンライン辞書・事典サービスです。
「国史大辞典」「日本古典文学全集」「日本国語大辞典」「世界大百科事典」「日本大百科全書」など80種類以上の辞書・事典をパソコン、タブレット、スマートフォンで利用できます。
「国史大辞典」「日本古典文学全集」「日本国語大辞典」「世界大百科事典」「日本大百科全書」など80種類以上の辞書・事典をパソコン、タブレット、スマートフォンで利用できます。

歌経標式(日本大百科全書(ニッポニカ))
奈良時代の歌学書。藤原浜成(はまなり)著。序、跋(ばつ)によれば、772年(宝亀3)5月勅命により成立。偽作説もあったが、真作と認めうる。最古の歌学書で、とくに歌病(かへい)論は平安時代以降、変化しつつも大きな影響を残した。序によれば書名は『歌式(かしき)』。

百万塔(改訂新版 世界大百科事典・国史大辞典)
奈良時代に作られた轆轤びき木製三重小塔で,塔身部に〈陀羅尼経〉を納めている。相輪部と塔身部に分かれ,それぞれ一木を用いて削り出す。大きさは個体によって異なるが,標準的なもので総高21.4cm,基底部径10.5cm,塔身部のみの高さは13.4cmある。塔身部の軸部上端を筒状にえぐり

凌雲集(世界大百科事典・国史大辞典・全文全訳古語辞典)
平安初期の勅撰第1漢詩集。1巻。《凌雲新集》とも。782年(延暦1)以来の漢詩を集め,814年(弘仁5)成立。書名は〈雲を凌(しの)ぐ〉ほど優れた詩集の意。小野岑守(みねもり)が嵯峨天皇の勅命を奉じ菅原清公(きよきみ)らと慎重に協議して編集したことが

性霊集(日本大百科全書・改訂新版 世界大百科事典・国史大辞典・日本国語大辞典)
平安初期の漢詩文集。正しくは『遍照発揮性霊集』。10巻。空海作。弟子の真済が編纂したもので、当初10巻であったが、巻8以下の3巻が散逸し、1079年(承暦3)に済暹が逸文を拾集して『続性霊集補闕鈔』3巻を編み、ふたたび10巻に編纂した

菅家文草(世界大百科事典・国史大辞典)
菅原道真の漢詩文集。12巻。900年(昌泰3)成立。前半6巻は詩468首を年次順に,後半6巻は散文161編をジャンル別に集める。道真は政府高官であった得意時代,〈月夜に桜花を翫(もてあそ)ぶ〉(385),〈殿前の薔薇を感(ほ)む〉(418)など艶冶巧

倭名類聚抄(和名類聚抄)(世界大百科事典・国史大辞典)
〈わみょうるいじゅしょう〉とも読み,《和名抄》と略称する。また〈和〉は〈倭〉とも記す。醍醐天皇の皇女勤子内親王の命により,源順(みなもとのしたごう)が撰上した意義分類体の漢和辞書。承平年間(931-938)の編集か。10巻本と20巻本とがあるが,どち

本朝文粋(国史大辞典・世界大百科事典)
平安時代の漢詩文。藤原明衡編。十四巻。康平年間(一〇五八―六五)に成るか。弘仁期から長元期に至るまでの二百年間の詩文四百二十七篇を収める。書名は宋の姚鉉の『唐文粋』に倣い、わが国の文章の精粋を集めたことによる。平安時代中期から邦人の秀句の朗詠が行われ『和漢朗詠集』が

和漢朗詠集(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典・日本古典文学全集)
平安時代、貴族の間に口ずさまれた漢詩文の佳句、および和歌の詞華選集(アンソロジー)。藤原公任の撰として疑われない。二巻。成立年は不明であるが、藤原道長三女でのちに後一条天皇皇后となった女御威子の入内屏風に、倭絵(やまとえ)・唐絵(からえ)とともに配されていたものと
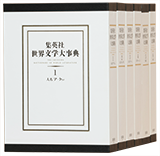
アイルランド文学(集英社世界文学大事典・日本大百科全書・世界大百科事典)
アイルランド文学は,文字に残されたものとしては,6世紀ごろまでさかのぼることができる。それまでの文学は口承によるもので,特別な修業を積んだ詩人たちが神々,英雄,美女,妖精(ようせい)の物語を語り伝えた。文字としては,石の角(かど)に長短の直線を刻み


