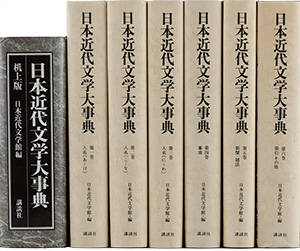イタリア最大の詩人。同時に,古代ギリシャ文学の
ホメロス,ラテン文学の
ウェルギリウスと並ぶ,ヨーロッパ最大の叙事詩人。キリスト教精神の理想を高く掲げた不滅の古典『神曲』(解説後出)を著すことによって,文学のみならず,神学,哲学,
修辞学,その他諸科学の知識を集め,アラブの新知識をも吸収し,ヨーロッパ中世文化を締め括
(くく)りながら,当時の文章語であったラテン語はもちろん,俗語すなわち発生期のイタリア文章語をも用いて,彼の後に踵
(くびす)を接して現れた
ペトラルカ,
ボッカッチョと共に,いわゆる
ルネサンス文学の開花を用意した。
ダンテの伝記にまつわる正確な資料はけっして豊かでない。ほぼ同じ時代に生活したボッカッチョによる論稿——祖国フィレンツェを追放されたダンテが56歳でラヴェンナに客死したとき,ボッカッチョは8歳でフィレンツェ市内もしくはその周辺に住んでいた——から20世紀の研究論文に至るまで,膨大な量の文献がこれまでに書き継がれてきたが,諸論はダンテの生涯や文学上の重要な結節点に関して,必ずしも意見の一致を見いだしてこなかった。むしろ,不明なデータや未解析な要素のほうが多い,といってよいであろう。
〔家系〕
ダンテ(ドゥランテDuranteの略称)・アリギエーリは,1265年,北イタリアはトスカーナ地方,フィレンツェ市国の小貴族の家柄に生まれた。生年の月日までは確定できないが,『神曲』「天国編」第22歌,112~117行の次の記述によって,それはほぼ推察される。
おお栄光の定めの双
(ふた)つ星よ,その光に漲
(みなぎ)る
大なる詩才よ,そこから発せられたのだ,
すべての,たとえ何であれ,私の才能は。
あなた方と共に昇りその星座と共に沈んだ,
一切の死すべき命の父である太陽は,
私がトスカーナの息吹に初めて触れたとき。
すなわち,この記述の星座の位置関係から判断して,1265年5月14日と6月13日のあいだに,そしておそらくは5月末日に,ダンテはこの世に生を享
(う)けた,と考えられる。生まれた場所は,現在のフィレンツェ市街中心にある聖マルティーノ・デル・ヴェスコヴォ小聖堂(古教会は一時廃
(すた)れて1432年に再建)とその向かいにある中世の建造物トッレ・デッラ・カスターニャの周辺にあったアリギエーリ家。ただし,現在のダンテ生家記念館は後年(1875年および1910年)に建造されたもの。家系はほぼ5代前まで溯
(さかのぼ)ることができるが,4代前の曾々祖父
(そうそうそふ)カッチャグィーダはフィレンツェの人で,第二次十字軍(1147−49)に参加し,ドイツ皇帝コンラート3世麾下
(きか)の騎士となって,イスラーム教徒を相手に戦死した。その次第を,「天国編」第15歌,133~148行において,曾々祖父自身の口を借り,次のごとくに述べている。
呻
(うめ)き声のうちに御名を呼ばれて,マリーアさまがわたしを世に授けた。
そしておまえたちの古い洗礼堂で
わたしはキリスト教徒となりカッチャグィーダとなった。
モロントはわたしの兄弟,そしてエリゼーオも。
わが妻はポー川の岸辺から嫁いできた,
そこにおまえの姓は由来している。
その後クッラード皇帝に付き従って,
騎士の列にわたしは加えられたが,
働きはめざましく覚えもめでたかった。
皇帝に従い討伐へ出かけたのだ,邪悪な
教えの掟
(おきて)を持つ者たちが占拠していた,
教皇たちの過ちゆえに,失われた聖地へ。
そこであの卑劣な異教徒たちの手にかかり
現世の汚濁から解き放たれた,そこに
執着するあまりに落ちてゆく魂は多い。
そして殉教から一挙にこの安らぎへ達した。
曾々祖父カッチャグィーダの父はアダーモという名のフィレンツェ人ではないかと推定されていて,カッチャグィーダの妻はフェッラーラの人アルディギエーロ・デッリ・アルディギエーリの娘であり,ダンテの姓はこれに由来する。カッチャグィーダの次男,すなわちダンテから見て曾祖父
(そうそふ)に当たるアリギエーロ1世は,12世紀末にフィレンツェに暮らしていたが,1201年にはすでに没して,煉獄
(れんごく)の第1環を100年以上も歩き回ることになっている。これらの祖先の動向は,アリギエーロ1世の次男,すなわち祖父ベッリンチョーネの記憶や家族の言い伝えによって,ダンテが幼時から承知していたものであろう。祖父は,幼いダンテから見れば,むしろ商才に長
(た)けた人物であり,土地の売買や金融業によって利益を得ていたらしい。ただし,フィレンツェの上層社会を商売相手にしていて,貴族としての体面は保持していた。おそらくそのためであろう,ベッリンチョーネは13世紀半ばにフィレンツェ市国の政争に巻き込まれ,2度にわたって追放の憂き目を見ている。ベッリンチョーネには6人の息子たちがいた。その長男アリギエーロ2世が,ダンテの父に当たる。父親に関して,詩人は黙して語らない。が,後年,
テンツォーネ(論争詩)のなかで,フォレーゼ・ドナーティが揶揄
(やゆ)して述べていることから判断しても,社会的にあまり立派な人物ではなかったであろう——むしろ強欲な高利貸しであった——と一般には考えられている。
母親はベッラ(ガブリエッラの略称)という名で呼ばれ,出身は必ずしも明確でないが,たぶんアバーティ家のドゥランテの娘であり,この母方の祖父の名を承
(う)けてダンテ(ドゥランテの略称)と詩人は命名された。ただし,洗礼を受けた日付は明らかであり,1266年3月26日に,現存する聖ジョヴァンニ洗礼堂で行われた。母親に関しても,詩人は黙して語らない。ダンテのほかに妹が生まれ,後にレオーネ・ポッジに嫁した。おそらく,この妹が誕生して,あまり歳月が経
(た)たないうちに——70~75年に——母親が亡くなった。父親アリギエーロはその後ほどなく——75~78年ころに——ラーパ・ディ・キアリッシモ・チャルッフィを後妻に迎え,彼女から弟フランチェスコと妹ターナが生まれた。なお,この妹は後にラーポ・リッコマンニに嫁している。
ダンテの幼少年時代に関して残されたデータは非常に少ない。それらのなかで,特筆すべき第1としては,生家がフィレンツェ市街のほぼ中央に位置し,市国の栄華と政争と芸術美の渦巻くなかで育ったこと,また郊外の丘陵にあった所有地(カメラータその他)に赴き,美しい自然に囲まれて生活する機会のあったことを,指摘しておかなければならない。このような生活環境で多感な幼少年時代を送った事実は,
清新体派の詩人として出発したダンテの詩的情緒の形成に大きく寄与したであろう。特筆すべきデータの第2は,幼くして交わされた婚約である。ダンテ・アリギエーリとジェンマ・ドナーティとの婚約は,1277年1月(ダンテが12歳未満)に,すでに成立していた。このように幼い男女を婚約者として定める習慣は,当時,珍しいものではなく,多分に,家の事情が考慮されねばならない。ダンテの場合にも,生母を早くに失って継母を家に迎えていたことと,またおそらく父親の健康がすぐれなかったことなどが,これに関与していたであろう。幼い婚約者ジェンマは,フィレンツェの名門ドナーティ家に属してはいたが,血筋としては傍系であり,彼女の父親マネット・ドナーティの家は政治的にも経済的にもさほど大きな力を保有していなかったことが,比較的少額の持参金から推定される。
ただし,ダンテとジェンマの婚約成立をめぐって見過ごせない重要な点は,アリギエーリ家とドナーティ家のあいだに設定された持参金が,文書作成のための単なる形式上のものではなく,77年から実効に移されたことである。ジェンマの父親マネット・ドナーティ(1304年以降まで生存)の側に立ってみれば,持参金の支払いはアリギエーリ家との絆
(きずな)を固めるため以外の何事をも意味しなかったであろう。加えて,病身であったダンテの父親アリギエーロが,1281~82年に,もしくは83年の初めには,おそらく死去していた。死因については,病気説や事故説など種々取り沙汰
(ざた)されているが,定説を見ない。確かに推測できるのは,先に生母を失い,加えていま父親を亡くした以上,ダンテとジェンマの婚約の履行がむしろ急がされたであろうことである。2人の結婚の時期は分明でないが,当時の風習から推量して,85年(ダンテ20歳)前後であろう。これには異説が多く,一般には,90年以降とされてきた。その理由は,要するに,『新生』(解説後出)や『神曲』に登場する
ベアトリーチェを実在の人物と考え,そのモデルというフォルコ・ポルティナーリの娘ビーチェの死(1290年6月)以降に,ダンテの結婚を設定したかったからである。
ところで,ダンテとジェンマのあいだに生まれた子供の数も,3人もしくは4人といわれて,判然としない。ピエートロ,ヤーコポ,アントーニアの3子があることは,早くから知られていた。たとえば,ピエートロ(1364没)の墓は,北イタリアの都市トレヴィーゾの聖フランチェスコ教会堂にあり,その内陣の左翼廊上部に横臥
(おうが)像の石棺が,現存する。娘アントーニアは,後年にラヴェンナの聖ステーファノ・デッリ・ウリーヴィ修道院に入り,修道女ベアトリーチェとなったが,その許
(もと)へ,1350年に,アリギエーリ家が被った損害賠償金の一部を,フィレンツェ共和国の使節となって37歳のボッカッチョが届けた。時代は遥かに下るが,1921年になって,ルッカの古文書館から,1308年10月21日付の証文が見つかった。そこに「フィレンツェの人ダンテ・アリギエーリの息子ジョヴァンニ」の名が記されていて,俄然
(がぜん),世の関心を集めた。このジョヴァンニを,ダンテとジェンマ以外の女性とのあいだにできた息子とする説,あるいはダンテ・アリギエーリという同姓同名の別人の息子とする説などが発表され,議論が沸騰した。これらの諸説を検討,反駁
(はんばく),整理した,20世紀イタリア最大の文献学者にしてダンテ学者であったミケーレ・
バルビの論考は,十分な説得力をもっている。その説を要約するならば,このジョヴァンニなる人物は,詩人ダンテとジェンマのあいだに生まれた可能性が大であるという。また,その論旨を延長して,バルビはこのジョヴァンニをダンテの長男と考え,1287年ごろの生まれと推測した。
さて,ジェンマとの婚約が成ったころの,少年時代のダンテに話を戻しておこう。この時期に関しても,確たる資料はほとんど残されていない。概略の事実から判断すれば,父親アリギエーロ・ディ・ベッリンチョーネの代には,家運がかなり傾き,当時の新興商人たちの活動の狭間
(はざま)にあって,詩人の起居する家は,辛うじて没落小貴族の体面を保つ程度に過ぎなかった。したがって,少年ダンテが特別な高等教育を受けたとは考えにくく,むしろごく一般的な基礎教育によって,ラテン語の読み書きや算術などを身につけたものと想定される。また,幼くして生母を失ったために,ダンテは聖クローチェ教会で見習修道士に似た生活をしていたのではないかという憶説も盛んに行われたが,早い時期にジェンマとの婚約が成り立ったことを考慮に入れれば,おそらく病身の父親と理解のある継母のもとで,むしろ自由な生活の少年時代を享受した可能性のほうが大きい。当時の教育機関に俗語(発生期のイタリア文章語)を扱う習慣はなかったから,比較的自由な生活環境のなかで,10代後半に,折から流行しつつあった俗語詩の新しい運動へ,個人的な感性をばねにして,入り込んでいったものと推測される。
〔詩的探究の出発点〕
ここで,ダンテの時代の詩的状況を概観しておこう。イタリア半島は,古代にはローマ帝国の文化の栄えた土地であり,中世には教皇勢力を支える母体の土地となった。このため,文章語としては,ラテン語が圧倒的な優位を保ってきたが,1200年代の半ばに,周辺諸国とりわけプロヴァンス地方の文学の影響を受け,半島各地に俗語文学が発生した。まず,シチリア島パレルモに本拠を置くホーエンシュタウフェン家の宮廷は,多数の吟遊詩人たちを招き入れ,ラテン文化の中心地であるローマの教皇庁と政治的に対立しながら,フェデリーコ2世(1194−1250)自らが,プロヴァンス風の宮廷恋愛詩をイタリア俗語で書いた。一般に〈
シチリア派〉と呼ばれた詩人たちの文学運動であり,彼らが綴った〈愛〉の詩編は,この派を代表する一人
ヤーコポ・ダ・レンティーニが考案したと伝えられる
ソネット(14行詩)によって,多くの追随詩人たちを生んだ。しかしフェデリーコ2世の没後,急速に衰退したホーエンシュタウフェン家の庇護
(ひご)を失い,〈シチリア派〉の宮廷詩人たちは四散し,俗語詩は北イタリアに広まった。そしてボローニャの哲学的な詩法と影響しあい,トスカーナ地方に〈清新体派〉の詩法を誕生させた。この派の詩の中心テーマも〈愛〉であり,派の創始者もしくは先駆者として,ボローニャの詩人グィード・
グィニツェッリの名をまず掲げておかねばならない。
グィード・グィニツェッリは,初めプロヴァンス風の恋愛詩を書いたが,やがて「気高い心にいつも愛は憩う/緑の森の小鳥のように」と歌って,〈愛〉と〈貴人〉もしくは〈貴婦人〉との関係性を定めた。この詩法を承けて,フィレンツェの詩人グィード・
カヴァルカンティが〈清新体派〉の雄となった。ダンテの言を信ずるならば,彼は18歳のときには,同じ市国に住む詩壇の第一人者グィード・カヴァルカンティと文学上の交友関係をもっていたという。そしてダンテ自身も〈清新体派〉の一員として,多数の俗語詩を書いた。また22歳のときに,詩人はボローニャ大学へ赴いているが,一時的な滞在であって,長期間の勉学のためとは認めがたい。むしろ,文学的関心からボローニャを訪ねた,と見なしたほうがよいであろう。このヨーロッパ最古の大学都市への滞在は,たぶん86年後半から87年前半へかけての数カ月間であり,フィレンツェ出身の青年学徒ヤーコポ・カヴァルカンティ,ジャンニ・デッリ・インファンガーティ,あるいは親戚のダンテ・デッリ・アバーティたちと交友関係をもち,ボローニャ派の詩人たちとも交わって,プロヴァンスなど北方からの新しい詩の知識を身につけた,と推測される。しかしながら,ダンテがいつボローニャ遊学からフィレンツェに帰国したのか,また88年に詩人が何をしていたのかも,いっさい不明である。
確かな事実は,89年6月11日のカンパルディーノの戦闘と,8月16日のカプローナ城砦
(じようさい)の攻略とに,詩人が加わっていたことである。これから逆算して,少なくともその前年,すなわち88年には,フィレンツェ共和国の軍事訓練に参加するため,詩人は故郷へ呼び返されていたであろう。戦いの原因は,当時,北イタリアの諸都市を二分していたギベッリーニ(皇帝派)とグェルフィ(教皇派)の争いにあり,直接的には,フィレンツェ南方に位置する2都市アレッツォとシエーナの抗争に端を発していた。やや後年にフィレンツェ共和国書記官となり,人文主義者として名を馳
(は)せたレオナルド・
ブルーニの記述によれば,共和国の文書館でダンテの書簡を発見したという(今日では失われた)。そのなかにカンパルディーノの戦闘の回想部分が含まれていて,ダンテは騎馬に乗り,第一線で戦ったが,初めは「大いに恐れたものの,終
(つい)にはこの上なく楽しい結末を迎えた」という。史実によれば,戦闘の最初の段階では,皇帝派の盟主アレッツォ軍の軽騎兵
(フエデイトーレ)たちが馬に鞭
(むち)打って大胆にフィレンツェ側陣営に攻め込んできたため,教皇派の軽騎兵たちは算を乱して逃げだした。ところが,アレッツォ軍が深追いをしたため,退路を絶たれて,結局は惨敗を喫したのであった。また,フィレンツェ西方の都市国家ルッカの軍勢がピーサを攻略したさいに,盟友のフィレンツェ共和国は騎兵400と歩兵2000の援軍を送った。これにダンテも騎兵として参加したのである。
時代は再び遥かに下るが,1881年に,フランスの研究家フェルディナン・カステが,モンペリエの文書館に眠っていた13世紀イタリア語の古写本を復刻して,
『フィオーレ(花)』と題する詩集を刊行した。作者はドゥランテDurante。全232編のソネットから成り,内容は中世フランスの
『ばら物語』を自由に翻訳改変したもの。この作者ドゥランテが——古写本に作者名もしくは訳者名はなく,ソネット82番と202番の2箇所に,「私」と名乗って,作者を思わせる人物が登場する——果たしてダンテ・アリギエーリその人か否かをめぐり,この100年間,熾烈
(しれつ)な論争が繰り広げられてきた。多くの否定論者たちの主張の根底には,理想の女性像ベアトリーチェを要
(かなめ)に据えた『新生』や『神曲』という志の高い作品群を著した詩人ダンテの作品にしては,『フィオーレ』のうちには精神的に低い次元の部分が,すなわち〈愛〉にまつわる卑猥
(ひわい)な表現描写が含まれていることへの,批判もしくは反発が働いてきたのである。
にもかかわらず,他方で,この中世フランス寓意
(ぐうい)文学の傑作を巧みなフィレンツェ語に置き換えた並々ならぬ語学的才能と,深い学識と,卓抜な詩的技法の持ち主が,文学史上まったく無名の人物であるとは,誰の目にも映らなかった。そこから,ダンテと同時代の別人に,たとえばダンテが師事したブルネット・
ラティーニに,あるいは詩人
フォルゴーレ・ダ・サン・ジミニャーノに,あるいはまた詩人ダンテ・ダ・マイアーノに,『フィオーレ』の作者を推定する説が,次々に発表されてきた。それらの諸説を,結果的に,反駁
(はんばく)し尽くしたのが,20世紀の碩学
(せきがく)G.
コンティーニの業績である。1984年公刊の国定版ダンテ著作集第8巻に収められた『フィオーレ』および
『愛の教え』は,同時に収録された浩瀚
(こうかん)な論文,綿密な注解,そして周到な文献学的研究によって,ほとんど確実に,この特異な寓意詞華集がダンテ・アリギエーリの手になるものであることを証明してみせた。なお,モンペリエにおける『フィオーレ』の発見にやや遅れて,フィレンツェの古文書館から発掘された断片詩編『愛の教え』も,同一人物の手になることが,明らかにされた。ただし,コンティーニ自身は,この国定版の作者を,なおも慎重に「ダンテ・アリギエーリと推定される」と記している。
〔詩人ダンテの手になるか?『フィオーレ』〕
ところで,ダンテの著作に『フィオーレ』を組み込むならば,かつて考えられなかった,いくつかの重要な観点が生じるであろう。そして詩人の全体像に修正を施す必要に迫られるであろう。今後,数十年間のダンテ研究はその方向へ展開するものと考えてよい。ただし,もちろん,逆の立場もあり得て,『フィオーレ』をダンテの著作と認めまいとする考えや,たとえそれを認めても『フィオーレ』を詩人の重要な作業ではないと位置づける主張も,現に進行しつつある。後者の考え方に依
(よ)った場合には,清新体派の詩人ダンテを基本とし,『新生』から『神曲』へとその文学的方向性を延長し,その基本線からむしろ逸脱した行為として『フィオーレ』を考えるであろう。いずれにせよ,ここで生ずる問題の第1は,ダンテがいつごろ,すなわち彼の生涯のいかなる時期に,中世フランス寓意文学の翻案を行ったかという点であり,第2は,それが詩人ダンテの文学形成にいかなる役割を果たしたか,という点である。
先に掲げたコンティーニは,『フィオーレ』および『愛の教え』の制作年代の決定を,最後の最後まで持ち越されるダンテ研究の課題であろう,と述べた。けれども,その大要はすでに決定されているといえよう。なぜなら,『ばら物語』は1280年に完成しているし,これを自由に翻訳改作した『フィオーレ』のなかに『ばら物語』の作者たち——前編は
ギヨーム・ド・ロリス,後編は
ジャン・ド・マン——の関知しない,イタリア半島における歴史的事実が含まれているため,『フィオーレ』が1285年以降90年以前に書き上げられたことは,まず否定できないからである。細かい記述は省略するが,この議論をより狭めていけば,寓意詞華集『フィオーレ』の作成時期は,86~87年になるであろう。ここで,この小文の当面の目的であった,ダンテの生涯の時代的吟味に,話を戻してみる。すなわち,私たちがすでに承知している確かな事実は,1287年にダンテがボローニャに滞在していたこと,また86年と88年には確かな事実の記録がないことである。さらに想起しておいたほうがよいのは,85年までには,おそらく,ジェンマとの結婚は成っていて,その1,2年後に,子供も生まれていて不自然ではないという事実である。
このような考えを辿
(たど)っていくとき,重要性を帯びてくるのは,プロヴァンス地方からパリまでダンテが旅をしたかもしれない,という推測である。ダンテがパリまで行ったという記述は古くからあって,たとえばボッカッチョはその『ダンテ賛美論』のなかで,詩人がより豊かな知識を求め,かつ才能をいっそう磨くために,ボローニャに赴いたことがあり,さらにパリにも出かけて行った,と述べている。ただし,「老境に近づいてから」という限定も,そこにはついている。ボッカッチョの記述は,ダンテを知るためより,むしろボッカッチョ自身の文学観を知るために役立ち,事実関係の資料としては必ずしも正確なものではない。それにしても,『フィオーレ』のなかにはフランスの言語を自在に操る卓抜な才能が示されていて,もしもダンテの手に成るものであるとすれば,20歳代初めまでにダンテが,どこで,どのようにして,それに習熟したのかが,明らかにされねばならない。したがって,『フィオーレ』をめぐる今後の課題の一つは,この寓意詞華集に示された詩法と,ダンテ自身の初期詩編群との,比較検討である。たとえば『フィオーレ』に認められる諧謔
(かいぎやく)の精神と,ダンテが同世代の詩人フォレーゼ・ドナーティと交わした論争詩
(テンツオーネ)との関係などは,いっそう吟味が必要になるであろう。
〔ベアトリーチェ体験と『新生』〕
ともあれ,1980年代までの諸説においては,『新生』以前に最初のまとまった文学作品として翻案詩集『フィオーレ』が存在することを考慮に入れなかったり,ジェンマとの結婚もベアトリーチェ死後に設定するのが一般であった。これら重要な2点の変更もしくは修正は,詩人ダンテの実像を浮かび上がらせるために大きな寄与をするであろう。『新生』の執筆は1293年前後であり,これは詩と散文とを混淆
(こんこう)させた小冊子である。しかしながら,タイトルが端的に示すように,〈清新体派〉のなかから一頭地を抜いた者の詩法の自負に,貫かれている。青年詩人ダンテは,清新体風のそれまでの若書きの詩編を整理し,かつ整理しきれない新たな詩法の存在を,この小冊子のうちに提示してみせた。なかでも,鮮やかに新しい部分は,ベアトリーチェをめぐっての叙述である。それによれば,周知のごとく,ダンテは9歳の終わりごろ(すなわち,74~75年に)ベアトリーチェに初めて出会うが,そのとき彼女のほうは9歳の初めであった。それから9年を経て,18歳のある日,フィレンツェの路上でたまたま再会した。そのとき,彼女はダンテに会釈をしたという。が,2人のあいだにさしたる交渉もないまま,時は過ぎ去っていく。この少女ベアトリーチェを実在の人物とする説——元を質
(ただ)せばこれもボッカッチョの前掲書『ダンテ賛美論』に発するのだが——によれば,彼女はフィレンツェの名門フォルコ・ポルティナーリの娘ビーチェ(ベアトリーチェの略称)であって,後に銀行家シモーネ・デ・バルディに嫁したが,先述したごとく,1290年6月に亡くなってしまった。
古来,ベアトリーチェの実在説をとるか,それを久遠
(くおん)の女性
(によしよう)と美化してキリスト教的寓意の存在に近づける象徴説をとるか,論は区々として分かれ,いまだに定まるところを知らない。イタリア本国の学説はもとより,欧米諸国の説の流れを汲
(く)む日本の紹介論文もまた,おおよそ,その域を出ない。しかしながら,一方において実在説をとりつつ,たとえばビーチェが絶世の佳人であってダンテに詩想を吹き込んだ等々と説きつつ,他方において詩人が初めて彼女と出会ったのは9歳のときであり,再会したのは18歳のときであったという,三位一体説ゆかりの数(9)にこだわり続けるのは,簡単に言って,論の矛盾である。もしくは,混濁した考え方である,と言わざるをえない。また逆に,寓意の像としてのベアトリーチェを掲げながら,同時にフォルコ・ポルティナーリの娘やシモーネ・デ・バルディの妻の存在にこだわり続けるのは,いかにも説得的でない。諸説は沈黙しているが,ここに改めて私見を述べておく。ダンテが9歳と18歳の2度にわたって経験したのは,見神の体験であって,そのとき認めた異象を,詩人はベアトリーチェ(恵みを与える女)と名づけた。そのことにおいて,並み居る〈清新体派〉の詩人たちから抜け出して,ダンテは字義どおり『新生』の作者になったのである。
また,この見神の体験——すなわちベアトリーチェ体験——を核にして,詩人は壮大な叙事詩『神曲』を構築しようとした。それゆえ,断固として主張しておこう。詩想のなかの人物ベアトリーチェは,銀行家シモーネ・デ・バルディの妻になったビーチェとはなんの関係もない,と。ただ,それならば,ダンテが9歳と18歳の折にめぐり会った異象の体験の契機は,何であったのか? この点に関して,いまは結論だけを記しておく。詩人の生涯を虚心に辿
(たど)り返してみるとき,幼年期から少年期の終わりにかけて,2度にわたって,ダンテは正常と異なった事態に直面した。その1は,ほかでもない,母親の死であり,その2は,父親の死である。幼い日のダンテがどのような形で母親の死に直面したのかは審
(つまび)らかにしないが,そのときの衝撃がさほど強烈でなかったとするのは,あまりにも少年の心を鈍磨したものと捉える考え方であって,到底承服しがたい。また父親の死期の近いことは,ダンテとジェンマの幼時においての婚約からも推量できるように,ある程度までは予測可能な事態であったであろう。それにしても,再び現前した,身近な死をまえにして,ダンテの心が深い衝撃を受けなかったと考えるのは,あまりにも不自然である。むしろ,この2つの死を契機にして,ダンテは詩的世界へ大きく踏み込んでいったはずであり,この2つの死の経験の彼方
(かなた)に,感じやすい青年は異象を認めて,それをベアトリーチェと名づけたにちがいない。さもなければ,何が彼を文学へ向かわせたと言うのであろうか。『新生』のなかで,ベアトリーチェ体験がおのれの特異な詩想の源泉であることを,ダンテは縷々
(るる)として述べている。
〔新しい詩学の確立へ〕
『新生』が成った直後(1294年頃)から数年間は,2度にわたったベアトリーチェ体験を,より壮大な枠組みのうちに捉え返そうとした,そのための修学期間である,と考えておきたい。ただし一般には,1290年6月に,シモーネ・デ・バルディの妻ビーチェが24歳の若さで亡くなったため,詩人は深い悲しみに襲われて,彼女の像を〈久遠の女性
(によしよう)〉として美化するべく詩法の研鑽
(けんさん)へ向かったとされるが,そのような俗解は退けておきたい。そしてこの時期にダンテがとった方法は,2つに大別できる。
ダンテは先に,フィレンツェ生まれの百科全書的博学の師ブルネット・ラティーニに就いて,おそらく
キケロ,
ボエティウスなど,古典の手ほどきを受けていた。ラティーニとダンテの師弟関係を証明する記録は残されていないが,『神曲』のなかの記述は何よりも両者の心の絆
(きずな)が確かなことを示している。
記憶に深く刻みつけられ,いまも悲しみを搔
(か)き立てるのは,
慈父にも似て優しく慕わしかった面影の
あなたです,現世にあったとき折に触れ
いかにして不朽の名声を得るかを教えてくださったのはあなたです。
そしてどれほど深くあなたに負うているかは,わが命のある限り
わが言の葉のうちに必ずや示されるでしょう。
(「地獄編」第15歌,82−87行)
しかし,『神曲』を構想するにあたって,ダンテはいまや,抒情詩から叙事詩へと詩法を大きく転換させ,過去の歴史の全知識を溶かしこむほどの坩堝
(るつぼ)を,また師ラティーニの『宝典』や『フィオーレ』を乗り越える遥かに大きな詩的枠組みを,おのれのうちに用意しなければならなかった。このための方法の第1は,ラテン文学を読破し,ギリシャ思想を含めて,古典世界の伝統を習得することにあった。
オウィディウス,
スタティウスなどが当面の学習の対象であり,とりわけマントヴァの人ウェルギリウスが関心の的になった,と推定される。方法の第2は,自らの書斎を出て,論争の場に身を晒
(さら)すことであった。当時,学問(神学,哲学,その他の諸科学)の府となっていたのは修道会である。中世末期のフィレンツェにあっては,新興の2つの修道会が学問を支える柱であった。すなわち,聖女マリーア・ノヴェッラ教会を擁するドミニコ会と聖クローチェ教会を擁するフランチェスコ会である。ダンテは前者の修道会に通って,
アルベルトゥス・マグヌスやトマス・
アクィナス(イタリア名はトンマーゾ・ダクィーノ)のスコラ哲学に精通するようになった。トマスがこの修道会に滞在した(1273)のは当時の人々の記憶に新しく,その弟子レミージョ・デイ・ジローラミがまだ講壇に立っていた。また,後者の修道会では,
聖フランチェスコの清貧思想を継承する大胆な教会改革運動に接したものと考えられる。後に異端と宣告されたペトルス・ヨアンニス・オリウィは,87~89年に,聖クローチェ教会の修道会に学僧として滞在していたし,ペトルスの没後,その過激な思想を承け継いで厳格主義派
(スピリトウアーリ)の頭目となった,ウベルティーノ・ダ・カサーレは,青年ダンテとしばしば相見
(あいまみ)えたにちがいない。『神曲』が一歌一歌,実際に執筆されていくのは,やや後年のことになるが,「地獄」「煉獄」「天国」の3編に隙間
(すきま)なく詰め込まれた該博な知識や天動説に基づく宇宙認識の基本は,この修学期間の坩堝のなかで早くも用意されつつあった,と考えておく必要がある。これらの百科全書的知識とギリシャやアラブの思想をも取り込んだ宇宙認識とが,〈愛〉の宗教感覚といかなる調和関係を築きうるか——そこにダンテの詩学の成否がかかっていた。なお,ここで〈ダンテの修学期間〉と規定した歳月のなかでの文学的・哲学的・神学的探求の内実に関しては,やはり後年に執筆された『饗宴
(きようえん)』Convivioのなかで,詩人自身がかなり詳細に言及している。
ところで,『新生』以前に,ダンテは相当量の俗語詩編をすでに書いていた。それらをまとめて,詩人が一本に著そうとしたか否かは,定かでない。けれども,最も若書きに属する,詩友ダンテ・ダ・マイアーノと交わしたソネット群の技法その他から判断しても,ダンテ・アリギエーリが若くしてシチリア派の詩作品に精通していたこと,13世紀後半に一世を風靡
(ふうび)した詩人
グィットーネ・ダレッツォの影響を強く受けていたこと,またプロヴァンスの詩法に通暁していたことは,明らかである。加えて,当代一流の詩人グィード・カヴァルカンティと親交のあったことから,またフォレーゼ・ドナーティとの論争詩
(テンツオーネ)に見られる諧謔
(かいぎやく)性などから,ダンテが俗語詩編群をまとめて,それらに,一定の秩序と構成を与えつつ,別個な構造の作品をまとめようとしていた意図は,十分に予感できる。この予感と予測の延長線上に,まず『新生』が現れるであろう。そのさい,詩と散文の混淆体
(こんこうたい)『新生』に内含された構造の吟味が,重要になる。しかも,それは232編のソネット群からなる『フィオーレ』の構造と無縁ではなく,寓意の詩法という観点からも,両者の関係性はいっそう重要なものとなるであろう。
〔政争の渦に巻き込まれて〕
ベアトリーチェ体験を叙述し,〈愛〉を寓意の存在たらしめた『新生』は,確かに新しい文学の行方を示した。しかし,もしもその限りであったならば,ダンテの詩的世界はむしろ小さいものに留
(とど)まり,個人の特殊な体験の域を出なかったであろう。そして同種の詩的感情を抱く一部の人々に熱愛されることがあったにしても,それ以上の社会的広がりをもつ作品にはならなかったのではないか。その意味において,ダンテがフィレンツェ共和国の政争の渦に巻き込まれ,ヨーロッパ歴史の命運のなかで苦しい後半生を送ったことは,彼の詩的世界を大きく広げるために,すなわち『神曲』という文学史上稀有
(けう)の叙事詩を作り上げるために,皮肉にも役立った。
1300年前後のイタリア半島を中心としたヨーロッパには,ローマの教皇庁と神聖ローマ皇帝の二大権力が存在していて,北イタリアは両勢力の狭間
(はざま)に置かれ,いくつかの都市国家に分割されていた。また,各コムーネ(自治都市)は,教皇派
(グエルフイ)と皇帝派
(ギベツリーニ)に分かれて,互いに反目していた。ダンテの住むフィレンツェ共和国内部でも両派が対立を繰り返していたが,ダンテのころには教皇派が政権を掌握していた。しかしこれが,市国の自立政策を掲げる白党と商業上の実利から教皇権力に結び付く黒党とに分裂し,さらにまた市国の名門チェルキ家とドナーティ家の確執がこれに絡まりあい,行政機関は熾烈
(しれつ)な政争の場となっていた。
1293年に,いわゆる正義の法令が出るや,貴族は公職に就くのをいったんは制限されたが,95年には,その制限が緩和された。ダンテも小貴族の家柄に属していたため,名目上は医薬業種組合に加入して,共和国の行政に携わるようになった。1296~97年に,ダンテは政府直属の百人委員会に加わり,1300年(ダンテ35歳のとき)には6名のプリオーレ(代表委員)の一人に選ばれた。任期は6月15日から8月14日までの2カ月間であった。こうして彼自身は白党に属し,共和国の自立政策に貢献しつつあったのだが,6月23日に,かねてから尾を引いていた黒白両党の争いが露
(あら)わになり,市当局は両派の重要人物各6名を両成敗の形で流罪にした。年長の詩友グィード・カヴァルカンティも白党の責任者の一人として,そのときフィレンツェを追われた。じつは,同じ白党のなかにも,ローマ教皇庁との妥協に傾く協調派と,断固これを拒む強硬派とがあって,ダンテは後者に属していた。
他方,フィレンツェ共和国の政権を白党側から奪還しようと策謀していた黒党は,野心家の教皇ボニファティウス8世と手を組み,内紛の続くフィレンツェ市政の調停者として,フランスのシャルル・ド・ヴァロアを迎え入れようとした。1301年10月,ダンテは他の3名の使節と共に,ローマの教皇庁へ赴き,ボニファティウス8世との妥協をはかろうとしたが,11月1日にシャルル・ド・ヴァロアの軍隊がフィレンツェに入城してしまい,黒党は政権に復帰した。おそらくそのとき,フィレンツェ市外に在ったダンテは,欠席裁判によって,1302年1月27日,教皇への反逆罪,公金横領罪などで,5000フィオリーノの罰金刑とトスカーナ地方外への2年間の追放,市民権剥奪
(はくだつ)などの宣告を受けた。さらに,3月10日には,裁判所へ罰金を支払うために出頭しなかったことを理由に,他の白党の者たちと共に永久追放となり,もしも市当局の手に落ちれば焚刑
(ふんけい)に処せられる,という宣告も出された。以来,詩人は二度と故国フィレンツェの土を踏むことなく,流浪の亡命生活のなかで,より大きな構想の作品『神曲』を著そうと意志を固めていった。
〔追放,亡命,流浪の生活〕
この追放,亡命を境に,ダンテの消息は,当然のことながら,不鮮明な記録の霧の彼方
(かなた)へ入っていってしまう。ただし,黒白両党の政争の渦中で,理不尽な罪を着せられただけであった事実を考慮するならば,ダンテは政治家としての汚名をすすぐために,また状況がいつ好転するかもしれないという期待を抱きつつ,おそらくフィレンツェ共和国の境界から,さほど遠くない土地に,身を潜めていたであろう。詩人は妻ジェンマと幼い子供たちを市国の城壁内に残したままであった。家族の消息や,いっさいの財産を黒党の者たちに奪われた模様は,風聞によって詩人のもとへ伝えられたであろう。残してきた家族の庇護
(ひご)には,さしあたって,弟フランチェスコが当たった。同時に追放された他の14名の白党の同志たちといっしょに,ダンテも初めのうちは政権を奪取する動きに加わり,フィレンツェ政界への復帰を果たそうとしたにちがいない。現に,追放から間もない6月8日,フィレンツェ東北約50キロの山間の村サン・ゴデンツォで開かれた会合に,ダンテは参加した。これを主催したのは,フィレンツェから追放されていた皇帝派
(ギベツリーニ)の者たちであり,ダンテは教皇派
(グエルフイ)白党に属してはいたが,同派黒党に追放されたため,黒党を打倒するという利害関係においては皇帝派に同調したのである。しかし事は成就しなかった。同年秋,亡命者側の態勢を立て直して新たな助力を得るため,ダンテは使節として,フォルリの皇帝派君主スカルペッタ・オルデラッフィのもとへ赴いた。1303年の初めの数カ月は,おそらく他の白党亡命者たちと共に,ダンテはオデルラッフィの庇護を受けていたであろう。その春のプリチャーノ城の攻略には,たぶん,ダンテも立ち会っていたが,事態は好転せずに,その後の詩人の足取りは判然としない。新たな援助を求めて,ヴェローナの君主バルトロメーオ・デッラ・スカーラのもとへ赴いた,と推測されている。
1303年,10月2日,ダンテたち白党追放の原因となった教皇ボニファティウス8世が死んだ。後任にベネディクトゥス11世が選ばれ,新たな希望が生まれかけた。新教皇はフィレンツェ共和国の内紛を収拾するため,調停役としてプラートの枢機卿
(けい)ニッコロ・デッリ・アルベルティーニを派遣し,1304年3月10日には,枢機卿がフィレンツェ市内に入った。そのころヴェローナにあったダンテは,事前に,再びトスカーナ地方へ戻ってきて,枢機卿に対する書状を認
(したた)めた。白党亡命者たちの心情を吐露した「書簡,一」にダンテの署名はないが,間違いなく詩人の手になるものであった。しかしながら,この枢機卿の調停も惨めな失敗に終わった。そして決裂と同時に,白党は武装闘争を再開し,党内からは脱落する者を許さなかった。ダンテ自身の行動は定かでないが,おそらく,白党亡命者たちのなかにあって,武力対決に批判的であった。この間の事情を,後年,詩人は『神曲』のなかで,曾々祖父カッチャグィーダの魂の口を借りながら,つぎのように,主人公ダンテに語りかけさせる。
おまえは喜びの種をみな棄
(す)てねばならないであろう
最愛のものまで。これが苦しみの矢だ,
追放という弓から放たれた最初の矢。
おまえは味わうであろう,いかに苦いかを
他人のパンが,いかに辛いかを他人の
階段を昇り降りするときの足取りが。
そしてひときわ肩に喰
(く)い込む重荷は,
邪悪で卑劣な仲間の仕打ちであろう,
その巻き添えで流浪の谷間をさ迷うであろう。
まったくの薄情,狂乱,不敬の果てに
おまえを敵視するであろう。だが,ほどなくして,
額を朱に染めるのは,おまえではない,彼らのほうだ。
彼らの取る行動は人の道を外れた彼らの
証
(あかし)となろう。結局はおまえの栄誉となろう
おまえ自身のためにおまえの党派をつくったことは。
(「煉獄編」第17歌,55−69行)
こうして〈一人一党〉を宣言したダンテは,ついに他の白党亡命者たちと袂
(たもと)を分かった。単独者としての行動はまさに茨
(いばら)の道を行くに等しかったであろう。ともあれ,かつての仲間たちが三たび,フィレンツェの黒党と戦闘を交えた場に,ダンテの姿はなかった。そして〈額を朱に染め〉たのは,彼らであった。すなわち,1304年7月20日,フィレンツェ市の北方わずか5キロの地点ラ・ラストラにおいて,市中に攻め込もうとした白党亡命者たちは,逆に決定的な敗北を喫したのである。
〔政治から文学へ〕
単独者としての詩人の旅は,文字どおりに流浪の日夜であり,苦渋に満ちたものであった。その実情はたとえば「書簡,二」にあからさまに記されている。
「あなた方の叔父アレッサンドロは,英邁
(えいまい)なる伯爵であったが,過日,その魂の依
(よ)って来たる天上の祖国へ,旅立たれた。彼はわが心の主君であった。その追憶は,わが命のこの世にあるかぎり,わたしを律しつづけるであろう……しかるに,さらに,どうか赦
(ゆる)していただきたい。その涙ながらの葬儀に,あなた方のもとへ,わたしの参列できぬ非礼を。それというのも,わが身を引き止めているのは怠慢でも非情でもなく,追放によって惹
(ひ)き起こされた思いもかけぬ貧窮であるがゆえに。いまや,酷薄なる追手のごとく,それは獄舎の洞窟
(どうくつ)の奥へとわたしを追い込んでしまった。哀れにもわが身に乗馬はなく武器はなく,持てる力を振りしぼって逃れんとしても,貧窮はことごとくわたしを圧倒して,無残にもわたしを打ち拉
(ひし)いでしまった」
ロメーナ伯オベルトとグィードに宛てて,彼らの叔父アレッサンドロの逝去を悼んで書かれた「書簡,二」は,1304年のものであるが,このころ単独者として行動しつつあったダンテは,政治において破れた理想を,文学において実現しようと,決意しつつあった。1304~07年にかけて,時期をほぼ同じくして書かれた2つの書物『俗語論』De vulgari eloquentiaと『饗宴』とは,それぞれ別個の素材(一方が言語,他方が思想)を扱い,別個の主題を追求しながら,双曲線のごとくに対称的な内容を含んでいた。しかも,いずれも未完となった,これら2書の目指した行く手に,より大きな構想の作品『神曲』が実現されるはずであった。逆の言い方をすれば,『神曲』が実現されるために,いわば不可欠の前提として,『俗語論』と『饗宴』が執筆されたのである。両者には,苦しい流浪の亡命生活のなかで,まず何よりも,詩人としての自己を回復するための努力が,新たなる詩法を確立するための詩学が,言語と思想の両面から,究明されていった。
この2著を,どこで,どのようにして,ダンテが書いたのかは,いまのところ不明である。まず『俗語論』は,ラテン語で書かれ,全4編で構成されるはずであったのが,第2編の第14章まで書き進めたところで中断し,未完に終わった。『饗宴』のほうは,イタリア俗語で書かれ,全15編から成るはずであったが,第4編まで書き進めたところで中断し,同じく未完に終わった。後者は,知の饗宴とも呼ぶべき,百科全書的性格の膨大な作品になる予定であって,これをいったん構想し,書き始めた(1304年から)時点で,前者『俗語論』の執筆に入ったらしい。そのことは,『饗宴』第1編,第5章の記述から窺
(うかが)い知れる。「この点に関しては,神の許しを得て,いずれ〈俗語論〉を展開するときに,その小著のなかで,仔細
(しさい)に述べるであろう」
同書,第1編,第3章に,以下のような記述もある。「ローマの最も美しく最も名高い娘,フィオレンツァ,彼女の優しい懐から——そのなかで私は生を享け,私の命の頂点まで育
(はぐく)まれたが,そのなかで,彼女の優しい安らぎとともに,疲れ果てたこの魂を休ませ,残された私の歳月を過ごしたいと,切に心から願っているのだが——この私を追い払うことが,彼女の市民たちの喜びであったがゆえに,この母なる言語の広まるほぼ全域を,ほとんど物乞
(ものご)いしつつ,さすらい歩き,傷ついた者にしばしば不当にもさらに加えられる,運命の傷を,心ならずも,私は人目に晒
(さら)しつづけている」
繰り返して言うが,ダンテがフィレンツェ共和国の政争の渦に巻き込まれ,母なる土地を追放されて,ヨーロッパ歴史の命運のなかで苦しい後半生を送ったことは,彼の詩的世界を広げるために,皮肉にも役立った。亡命生活の初期にあっては,追放された他の同志たちと謀り,フィレンツェ復帰を画策したが,いずれも不成功に終わって,徒党を組むことの虚
(むな)しさを嚙
(か)みしめ,ついには〈一人一党〉を宣言して,詩人としてのより強固な意志の道を歩みだした。母なる土地フィレンツェを「ローマの最も美しく最も名高い娘」と呼んだとき,ダンテはローマ帝国の再現を胸に描きつつ,おそらく現実的な政治方策として,『帝政論』Monarchia(13頃)を著したのであろう。彼の期待を担った神聖ローマ皇帝ハインリヒ7世は,1310年,イタリアに南下してきたが,13年8月21日,シエーナ近郊のブオンコンヴェントで急死してしまった。そのとき,ダンテが故郷フィレンツェに帰る望みは,いっさい断たれた。母なる言語の地域イタリア半島全体を,一つの政治的文化的ブロックとしてまとめようとする彼の願いは,虚しく潰
(つい)えたのである。
1307年前後には,『饗宴』と『俗語論』に盛り込もうとした詩学を理論から実践へと転換させ,叙事詩『神曲』が書き始められた。そしてハインリヒ7世の死去とともに,いっさいの政治的希望を失ったダンテは,いまや,北イタリアの宮廷のあちこちに安住の地を求めつつ,苦渋の生活のなかで,激しい怨念
(おんねん)と見神の体験に基づく魂の救済とを,「地獄」「煉獄」「天国」の三界の遍歴のうちに描き出していった。『神曲』を読了した者は,詩人の特異な〈ベアトリーチェ体験〉と並んで,全編を貫く〈正義〉の志に強く打たれるであろう。流浪の生涯のうちにダンテは,至る所で,跋扈
(ばつこ)する不正を見届けたにちがいない。この世は裏切られた〈正義〉に満ちみちている。もしも人間に彼岸
(ひがん)の世界が残されていなければ,またもしも此岸
(しがん)の世界の不正を糺
(ただ)す〈神〉の存在が心に思い描けなければ,私たちは永遠に地獄のごときこの世を生き続けるしかないであろう。〈正義〉を約束する〈神〉の存在,〈愛〉を通してかいま見える〈神〉の存在——これを,渾身
(こんしん)の力を振りしぼって歌い上げること。ダンテの詩学は,それ以外の何ものをも,目指さなかった。
1320年1月,マントヴァからラヴェンナに向かう途中,ヴェローナの君主カングランデの宮廷に立ち寄ったさい,同市にある聖女エーレナの小聖堂において行った講演を基に,ラテン語による『水陸論』Questio de aqua et terraが書かれた。また,このころ,ボローニャのラテン語学者ジョヴァンニ・デル・ヴィルジーリオの勧めによってラテン語の詩編『牧歌』Eglogheも書かれた。そして1321年9月,当時,賓客として厚遇されていたラヴェンナの君主グィード・ノヴェッロ・ダ・ポレンタの使節となって,ヴェネツィア共和国へ赴いたが,その帰途,急の病(マラリアであろうといわれている)を得て,同月13日夜半から14日未明にかけて,ラヴェンナに没した。遺骸
(いがい)は同市聖ピエール・マッジョーレ(現在は聖フランチェスコ)教会堂の一角に埋葬されている。



 過 ...
過 ... 衍之術、迂大而 ...
衍之術、迂大而 ... 〉押入の中・四「速度はアンダンテかアンダンチーノらしかったが ...
〉押入の中・四「速度はアンダンテかアンダンチーノらしかったが ... [ク] ...
[ク] ...