
ドイツの宗教改革者。農民の出で鉱夫であったハンス・ルターHans Lutherの子として中部ドイツのアイスレーベンに生まれる。のちマンスフェルトに移住し,事業に成功を収めた父の期待を受けて,同地,さらにマクデブルク,アイゼナハの学校を経て,1501年エルフルト大学に入学し,02年教養学士,05年修士となり,法学を学び始める。その年の7月2日シュトッテルンハイムで落雷に会い,そのおりの誓願に従ってアウグスティヌス隠修修道会に入る。07年司祭として聖別され,神学研究を始める。10-11年には修道会の要務でローマに旅行し,11年末にウィッテンベルクに移り,残りの生涯をほとんどそこに過ごすようになる。修道士生活の中で救いの確かさを求めて苦闘し,修道会ドイツ総長代理シュタウピッツの指導を受ける。12年神学博士となり,シュタウピッツの後任としてウィッテンベルク大学の聖書教授となり,翌年から《詩篇》,《ローマ人への手紙》などの講義を始める。これら初期の聖書講義の中で,ルターは,人間の救いが,イエス・キリストに示される神の恵みによるという宗教改革的認識に到達し,それを深めた。
そのころザクセン選帝侯領境まで来て頒布されていたテッツェルによる贖宥状(免罪符)頒布に上述の認識と信仰によって反対する〈九十五ヵ条提題〉を--一説にはウィッテンベルク城教会の扉に掲示して--17年10月末公にしたことが,歴史上の事件としての宗教改革の具体的なきっかけとなり,多くの賛同とローマ・カトリック教会の反対とを招くことになった。18年にはアウクスブルクで枢機卿カエタヌスによる教会審問を受け,自説の取消しを拒否,19年にはエックとライプチヒで討論(ライプチヒ討論)して,教皇も公会議も無謬ではありえないと主張した。そのころからみずからの信仰と神学を,学者のためにはラテン語で,民衆のためにはドイツ語で著作して公にしはじめ,20年にはそれは一つの山を迎えて《キリスト者の自由》をはじめとする多くの著作が出版される。20年末には破門脅迫教勅を焼却して,21年初めには遂に破門とされる。4月ウォルムス国会に召喚されるが,重ねて自説撤回を拒否し,帝国追放刑(帝国内においていっさいの権利を奪われる刑)を宣告された。
その帰途,選帝侯フリードリヒの保護検束によって以後9ヵ月ワルトブルク城にかくまわれる。騎士イェルクに身をかえたこの期間は著作活動とくに新約聖書のドイツ語訳という成果を残した(《ルター訳聖書》)。ウィッテンベルクでの改革の過激化と混乱の知らせを受けて,身の危険もかえりみず,22年3月そこに戻って,説教活動を基礎とした漸進的な具体的改革を指導し,礼拝改革,修道院解放,教会財産処理,貧民救済,学校教育確立のために働く。25年春,農民運動の高まりの中で農民団を訪れ,また著作を著して,福音を短絡的に社会的要求としないよう,また,正当な主張を暴力に訴えないよう訓戒するが,容れられず,農民戦争の事態となり,諸侯は団結してこれを鎮圧した。6月には元修道女カタリーナ・フォン・ボラKatharina von Boraと結婚(この結婚から3男3女が生まれる)。前年エラスムスが出した《自由意志論》に対する反論《奴隷的意志について》を同年末に公にして,神の恵みの絶対性を主張し,人文主義的キリスト教と袂を分かつことになった。
27年には,選帝侯ヨーハンに働きかけ,その命で領内教会巡察に取りかかり,プロテスタント教会の組織化をはじめるが,これはまた以後ドイツの領邦教会体制の始まりともなった。教会巡察はメランヒトンなどによる各地の教会規則制定に至るが,ルターは29年に大小二つの教理問答書(《ルター大小教理問答》)を著して,民衆の信仰教育を心がけた。その年プロテスタントの政治的結集を求める諸侯の願いでもたれたチューリヒのツウィングリとの神学会談は,聖餐論において一致に至らなかったが,30年アウクスブルク国会には,いくつかのルターの信仰告白を基とした,メランヒトン起草の〈アウクスブルク信仰告白〉が提出され,これによってルター派教会がしだいに西欧各地に形成されていく。ルター自身も37年には〈シュマルカルデン条項〉によって重ねてみずからの信仰的立場を明らかにした。34年には全聖書のドイツ語訳出版をみるが,こうして死に至るまで大学での聖書講義(《ガラテヤ人への手紙》《創世記》など),著作活動,改革の指導や牧会活動を,弱まっていく健康にもかかわらずつづけていった。46年1月マンスフェルト諸侯の係争調停のためアイスレーベンに旅行し,2月18日心臓発作により死去,ウィッテンベルク城の教会に葬られた。
ルターの思想はキリスト教信仰に基づく。しかもその特徴は神中心の徹底的な思考にある。若い日の大学教育や修道院での体験をとおして彼が学んだ中世末の哲学と神学,とくにオッカムに由来するオッカム主義のそれは意志と能力と能動的経験による個への注目を特色とする。ルターが修道院入りしたときの問い〈私はいかにして恵みの神を獲得するか〉はまさしくその宗教的表現にほかならない。思考においても,修道院での苦行によっても,人間(自己)中心の,神に至る上昇の可能性が空しいことに絶望する中で,ルターは聖書がイエス・キリストの生と十字架の死と復活とによってまったく逆方向の道を示していることを発見する。すなわち,恵みの神はイエス・キリストにおいて罪人である人間のところに降ってきて,罪人を救うためにすべてのことをなしとげてくださる,ということである。ここに,神中心への徹底的な注目が始まり,彼の信仰と神学とはこれに貫かれることになる。神のみへの注目はキリストのみへの注目となり,ここから三つの〈のみ〉もまた導き出されることになる。すなわち,いわゆる宗教改革原理としての〈聖書のみ〉〈恵みのみ〉〈信仰のみ〉である。
中世末の教会と神学は,聖書とならんで教会の伝統(伝承)や教皇の権威,公会議の権威をも,教会の教えや実践のよりどころとしていた。しかし,聖書によって神中心の発見へと導かれたルターは,神中心への徹底的な注目のゆえに,神の言葉としての聖書とならぶ,いかなる人間的な教えや権威も,教会の教えや実践の根拠として認めることはできなかった。神中心からする〈聖書のみ〉の原理の確立である。こうして,一方では,教皇や教会伝統に対する厳しい批判と反対とが叫ばれるとともに,他方では,聖書に示されている神の言葉を,人間に対する審(さば)きの言葉(律法)として,さらにより強く,人間に対する救いの言葉(福音)として心の中に聞き,受けとめていく真剣な取組みが続けられる。ルターの教授活動が聖書講義に終始したことも,みずから説教者でありつつ,教会の働きの具体的な中心が礼拝における神の言葉の生きた説教であると強調したこともその結果にほかならない。
ルターの〈聖書のみ〉はたんなる形式的なものではない。聖書の中心であるイエス・キリストに焦点をあわせた理解である。そこからは聖書の字句への拘泥や,それによる束縛は生じてこない。むしろ,聖書は,人間に対する神の恵みを証しする書物であり,まさにそのようなものとして,神の〈恵みのみ〉を告げるものとなる。このように〈恵みのみ〉とは,人間の救いのために神が恵み,愛の心をもって,神おひとりですべてのことを成し遂げてくださったし,今もそのように働き続けておられるということの確認である。ルターはこのような神の恵みの働きの極限をキリストの十字架にみるから,ルターの神学はまた〈十字架の神学〉とも呼ばれうる。
神の恵みはルターにとって圧倒的であり,一方的ですらある。人間の救いのために,人間がその意志においても,能力においても,実行においても,神と協力していささかなりとも貢献しうるといういっさいの可能性を拒否する。すなわち神の全能と全活動性の確認である。だから,どれほどキリスト教的にみえてもルターはエラスムスのキリスト教的人文主義を認めることはできなかった。人間の〈奴隷意志〉の主張は,神中心からの必然的な要請にほかならない。そして,神の恵みに相応じるのは,ただ信仰のみである。ルターによれば,信仰すらまず〈われわれのうちにおける神の働き〉であり,それゆえ〈神に対する固い信頼〉である。キリストの十字架による,神の救いの働きを神への感謝をもって受けいれ,受けとめることである。このようにして神中心の確立の中で,〈恵みのみ〉に〈信仰のみ〉が対応する。だがそれは決して,信仰者にとって安住坐臥や無為を意味しはしない。教会改革の実際においても,この信頼に徹したルターの日々をみてもこれはわかる。恵みに支えられ,動かされて,神から与えられた生の日々をこの世界の中で精いっぱい生きるキリスト者の生のありかたの積極的な示唆を,われわれはルターの信仰と神学の中に豊かに見いだすことができるであろう。
このようなルターの思想は西欧思想史にも大きな影響を及ぼした。以後の西欧思想史はルターの理解と誤解を伴っている。例えばカントやヘーゲル,ゲーテを挙げ,さらにはナチズムを挙げて,それを暗示することもできよう。日本では,1911年に《キリスト者の自由》が訳されたのが邦訳の始めであるが,相前後して伝記の出版もみられた。翻訳や論文,著作によってルターを紹介し,研究を深めたのは石原謙と佐藤繁彦(とくに後者の《ローマ書講解に現れたルターの根本思想》)である。これにつづく岸千年のルターの《ヘブライ人への手紙》講義の研究(《ヘブル書講解におけるルターの神学思想》)や,すでに数ヵ国語に翻訳されている北森嘉蔵《神の痛みの神学》がある。近くは金子晴勇《ルターの人間学》が学士院賞を受け,年々,ルター研究の著作,論文は増えている。邦訳は《ルター著作集》全36巻(既刊10巻)のほか,徳善義和編《世界の思想家5--ルター》および類似のシリーズにも手ごろのものが多い。日本のルター研究家は日本ルター学会を組織し,世界の研究者たちとも国際的つながりをもっている。
→宗教改革 →ドイツ農民戦争 →プロテスタンティズム
ドイツ宗教改革の指導的神学者。
1483年11月10日アイスレーベンに生まれる。農民出身の父はマンスフェルトで鉱夫になり、のちに鉱山業を営む。ルターは単純厳格な両親によりカトリックの信仰を学び、マクデブルクとアイゼナハで学校教育を受ける。1505年エルフルト大学で文学得業士となり、さらに法学部に進学する。同年旅行中に雷雨に突然襲われ、死の恐怖のため修道士になる誓願をたて、2年後に父の意志に反して修道院に入る。オッカム主義の神学教育を受け、1508年、当時新設のウィッテンベルク大学で一般教養科目を、さらに1512年神学博士となってから聖書学を担当する。この間、彼は自己の善行をもってしても心に平和を得ることができずに、己の罪に絶望するが、ただ信仰によってのみ神から授与される「神の義」を発見する。これが宗教改革的認識とよばれる新しい神学の出発点となる。このような認識に基づいて聖書の講義を行い、罪の赦しのために制定された悔い改めの礼典に疑問を抱き、ドイツのザクセン地方に販売され始めていた教皇の免罪証書(免罪符)について学問上の討論を開く目的で、1517年10月31日、有名な「九十五か条の論題」を当時大学の掲示板でもあった城教会の扉に提示した。この論題はたちまち全ドイツに広まり、宗教改革運動の発端となった。
改革運動の初期はルターの人格を中心にして展開した。重要な事件をあげると、彼が所属する修道会の総会が1518年にハイデルベルクで開かれ、討論がなされ、アウクスブルクで教皇の使節カエタヌスの審問を受け自説の撤回を求められたが拒否し、1519年にはライプツィヒで神学者エックと討論し、教皇も過ちを犯しうると認めたため、ローマ・カトリックと分裂し、1520年教皇から破門勅令を受けるも焼き捨てた。1521年ウォルムスの国会に召喚され、自説の撤回を拒否したため、帝国追放処分を受けた。しかしザクセン選帝侯によりワルトブルク城にかくまわれたが、急進的革命家の騒擾(そうじょう)を抑えて福音(ふくいん)主義教会の確立に努める。その間、ドイツ農民戦争(1524~1525)に巻き込まれ、ヒューマニストのエラスムスと自由意志論争をなし、さらにマールブルク会談では聖餐(せいさん)について一致が得られず、スイス宗教改革者ツウィングリとも決裂し、プロテスタント同盟の夢が破れた。1530年アウクスブルクの国会で宗教問題がふたたび討議され、メランヒトンが代行となり、「アウクスブルク信仰告白」を提出したが、皇帝との対立は激化した。ルターは最後まで説教、講義、勧告、著述に携わり、貴族たちの紛争和解のため郷里アイスレーベンに赴き、1546年2月18日同地で病を得て死去した。享年63歳であった。
2018年1月19日
ルターの著作は空前絶後のもので、600ページ以上の大冊が100巻を超えている。そのなかで改革文書として重要なものをまずあげると、宗教改革の全プログラムを提示した『キリスト者の身分の改善についてドイツ国民のキリスト教貴族に』(1520)、カトリック教会の礼典について批判した『教会のバビロン捕囚』(1520)、および信仰と愛にたつ自由な人間の本質を論じた『キリスト者の自由』(1520)がある。またエラスムスとの論争で神の恩恵の絶対性を力説した『奴隷意志論』(1525)や、皇帝への抵抗権を説いた『愛するドイツ人への勧告』(1531)、教義を平明に説いた『大教理問答書』(1529)、信仰から生じる倫理を解明した『善いわざについて』(1520)などが優れている。
次に、彼の本業である聖書講義は改革文書の母胎となっている重要なものであり、初期では「詩篇(しへん)」「ロマ書」「ガラテヤ書」「ヘブル書」と続き、完成期に入ると「ガラテヤ書」と「創世記」の講義がもっとも重要である。とくに「ロマ書」講義においては、宗教改革的認識にたつ思想がみごとに結実し、オッカム主義との対決のうちに信仰義認論が確立されている。
2018年1月19日
ルターの思想は、プロテスタントの三原理といわれているものに要約されている。それは「信仰によるのみ」「聖書のみ」「万人祭司性」であり、教皇主義者をさしていった「ローマ主義の三城壁」を攻撃するためにたてられたものである。そのなかでも「信仰によるのみ」の原理こそルターの信仰義認論を表明するもっとも重要なものである。彼はオッカム主義に従って義認のために諸々の準備をし、善いわざの功績を積んで救済に達しようと苦闘したが、「神の義」というのは、神が私たちに求める正しさではなく、信仰によって神が授与したまう正しさであることを知り、それがキリストの恩恵として与えられていることを理解した。こうして行為による義認に対決する、「信仰によるのみ」の義認が説かれた。したがって、もはや教会の授ける「免罪」はまったく不要であり、「悔い改め」も儀式ではなく、「心の転換」を意味すると主張された。この新しい神学は聖書を最高の権威とみなし、聖書に立ち返って宗教を改革してゆくもので、中世カトリック教会が定めた七つの礼典(洗礼、堅信(けんしん)、聖餐、悔い改め、終油(しゅうゆ)、叙任、結婚)も、洗礼と聖餐のほかは聖書的根拠を欠くものとして否定された。なお、ルターは、聖餐のパンとぶどう酒のなかに神の言と信仰によりキリストが現在すると説いたのに対し、スイスの宗教改革者ツウィングリは、聖餐はキリストの体を象徴しその受難を記念して行うと主張したため、その他の点では合意に達していたにもかかわらず、両者は分裂し、ヘッセン方伯フィリップPhilipp von Hessen(1504―1567)によるプロテスタント同盟は成立しなかった。
2018年1月19日
![クラナハ『マルティン・ルター』[百科マルチメディア]](https://japanknowledge.com/image/intro/martin_luther.jpg)


 [キョ]
[キョ] [0]
[0] [シェ]
[シェ]







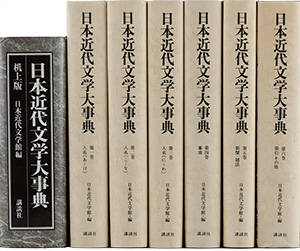

©2026 NetAdvance Inc. All rights reserved.