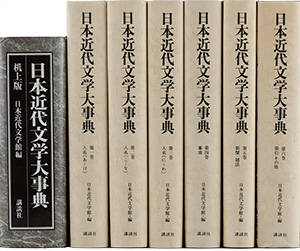イギリスの劇作家,詩人。中部イングランド,ウォリックシャーの小さな町ストラトフォード=アポン=エイヴォンに生まれた。誕生日は4月23日とされるが,それは記録に残る受洗日の4月26日から逆算して,後世がそのように定めたものである。父親ジョンは,近隣の牧農産品の集散地であったこの市場町で,皮革業,手袋製造業を営み,羊毛,木材,大麦の売買も手がけた。近在の裕福な農家の娘メアリー・アーデンと結婚して,4男4女をもうけたが,その第3子の長男がウィリアムであった。ジョンは1559年ごろから,町の役職に就くようになり,参事会員などを経て,68年には町長にあたる地位に至っている。彼は,当時珍しくないことであったが,無筆であったらしい。ウィリアムはこの町にあったグラマースクール(文法学校)に通ったと推定される。これは8歳から15歳ぐらいまでの男子の教育機関で,それ以前の初等教育で英語,算数の初歩を習得した生徒にラテン語を中心とする古典教育(文法,古典の読解,作文,論理学,
修辞学,さらにはある程度のギリシャ語)を施した。ウィリアムは,その際,詩文のほかに,
テレンティウスや
プラウトゥスなどローマの劇作家の戯曲を知る機会があった。また,当時ロンドンの劇団は地方巡業に出ると,それぞれの町で町長の許可を得て上演をしたが,そのような劇団がストラトフォードや近くの町で上演を何回も行っているから,ウィリアムにはそれらを観
(み)る機会があったろうし,さらに,近くの町コヴェントリーなどでは中世以来の
聖史劇の上演もまだ行われていたから,そういう土着の演劇を観る機会もあったと考えられる。この間,父親のジョンは,なんらかの理由で経済的に窮迫し,羽振りがわるくなったらしい。
1582年ウスター主教区法院はウィリアムと8歳年上のアン・ハサウェイ(ストラトフォード近くの村ショッタリーの農家の娘)との婚姻を11月27日付で認可している。次いで翌年5月末には長女スザンナが誕生している。この日付から,シェイクスピアの結婚について想像をめぐらす余地はあるが,当時の習慣として教会法によらない婚姻方式も広く存在したことを考慮に入れる必要がある。次いで85年には,長男ハムネットと次女ジュディスの双生児が生まれている。この2人の名前は,近所の友人夫婦の名をもらってつけたものである。これらウィリアムの妻子は,彼がロンドンに出たのちも,ストラトフォードで生活したと考えられるから,彼は故郷との縁を完全に切ることは生涯に一度もなかったことになる。その後,92年にロンドンでシェイクスピアへの言及と見られる文章が現れるまでの彼の動静はわからない。ランカシャーで家庭教師をしていたというかなり有力な説があるが,確実ではない。近所の豪族の庭苑から鹿泥棒をしたのが露顕して出奔したとか,ロンドンに出て劇場の馬番からはじめたというような言い伝えが古くからあるが,いずれも伝説の域にとどまる。ロンドンの劇団になんらかのつながりができて出て来たと考えるのが自然であるが,はっきりした証拠は何もない。この期間のことは一般に〈失われた年月〉と呼ばれる。
ロンドンでのシェイクスピアへの最初の言及とみられる記録は,ロバート・
グリーンという先輩劇作家が書き残したものである。そこでは,状況証拠から推してシェイクスピアと思われる人物が,俳優でありながら劇作にも手を染め,演劇界で頭角を現しかけている様子が嫉視
(しつし)の角度から「一羽の成り上がり者の烏
(からす)がいる……」と記されている。このころすでにシェイクスピアは劇の各ジャンルにわたって,劇作を開始しているのであるが,どのような劇場や劇団のためにそれらを書いたのかは,必ずしも明らかではない。グリーンの『一文の知恵』が著された92年の夏から94年初頭まで,ロンドンは当時周期的に頻発していた疫病流行のうちかなり大規模なものに見舞われた。ペストが流行すると,伝染を恐れて劇場は閉鎖を命じられるので,劇団は財政的に苦しい状況におかれる。この時のそれは,在ロンドンの各劇団に大きな打撃を与え,その再編成を促すことになった。この間に,シェイクスピアは詩作に手を染めて,サウサンプトン伯ヘンリー・リズリーに捧げたりしている。疫病の流行が収束した94年にロンドンには再編成後2つの劇団が残ったが,その1つが当時の宮内大臣ハンズドン卿
(きよう)ヘンリー・ケアリーの庇護
(ひご)をうけた劇団で,
宮内大臣一座と呼ばれるようになった。この時すでにシェイクスピアはその幹部の一人になっていることが記録によって明らかである。この一座は,ジェイムズ・バーベッジに率いられ,その息子リチャード・
バーベッジを看板俳優とし,シェイクスピアを座付き作者として,これよりのちロンドンの演劇界をしだいに席捲
(せつけん)していくこととなる。
この劇団は当初
シアター座を中心に公演していたが,ジェイムズ・バーベッジが没した97年ごろから,この劇場の借地契約のことで地主との間に悶着
(もんちやく)が起こり,99年この劇場を解体して,テムズ南岸バンクサイドに移築し,
グローブ座と名づけて,そこを用いるようになった。以後1608年ごろまで,シェイクスピアはもっぱらこの劇場での上演のために一座に戯曲を提供することになる。この劇場の開場時までに,彼がすでに劇作家として名をなしていたことは,1598年に出版されたフランシス・ミアズの雑録集『知恵の宝庫』に,シェイクスピアが喜劇と悲劇の両分野においてイギリスで最も優れていると述べられ,いくつかの戯曲の名が挙げられていることからも,うかがえる。また,劇場経営者としても成功を収めていたことは,96年に父親がかねてから望んでいた紳士の紋章を認可されたこと,翌97年ストラトフォードに〈ニュー・プレイス〉と称される立派な邸
(やしき)を購入したことからもわかる。しかし96年には一人息子のハムネット(享年11歳)を喪
(うしな)ってもいる。
この一座には,その後いくつかの出来事——世紀の変わり目ごろに少年劇団がロンドンで活動しはじめて成人劇団との間で激しい競争が行われたとか,1601年のエセックス伯の反乱に一座が多少の関わりをもったとか,あるいはまた,1603年にエリザベス女王が没してスコットランド王ジェイムズが王位を継いだのち,一座が国王一座と名を改めたとか——が起こったが,劇団そのものは順調に発展して,ジェイムズ1世の宮廷での御前公演も他の劇団を圧倒して頻繁に行うようになった。その間,シェイクスピア自身は1602年に郷里の近郊に100エーカー以上の耕地を購入し,さらに1605年にはやはり郷里近郊の3つの村落の10分の1税徴税権の半分を買い取るなど,着々と財をふやしている。また,1607年には長女スザンナが故郷の医者ジョン・ホールと結婚している。
1608年,国王一座はシティの内側にあって少年劇団が使用していた
ブラックフライヤーズ座を借り受け,冬期にはそこで上演するようになった。これは入場料が高い屋内の小劇場で,観客の階層もグローブ座とは異なっていたから,夏期にはグローブ座で冬期と同じような演目による上演を依然つづけていたのではあるが,一座の上演方針はある程度の影響を受けたと考えられ,したがってシェイクスピアの戯曲も変化せざるを得なくなったと考えてよかろう。ともかく,10年ごろから,国王一座のレパートリーには宮廷好みの新しい作風をもつジョン・
フレッチャーの戯曲が組み入れられはじめ,シェイクスピアとも合作を行ったりするようになったらしい。また,このころシェイクスピアは生活の本拠を故郷に移し,しだいに悠々自適の境地に入っていったと思われる。もっとも,この時期のストラトフォードの記録から推すと,近郊に生じた土地の〈囲い込み〉enclosure問題で,彼が周囲から批判されるような態度をとったらしいこと,また,次女ジュディスの結婚直後にその夫の性的不品行が明るみに出たため,すでに作成していた遺言書の書き直しをしていることなどがあり,世俗のことに全く悩まされなかったわけではない。この書き直された遺言書は1616年3月25日の日付をもち,すでに体力が衰えたことがうかがえる筆跡の署名のあるものであるが,当時の慣例どおりのさまざまな文言の中に,妻アンへの遺贈が「二番目によいベッド」とだけ記されている点は,さまざまな推測や議論の種となっているが,いまだに妥当な解釈が見つかっていない。
シェイクスピアは1616年4月23日に没した。ちょうど満52歳であった。友人の作家たちと酒を飲みすぎて熱病にかかったのが原因であるとする逸話が残っているが,これも伝説に属する話かもしれない。遺体はストラトフォードのホーリー・トリニティ教会に葬られた。直系の子孫は70年までにすべて死に絶えている。
〔演劇人として〕
上記の生涯の概略からもうかがえるように,シェイクスピアはある時期に詩を作ることもあったが,その主要な活動領域は演劇人としてのものであった。それは,(1)劇団運営者または劇場経営者,(2)俳優,(3)座付き作者の3つの役割を含む。彼の名が今日に残っているのは,(3)の役割においてであるが,それは他の2つの側面と密接に絡むものであった。
俳優としてのシェイクスピアについては知られていることは多くない。死後1623年に刊行された彼自身の戯曲全集に付せられた主要な出演俳優表の中で彼の名は筆頭におかれているし,また,やや後輩の劇作家ベン・
ジョンソンの戯曲『気質くらべ』と『シジェイナスの没落』の出演俳優表にも彼の名が出ている。一方,彼が,自作の劇では,『ハムレット』の亡霊の役や『お気に召すまま』の老僕アダムの役をやったという伝説があるが,それは彼が少なくとも立役者ではなかったことを物語るものかもしれない。俳優の仕事と同時に,彼には劇団運営者としての仕事があった。当時の劇団の上演方式は,今日の言葉でいえば,レパートリー・システムによるもので,数人の幹部俳優が助演の俳優や少年俳優(主として女性の役柄を演じた)を使って,日替わりでさまざまな演目の興行を行った。原則的には平日の午後,明るいうちの数時間に,グローブ座のような大劇場では照明や書き割りなどはあまり用いない舞台で演じた。幹部は常時多数のレパートリーをいつでも舞台に出せるように用意しておくことのほかに,客を呼べるような台本の獲得に絶えず心を配っておかねばならなかった(また,その結果が自分たちの歩合収入に直ちにはね返ってきた)。台本の補給については,外部の劇作家に注文するという方式もあった(当時宮内大臣一座とライバル関係にあった
海軍大臣一座という劇団はこの方法をとっていた)が,宮内大臣一座がとった方針は,シェイクスピアという幹部の一人を核となる演目の提供者にするという座付き作者制であった。このようにして,シェイクスピアは1590年ごろの数年は別として1594年ごろから1610年ごろまで,自己の属する劇団のために,年平均2本(厳密に言えば,初期において比較的多作であり,後期には少しゆっくりしたペースで書いているという多少の変化はある)の戯曲を生産し続けたのである。このような着実な創作ペースと活動期間の長さ,および単一の劇団への忠誠度をあわせもった劇作家は,この時代にほとんど他に例を見ない。破滅の道を歩むことの多かった同時代の劇場人の中で,彼のような成功した市民の生涯を送った例は比較的珍しいといえよう。
〔劇作活動〕
彼の戯曲で現存するものは38本ある。これらの中には他の劇作家との合作とみられるものも数本ある。制作年代が確実にわかっているものは少ないが,過去の研究によって大体のところは学者のコンセンサスが得られている。一般に最も権威があるとされるE. K.
チェインバーズの年代推定を基本としたものを以下に掲げておこう(なお,ここには主要な詩作品も含めておく)。
1590~91 『ヘンリー6世・第二部』2 Henry VI,『ヘンリー6世・第三部』3 Henry VI
1591~92 『ヘンリー6世・第一部』1 Henry VI
1592~93 『リチャード3世』Richard III,『間違いの喜劇』The Comedy of Errors,『ヴィーナスとアドーニス』Venus and Adonis(詩)
1593~94 『タイタス・アンドロニカス』Titus Andronicus,『じゃじゃ馬ならし』The Taming of the Shrew,『ルークリースの凌辱
(りようじよく)』The Rape of Lucrece(詩)
1594~95 『ヴェローナの二紳士』The Two Gentlemen of Verona,『恋の骨折り損』Love's Labour's Lost,『ロミオとジュリエット』(解説後出)
1595~96 『リチャード2世』Richard II,『夏の夜の夢』(解説後出)
1596~97 『ジョン王』King John,『ヴェニスの商人』(解説後出)
1597~98 『ヘンリー4世・第一部』1 Henry IV,『ヘンリー4世・第二部』2 Henry IV
1598~99 『空騒ぎ』Much Ado About Nothing,『ヘンリー5世』Henry V
1599~1600 『ジュリアス・シーザー』Julius Caesar,『お気に召すまま』(解説後出),『十二夜』(解説後出)
1600~01 『ハムレット』(解説後出),『ウィンザーの陽気な女房』The Merry Wives of Windsor
1601~02 『トロイラスとクレシダ』Troilus and Cressida,『不死鳥と雉鳩
(きじばと)』The Phoenix and the Turtle(詩,出版)
1602~03 『終わりよければすべてよし』All's Well That Ends Well
1604~05 『尺には尺を』Measure for Measure,『オセロー』(解説後出)
1605~06 『リア王』(解説後出),『マクベス』(解説後出)
1606~07 『アントニーとクレオパトラ』(解説後出)
1607~08 『コリオレイナス』Coriolanus,『アテネのタイモン』Timon of Athens
1608~09 『ペリクリーズ』Pericles
1609~10 『シンベリン』Cymbeline,『ソネット集』Sonnets(詩集,出版),『恋人の嘆き』A Lover's Complaint(詩,出版)
1610~11 『冬の夜ばなし』The Winter's Tale
1611~12 『あらし』(解説後出)
1612~13 『ヘンリー8世』Henry VIII,『二人の血縁の貴公子』The Two Noble Kinsmen
以上から明らかなように,シェイクスピアは最初期から
悲劇,
歴史劇,
喜劇といったさまざまなジャンルの戯曲を満遍なく書いているが,大まかな傾向としては,1600年以前の前半期には,歴史劇と喜劇が,また,1600年以降の数年間には悲劇が比較的多く書かれ,最後の数年は喜劇の一種である通常
ロマンス劇と呼ばれる形式によっているといえよう。このような印象をもう少し厳密に整理して,(1)初期の習作時代,(2)1590年代後半の主として喜劇と歴史劇を書いた時代,(3)1600~08年の悲劇の時代,(4)そののち引退するまでの晩年の劇の時代と4つに区分することが一般に行われている。
(1)の習作時代の劇はのちの戯曲に比べると,ときに未熟さや生硬な台詞
(せりふ)表現が見られる部分もあるが,すでに天才の片鱗
(へんりん)は随所にうかがわれる。例えば,『間違いの喜劇』の技術的完成度,『リチャード3世』における主人公の魅力的な造型などである。また,『タイタス・アンドロニカス』や『ヘンリー6世』3部作などは,長い間,稚拙な作品として無視された時期があったが,初演時には時代の嗜好
(しこう)に合致し,非常な人気を博した劇であったし,近年の上演(前者については1955年のピーター・
ブルック演出,ローレンス・
オリヴィエ主演のもの,後者については,テクストに多少手を加えてはいるが,1963年のピーター・
ホール演出『薔薇
(ばら)戦争』が代表的)が,これらの劇に戯曲として読むだけでは察知しにくい迫力があることを示した。
(2)第2の時期にシェイクスピアの才能は開花する。悲劇『ロミオとジュリエット』は青春の魂の稲妻のように激しい瞬時の燃焼を思わせる劇で,抒情的な美しい場面のまわりに,野卑ではあるがエネルギーにあふれる脇役
(わきやく)を配して,青春前期の男女の一途
(いちず)で危うい美をみごとに定着させている。これと一対をなす喜劇『夏の夜の夢』も,抒情性に富み,また祝祭的な気分に満ちた傑作である。同じころに書かれた歴史劇『リチャード2世』についても,この優雅でわがままな王が王位を追われ,殺害されるにいたる過程を情緒纏綿
(てんめん)たる嘆きの歌でつづる抒情悲劇の側面をもつといえるであろう。
この『リチャード2世』は,『ヘンリー4世』2部作,『ヘンリー5世』と続いてイギリス歴史劇の第2・4部作をなすものである。先にふれた初期の第1・4部作(『ヘンリー6世』3部作と『リチャード3世』)と合わせて,これがシェイクスピアが書いた歴史劇の中核となる(ほかに『ジョン王』と『ヘンリー8世』がある)。2つの4部作が扱うのは,テューダー朝がヘンリー7世によって確立される以前の戦乱の一世紀で,フランスとの百年戦争の後半から,ヨーク家とランカスター家の血で血を洗う薔薇戦争を含む。エリザベス女王の時代には,イギリスは相対的に安定し,国威を高めつつあったが,これらの劇は自国の歴史を顧みようとする関心が強まったなかで,それを演劇の形で提出したものであるということができよう。そこでは政治的権力の性質,それをめぐって葛藤
(かつとう)を繰り返す王侯貴族の野心と挫折
(ざせつ),上昇と没落の悲劇,彼らと異なる価値観をもちながらも上層部の動きに引き回されて右往左往せざるを得ない民衆の姿などが,広い視野で劇化されている。権力闘争に直接従事するボリングブルック,反乱者のホットスパー,王子ハル,リチャード3世などの多彩な中心人物たち,また,それに劣らず,あるいはそれ以上に人間的魅力をそなえた脇筋の人物群——滑稽
(こつけい)な天一坊
(てんいちぼう)を思わせるジャック・ケイドや,とりわけ酒と女を好む肥満した老貴族フォールスタフなど——が登場して,パノラマ的な絵巻を繰りひろげる。歴史劇の主人公は結局イギリスそのものだと評する人もいる。
この時期は,同時に,シェイクスピアが喜劇の分野で充実を示した時期でもあった。先に述べた『夏の夜の夢』を皮切りに,『ヴェニスの商人』『空騒ぎ』『お気に召すまま』『十二夜』などの代表作を出している。これらは〈ロマンティックな喜劇〉と呼ばれることもあるように,ほとんどの場合,当時の社会的現実から隔たった物語の環境——地中海世界,とりわけイタリアが多いが,もちろん,現実のそれらの場所ではない——に設定される。そのうえで,そこに美しく才気煥発
(かんぱつ)な若い女性(ポーシャ,ベアトリス,ロザリンド,ヴァイオラなど)が登場して中心的な活躍をする。彼女たちが多く男装をして,国元を離れ,森の中などの非日常的な場所へ出かけ,さまざまな取り違えの混乱を含む事件を経験したのち,障害が解消して,恋する男性と結ばれるという筋立てのものが多い。若い世代が古い世代を説得,慰撫
(いぶ)して,自らが結婚の祝宴というゴールに到達する劇だと図式化することもできよう。悲劇が時間に支配されて死へ向かう人間の相を呈示するとすれば,喜劇は時間からの一時的超越,あるいはその願望の相を示しているともいえよう。脇には,祝祭の気分に影を落とすようにたたずむ人物(シャイロック,ドン・ジョン,ジェイクィーズ,マルヴォーリオなど),また,華やいだ雰囲気を増幅するようなおかしみを発散する人物(ボトム,ドグベリー,
道化たちなど)が配されている。全体として,若々しい抒情性,あふれるばかりの活力,豊かな言葉,のびやかな空想,演劇と現実との関係の深々とした捉え方,一抹の哀愁など,のちの悲劇も凌駕
(りようが)できない独特の魅力をもっている。
(3)しかしシェイクスピアは1600年ごろから悲劇への傾斜を示しはじめる。悲劇のジャンルに属する戯曲が多く書かれるようになったというだけではなく,この時期の喜劇においては,登場人物が直面する問題の性質やその取り扱いに深刻味が増し,その結果,劇は形式的には喜劇的な結末を迎えても,第2期の喜劇のような充実した満足感を必ずしも観客に与えず,ある種の後味のわるさを残す。『尺には尺を』や『終わりよければすべてよし』などがそうである。そのため,これらの劇は〈暗い喜劇〉とか
問題劇などと呼ばれることもある。このようなことになったのは,作者がこの時期に人間を一面では悪への誘いに屈服しやすいもろさをもつものとして,その相から劇の世界を形作っていこうとする姿勢を強めているからだと感じられる。なぜそうなったかについては,時代の社会的状況や作者個人の環境などからさまざまな説明が試みられてきたが,いずれも満足のいくものではない。あるいは同じ喜劇の枠内でも晩年の劇に通じる方向が模索されているということも考えられる。
ともかく,この時期に彼が通常の人物よりも身の丈の大きな英雄を主人公とする悲劇を,集中して書きはじめたという事実がある。それは,『ハムレット』『オセロー』『リア王』『マクベス』のいわゆる四大悲劇を中心とし,その前後に
プルタルコスの『対比列伝』から材料をとったローマの貴族たちの悲劇——『ジュリアス・シーザー』『アントニーとクレオパトラ』『コリオレイナス』など——をもつ作品群である。これらの悲劇はそれぞれが独特であって,一般的な特徴を取り出すことは困難であるが,イギリス歴史劇のように当時の現実社会から比較的近い過去に起こった出来事を材料とした劇と比べると,ローマ悲劇は同時代のイギリス人によく知られていたという意味で中間的な距離を隔てた歴史上の事件を劇化したものであるのに対し,四大悲劇は『オセロー』を除けば,歴史といっても伝説の中に神話のように茫漠
(ぼうばく)と沈む世界の人間行動の軌跡であり,『オセロー』に至っては,もともと物語の世界に属する材料であったというような区別はできよう。別の言い方をすれば,ローマ悲劇の人物たちは,具体性がより稠密
(ちゆうみつ)な環境の中で行動するため,劇が政治的・社会的色彩を強く帯びているのに対し,四大悲劇では人物がより抽象的な空間の中で,より儀式的,より原型的な動きを見せる。『ジュリアス・シーザー』では,シーザー(
カエサル)を暗殺すべきか否かで公的義務と私的感情のあいだを揺れたあげく,行動に踏みきるブルータスの姿が,個人と政治の両面から,いわば政治倫理の問題として劇化される。他方,『マクベス』においては,魔女のそそのかしによる王殺害の思いつきから実行にいたる過程,実行後その行為が当の人間にどのような恐ろしい結果を引き起こすかが,個人の心の問題として造型され,スコットランドの具体的政治状況は視野には入っているが,劇的関心の中心部にはなっていない。
大まかに例示すれば,このような相対的差異を含んではいるが,これら悲劇においては,主人公たちは何かのきっかけから人並みはずれた激しい情念の狂熱に陥り,孤独な苦闘の果てに滅びていく。周囲の世界は,主人公の死後に生き残るが,その平和な世界は色褪
(あ)せたものに感じられる。(4)晩年の数年間に,作者は,ロマンスの筋立てをもつ
悲喜劇に観客の好みが移ったことを一面では反映して,そのような傾向の劇を書いている。『ペリクリーズ』以下,『シンベリン』『冬の夜ばなし』『あらし』がそれで,フレッチャーとの合作による『二人の血縁の貴公子』もそこに加えてよい。このジャンルの劇の構造は,前半部で悲劇的事件が起こり,そのために主人公の家庭は離散するが,放浪の果てに再会と和解がなり,めでたい結末を迎えるというパターンをとることが多い。例えば,『冬の夜ばなし』では,前半でシチリアの王が自分の妃
(きさき)ハーマイオニと友人のボヘミア王が不倫の関係にあるのではないかと妄想し,生まれたばかりの女児を捨てさせ,妃を死に至らしめるが,直後に自分の非を悟る。後半は前半から16年の歳月が経過したことになっていて,そのあいだ贖罪
(しよくざい)の生活を続けてきた王が,ボヘミアで羊飼いに拾われて美しく成長した娘と,実は生きていた妃に再会し,友人のボヘミア王とも和解し,娘は彼の息子と結ばれるという締めくくりとなる。『あらし』の場合は,シェイクスピアには珍しく
三一致の法則に合致した劇であるが,上のような一般的構造の後半部にあたる地中海の孤島での事件に劇を凝縮し,前半部は回想で処理したのだとみることができよう。これらの劇では,この時期に宮廷でさかんに行われた仮面舞踏劇の趣向が取り入れられたり,魔術(プロスペローなど)や,死んだと思われていた人物のよみがえり(ハーマイオニや『シンベリン』のイモジェンまたはイノジェンなど)のようなロマンスの素材が取り入れられて,演劇的な効果を狙
(ねら)っている。1590年代の喜劇との違いとしては,前半の悲劇性がより深刻なものであること,それに対応して後半の解決に宗教的法悦に近いしみじみとした味があること,特に父親の立場に力点がおかれ,親子関係の回復のテーマ(プロスペローとミランダ,ペリクリーズとマリーナなど)が大きな比重をもつことなどが挙げられよう。やがて引退しようとする大劇作家の晩年を特に感傷的に見るべきではなかろうが,これらロマンス劇には諦観
(ていかん)と寂寥
(せきりよう)が微妙に忍びこんでいる。
〔シェイクスピア劇の一般的特徴〕
以上劇作の軌跡を略述したが,彼の劇全体に共通していえることをまとめてみる。
(1)台詞はブランク・ヴァース(1行が弱強5詩脚10音節からなる
無韻詩)と呼ばれる詩型で書かれている。これが量的に全体の約7割を占める。これは比較的制約の少ない自由な詩型である。韻文の台詞としては,ほかにもっと制約の多い詩型が用いられている場合もあるが,それは初期の劇か,劇中に挿入された歌や劇中劇の部分,あるいは場を締めくくる際の対句表現などで,そこでは当然様式性が強くなる。残りが散文の台詞で,これは,主として低い社会階層の人物の口にする言葉として,あるいは喜劇的な部分(
笑劇的な部分のみでなく,上層階級の人物の機知に富む応酬とか,ハムレットのように狂気に陥っていることを示すような場合)にも用いられる。また,劇中で読み上げられる手紙や布告文なども散文であることが多い。いずれにしても,シェイクスピア劇は台詞が大きな比重を占める演劇であり,異なったリズムの台詞を駆使して様式性の度合いにさまざまな変化をつけている。翻訳ではわかりにくいが,この点はシェイクスピア劇が,もっぱら散文の対話からなる近代の写実的演劇と異なる点で,日常的現実に近い場面から寓意
(ぐうい)的・象徴的な部分にいたるまで,幅広い音域で織りなされた構築物であることを台詞の面からも示す特徴である。
(2)イギリス演劇の伝統に立つ特徴として,劇ジャンル間の流動性,弾力性が挙げられよう。筋立てが多くの場合,複数である。
古典主義理論における時,場所,アクションの単一性を求める,いわゆる三一致の法則は無視されるのが普通である。喜劇においても悲劇においても,まじめで深刻な部分と笑いを誘う陽気で滑稽な部分が共存することが多い。したがって劇ジャンルの区別は相対的にすぎないといえる面をもつ。筋の複数性は当然感情やヴィジョンの複数性を内包している。古典劇におけるような感情のレベルの統一というよりは,むしろさまざまな緊張度の場面の交錯にその特徴があり,それが多面的な印象を作りだす。ここからシェイクスピア劇が人間ないし世界を幅広くその複数性において捉えているという感じが出てくる。
〔詩作について〕
量的にはさほど多くない詩作品のうち,2編の
物語詩,『ヴィーナスとアドーニス』および『ルークリースの凌辱
(りようじよく)』は,当時流行した短い叙事詩の伝統を受け,神話とローマ史に材料を得て,性愛と潔癖,情欲と貞淑の葛藤をつづったものである。これらは当時の若い知識人層に人気を博したが,彼の残した最大の詩業はなんといっても154編からなる『ソネット集』である。1609年に刊行されているが,それより先1590年代に大半が書かれたのではないかと考える学者が多い。この点を含めて,この作品は多くの謎
(なぞ)に包まれていて,さまざまな研究批評を誘発してきた。最初の126編は詩人と美しい青年との愛を,127~152番は色の
黒い女(ダーク・レディー)との愛欲を歌っているが,これが実生活の反映を含んでいるのか,それとも恋愛詩の伝統に立つ虚構であるのかという根本的な見方の対立を中心にして,前者だとすれば,それが何を反映しているのか,献呈の辞に出てくる〈
ダブリュー・エイチ氏〉Mr. W. H.とはだれなのか(そもそも献呈の辞の文法構造はどうなっているのかという点にまで議論がある),美しい青年と詩人との〈愛〉はどのような性質のものなのか,後者の立場をとるとしても,各
ソネットの配列順序をそのまま受け入れるかどうかなど多数の論点がある。これらの問題は実証的な根拠が存在しない以上,完全な解決をみることは難しいのであろう。ただ,このことは,『ソネット集』が詩作品としてこのような論議を引き起こす力をもっていることを間接に示しているのである。ここには迷い,疑惑,情欲の泥沼に浸りながら,なおかつ永続する愛を願う生身の人間の心の様態が多様で複雑な表現によって語られている。
〔近年の上演および批評研究〕
シェイクスピア劇の上演や批評はイギリス本国では約400年の,他の欧米諸国では約200年,日本でも100年に及ぶ歴史をもつ。それらの全体については項目を挙げるだけでも膨大なスペースを要するので,ここでは20世紀に入ってからの,それもごく大まかな,略述にとどめざるを得ない。
(1)上演——イギリスにおけるシェイクスピア劇の上演は20世紀に入ってから,それまでになかった2つの特徴を示している。1つは,18,19世紀においては,立役者が同時に劇団の主宰者あるいは劇場経営者として公演を主導するのが普通であった(デイヴィッド・
ギャリック,ヘンリー・
アーヴィングなど)のに対して,20世紀になってからは演出家の理念に俳優が名優といえども従って上演するという傾向になったということである。また,他の1つは,エリザベス朝時代の劇場や劇団のあり方に関する研究が進んで,当時の上演の姿についての見当がある程度ついてくるにつれ,それと同じではないが等価なものを作り出して,シェイクスピア劇の真価を舞台に表現しようとする試みが行われるようになったことである。この2つの特徴を20世紀初頭において代表したのは,
グランヴィル=バーカーで,比較的簡素な装置を用い,衣装の時代的制約を排除し,場面転換を早めることによって劇に連続性をもたせ,俳優にはあまり削除しない台詞をスピーディーにしゃべらせるという20世紀の上演法の基礎を定めた。このうち,時代設定の自由化は1920年代のバリー・
ジャクソンの現代版上演に,また速い台詞まわしは1930年代のハーコート・ウィリアムズの
オールド・ヴィック劇場における上演などに引き継がれていく。もっとも,演出家が登場したといっても,もちろんスターがいなくなったわけではなく,20世紀を代表するシェイクスピア役者としてジョン・
ギールグッドとローレンス・オリヴィエが名声を確立したのも1930年代である。また,第二次大戦前後に活躍したドナルド・ウルフィットのように立役者兼座長というタイプは残っていた。しかし全体としては演出家が自己の方針の下に舞台を構成していくことが常態となってきた。第二次大戦後の演出家としては,グレン・
バイアム・ショー,マイケル・ベントール,ピーター・ブルック,ピーター・ホール,ジョン・
バートン,トレヴァー・
ナンなどがいる。ベントールを除くと,彼らは少なくとも一定期間は
ロイヤル・シェイクスピア劇団のために演出をしたが,それぞれ上演史に記憶される名舞台を作った(1つだけ挙げるとすれば,1970年初演のピーター・ブルック演出『夏の夜の夢』であろうか)。それらはそれぞれの時期に日本の演劇人に刺激を与え,単にシェイクスピア劇に目を開かせただけでなく,演劇のあり方についても強い影響を与えたといってよかろう。
日本では1885(明治18)年以来,翻案による上演や特定の場面だけの上演の時期を経て,20世紀に入ると,翻訳によるある程度本格的な上演が徐々に行われるようになった。第二次大戦前までの期間に,坪内逍遥
(しようよう)の全訳が果たした役割は大きかった。戦後1946年に帝国劇場で行われた土方与志
(ひじかたよし)演出による『夏の夜の夢』が暗い戦争の後にもたらした喜びはさぞやと思われるが,画期的だったのは1955年の福田恆存
(つねあり)訳・演出による文学座の『ハムレット』で,これは当時のイギリス本国での上演を取り入れた斬新
(ざんしん)なものであった。その後約15年,福田訳のシェイクスピア劇が日本における代表的な公演であった。1970年代に入ると,ロイヤル・シェイクスピア劇団が数回にわたって来日して優れた公演を行い,日本の演劇界に波紋を投じたが,それとほぼ時期を同じくして,小田島雄志
(おだしまゆうし)が全訳の仕事にとりかかり,1980年に完成した。これにより,1970年代後半から80年代にかけて,福田訳や主として俳優座の用いる三神勲
(いさお)訳とともに,新しい世代の日本語感覚をもつ小田島訳が多くの上演に用いられるようになる。この時期の多彩な公演の中で,記録的には,劇団シェイクスピア・シアター(出口典雄
(のりお)演出)の全戯曲上演(1975.5−81.6)は特筆すべき壮挙であった。
(2)批評研究——近年のシェイクスピア劇についての批評研究は,1960年代以降新たな展開を示している。20世紀の初めには,A. C.
ブラッドリーの『シェイクスピアの悲劇』に代表されるような登場人物の性格に関心の重点をおく傾向が支配的であったあとを受けて,1930年代からの約30年間は,劇というものを詩的言語によって構築され,自己完結した一つの大きな暗喩
(あんゆ)として捉え,その主題や
イメジャリーを分析するという,
新批評の考え方と共通する流れが強かった。そこからさらに,劇の構造を重視して,登場人物をその構造の関係性に規定されるものとして捉える考え方(
神話批評とも呼ばれ,やがては
構造主義にも通じていく)が出てくるが,それはあくまで非歴史的な立場に立つもので,その点新批評の立場と共通していた。
1960年代に入ると,戯曲は上演用台本なのであるから,シェイクスピア劇は劇場経験として捉えるべきであるという,ある意味で当たり前な考え方が戻ってきた。そのうえで,劇場経験を基礎におきながらも,歴史的な立場と非歴史的な立場は相変わらず対立し続けることとなった。歴史的な立場は,初め,エリザベス朝で実際に戯曲がおかれた位置,上演の諸条件,観客層の分析といった研究の洗い直しという形をとった。それは,やがて,劇のテクストを時代の社会的・政治的・文化的コンテクストと切り離せないものとして,コンテクストを劇の背景ではなく,劇に内在して意味を形成するものとして考える
ニュー・ヒストリシズムの主張となっていく。これは
マルクス主義の立場から劇を分析する文化唯物論の立場にもつながっている。他方,非歴史的な立場は劇の経験を観客の意識に現象するものとして捉える受容理論(
読者反応論)の立場,あるいは劇場で生じることを記号論的に把握しようとする立場,またシェイクスピア劇に
ディコンストラクションの手法や
フロイト以後の
精神分析の手法を適用して新しい見方を切り開こうとする立場などがある。そして,両者にまたがるものとして,フェミニズムの観点からシェイクスピア劇の読み直しを行おうとする批評(
フェミニズム批評)もさかんである。
文献学的研究もこのような潮流と無縁ではない。20世紀前半に飛躍的に発展した書誌学や本文批評の成果をふまえて,戯曲を単に文字で表現された文学としてではなく,演劇の台本としていっそうダイナミックに捉えようとする立場が顕著になってきている。その一つの結果が1986年に刊行されたオクスフォード版一冊本全集で,そこでは定本の概念に対して基本的な洗い直しが行われた結果,例えば『リア王』については2種類の本文が収録されるというようなことが生じている。