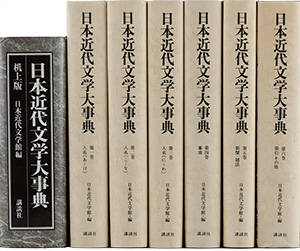小説家。江戸の芝中門前町に生れた。本名は徳太郎。縁山、半可通人などの別号があり、俳句には十千万堂(十千万)などの別号を用いた。慶応三年一二月一六日は太陽暦では一八六八年一月一〇日に当たる。なお、一説では慶応三年一二月二七日の出生とする。父は惣蔵、母は庸。尾崎家は代々伊勢屋という屋号の商家であったが、惣蔵は廃業して、角彫りの名人谷斎として有名で、根付け彫りなどにすぐれた作品を遺している。しかし、いわゆる名人気質で、多作家ではなかったから、生活は余裕がなく、そのため幇間として料亭や角力場などに出入りした。いつも緋縮緬の羽織を着た坊主頭の谷斎は人目を引き、「赤羽織の谷斎」といわれて大衆の人気者でもあった。母の庸は、当時芝神明町に住んでいた漢方医荒木舜庵、せんの長女で、かぞえ年一九歳のとき紅葉を生んでいるが、荒木家はそのころ家計が苦しく、舜庵は茶碗の上絵を描いたり、寒暖計の目盛りを入れたりするような内職をしていたといわれるので、娘の庸は、あるいは柳田泉が推測しているように「神明社の茶汲み女」かなにかのような勤めに出、そこで谷斎と結ばれることになったのかもしれない(『ある幻想的ロマンス―尾崎紅葉の素性―』)。しかし不幸にも、庸はそののち明治三年にはるを生んだが、五年五月一九日かぞえ年二四歳で没した。紅葉は満五歳であった。つづいて八月には妹のはるも夭折した。紅葉は荒木家に引取られ、祖父母の手によって育てられることとなった。谷斎は二年後の七年、平井とくと結婚し、紅葉とは別居したままで二七年二月に没するが、紅葉がこの父のことをひたかくしにしていたことは硯友社同人らの記述によって知られる。しかし、その芸術家としての血統が伝わっていることは否定すべくもない。なお、継母とくは三一年一〇月に没している。
紅葉はまず明治六年七月、久我富三郎の寺子屋梅泉堂に入り、この梅泉堂はのち私立梅泉小学校と改称されたが、この学校で小学校の教育をうけ、ついで一四年東京府第二中学(現・都立日比谷高校)に入学したが、在学二年で中退し、三田英学校の大学予備門受験科に入って英語を修め、一六年九月、首尾よく神田一ツ橋の東大予備門に入学した。この間、中学中退前後から岡千仭の漢学塾綏猷堂、石川鴻斎の崇文館に入って漢学、漢詩文を学んだ。明治一五年五月、「頴才新誌」に発表された漢詩『柳眼』は当時の文学活動を物語っている。予備門入学後、友人らと文友会、凸々会などに参加する一方、人情本などをも耽読し、一七年八月には『春色連理梅』を筆写したりした。この年九月、芝神明町での竹馬の友、山田武太郎すなわち美妙斎が予備門に入学、友情が復活した。かくして翌一八年二月、美妙、石橋思案、丸岡九華らと硯友社を結成、文壇でのはなばなしい活動の第一歩を踏出したのである。同年五月、機関誌「我楽多文庫」を筆写回覧本の形式で創刊。同誌はその後印刷され、また公刊されるようになり、紅葉ら同人の文壇進出を果たして、二二年一〇月、改題された「文庫」の二七号をもって終刊した。紅葉はこの雑誌にはじめ半可通人などの別号で戯作風の小説、雑文、批評、新体詩、落語、狂歌などを書いていたが、坪内逍遙の『当世書生気質』『小説神髄』(明18~19)などの影響をうけ、ヨーロッパ文学に範をとって近代小説確立への方向を目ざすようになった。明治一九年、大学予備門から改称された第一高等中学の英語政治科へ、さらに進んで二一年帝大法科大学政治科に入学していながら、翌年には文科大学和文科に転じ、二三年には学年試験に落第したのを契機に、そのまま中退して創作活動に専念することとなった。紅葉の経歴は、他面から彼のこうした文学への決意を、そのまま解明かしてもいる、といえよう。
その作家活動をたどると、明治二二年四月、『新著百種』第一号に書下ろし刊行された出世作『二人比丘尼色懺悔』の出現までの文壇登場以前、すなわち「我楽多文庫」時代を習作期と見ることができよう。この時期は、『江島土産滑稽貝屛風』(明18・5~19・5)『偽(偐)紫怒気鉢巻』(明19・5~20・1)などのような戯作風の小説、『書生歌』(明18・6)の新体詩から出発したが、文明開化のいわゆる鹿鳴館時代風俗をとらえた「写実」的な『娘博士』(明20・10)『風流京人形』(明21・5~22・3)『YES AND NO』(明22・1)などの小説へと進み、その清新さが読者の注目をよんだ。前記のように逍遙から示唆せられたところが大きい。が、もともと洒落を愛し、ユーモアを好んだ江戸っ子の彼は、一九、三馬、京伝など、江戸後期の文学に多くを学びつつ、しだいにイギリス近代文学のユーモアにも心ひかれていったので、そういう明るいユーモラスな色調が、この時期の文学をおおっている。その意味では、硯友社同人たちをいきいきと描いた『紅子戯語』(明21・10~12)をもって、この時期を代表させることもできる。未刊のまま稿本として遺されていた明治二一年作の『夢中夢』(「改造」昭3・4)も「諷刺戯作」という角書が示すように、この傾向を追ったものといえる。一方、彼は淡島寒月を介して西鶴を知り、二一年ごろから『好色一代男』などを愛読するようになった。それは次期のいわゆる西鶴調文体を成熟させる萠芽となり、たまたまこの二一年都の花主筆となって袂をわかった山田美妙の言文一致体にたいし、彼なりの文体樹立への意欲を思わせたのである。
明治二二年四月の『二人比丘尼色懺悔』は「涙を主眼とする」中世的な悲哀の情趣をたたえた優艶な小説として歓迎され、紅葉をはなばなしく文壇に登場させた。それは鹿鳴館時代が過去った反動としての復古的思潮に投じたともいえるが、いまひとつ紅葉年来の苦心になる「一風異様の文体」が魅力として人びとの心をとらえたためである。文章家紅葉が、こののちさらに文章の練磨、新文体の創造へと、全力を傾注するようになるのはもはや必至であった。すなわち、二五年ごろまでの紅葉は、主として西鶴を学んだ雅俗折衷体の文章をみがきあげて、『伽羅枕』(「読売新聞」明23)『三人妻』(「読売新聞」明25)のような、前期における代表作を生むこととなる。紅葉は、この時期、もっとも創作力が活潑で、明治二二年一二月、東大在学中に読売新聞社に入社し、同紙につぎつぎと長短編を発表しながら、他方で「我楽多文庫」につづく硯友社の機関誌ともいうべき「小文学」「江戸紫」「千紫万紅」などにも諸短編を書き、また『此ぬし』(明23・9刊『新作十二番』)『新桃花扇・巴波川』(明23・12刊『新著百種』)などの書下ろし刊行や、求められて「都の花」に中編『二人女房』(明24・8~25・12)を連載するなど、めざましい活躍を見せた。彼は二四年三月、牛込横寺町の新居で樺島喜久と結婚したが、かぞえ年二五歳であったにもかかわらず、すでに文壇の大家と仰がれ、泉鏡花、田山花袋、小栗風葉、山岸荷葉ら、入門を志す子弟があいついで横寺町の宅をたずねた。紅葉はそのような自身の立場を考え、たえずその創作に新機軸を出そうとした。文体の上で西鶴を学んだのもそのひとつだが、さらにその構想やストーリイの展開の技法にも西鶴を摂取して『伽羅物語』(「読売新聞」明24・1・1「筆はじめ」所載)や『子細あつて業物も木刀の事』(「千紫万紅」明24・6、8)などを書き、また田山花袋が『東京の三十年』で回想しているように、ゾラをはじめとする近代ヨーロッパ文学をしきりに愛読して心理的写実主義を体得しようとしていた。妻をよく理解していながら、どうしても愛することのできない夫の心理を追求した『焼継茶碗』(「読売新聞」明24・5・15~6・25。のち『袖時雨』と改題)などはその一成果であり、ゾラを題材として翻案した『むき玉子』(「読売新聞」明24・1・11~3・21)もこの時期の作である。このほか『二人椋助』(明24・3 博文館刊『少年文学』第二編所収)『鬼桃太郎』(明24・10 博文館刊『幼年文学』第一号所収)のような児童文学のこころみもあり、『二人女房』における文体の言文一致体への移行も注目される。
明治二六年からは、いわば後期に当たる。その前半、すなわち二七、二八年ごろまでは翻案や鏡花、花袋その他との合作なども多く、当時の批評家らに想が枯れたなどと酷評されたこともあるが、紅葉は新生面を開拓しようとして摸索していたのであり、『隣の女』(「読売新聞」明26・8・20~10・7)『紫』(「読売新聞」明27・1・1~2・16)『冷熱』(「読売新聞」明27・5・27~7・6)などに見られる言文一致体の修練とあわせて、その写実主義を完成するために日夜努力を惜しまなかった。未完成に終わったが、野心的長編の『男ごゝろ』(「読売新聞」明26・3・1~4・13)のあと、盲人の無気味な愛執の念をとらえた『心の闇』(「読売新聞」明26・6・1~7・11)に写実の深まりを見せ、『不言不語』(「読売新聞」明28・1・1~3・12)ではその怪奇味をより強調するとともに当時愛読していた『源氏物語』にもとづく雅文体で芸術的完成度を高めようとした。やがて愛弟子風葉の発病入院という身辺生活に取材した『青葡萄』(「読売新聞」明28・9・16~11・1)の私小説的作品を経て、花袋らも激賞した写実主義の最高作『多情多恨』(「読売新聞」明29)に到達した。この長編は、また、いわゆる「である」調の口語文を彫琢しつくした言文一致体の小説として、その意義が高く評価されている。その後の多くの作家に与えた影響も大きい。
紅葉が晩年にその全精力を傾け、文字どおり心血を注いだ大作は『金色夜叉』である。「読売新聞」紙上に明治三〇年から三五年にかけて断続連載、あしかけ六年におよんだが、完成せず、健康もすぐれぬまま読売を退社し、さらに三六年からは雑誌「新小説」に連載することとして、まずその『新続金色夜叉』を再掲し、稿をつづけようと企図した。が、三月号の再掲部分までで中絶し、その続稿は成らなかった。成らなかった理由は、紅葉みずから『十千万堂日録』明治三四年一月二二日の条で、「一に胃患の為に妨げられ、二に客来の為に碍げられ、三に推敲の為に礙けらる」と述べ、「金色夜叉の三害と作すか」といっている。そのことばどおり、胃病は明治三二年ごろから彼の肉体をむしばみはじめ、ついにその生命を奪ったのであった。紅葉は三二年七月から八月にかけて新潟、佐渡に旅行したが、それは『煙霞療養』(「読売新聞」明32・9・1~11・13、原題『反古裂織』)の旅であり、その後も三四年五月には修善寺、三五年五、六月には成東などへおもむいて療養につとめたが、病状は好転せず、三六年三月大学病院に入院して、胃癌という診断をうけた。しばらく妻喜久の実家である芝新堀町の樺島方で養生したが、やがて牛込横寺町の自宅に帰り専心療養につとめた。が、病勢はさらに進み、「モルヒネの量増せ月の今宵也」などのいたましい作句をなしている。また、当時の心境は、没後の三七年三月刊、巌谷小波編『病骨録』(文禄堂)などによって知られる。かくてこの年一〇月三〇日、家族、知友、門弟らにみとられつつ没した。
明治三〇年以後の紅葉は、文壇の大家でかつ社会的名士でもあり、生活も多忙なうえに、弓術、写真その他、趣味人でもあったから、『金色夜叉』をのぞけば、ほかには『寒牡丹』(「読売新聞」明33・1・1~5・10)のような翻訳、翻案の作品が多い。が、随筆、紀行、また俳句にはとくに熱心で、かつての談林風から飛躍して情趣深い佳句を遺している。秋声会の一員でもあり、星野麦人ら門弟たちの「俳藪」を指導した。なお、小説の面で多数の門下を育成したのは有名で、世に「牛門」といわれ、泉鏡花、小栗風葉、徳田秋声、柳川春葉はその「四天王」と称された。人がらとしては、信義にあつく、義俠心に富み、親分はだでもあったから硯友社の総帥に推され、つねに文士の社会的地位の向上を心がけていたことも忘れられない。文章報国を念願していた一代の文章家で、文字どおりの明治の文豪でもあった。
博文館版『紅葉全集』全六巻(明37)、中央公論社版『尾崎紅葉全集』全一〇巻のうち三巻(昭16~17)がある。
代表作
代表作:既存全集



 云」*多情多恨〔1896〕〈
云」*多情多恨〔1896〕〈 (アア)もう何を為
(アア)もう何を為 」*金色夜叉〔1897~98〕〈
」*金色夜叉〔1897~98〕〈