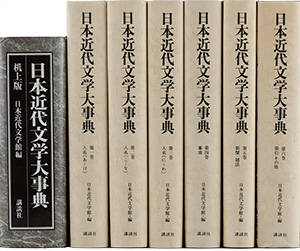小説家、劇作家。東京市四谷区永住町二番地に生れた。本名は平岡公威。父梓と母倭文重の長男。父は農林省官吏で、祖父の定太郎は樺太庁長官をつとめた。母は、前田藩儒者で東京開成中学校長をつとめたことのある橋健三の次女である。祖母の夏子(奈津)は、大審院判事永井岩之丞の長女。祖父母と両親とともに過ごした幼年期の家庭の雰囲気の一端は、『仮面の告白』(昭24)にも語られている。なお大正一四年生れということは、満年齢が昭和の年数と一致するという点で象徴的であり、また吉本隆明より一つ年下で井上光晴より一つ年上であることは、いわゆる「戦中派」思想の帰趨を考えるうえでも重要である。
昭和六年、学習院初等科に入学。一九年九月に高等科を卒業するまで、学習院で学ぶ。初等科のころから詩歌、俳句の試作があったが、小説の処女作といえるものは短編『酸模』(「輔仁会雑誌」昭13・3)である。一六年、国文学の師である清水文雄の推薦で、『花ざかりの森』を「文芸文化」(昭16・9~12)に発表、「三島由紀夫」の筆名をはじめて用いた。このころから清水文雄を通じて「文芸文化」の同人と交渉をもち、さらに日本浪曼派の間接的影響をうけた。こうした影響もあって、日本の中世文学に関心をもったが、他面、ラディゲの『ドルジェル伯の舞踏会』(堀口大学訳)やワイルドの『サロメ』などを愛読した。前者が日本の伝統につながるとすれば、後者は西欧的知性に通じる契機をもち、この二面性は三島文学の特性を大きく規定することになる。一九年一〇月、東大法学部に入学、中島飛行機小泉工場に勤労動員。同時に処女小説集『花ざかりの森』(昭19・10 七丈書院)を刊行。二〇年二月に召集をうけたが、軍医の誤診により即日帰郷となる。八月一五日、一家が移り住んでいた豪徳寺の親戚の家で、日本の敗戦を知る。
三島にとって敗戦がなにを意味していたかを厳密にたどることは容易ではない。しかし作品に即して見るかぎり、戦時下の作品が終末観をふまえて卑俗な現実のかなたに純粋な夢想を求めていたのにたいして、戦後は「凶々しい挫折の時代」(『林房雄論』)であり、敗戦を境とした神話の崩壊をふまえて、生死の根拠たるべき神話を虚構のうちに逆説的に求める姿勢が、戦後の作品にはうかがわれる。二一年六月、川端康成の推薦で『煙草』を「人間」に発表して文壇に登場したが、最初の連作長編『盗賊』(昭23・11 真光社)が失恋と情死を描いている点は、ニヒリズムと死の主題をうかがわせるに十分である。学生作家として早熟の才をもって登場しただけでなく、悪や死の香気をもった作品を好んで書いた当時の三島は、前向きの社会建設に同調できなかった特攻隊帰りの青年や、ニヒリズムを心にもっていた同時代の青年層に、潜在的な支持者を獲得しつつあった。
昭和二二年一一月、東大法学部を卒業、一二月高等文官試験に合格して大蔵省に就職したが、二三年九月に退職して作家生活に入る。二四年七月、『仮面の告白』(河出書房)を刊行、新進作家としての地位を確立した。この作品について花田清輝は『聖セバスチャンの顔』(「文芸」昭25・1)を書き、三島の堅固な知的仮面の新しさを称揚した。二五年六月、長編『愛の渇き』(新潮社)を刊行、つづいて、金融業光クラブの学生社長、山崎晃嗣をモデルにした『青の時代』(「新潮」昭25・7~12。昭25・12 新潮社)を書いた。三島のモデル小説は、金閣の放火犯人をモデルにした『金閣寺』などを含めて、一定の確信をもって反社会的行為におもむくいわゆる「確信犯罪」を扱ったものが多い。
『禁色』(「群像」昭26・1~10。昭26・11 新潮社)を書きながら、評論『新古典派』(「文学界」昭26・7)を発表した。『禁色』はのちにその第二部『秘楽』(「文学界」昭27・8~28・8)とあわせて完成されるが、『新古典派』が近代芸術の個性崇拝にたいして「様式」の重要性を説いている点は注目に値する。この確信は二七年におけるギリシア訪問において、古代ギリシア人が「内面」よりも「外面の均斉」を重んじたことへの共感を通じて、さらに補強されたといってよい。すなわち、芸術的には様式美の重視、生活的にはギリシア的健康への希求が生れたわけで、のちにボディー・ビルを行う伏線はこのへんにあると考えられる。この時期は三島の作品歴のうちでは古典主義の色彩の強い時期で、『真夏の死』(「新潮」昭27・10。昭28・2 創元社)など秀れた短編のほか、牧歌的な書下ろし長編『潮騒』(昭29・6 新潮社、第一回新潮社文学賞受賞)があり、この時期の頂点に位するのが『金閣寺』(「新潮」昭31・1~10)である。なお『金閣寺』については、「やっと私は、自分の気質を完全に利用して、それを思想に晶化させようとする試みに安心して立戻り、それは曲りなりにも成功し」たと、作者自身が書いている。なお戯曲の名作といわれる『鹿鳴館』(「文学界」昭32・3 東京創元社)の発表されたのは、『金閣寺』完成の年の一二月である。三三年六月、杉山寧の長女、瑤子と結婚し、季刊誌「声」の創刊に際して編集同人となり、九月同誌に『鏡子の家』の第一、二章のみを発表、三四年九月に二冊本として新潮社から同時刊行した。この作品は、戦後というニヒリスティックな時代そのものを、鏡子という女性の家に出入りする人々を通じて描いていて、戦後への挽歌という面をもった作品でもある。
昭和三五年、『宴のあと』(「中央公論」昭35・1~10。昭35・11 新潮社)を連載。翌三六年三月、モデルにあたる代議士有田八郎に「プライバシー侵害」の理由で告訴された。いわゆる「プライバシー裁判」として話題になったが、三年後に結果は敗訴となり、のちに有田と和解が成立。三六年一月『憂国』(「小説中央公論」昭36・1 新潮社刊の『スタア』収録)を発表し、これが一九六〇年代の歩みの端緒としての意味をもつ。この作品は、二・二六事件の精神史的意味に触発されつつも、他方、「エロティシズムのニーチェ」というべきジョルジュ=バタイユの影響もあり、政治的殉教がエロスの燃焼としての至福にいたるという情念の構図を描いている。ここにおいて、日本的テロリズムの精神を通じて『葉隠』にいたる通路が開かれ、他方、エロティシズムを媒介とした「死」の美学が表面化された。この傾向は、評論『林房雄論』(「新潮」昭38・2。昭38・8 新潮社)において昭和史における日本的心情の発掘となってあらわれ、のちに『英霊の声』(「文芸」昭41・6。昭41・6 河出書房新社)にあっては、天皇を死の根拠とした英霊という虚構をかりて、戦後の「人間天皇制」を批判する軸となって提出された。また『葉隠』に通じる「無私」の思想は、戯曲『朱雀家の滅亡』(「文芸」昭42・10。昭42・10 河出書房新社)のうちにもうかがわれる。ほかに、こういう傾向とは異なる作品として『絹と明察』(「群像」昭39・1~10。昭39・10 講談社、毎日芸術賞受賞)や戯曲『サド侯爵夫人』(「文芸」昭40・11。昭40・11 河出書房新社)があったが、三島文学を解く最も重要なカギを提出しているものの一つは『太陽と鉄』(「批評」昭40・11~43・6。昭43・10 講談社)である。ここには、「不朽の花」を作る「文」と「花と散る」ことをめざす「武」との統合をめざす「文武両道」が、たんなる主義としてではなく、精神の深部から問われている。
『豊饒の海』の第一部『春の雪』は、昭和四〇年九月から「新潮」に連載されていたが、作家生活とは次元の異なる実践としては、四二年四月に久留米陸上自衛隊士官候補生学校、富士学校、習志野空挺隊に体験入隊した。この種の体験入隊は、四三年二月と七月にも行われた。体験入隊に同行した学生を中心に四三年九月楯の会を結成した。なお、天皇制と軍隊のあり方についての理論は『文化防衛論』(「中央公論」昭43・7。昭44・4 新潮社)に述べられている。この時期の作品としては、『豊饒の海』が『春の雪』の完結(「新潮」昭42・1)後に第二部『奔馬』(「新潮」昭42・2~43・8)、第三部『暁の寺』(「新潮」昭43・9~45・4)、第四部『天人五衰』(「新潮」昭45・7~46・1)と書きつがれていたし、戯曲では『わが友ヒットラー』(「文学界」昭43・12)『癩王のテラス』(「海」昭44・7。昭44・6 中央公論)がある。
昭和四五年五月一二日、東大全共闘と討論、一一月一一日から東京池袋の東武百貨店で「三島由紀夫展」を開催、同二五日午前、『豊饒の海』最終回の原稿を新潮社に渡したのち、楯の会の学生森田必勝ほか三名とともに自衛隊市ケ谷駐屯地にいたり、自衛隊の決起をうながしたが果たさず、東部方面総監室で割腹自決をとげた。
なおこの自決事件については諸種の見解があり、(1)憂国の至情による諫死と見るもの、(2)右翼的事件として弾劾すべきとするもの、(3)美学が文学的虚構をこえて生活までも支配したと見るもの、など枚挙のいとまがない。だが、自己を反時代的な仮面とさえ自覚していた三島は、自分の行為が外側の社会から見て愚行と見えることを知りぬいていたはずである。とすれば、このきわめて逆説的な自己完結の行為のうちに、精神の自律性の証明と、風化した戦後社会への批判の契機を読みとることは可能であると思われる。そのほか、『橋づくし』(昭33・2 文藝春秋新社)『近代能楽集』(昭31・4 新潮社)『私の遍歴時代』(昭39・4 講談社)などの作品がある。
テクストには諸版があるが、新潮社『三島由紀夫全集』全三五巻補巻一(昭48・4~51・6)が信頼できる全集になる。
代表作
代表作:既存全集