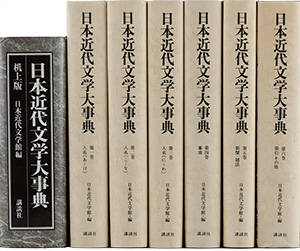ロシアの小説家。レフ・
トルストイと共に19世紀ロシア・
リアリズム文学を代表する世界的巨匠。現実の客観的反映を重んずるトルストイに対して,〈魂のリアリズム〉と呼ばれる独自の方法で,人間の内面的,心理的な矛盾と相克を追求,近代小説に新しい可能性をひらいた。農奴制的旧秩序が崩壊し,新しい資本主義的諸関係がそれに代わろうとする過渡期のロシアで,自身が時代の矛盾に引き裂かれながら,その引き裂かれる自己を全的に作品世界に投入しえた彼の文学は,異常なほどの今日性をもって際立っており,20世紀の思想,文学に深刻な影響を与えている。
ドストエフスキーはモスクワのマリヤ慈善病院の医師の次男に生まれた。父のミハイルは聖職者の家系の出だが,この家系をさかのぼると,1506年にリトアニアのドストエヴォに領地を賜った古い貴族の家柄につながる。1828年に父は八等官として貴族の身分を与えられ,31~32年にはトゥーラ県にダーロヴォエ,チェレモシナの2つの持ち村を手に入れた。農奴100人ほどの小領地である。作家が10歳のころから一家は毎夏この持ち村を訪れるようになり,ドストエフスキーはここで初めてロシアの農村に親しむことになる。〈狼
(おおかみ)がきた〉という幻聴におびえる少年の彼をやさしく抱き上げて,「キリストさまがついていらっしゃる」と十字を切ってくれたという『百姓マレイ』Мужик Марей(1876)の物語も,ここでの記憶である。なお父は,持ち村の農奴たちへの苛酷
(かこく)な扱い,村の娘たちへの手出しなどの恨みを買って,39年に農民たちによって惨殺された。長らく秘密にされていたこの事件は,生涯にわたって作家に深刻な衝撃を与えたようで,『罪と罰』(66,解説後出)のスヴィドリガイロフ,『カラマーゾフの兄弟』(79−80,解説後出)のフョードル・カラマーゾフなどには,この事件の反映を見いだすことができる。教育熱心だが,気むずかしく,暴君的だった父とは対照的に,富裕な商家ネチャーエフ家の出であった母のマリヤは,従順で信心深い女性で,作家は37年に死んだこの母から大きな感化を受けている。『新旧約聖書から取った百四の物語』という本をテキストに使って,作家に読み書きの手ほどきをしてくれたのもこの母であり,またモスクワの教会に幼い彼を伴っていったのも母であった。
1833年に彼は年子の兄ミハイル・
ドストエフスキーと共にフランス人スシャールの経営するモスクワの私塾に入り,翌年にはチェルマークの指導する寄宿学校に移った。ここは文学的雰囲気に恵まれた学校で,ドストエフスキーはこの時期に西欧,ロシアの文学作品に広く親しんだらしい。37年に
プーシキンがダンテスとの決闘に倒れた事件には非常な衝撃を受け,「もし母の喪に服していなかったら,プーシキンのために喪に服したかった」と述べたという。5月,ペテルブルグへ出て,
コストマーロフ経営の寄宿制予備校に入り,工兵学校への入学準備に励む。このころ5歳年上のシドロフスキーを知り,その特異な性格と文学的教養に強い影響を受ける。
1838年1月,ドストエフスキーは工兵士官学校に入る。兄ミハイルは試験に失敗し,少し遅れて入学する。軍の学校へ進んでもドストエフスキーの文学熱は冷めず,このころまでに
バルザック,
ユゴー,
サンド,
シェイクスピア,
ディケンズ,ウォルター・
スコット,
ゲーテ,
シラー,
ホフマン,
セルバンテス,
ラドクリフらの西欧作家に親しみ,ロシア文学では
カラムジン,
ジュコフスキー,プーシキン,
レールモントフ,
ゴーゴリらに親しんでいた。40~41年には,現存していないが,『マリヤ・スチュアルト』と『ボリス・ゴドゥノフ』の2つの史劇を創作している。当時兄ミハイルも,シラーの『スペインの王子ドン・カルロス』『群盗』,ゲーテの『ヘルマンとドロテーア』などを訳し,兄弟で見せ合って,評価しあっていた。2人の関係には単なる兄弟の枠を越えた親友同士のような雰囲気があったといえる。
5年半にわたる工兵士官学校の課程を終えて,43年8月,ペテルブルグ工兵団工兵局製図室付きを命ぜられる。しかし半年ほどで「勤務はじゃがいものように飽き飽きしました」という心境になり,1年ほどで辞表を提出する。たまたま翻訳したバルザックの『ウージェニー・グランデ』が44年の「レペルトゥアールとパンテオン」誌に載り,好評を得たことに力を得て,職業作家を志し,数次の改作と推敲
(すいこう)を経て45年5月処女作『貧しき人々』(46,解説後出)を完成した。この作品は15年後,
「ヴレーミャ」誌に載った随想『詩と散文で綴るペテルブルグの夢』Петербургское сновидение в стихах и прозе(61)に語られるように,44年1月,ふいに彼を襲ったいわゆる〈ネヴァ川の幻影〉が着想の発端になった。
「あたりを注意して見回すと,ふいに何やら奇妙な人たちが見えてきた。どれもこれも奇妙で不可思議な人物たち,あくまでも散文的な人物たちで……完璧
(かんぺき)な九等官たちなのだが,それでいながら何やらファンタスティックな九等官たちである。ふと見ると,だれやら,このファンタスティックな群像のかげに隠れて,しかめ面をして見せるものがあり,彼が糸だかゼンマイだかを引っぱると,これらの人形たちが動きだす。そしてそのだれやらはげらげらと笑いだし,いつまでも哄笑
(こうしよう)を続けるのだ! するとそのとき,私の脳裏には別の物語が浮かび始めた。どこかの暗い間借り部屋の片隅に,だれやら九等官らしき心根の男がいる。清廉潔白,志操堅固で,上司に忠勤を励むタイプ。そして彼と一緒に一人の少女がいる。辱しめられた,悲しげな少女。そしてこの2人の物語の一部始終が私の心を深く引き裂いた。あのとき私が夢に見た群像を全部集めたら,さぞかしみごとな仮面舞踏会ができたことだろう」
見るとおりここでは『貧しき人々』一編が〈仮面舞踏会〉の一齣
(こま)として構想されている。しがない小役人マカール・ジェーヴシキンと薄幸の少女ワルワーラの悲恋物語として,〈
ちっぽけな人間〉への同情の目を注いだ人道主義的,写実主義的な傑作とこの作品を評価した
ベリンスキー流の解釈には,作者自身がここで異を唱えているわけである。この点を踏まえることで,ベリンスキーがその後のドストエフスキーの作品を正しく評価できなかった理由も明らかになるだろうし,
パロディーと一種の〈
カーニバル〉手法のうえに処女作を構築しえたドストエフスキーの才能の特異性を納得できることになるだろう。
しかし,ともあれ彼の文壇へのデビューは,まれに見る華々しいものであった。『貧しき人々』の原稿を夜を徹して読んだ
グリゴローヴィチとニコライ・
ネクラーソフが,感動のあまり朝の4時に作者をたたき起こして,「新しいゴーゴリの出現」を祝福した話は,ロシア文学史上あまりにも有名なエピソードである。この小説は,当時の批評界の大立者ベリンスキーにも絶賛され,24歳の無名作家の名を一躍高めた。ドストエフスキーは社交界にも出入りするようになり,当時ペテルブルグの文芸生活の中心であった
パナーエワのサロンに訪れるようになった。ドストエフスキーは夫人に淡い恋情を抱いて,しげしげとサロンに通ったが,社交なれしない不器用な人柄がわざわいして,社交界での評判は芳しくなかった。
だが処女作の成功にひきかえ,『分身』(46,解説後出),『プロハルチン氏』Господин Прохарчин(46),『主婦』Хозяйка(47)など,続いて発表された作品の評判はあまり芳しくなく,ベリンスキーもそこに異常心理への病的な関心とリアリズムからの逸脱を見て,作者を手厳しく非難した。しかしこの時期の作品も,処女作からの単なる後退ではなく,後期の作品で発展させられる彼独自のテーマ,思想,方法意識などの原型を豊かに含んだものであった。内気なゴリャートキン氏と,その前に突如出現したシニカルなそっくりさん新ゴリャートキン氏の葛藤
(かつとう)を,独特の文体模倣の手法で描き出した『分身』は,後期の作品に見られる人格の心理的分裂のテーマを先取りしたものだし,『プロハルチン氏』にも,ナポレオン的,ロスチャイルド的強者思想の萌芽
(ほうが)がうかがえる。『主婦』の呪術
(じゆじゆつ)師ムーリンの悪魔的超人性は,『虐げられた人々』(61,解説後出)のワルコフスキー公爵,『悪霊』(71−72,解説後出)のスタヴローギンらの原型となっており,『ポルズンコフ』Ползунков(48)には,後年のドストエフスキー文学で重要な要素となる道化の問題への最初の接近が見てとれる。『九つの手紙から成る小説』Роман в девяти письмах(47),『他人の妻と寝台の下の夫』Чужая жена и муж под кроватью(48),『クリスマス・パーティーと結婚式』Елка и свадьба(48),『正直な泥棒』Честный вор(48)のような小品にも,病的な人間心理への深い透徹と,社会的な弱者,とりわけ子供への強い同情を読み取ることができる。特に『弱い心』Слабое сердце(48)は,他者への気遣いと恐怖から自分を見失って破滅する〈弱い心〉の悲劇を描いた傑作である。これに加えて,処女作以来顕著に現れていたパロディー精神,文体への強烈なこだわり,
フォークロアへの関心が,すでに後年のドストエフスキー文学を予感させている。
このころからドストエフスキーは空想的社会主義の思想への関心を見せ始める。愛すべき佳品『白夜』Белые ночи(48)で,偶然知り合った可憐
(かれん)な乙女の恋人との邂逅
(かいこう)をわきから見守る,いわゆる〈空想家〉のタイプを創造し,『ネートチカ・ネズワーノワ』Неточка Незванова(49,未完)では,不遇な音楽家の執念,女主人公をめぐるレスビアン的関係など,人間の情熱の深淵
(しんえん)を探り,小品『小英雄』Маленький герой(57)では年上の女性への少年期の初恋体験を生々しく綴るなど,作品面には反映していないが,彼はベリンスキーが死去した48年ごろから,
フーリエの思想を奉ずる
ペトラシェフスキーのサークルに接近していった。このサークルは一種の談話会で,直接に革命的行動を目指したものではなかったが,ドストエフスキーはここで急進的なグループに近く,印刷機の保管など実際的活動にも参加していたらしい。この時期のいわば革命体験は,生涯にわたって彼の創作に大きな痕跡
(こんせき)を残すことになる。49年春,彼はサークルにもぐりこんだスパイの密告で,ほかのサークル員と共に逮捕される(
ペトラシェフスキー事件)。ゴーゴリに宛てたベリンスキーの有名な書簡を朗読した,というのが直接の罪状であった。ドストエフスキーらは,ペテルブルグのペトロパヴロフスク要塞
(ようさい)内の陰惨な石牢
(いしろう)アレクセーエフ半月堡
(ほ)に収容され,苛酷な取り調べを受けたが,ドストエフスキーはこの取り調べで不屈の態度を見せ,当局の追及に対してしぶといばかりの抵抗を見せたらしい。しかし当局は彼らに残酷な死刑執行の芝居を仕組んでみせた。死刑の判決を受け,銃殺される直前に,皇帝の特赦と称して,初めて実際の判決が示されたのである。ドストエフスキーは4年の懲役,その後兵卒勤務であった。しかし,死と間近に対決させられたこの時の恐怖の体験は,のちに長編『白痴』(68,解説後出)の主人公ムイシキン公爵の口から生々しく語られるように,生涯消えない傷痕
(きずあと)を彼の心に印
(しる)した。持病の癲癇
(てんかん)もこの前後から急激に悪化する。
ドストエフスキーは約1カ月かかって,シベリアのオムスクの監獄に到着した。途中トボリスクでは,同地にいた
デカブリストの妻たちから,1823年版のロシア語訳聖書を贈られた。この聖書はその後生涯を通じて愛蔵され,死の時にもこの聖書で聖書占いを行ったと伝えられる。シベリアでの獄中生活については,体験録風の小説『死の家の記録』Записки из Мертвого дома(60−62)に詳しい。小説そのものは,妻を殺してシベリアに送られたゴリャンチコフという架空の人物の手記ということになっているが,作者自身の体験を綴ったものであることは疑いがない。
ツルゲーネフをして〈ダンテ的〉と評させた監獄の風呂場の場面をはじめ,この小説は帝政時代の監獄の実情をつぶさに伝え,またさまざまな囚人のタイプをリアルに描き出しており,のちの彼の小説に登場する人物たちの原型ともなっている。また獄中で彼が記憶した囚人たちの独特の言葉遣いやフォークロアは,出獄後,『シベリア・ノート』Сибирская тетрадь(1934,36没後発表)の形にまとめられて,これまたその後の作品で広範に利用されている。
しかしシベリアの獄中では,ドストエフスキー自身の考え方にも微妙な変化が起きたことを否定できない。彼にとって最大の衝撃であったのは,一般囚人に代表されるロシアの民衆が,知識人政治犯を〈旦那衆
(だんなしゆう)〉とみなし,彼らに憎悪と敵意をさえ抱いていたことだった。自分たちは本来の民衆からあまりにも遊離していたのではないか——この発見と内省が,かつての空想的な革命家を忍従の思想の説教者に,
西欧派的思想家をスラヴ的神秘主義者,ロシア
正教の徒に変えていく。苛酷なここの条件のもとで彼の内部に価値の転換が,いわゆる〈信念の更生〉と呼ばれるものが起こったのである。
1854年2月,ドストエフスキーはオムスク監獄を出獄,セミパラチンスクへ護送されて,シベリア独立軍団部隊に配属される。1年半ほどは一兵卒として勤務し,その後下士官に昇進するが,この間,かつて彼の作品の愛読者であったヴランゲリが州検事として赴任し,2人の間に友情が芽生える。ヴランゲリはドストエフスキーに同情して,さまざまな便宜をはかってやった。このころ,『ニコライ1世陛下の崩御を悼む』На смерть Николая I,『アレクサンドラ皇太后陛下の誕生日に寄せて』На день рождения имп. Александры Федоровныなど,改悛
(かいしゆん)の情を表明するための詩をいくつか書き,またトトレーベンに宛てて恩赦の嘆願書を書き,「人間も思想も変わるものです」と,本心とは少し違う告白を行う。また55年ごろから,税務官吏イサーエフの家に頻繁に出入りし,その夫人マリヤ・イサーエワに恋情を募らせる。その年8月,クズネツクに移っていたイサーエフが死去し,57年2月,ドストエフスキーはマリヤ・イサーエワと結婚する。このころ,ドストエフスキーには世襲貴族権が復権され,また少尉補にも任官されて,作品執筆の余裕ももてるようになる。
この地で書かれたのは,中編『伯父様の夢』Дядюшкин сон(59)と長編『ステパンチコヴォ村とその住人』Село Степанчиково и его обитатели(59)だが,この2作は,ドストエフスキーの作品系列ではいくぶん例外的現象となっている。「モルダソフ年代記」の副題をもつ『伯父様の夢』は,北方の町モルダソフを舞台にぼけた大金持ちの老公爵を結婚させようとする陰謀が失敗する物語で,どちらかというと不器用な喜劇仕立てといった趣向である。『ステパンチコヴォ村とその住人』も喜劇仕立ての作品だが,善人そのもののような地主ロスターネフ大佐と,その食客でありながら,やがて一家で専制的な役割を演ずるようになる偽善者フォマ・オピスキンの2つの性格を創造しえた点で,独自の意義をもつ。特に
モリエールのタルチュフを深化させたようなフォマの人物像は長い文学的生命を保つことになった。
1859年7月,ドストエフスキーは中央への帰還を許され,一時トヴェーリに居住したのち,同年末,ほとんど10年ぶりに首都ペテルブルグの土を踏むことができた。
首都に帰ったドストエフスキーは,61年の農奴解放令を前に高揚した社会的空気の中で,兄ミハイルと共に雑誌発行の準備を進め,61年1月,雑誌「ヴレーミャ」の発刊にこぎつける。同誌は
グリゴーリエフ,
ストラーホフらの寄稿者を集め,〈
土壌主義〉を編集方針に掲げて,当時のジャーナリズムの一中心となった。〈土壌主義〉とは,民衆という〈土壌〉から遊離してしまった貴族,知識人を民衆に近づけることによってのみ,人類の幸福もロシアの救いも見いだされるという立場で,ロシアは西欧のような革命の動乱と非人間的な資本主義を通じてでなく,君主制と正教教会のもとにロシア独自の発展の途
(みち)を進むべきであると説いて,ロシア・メシアニズム的思想を鼓吹した。ドストエフスキー自身,この立場にたって,雑誌に次々と論文を発表し,『


ボフ氏と芸術の問題』Г-н—бов и вопрос об искусстве(61)では,ニコライ・
ドブロリューボフの芸術観を〈功利主義〉と断じ,続いて『「呼び子」と「ロシア通報」』《Свисток》и《Русский вестник》(61),『「ロシア通報」への答え』Ответ《Русскому вестнику》(61),『書物と読み書きの能力』Книжность и грамотность(61),『純粋さの見本』Образцы чистосердечия(61),『「ロシア通報」の哀歌的記事について』По поводу элегической заметки《Русского вестника》(61),『理論家の二つの陣営』Два лагеря теоретиков(62),『スラヴ派,モンテネグロ人および西欧派』Славянофилы, черногорцы и западники, самая последняя перепалка(62)などの論文を精力的に執筆して,
カトコーフの
「ロシア通報」,ネクラーソフの
「同時代人」などに激しい論争を挑んだ。そのほか同誌には『ペテルブルグ年代記』Петербургская летопись(47)の14年後に書かれた随想『詩と散文で綴るペテルブルグの夢』,ゴーゴリのパロディーと見られる中編『いまわしい話』Скверный анекдот(62)などが発表されたほか,63年2,3月号には,62年夏のドストエフスキーの最初の西欧旅行の印象を綴った『冬に記す夏の印象』Зимние заметки о летних впечатленияхが掲載された。ロンドンの万国博覧会をはじめ,じかに見た西欧ブルジョワ文明に対して,ドストエフスキーは概して否定的であり,万国博で目にしたガラス製の宮殿〈水晶宮〉はのちに『地下室の手記』(64,解説後出)で揶揄
(やゆ)の対象となる。この旅行の途次,ロンドンで
ゲルツェンとも会見したが,印象記にはゲルツェンに対する論争的調子も聞かれる。
「ヴレーミャ」にはまた,前期の仕事の総決算ともいうべき長編『虐げられた人々』とシベリアの獄中体験に基づくユニークな長編『死の家の記録』も連載された。この2作によってドストエフスキーは10年の空白をおいて文壇への返り咲きを確実にする。
この間,61年の「ヴレーミャ」誌に短編を寄稿したのが縁で知り合った女子学生アポリナリヤ・スースロワと愛人関係になるが,63年夏,ドストエフスキーに飽きたスースロワが外国に出発したのを追って,パリへ赴く。同地でスースロワからスペイン人医学生サルバドールとの関係を打ち明けられ,〈兄妹〉のような間柄でという約束で,ドイツ,スイスを経て,彼女とイタリアへ旅する。この旅行中,ドストエフスキーは賭博
(とばく)に熱中し,しばしば一文無しになるが,この時の体験はのちに中編『賭博者』Игрок(66)で生かされる。63年10月,スースロワと別れてモスクワに帰り,肺結核が高じて精神的にも変調を来たしていた病妻の看護に打ち込む。
「ヴレーミャ」誌は,63年4月,ポーランド問題を論じたストラーホフの論文『宿命的問題』を掲載したかどで発行禁止の処置を受けていたが,ようやく
「エポーハ」と名を変えた新雑誌の発行許可がおり,ドストエフスキーは同誌の64年1号に発表するため,中編『地下室の手記』を,隣室に病妻のうめき声の聞こえる中で書き上げる。スースロワとの愛欲生活の思い出,病妻への自責の念が重なって,この中編の執筆環境は凄絶
(せいぜつ)なものであったらしい。しかし,そういう状況の中で書かれたこの『地下室の手記』は,ドストエフスキー自身の文学観をも一転させるほどの迫力にあふれた傑作となり,
ジッドをして,ドストエフスキーの後期の大作群を解く〈鍵〉とまで絶賛させることになった。
1864年4月,妻のマリヤがモスクワで死去する。妻の遺体を前に書きとめられた4月16日付の日記「マーシャはテーブルの上に横たわっている。再びマーシャに会えるのだろうか?」は,続いてキリストのみがよくなしえた他者への愛の可能性,女犯
(によぼん)も結婚も必要でなくなる人類の未来への考察を含み,その後のドストエフスキーの作品を理解するためにかけがえのない重要文献となっている。続いて7月,幼時から親友以上の存在であった兄ミハイルが死去し,作家は兄の遺族の世話を一人で続けねばならなくなり,「エポーハ」誌の事務などに忙殺される。この間,有名な数学者ソフィヤ・コワレフスカヤの姉であるアンナ・コルヴィン=クルコフスカヤを知り,彼女に結婚を申し込んで断られたりしている。なお65年3月には『鰐
(わに),異常な出来事,またはアーケードでのアクシデント』Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассажеが「エポーハ」誌に発表された。これは,人間を飲み込んでしまった見世物の鰐をめぐるファンタスティックな物語で,ドストエフスキーの純文学的ないたずらとでもいった作品であった。
大作『罪と罰』は65年,ヴィースバーデンで着想された。賭博ですって一文無しになり,ホテルで食事も出してもらえぬ状況になり,「ロシア通報」誌の編集長カトコーフに宛てて前借300ルーブルの無心をした時,この長編の構想が売り込まれたのだった。「これは一つの犯罪の心理的報告書です」と始まるこの手紙には,すでにのちの長編の骨格が完璧に書かれており,カトコーフもただちに300ルーブルを送付している。もっとも,この時に構想されていたのは300枚程度の中編であったらしいが,やがて別に構想されていた長編「酔いどれたち」からマルメラードフ一家の悲劇が入り込んできて,いま見るような大長編となった。
『罪と罰』が「ロシア通報」誌に連載されていた66年末,悪徳出版業者ステロフスキーと交わした契約のために,ドストエフスキーは短期間に中編1本を仕上げなければならない羽目になり,急遽
(きゆうきよ)速記者をやとって,中編『賭博
(とばく)者』を一気に書き上げた。この口述が縁で,その時の速記者アンナ・スニートキナと翌年再婚することになる。彼女は才能豊かな主婦で,口述筆記で夫の仕事を手伝うかたわら,出版社との交渉,夫の著作の刊行なども手がけ,彼との間に4人の子を儲
(もう)けた。2週間ほどしか生きなかった長女ソフィヤ,のちに〈エーメ〉の名で父親の回想録を出す次女リュボーフィ,長男のフョードル,3歳で死亡して作家に大きな悲しみをもたらし,『カラマーゾフの兄弟』にもその面影をたどることのできる次男のアレクセイである。彼女自身も夫との生活について『日記』と『回想』(1925)を残している。
1867年2月に結婚式を挙げた45歳の作家とまだ20歳のアンナは,新婚早々,夫の激しい癲癇の発作に新妻が驚かされる一幕などを経て,4月には早くも西欧旅行に旅立った。債鬼の追及を逃れるためで,当初は秋ごろまでの予定だったが,この旅行は4年間にも長引いた。ドレースデン,バーデンを経て,8月にはジュネーヴに落ち着くことになるが,この間は,頻発する癲癇の発作と,どうにも収まらない作家の賭博癖のせいで,新婚旅行とはほど遠いものであったらしい。ただ各地の美術館で西欧絵画の傑作に親しむことができて,これはその後のドストエフスキーに強烈な印象を与えることになる。ドレースデンで見たラッファエッロとホルバインの「聖母」,ティツィアーノの「皇帝の金貨」,ロランの「アシスとガラテヤ」,レンブラントの諸作,バーゼルで見たホルバインの「死の舞踏」,とりわけ「キリストの遺骸
(いがい)」などである。最後の作品について作家は妻に「こういう絵は信仰を奪いかねない」ともらしたと伝えられ,これはそのまま『白痴』の重要なモチーフとして利用されることになる。ジュネーヴではまたロシアから亡命してきた
オガリョーフや
バクーニンらの革命家と付き合い,また8月末に開かれたガリバルディらの自由平和連盟国際会議にも顔を出したという。
このころから長編『白痴』の稿が進み始め,これは68年の「ロシア通報」に連載された。その間スイスのヴヴェ,イタリアのミラーノ,フィレンツェなどを旅する。再びドレースデンに戻った69年には,「黎明
(れいめい)」誌に中編『永遠の夫』(70,解説後出)の原稿を送っている。またこの時期には,長編「無神論」「大いなる罪人の生涯」などの創作プランが相ついで書かれ,ドストエフスキーの創作意欲の高揚を物語っている。この創作プランには,後年のドストエフスキーを悩ませていた根本的な問題——深刻な動揺ののちに,最後には「キリストを,ロシアの大地を,ロシアのキリストとロシアの神を獲得することになる」という思想がさまざまなバリエーションで語られており,プランそのものは独立した形でまとめられることにはならなかったが,その主要な要素は『悪霊』,『未成年』(75,解説後出),『カラマーゾフの兄弟』など後期の大作群でそれぞれに実現されることになった。
1869年11月,革命家
ネチャーエフが,秘密結社からの脱退を申し出た農業学校生イワーノフをリンチ殺人する事件があり,たまたまこの事件を知ったドストエフスキーは,それを材料に「たとえ政治的パンフレットになろうとも」という覚悟で新作『悪霊』の執筆にかかった。『悪霊』は71年1月から「ロシア通報」に連載されるが,その連載中の71年7月,ドストエフスキー夫妻は4年ぶりでペテルブルグに帰る。同年末,『悪霊』の重要なエピソードである「スタヴローギンの告白」の章が,「ロシア通報」編集部から「家庭的な雑誌にふさわしくない」と掲載を拒否され,それをめぐるごたごたのために『悪霊』は約1年間休載となり,結局この章を欠いたままで72年12月に完結する。
同年末,保守派の有力者メシチェルスキー公爵の発行する雑誌
「市民」に編集人として参加する話が本決まりとなり,ドストエフスキーは翌年から同誌に「作家の日記」の欄を受け持つことになる。この欄は極めて自由に利用され,文壇デビュー当時,ペトラシェフスキー時代の回想記あり,ネクラーソフの『ヴラース』や
レスコフの『封印された天使』をめぐる随想あり,さらには,墓地の地下での亡者たちの対話を描いた実験的な小説『ボボーク』Бобок(73)ありと,そのジャンルも多様で,非常な好評を博した。このために「市民」の発行部数が3倍に伸びたという。これは74年1月,同誌の編集を辞退するまで続いた。
1874年4月,ネクラーソフとの間で次作『未成年』を
「祖国雑記」誌に掲載する話がまとまる。進歩派と目されていた同誌に保守派のドストエフスキーが作品を発表するのは,文学史的な事件であった。6月,ドストエフスキーはドイツの保養地エムスに赴き,7月に帰国後はペテルブルグ南方のスターラヤ・ルッサにこもって『未成年』の創作に打ち込んだ。この長編は約束どおり75年1月から「祖国雑記」誌に掲載される。この進歩派との〈協力〉が一因をなして,多年友情で結ばれていたアポロン・
マイコフ,ストラーホフとの間がこじれる。
1876年からドストエフスキーは,月刊で個人雑誌形式の単行本『作家の日記』Дневник писателя(76−77,80−81)の刊行に踏み切る。これは「市民」誌の「作家の日記」欄よりもさらに自由な形式の文集であり,ドストエフスキー個人の人気も手伝って,当初2000部で出発したものが,数カ月後には早くも6000部に達したという。時事問題に敏感に反応し,ロシア政府の対外政策,ビスマルクのドイツを論ずるかと思えば,バルカンの動乱に関連してスラヴ同胞のためにロシアが立ち上がるべきだと論陣を張り,トルストイの『アンナ・カレーニナ』を本格的に論評し,ロシアの国民性とロシア民衆について深遠な考察を披露するいっぽう,裁判事件,市井の出来事にも目くばりを怠らず,その間には『キリストの樅の木
(ヨールカ)に召された少年』Мальчик у Христа на елке(76),『百姓マレイ』,『百歳の老婆』Столетняя(76)などの小品をちりばめ,また『柔和な女』Кроткая(76),『おかしな男の夢』Сон смешного человека(77)といった本格的な中編も同誌に発表された。『柔和な女』は,両手に聖像を抱いて飛び降り自殺を遂げたモスクワのお針子ボリーソワの死に想を得た作品で,この事件をまず「これまでの自殺にはない,何やら柔和な,謙虚な自殺である」と評論的に取り上げ,翌月号にはこの事件にヒントを得た中編小説を発表した。これは中年の質屋の若い嫁を主人公に,彼女が質屋への反発を感じ,不倫を犯したり,ついには質屋にピストルを擬する緊迫した関係を語りながら最後には彼女が聖像を抱えて窓から飛び降り自殺するまでを,彼女の遺体を前にした質屋の手記の形で,いわば〈
意識の流れ〉とでもいった手法で突き詰めた密度の高い作品で,〈他者の意識〉という重い主題を扱って成功した珍しい佳編である。それに対して『おかしな男の夢』は,SF仕立てのユニークな作品で,他の星に存在する原初の人類のユートピアが罪ある人間によって堕落させられる顚末
(てんまつ)を語りながら,人類の見果てぬ夢としての地上の王国への懐疑と渇望を描いている。
最後の大作『カラマーゾフの兄弟』の執筆に没頭するため,78年初め,『作家の日記』は休刊となる。しかしこの時期にもドストエフスキーの創作意欲をかきたてるような事件はあとを絶たなかった。78年3月には,ペテルブルグ市長トレーポフを狙撃
(そげき)した革命家ヴェーラ・
ザスーリチに対する裁判を傍聴し,被告に対する無罪判決に大きな衝撃を受けた。79年夏には,〈人民の意志〉派が皇帝アレクサンドル2世に対して死刑の宣告を下し,以後皇帝暗殺未遂事件が頻発することになる。事実,皇帝はドストエフスキーの死後1カ月の81年3月1日に,〈人民の意志〉派のグリネヴィツキーによって暗殺されることになる。『カラマーゾフの兄弟』の続編の構想をそのまま実現したような事件であった。
『カラマーゾフの兄弟』は79年1月から「ロシア通報」に連載が開始され,80年11月まで掲載された。この間,春から秋にかけてはスターラヤ・ルッサで過ごしており,この町が『カラマーゾフの兄弟』の舞台の原型となっているともいわれる。少しさかのぼるが,ドストエフスキーは77年夏に久しぶりでトゥーラ県のかつての領地を訪れ,ダーロヴォエ村,チェレモシナ村を訪ねた。また78年夏には,若い哲学者ウラジーミル・
ソロヴィヨフと共にカルーガのオプチナ修道院を訪れ,アンヴローシー長老と面会した。これらの事件は『カラマーゾフの兄弟』の創作に大きな影響を与えている。79年夏には再びエムスを訪れている。
1880年6月,モスクワのプーシキン像除幕式を機に記念講演会が催され,ドストエフスキーはここで『プーシキンについて』Пушкинの有名な講演を行った。プーシキンを〈世界的な現象〉であると断じ,〈ロシアの国民的受難者〉プーシキンを国民的正義によって復権させるべきであると論じて,『ジプシー』のアレコや『エヴゲーニー・オネーギン』のタチヤーナにロシア文学が創造した最も重要な,最も美しい人間像を見てとったこの講演は,聴衆に圧倒的な感銘を与え,出席していたツルゲーネフは感動のあまりドストエフスキーを固く抱擁した。この講演は,多年対立していた西欧派と
スラヴ派を和解させたものとしても評価される。
この講演は,再刊された『作家の日記』の80年8月特別号に掲載された。『作家の日記』は81年1月,2月,3月号まで出るが,すでにこの時にはドストエフスキーは世を去っていた。
1881年1月26日(西暦2月7日)夜,ドストエフスキーはペテルブルグのクズネチヌイ横町にあった自宅で喀血
(かつけつ)する。その後も喀血が続き,1月28日(西暦2月9日)午前7時,妻のアンナに聖書占いをしたいと告げた。トボリスクでデカブリストの妻たちからもらった聖書が開かれた。マタイ福音書3章のイエスの言葉「いまはとどむるなかれ」が出てきた。死期を悟ったドストエフスキーは,その夜の8時38分に永眠した。死因は肺気腫
(きしゆ)にともなう肺動脈の破裂であった。遺体はペテルブルグのアレクサンドル・ネフスキー修道院の墓地に葬られた。
ドストエフスキーが本国だけでなく,その後の世界文学に与えた影響ははかり知れないほど大きい。
ニーチェから
実存主義に至る思想の系譜は彼の存在を抜きにしては考えられないだろう。そのほかにも,シュテファン・
ツヴァイク,
カフカ,ジッド,
プルースト,
カミュ,
ワイルド,トーマス・
マン,ハインリヒ・
ベル,
ドライサー,S.
アンダーソンら,個々の作家に与えた影響も無視できないものがあり,ロシアでは,
アンドレーエフ,
ガルシン,ソヴィエト時代の
レオーノフらに直接的な影響が指摘される。
ドストエフスキーについては,すでに存命中からベリンスキーの諸論文をはじめ,『虐げられた人々』を論じたドブロリューボフの『うちのめされた人々』,『罪と罰』解釈に新しい視点を持ち込んだ
ピーサレフの『生活のための闘い』,
ミハイロフスキーの『非情なる才能』など多様な評価が目立ったが,1900年前後のロシアで,哲学者ソロヴィヨフのドストエフスキー観を受け継ぐ形で,この評価には大きな転換が見られた。このころ,
ローザノフの『ドストエフスキーと大審問官伝説』,
メレシコフスキーの『トルストイとドストエフスキー』,
ヴォルインスキーの『カラマーゾフの王国』『偉大なる憤怒
(ふんぬ)の書』,
シェストフの『ドストエフスキーとニーチェ——悲劇の哲学』,少し遅れては
ベルジャーエフの『ドストエフスキーの世界観』などが出て,人間を霊的に,悲劇的に捉えようとしたドストエフスキーの独自な思想,哲学に注目しようとする新しい傾向が確立した。この傾向はその後も長く影響を保つことになる。これに対して
マルクス主義批評の側からは,ドストエフスキーの思想の反動的な側面を強調しようとする動きが目立ち,
ゴーリキーの『カラマーゾフ主義について』などが現れた。この動きは,作家の創作に初めて社会学的な分析を試みた
ペレヴェールゼフの『ドストエフスキーの創作』などを経て,
スターリン死後に出た
エルミーロフの『ドストエフスキー』あたりにまで継承される。
しかしソヴィエト時代にもドストエフスキー研究はそれなりに深められた。まず挙げなければならないのは,レオニード・
グロスマン(『ドストエフスキーの詩学』,ドストエフスキーの本格的な年譜である『ドストエフスキー,生涯と創作』),
ドリーニン(『書簡集』『後期長編の研究』),文体論研究に成果を上げた
ヴィノグラードフらの仕事で,ほかにコマローヴィチ(『ドストエフスキーの青春』『ドストエフスキーの〈世界調和〉』『カラマーゾフの兄弟の原型』),ベーリチコフ(『ペトラシェフスキー裁判におけるドストエフスキー』),ベーム(『ドストエフスキーの創作の源泉にて』)などの活躍が目立った。しかしこれらの中で,ドストエフスキー理解に革命的な役割を果たしたのは,
トゥイニャーノフの『ゴーゴリとドストエフスキー——パロディーの理論のために』,とりわけ
バフチンの『ドストエフスキーの創作の諸問題』だろう。この書はドストエフスキーの文学の本質を〈モノローグ〉の文学に対立する〈
ポリフォニー〉の文学と規定し,メニッペア劇,
ソクラテスの流れをくむ対話の文学として位置づけた。またカーニバルの概念を大胆に適用して,ドストエフスキーの解釈に全く新しい地平を開いた。このバフチンの視点は
ルナチャルスキーの論文『ドストエフスキーの〈多声性〉について』で正当に支持され,その後の発展が期待されたが,折あしくソ連はスターリン個人崇拝の時期に入り,ドストエフスキー研究はほとんど禁圧された。
スターリン時代の約25年間には,作品の再版そのものもほとんど途絶え,研究書も1939年にゲオールギー・
チュルコーフの『ドストエフスキーはいかに仕事したか』,47年に
キルポーチンの『若きドストエフスキー』の2冊が出たにすぎなかった。スターリン死後の56年以降,まず10巻選集が刊行され,さらに72年からは,異本を網羅し,詳細な注解をほどこした全30巻の全集が出て,ドストエフスキー研究はようやく科学的な基礎をもつことになった。研究書の刊行も未曾有
(みぞう)の活況を呈し,バフチンの著作が63年に増補再刊されたほか,
シクロフスキーの『肯定と否定——ドストエフスキー論』,グロスマンの評伝『ドストエフスキー』,カリャーキンのユニークな著作『ラスコーリニコフの自己欺瞞
(ぎまん)』,セルゲイ・ベローフの『〈罪と罰〉注釈』,
フリードレンデルの『ドストエフスキーと世界文学』,ほかにキルポーチン,セレズニョーフ,詩人のセルゲイ・
ソロヴィヨフ,チルコーフ,ヴェトローフスカヤらの著作が出ている。さらに72年には雑誌「ヴレーミャ」と「エポーハ」についてのネチャーエワの研究,75年にはドストエフスキーの作中人物名を研究したアーリトマンの著作なども刊行された。
ドストエフスキー研究は海外でも盛んで,ツヴァイクの『三人の巨匠』,
フロイトの『ドストエフスキーと父親殺し』,ジッドの『ドストエフスキー』などすでに古典となったもののほか,
モチュリスキーの本格的評伝『ドストエフスキー・生涯と作品』,J. M.
マリーの『ドストエフスキー』,E. H.
カーの『ドストエフスキー』,トゥルナイゼンの『ドストエフスキー』,西ドイツに亡命したマイエルのユニークな『罪と罰』論『夜の中の光』などが知られ,また最近はイギリスの研究家ピース,アメリカのテラス,フランク,フランスのパスカル,カトーらの著作が出色である。
日本では米川正夫,小沼
(こぬま)文彦による個人訳全集がそれぞれ刊行されているほか,1892,93(明治25,26)年の内田魯庵
(ろあん)による『罪と罰』の本邦初訳以来,幾多の訳者による翻訳が出ている。評伝も1914年の瀬戸義直,15年の新城和一
(わいち),21年の谷崎精二,36年の中山省三郎
(せいざぶろう)のものに続いて,39年には小林秀雄の『ドストエフスキーの生活』が出て,日本的なドストエフスキー理解の基礎が置かれた。この間36年には木寺黎二
(きでられいじ)の『ドストエフスキイ文献考』も出ている。その後も池島重信,阿部六郎,河上徹太郎,唐木
(からき)順三,西谷
(にしたに)啓治,森有正
(ありまさ)ら,主として哲学者グループによるドストエフスキー読解の作業が続き,米川正夫,昇曙夢
(のぼりしよむ),中村白葉,中村融
(とおる)らロシア文学畑の人々による研究がこれを補完していたが,1950年代中期以降,埴谷雄高
(はにやゆたか),椎名麟三
(しいなりんぞう),秋山駿
(しゆん),日野啓三,寺田透,桶谷
(おけたに)秀昭,加賀乙彦ら,文芸畑の人々による発言が活発になり,その多くの人によって独自のドストエフスキー論も書かれた。これと並行して,新谷
(あらや)敬三郎,内村剛介,原卓也,江川卓,中村健之介ら,ロシア文学専門家の研究も深められた。そのほか,太宰治,野間宏,武田泰淳,小島信夫,後藤明生,大江健三郎ら戦後文学の担い手たちにドストエフスキーの文学が与えた影響の大きさははかり知れないものがある。




 Dostojevskij フョードル=ミハイロビチ─)ロシアの小説家。トルストイとともに一
Dostojevskij フョードル=ミハイロビチ─)ロシアの小説家。トルストイとともに一