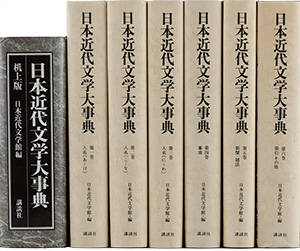小説家、随筆家。東京市小石川区金富町に、永井久一郎、恆の長男として生れた。本名壮吉。別号断腸亭主人、石南居士、鯉川兼待、金阜山人など。久一郎は尾州(現・愛知県)の出身、藩儒鷲津毅堂に漢学を学び、上京後、大学南校貢進生となり、明治四年渡米、六年帰国して官途につき、帝国大学書記官、文部大臣官房秘書官や同会計課長などを歴任、三〇年退官後、日本郵船上海支店長や横浜支店長を勤めた。明治一〇年、毅堂の次女恆と結婚、荷風出生のときは内務省衛生局事務取扱に任じられていた。漢詩人として令名があり『来青閣集』その他がある。一六年、荷風は弟貞二郎出生のため、下谷竹町の鷲津家に預けられ、翌一七年東京女子師範付属幼稚園に通いはじめ、一九年一月(カ)小石川区内の黒田小学校に初等科第六級生として入学、二二年四月、同校尋常科第四学年卒業、七月、東京府尋常師範付属小学校高等科に入学、二三年一一月、同校を退学して神田錦町の東京英語学校に学び、二四年九月、高等師範付属尋常中学科(六年制)第二学年に編入学した。二七年末、ルイレキ(カ)治療のため、下谷の大学病院に入院、翌二八年正月から流感にかかって三月末まで病臥、中学は落第となった。四月、小田原十字町の足柄病院に転地療養して、九月、第四学年に復学したが、学校の空気になじめなくなった。三〇年三月、同校卒業。この月、父久一郎は退官して、四月、日本郵船会社上海支店支配人となった。七月、高校入試に失敗。九月、父母とともに上海に渡り、一一月末、母や弟と帰国し、高等商業学校付属学校清語科に臨時入学。三一年九月、『簾の月』という作をたずさえ、かねてより尊敬していた広津柳浪の門をたたき小説修業をはじめた。翌三二年には、人情噺をしたいという熱望のため、三遊派の落語家朝寐坊むらくの弟子となり、夜々市内の席亭に出入りするかたわら、小説や俳句を試み、また初冬のころ、清国人羅臥雲(蘇山人)の紹介で巌谷小波の木曜会に参加した。外国語学校は第二年(原級留年)のまま除籍になった。三三年、父は日本郵船横浜支店長に転任、荷風は歌舞伎座立作者福地桜痴の門弟となったが、翌三四年四月、桜痴が日出国新聞社の主筆に迎えられ、荷風も行を同じくして雑報欄の助手のほか『新梅ごよみ』を連載したが、九月、桜痴のやり方をめぐって内紛が起き、荷風は桜痴系のために解雇された。同月から暁星学校の夜学に入りフランス語を学びはじめた。このころ英訳を通してゾラの文学に心酔し、これがやがて三五年発刊の「饒舌」(木曜会機関誌)誌上におけるゾラ紹介となり、同年四月刊『野心』(美育社)、九月刊『地獄の花』(金港堂)、翌三六年五月刊『夢の女』(新声社)、九月刊『女優ナヽ』(新声社)などとして展開した。この時期は日清戦争後の社会的昂揚期であり、西洋近代思想の移入紹介と結びついて、個我の覚醒、主張の気運が強まっており、ゾラはニーチェと同心円を描くところの旧道徳、旧文芸への反抗として受容されていた。荷風のゾラへの親近とその摂取には、良家の子弟としての拘束にたいする自立と自己主張とをモチーフとする青春の真実が賭けられていた。柳浪風の写実主義と木曜会のひきずっている古風さが濃く残っているとはいえ、当代のゾライズムの作品の中で、もっとも文学的に肉付けされており、注目されるべきものとなっている。『新任知事』という作品で叔父阪本釤之助をモデルに扱って絶交を宣せられたこともあり、父久一郎は荷風を渡米留学させ、実業家への道を歩かせようとした。荷風はかねてから西洋文化に憧れていたので、父の話をうけて、三六年九月、信濃丸にて出帆、一〇月、タコマに到着した。そこでは古屋商店タコマ支店支配人山本方に寄寓し、日本人出稼ぎ人の生活に触れたり、アメリカの自然の景色に深い感銘をうけた。翌三七年一一月、ミシガン州カラマッズウ大学の聴講生となり、英文学とフランス語の講座に出席。三八年六月、ニューヨークに出て、七月、アメリカの生活が詩情に欠けているのを嘆じてフランス行きをもくろみ、旅費稼ぎにワシントン日本公使館に雇いとして住込んだが、このフランス行きは父の同意を得ることを得ず、憂悶の中でイデスという女性と知合い耽溺生活にのめりこんだ。日露戦争講和とともに公使館を去って、いちじカラマッズウに帰ったが、父の命で正金銀行ニューヨーク支店に勤めることになった。四〇年七月、ついに父の配慮で正金銀行フランス、リヨン支店に転勤することを得たが、銀行業務に甘んじることができず、翌四一年三月、辞職した。しかし父の意志により長期のフランス滞在を果たしえず、五月末、パリに別れを告げ、ロンドン出帆讃岐丸にて帰国した。荷風の外遊は、四年の歳月をアメリカで送るものであり、フランス滞在は一〇ヵ月にすぎなかったが、市民的社会における個人主義と自由を愛する精神において、深い影響をうけた。日露戦争の間、ちょうどアメリカに滞在、戦争の推移にほとんど国民的関心を示さなかったことも注目されるが、外から旅人の目で日本を観る眼を養ったことは、外遊体験の大きい収穫であった。
明治四一年七月、荷風は、父のもくろみに反し、ひとまわり大きい新時代の文学者としての見識と個性の持ち主として帰国した。かねて送ってあった滞米、渡仏直後執筆の『あめりか物語』(明41・8 博文館)は、好評をもって迎えられ、新帰朝者としてつぎつぎに作品を発表。『ふらんす物語』(明42・3 博文館)は納本とともに発禁処分を蒙り、ここに当局の荷風文学にたいする干渉の歴史がはじまった。しかしこの前後は、荷風の生涯におけるもっとも文学意欲の充実した時期であり、『狐』『深川の唄』『監獄署の裏』『祝盃』『歓楽』などの短編集『歓楽』(明42・9 易風社、発禁)に結晶する作品、『帰朝者の日記』(のち、『新帰朝者日記』)『すみだ川』などを発表し、また漱石の依頼で「朝日新聞」に長編『冷笑』(明42・12・13~43・2・28)の連載をはじめ、おりからの自然主義主流の文壇に耽美主義の新風を吹込んだ。翌四三年二月、森鷗外、上田敏の推薦をうけ、慶大の文科刷新の期待をになって、教授に就任し、五月「三田文学」を主宰創刊、随筆『紅茶の後』の連載をはじめとし、戯曲『平維盛』などがあり、反自然主義陣営の中心的存在の一人となった。
荷風には早くから快楽主義的嗜欲が強く、それが良家の家風への反逆と結びついてその青春を彩っていた。帰国後の孤独の中で柳橋や新橋の花柳界に親しんだが、あいつぐ自著の発禁や大逆事件に象徴される圧力状況下において、近代的文学者として生きることの困難さを痛切に感じ取り、江戸戯作者の姿勢に身をやつすことを好むようになるにおよび、芸術的審美的にも生活態度の上でも花柳狭斜趣味が顕在化していった。それはまず『妾宅』『掛取り』『風邪ごこち』『五月闇』などの『新橋夜話』(大元・11 籾山書店)にまとめられる諸作品の上にあらわれた。大正元年九月、本郷湯島四丁目の斎藤政吉の次女ヨネと見合い結婚したが親しまなかった。二年一月二日、父久一郎が脳溢血で死去、これを機会にヨネと離婚、八重次を外妾とした。帰国以後、持続的にフランス近代詩を翻訳紹介し、また海外文芸の批評紹介を行ってきたが、それらを合して翻訳詩文集、評論集『珊瑚集』(大2・4 籾山書店)一巻を上梓し、アクチィブな近代芸術思潮の鼓吹者として奮戦した記念碑とした。これは、荷風の眼が西洋から江戸へ向けられたことと表裏をなしていた。その江戸文化、趣味への傾斜は急速にすすみ、柳亭種彦を主人公にした『戯作者の死』(のち、『散柳窓夕栄』)、笠森お仙を扱った『恋衣花笠森』などの創作のほか、浮世絵、狂歌、演劇などにおよぶ包括的な江戸文化への考察となって展開していった。三年八月、かねてから交情濃やかな八重次を正妻としたが、この結婚をめぐり弟威三郎との間に感情的対立を生じ、母恆と威三郎とが同居することになった。家督相続人、長男でありながら、「家」から進んで遠ざかるという自覚は、以後いっそう強くなっていった。荷風はこの年、東京市中の散策をこころみ、「三田文学」に『日和下駄』を連載(大4・11 籾山書店)、また『夏すがた』(大4・1 籾山書店、発禁)を書きおろした。大正四年二月、八重次が荷風の浮気を嫉妬して家出を敢行、ついに離婚。以来荷風は多くの女性と関係をもつが妻帯はしなかった。胃腸をこわし慶應義塾のほうも休講がちになり、五年二月限り、教授および三田文学編集を退任、この前後、築地や代地河岸に隠れ住んだ。四月、井上啞々、籾山庭後らと「文明」を創刊(大6・12、以後手を引く)、反時代的戯作者的態度をいっそう鮮明にして、『腕くらべ』や『断腸亭雑稾』(大7・1 籾山書店)所収の雅致に富んだ随筆をつぎつぎに掲げた。七年五月、啞々、久米秀治と「花月」を創刊(大7・12廃刊)、一二月、大久保余丁町の邸を売却して築地二丁目に移居した。また春陽堂から元版『荷風全集』全六巻が刊行されはじめ、ここに著者自身の編集と校訂によって荷風文学が統一的世界として読者の前に現れることになった。こういう気運も作用してか、荷風の創作力はこの時期に生気を回復し、『腕くらべ』(大6・12 私家版)『おかめ笹』(大9・4 春陽堂)などに結晶している。九年五月、麻布市兵衛町一ノ六に偏奇館を建てて移居した。この前後から玄文社芝居合評会に出席したり、『三柏葉樹頭夜嵐』『夜網誰白魚』の創作と上演があったりして演劇方面の仕事が目だち、脚本集『三柏葉樹頭夜嵐』(大10・7 春陽堂)『秋のわかれ』(大11・3 春陽堂)などがある。しかしようやく小説創作力に劣えが見え、『雨瀟瀟』などのほかはめぼしいものがない。むしろ、荷風文学の別の大きい側面である随筆において、反時代的な文明批評と懐旧的情趣との渾然とした世界が創り出された。大正初期からのものをまとめた『江戸芸術論』(大9・3 春陽堂)や『雨瀟瀟』(大11・7 春陽堂)『麻布襍記』(大13・9 春陽堂)『下谷叢話』(大15・3 春陽堂)『荷風文稾』(大15・4 春陽堂)など、および『荷風随筆』(昭8・4 中央公論社)がそれである。これらの背景には、大正から昭和へという時勢の激しい推移や関東大震災以後の東京風物の変化などがあるわけだが、荷風は隠者的な傍観の目で時勢を白眼に見据えながら、一方で新しい世相に強烈な好奇心を抱きつづけていた。荷風の快楽追求の対象も芸妓から私娼へと移ってき、大正末年からは銀座のカフエ、タイガーに通いはじめ、女給や私娼との交渉も生れた。しかし荷風は、昭和六年に入ると、『榎物語』(執筆は昭4)『あぢさゐ』などについで『つゆのあとさき』を「中央公論」に発表し、齢五〇を越えた作者の新しい飛躍と充実とを見せたのである。つぎの『ひかげの花』(昭9)は私娼とヒモの生態を冷徹に描き出しており、そこに若き日以来親しんだフランス自然主義の「肉化」と「再生」を見ることも可能である。一一年、荷風は私娼の町玉の井をしばしばたずねたが、一二年、これが大作『濹東綺譚』として「朝日新聞」夕刊に連載され、時代の閉塞された重苦しさに涼気を送るものとして読書界に迎えられた。同年九月母恆が死去した。一一月、ひさしぶりに浅草公園の興行ものを観て以来、とくにオペラ館の常連となった。オペラ脚本『葛飾情話』(昭13)はその産物である。一三年刊行の小説随筆集『おもかげ』(岩波書店)以後、二、三の随筆を発表したのみで作品の発表は諦め、作家として直接的に時勢と相渉ることを拒否した。しかし文学者としての営みを停止し放棄したのではなく、彼はかえって、峻拒と緘黙とを通じて文学者の道を守ろうとしたのである。日米開戦の日には、『浮沈』の稿を起こし、ついで『勲章』『踊子』『来訪者』『問はずがたり』などの諸作の執筆と完成への情熱を燃やしつづけ、文学一途に生きたのであった。二〇年三月一〇日の大空襲で偏奇館も焼亡、岡山へ疎開して敗戦を迎えた。その後、熱海にもどり、やがて千葉県市川市菅野の大島五叟方に寄寓した。大正六年以来休むことなくつづけられた『断腸亭日乗』の昭和二〇年度の『罹災日録』(昭22・1 扶桑書房)としてとくに注目されている。前記の戦時下執筆の諸作品は、戦後のジャーナリズムに迎えられ、文学に飢えていた人々の渇をいやし、文化再出発にあたって機運醸成にあずかる点があった。戦後の著作として、『偏奇館吟草』(昭23・11 筑摩書房)『葛飾土産』(昭25・2 中央公論社)『裸体』(昭29・2 中央公論社)『葛飾こよみ』(昭31・8 毎日新聞社)『あづま橋』(昭32・11 中央公論社)などがあり、『荷風全集』の編集刊行(中央公論社)があった。大正六年以来書きつづけられた日記『断腸亭日乗』も公表されるにしたがい、荷風文学の重大な面が明らかにされ、世の注目を浴びた。昭和二七年、文化勲章を受け、二九年にはさらに芸術院会員に選ばれた。だがその偏奇をつらぬく隠者的生き方は死にいたるまで変わりはなかった。三二年三月、市川市八幡町四ノ一二二八に移り、翌三四年四月三〇日朝、ひとり吐血し死亡しているのが通いの手伝い婦によって発見された。死因は胃潰瘍の吐血による心臓マヒと診断された。
おもなる全集の編集刊行はつぎのとおりである。『荷風全集』全二四巻(昭23~28 中央公論社)『荷風全集』全二八巻一刷(昭37~40 岩波書店)、全二九巻二刷(昭46~49 岩波書店)。
代表作
代表作:既存全集



 東綺譚〔1937〕〈
東綺譚〔1937〕〈