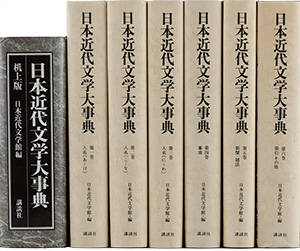小説家。北海道上川郡旭川町で生れたが、旭川は父の勤務地で、郷里は静岡県田方郡上狩野村大字湯ケ島字久保田。父隼雄は同村門野原の旧家石渡家の出で、母八重は井上文次の長女。井上家は七代ほど前の明和(1764~1771)のころ、四国から流れてきて湯ケ島に草鞋を脱ぎ、そのまま医者として住みついた家系で、曾祖父潔は最も著れ、初代軍医総監松本順の門に入り、県立三島病院長となり、晩年は郷里に退いて開業し、名望は伊豆一円にとどろいた。父隼雄も軍医で、任地を転々とし、幼年期の靖もそれに従がったが、大正二年に父母の膝下を離れ、湯ケ島に帰って、潔の妾で、戸籍上は祖母であったかのに托され、二人は六年間、分家の裏手の土蔵の中に暮らすこととなった。この元芸妓の孤独な老女との同棲は、靖少年の心に濃い影を投じた。この二人は強固な心の同盟を結び、親戚や村人を敵に廻して共同生活を送った。言わば彼女によって少年ははじめて世間というもの、他人というものの真実に触れた。かのは潔の師松本順を敬愛してやまず、人を尊敬する態度の美しさを、井上は彼女から学んだと言っている。『グウドル氏の手套』『あすなろ物語』その他、彼はかの女の肖像をしばしば小説に書いている。
大正九年一月、かの死し、彼は父の任地浜松に行き、一一年には父が台北に転任のため、伯母の縁故で三島へ行き、沼津中学へ通った。四年生のころ、二、三の文学ずきの友人から文学への眼を開かれ、また中学生らしい放埒ぶりを身につけた。彼らは小学生のときから三重吉、白秋らの、雑誌「赤い鳥」を中心とした綴り方、童謡などの運動に触れた、早熟の少年たちであった。このグループのリーダー格であった藤井寿雄の「秋が来た/カチリ/石英の音」という三行詩を見せられ、詩の何たるかが分ったと井上は言っている。自叙伝的連作小説『しろばんば』『夏草冬濤』『北の海』などに書かれている。
昭和二年四月、金沢の第四高等学校理科に入学、家業の医学を修めるつもりであったが、柔道部に入り、中学時代の徹底的な学業放棄が、ここでも続いた。だが、かつての放埒ぶりとは反対に、ここでは、柔道では練習量がすべてを決定するという考えのもとに、明けても暮れても道場での寝業の練習に没頭するという、極端な厳格主義、禁欲主義を自分に課した。三年生のとき、ゆえあって柔道部を退部したが、いまさら勉強生活にも帰れず、もはや医学部に進む気持ちはなく、離れていた文学にふたたび帰り、富山県の石動の詩人大村正次が出している詩誌「日本海詩人」に井上泰の名で投稿した。そして父隼雄を始めとする井上家の期待に反いて、昭和五年、理学部志望を棄て、その年定員の余剰があった九州帝大法文学部にはいった。だが聴講の興味を失い、上京して駒込の植木屋の二階にド宿して、気ままな生活を送った。このころ彼は民衆派詩人福田正夫主宰の詩誌「焰」の同人となって詩を作り、また植木屋の息子にアナーキストがいて、辻潤、高橋新吉などのダダイストたちも、見すぼらしい身なりでときどき現れた。昭和五、六年といえば、学生たちの間に風靡したマルクス主義運動が、次第に地下に追いこまれていた時代だったが、そのような一運動に対して終始冷静な第三者であった井上が、最も運動の渦に近づいた時期があったとすれば、この頃であった。だが、「あらゆることに、私は怠惰であり、常に傍観者でしかなかった」(詩『瞳』)という彼は、大胆不敵な決断と行動への意欲をかかえながら、同時にそれを凍結させてしまうような、人生からの退隠への欲求が生れてくる。それは井上家の家系には間歇的に現れてくるようで、六年に陸軍軍医少将に昇進した父隼雄は、退職して郷里湯ケ島に還り、以後二度と聴診器を手にせず、後半生をみずからの手で埋没させてしまった。息子の医学断念を知った衝動もあったかもしれぬ。井上はその翌年四月、九州帝大二年目を終わりながら、京都帝大哲学科に入学し、教授植田寿蔵のもとで美学を専攻した。二年ほど学生生活を延長することが魅力だったと、彼は言う。放埒怠惰の生活はなおつづき、学校へはほとんど顔を出さず、卒業試験を放擲して、さらに一年延長し、一一年、数え年三〇歳で、六年間の大学生活に終止符を打った。
昭和八年、「サンデー毎日」の半年ごとの懸賞小説に応募して選外佳作となり、翌年と翌々年は沢木信乃の匿名と本名で応募しともに入選し、三〇〇円ずつの賞金を得た。一一年七月には、同誌の千葉亀雄賞懸賞長編小説に、時代小説『流転』を書き、一〇〇〇円の賞金をせしめている。また、懸賞小説の技量を買われて、昭和一〇年春、新興キネマ脚本部に声がかかり、月に二、三回、京都東京間の国鉄二等パスを持って東京大泉撮影所に通ったこともあった。一〇年六月に、雑誌「新劇壇」に発表した戯曲『明治の月』が、同年一〇月に新橋演舞場で、守田勘弥、森律子らによって上演された。放埒な生活がやまなかった彼は、始終小遣いに困り、賞金稼ぎをして浪費した。だが、金のために短時日で仕上げた作品が、たちまち賞を受けるという幸運に、彼は有頂天になってばかりいたわけではない。自分の心がそれによって満されるわけではないやっつけ仕事が、世に受容れられたことの、苦い味のする空虚さを、彼は噛みしめた。それがきっかけで、原稿註文は殺到したが、みな断った。文学をやりたいという気持ちは強くなったが、それはこれらの読物やシナリオのような、いつでも書ける安易な仕事とは別の内面的な欲求だった。
昭和一〇年、田辺元門下の哲学科の仲間たちと「聖餐」という同人雑誌を作り、詩を発表した。学生時代に、彼が最も心をこめた文学作品といえる。同人に高安敬義という年少の秀才があり、始めは井上が後見役のような形で、詩作や古美術鑑賞などに引廻したが、高安はまたたく間にそれらに関する文献を読みあさり、逆に井上にその非凡な見解を披露した。井上が書いた卒業論文『ヴァレリーの純粋詩論』は、高安の講義に基づくところが多かった。
昭和一〇年一一月、彼は京都帝大名誉教授で、軟部人類学の創始者足立文太郎の長女ふみと結婚した。文太郎は井上潔の甥で、井上家に育てられた。井上一族に流れる学問の血統を代表する人で、井上は彼をモデルとして『比良のシャクナゲ』(「文学界」昭25・3)を書いている。父隼雄にすれば、靖を結婚させることでその放埒な生活に終止符を打ち、いつまでも卒業する気のない彼の身を固めさせようとしたのだ。そのもくろみは図に当たり、翌年三月卒業、八月には『流転』入選が機縁で、毎日新聞に入社、「サンデー毎日」編集部勤務となった。
部署は社内でも居心地がよいので、小説家志望は捨ててもよいと思った。だが、翌年九月には日支事変に応召し、第三師団輜重隊に入隊し、北支方面に駐屯して、病気になり、翌年四月には除隊となった。この短い戦争経験について、彼はほとんど語らず、わずかに『元氏』などの散文詩を作っているにすぎない。かつて左翼思想の嵐にいささかも動じなかった彼は、戦時下の思想的な動きにも超然と身を持した。
応召前から彼は学芸部に転じていたが、帰ってから宗教欄つづいて美術欄を担当し、新聞記者でありながら学究的な雰囲気の中にあって、仏教経典の解説を書き、美術批評をやった。またしばしば大和や京都へ調査や取材に出かけて、古美術についての知識を身につけた。これは井上にとって、大きな蓄積の時代であり、同時にまた成長と変貌の時代でもあった。幼少時代からの孤独で非社交的な性質が、この記者時代に矯め直され、それは後に彼の作品に幅と拡がりと健康さとをもたらした。
終戦のとき、彼は社会部勤務で、終戦の玉音拝聴の記事を井上が書いたのは、その端正で達意の文章が社内でも注目されていたことを物語る。終戦直後から彼には詩作が多くなったが、二二、二三年には、『闘牛』と『猟銃』とを脱稿、文芸雑誌「人間」の懸賞募集に応じたが、二編とも選外佳作。時は戦後派文学の時代で、彼の青年時代からの友人野間宏らの擡頭期であった。だが、これらの作品がたまたま佐藤春夫の知るところとなり、その紹介で雑誌「文学界」に相次いで発表され、そのうち『闘牛』(「文学界」昭24・12)によって芥川賞を受けた。四十代の新人としてデビュウした彼は、「小説を書く以外、もう私には別段他に何も面白いことはないようである」と言った。この言葉は、「びょうぼう磧のごとき過ぎし歳月、そのおちこちに散乱する私の愚かな所行の数々」(散文詩『半生』)と彼自身がいった空しく過ぎ去った過去半生を踏まえて言っているのである。彼はもともと物語作家としての才能がきわめて豊かだったから、このたびの再デビュウには、適宜に内面の第一次的欲求と読者へのサーヴィスとの二本だてで進む。東京へ移住し、二六年新聞社を退社し、多忙な作家生活にはいる。新聞小説、中間小説などのエンターテインメンツとしては、『あした来る人』『射程』(昭32・5 新潮社)『氷壁』(昭32・10 新潮社)『城砦』『化石』(昭42・6 講談社)『夜の声』『欅の木』『四角な船』『星と祭』その他がある。題材としても多彩で、たとえば『射程』の主人公は、前の『闘牛』後の『氷壁』につながる現代の行動者の典型で、今日の社会機構の中で絶えず行動に直面していることを求める現代人に見るニヒリズムを描き、今日の根源の病患の一つをえぐり出す。だが、その物語性において最も成功したのは『氷壁』で、これは登山界を騒がせたある事件を捕え、絶えず冒険に生きる山男に寄せる氏の夢を造型した。その後は終始崩さぬペースで、ときに原爆病、ガン患者、環境汚染など、アクチュアルな題材をも取上げ、「中間小説の良心」と言われながら、ジャーナリズムの欲求を充たし、読者を楽しませてきた。だが、これらの仕事が井上にとって第一義的にやりたいことではなかったし、世間的成功の半面にともなう心の空虚がなかったわけではない。彼は比較的たやすくできて名声と金とをもたらすそれらの仕事と並行して、『玉碗記』『漆胡樽』『異域の人』などの西域小説というべき系列の作品があり、それはふくらんで『天平の甍』『楼蘭』(昭34・5 講談社)『敦煌』(昭34・11 講談社)『洪水』『蒼き狼』(昭35・10 文芸春秋新社)『風濤』(昭38・10 講談社)『おろしや国酔夢譚』(昭43・10 文芸春秋)などの労作となる。若いときからシルクロードに対する浪漫的な夢があり、それは美術への嗜好とともに、彼の中の学問的な血に支えられ、内的なモチーフの深さをうかがわせる。ほかに『後白河院』(昭47・6 筑摩書房)『淀どの日記』(昭36・10 文芸春秋新社)『額田女王』の歴史小説があり、歴史は彼の人間の運命について考えめぐらす最上の場であるようだ。
ストーリー・テラーとしての稀有の才能にめぐまれながら、物語離れの強い欲求を心に持ち、それが彼を述べて作らぬ歴史のほうに引き寄せ、同時に始終鷗外の言う歴史離れの欲求も心に秘めている。だが年とともに、東洋の詩人、芸術家の心をしばしば見舞う作ることへの嫌悪を、彼も見せてくる。歴史とともに、彼が主として短編小説において試みる私小説の比重は、井上の仕事の全体を考えてもきわめて大きいし、質的にも彼の最良のものを含む。それは彼が終始作ることをやめない散文詩の世界と相接している。『通夜の客』(「別冊文芸春秋」昭24・12)『比良のシャクナゲ』『澄賢房覚え書』(「文学界」昭26・6)『ある偽作家の生涯』(昭26・12 創元社)など初期の好短編にも自己の投影は濃厚だが、『姨捨』(昭31・6 新潮社)『孤猿』などを経て、『花の下』『月の光』(昭44・10 講談社)『雪の面』という『わが母の記』三部作、『墓地とえび芋』『道』(「新潮」昭46・6)『桃李記』(昭49・9 新潮社)『鬼の話』(「新潮」昭45・2)などになると、できるかぎり作為を避けた自然の姿勢で、自分とその周辺を捕え、おのずから到達した老作家の円熟した至境を見せている。物語の名手として印象づけられている作者も、歴史小説と私小説と散文詩の世界があることは、大きな救いであった。さらに『カルロス四世の家族』『美しきものとの出会い』などのすぐれた美術に関するエッセイや『西域物語』のような歴史、地理的随筆の世界があることも、彼の作家的な幅と厚みを思わせるものである。
昭和二六年、毎日新聞社を退社して創作に専心するようになって以後、順調なコースを歩み、とくに語るべき事歴はない。三二年、中野重治、本多秋五、堀田善衞、山本健吉らとまだ国交のない中国を訪問して以来、ヨーロッパ、アメリカ、ソ連(中央アジアを含む)、インド、中近東、ネパールなど、旅行も多く、彼の作品の舞台も世界各地に拡がっている。文学賞を受けることも多く、公私の役職も数知れず勤めた。三九年、日本芸術院会員に推され、五一年文化勲章を受けた。
『井上靖小説全集』全三二巻(昭47~50 新潮社)。
1981(昭和56)年5月、日本ペンクラブ第9代会長に就任。1984(昭和59)年5月に開催された第47回国際ペンクラブ東京大会では、実行委員長を務めた。大会メインテーマは「核状況下における文学――なぜわれわれは書くのか――」。開会式では「共存共栄の哲学」と題した講演をした。1981(昭和56)年11月、講談社より『本覚坊遺文』を刊行。弟子の本覚坊の視点から千利休を描いた長篇歴史小説である。井上靖の創作観、芸術観を千利休の侘茶にかける思いに託して表現し、歴史に擬した私小説の趣もある。日本文学大賞受賞。
1982(昭和57)年1月より『すばる』に散文詩の連載を開始。途中、2年間の中断を挟みながらも、死に至るまで続けた。その成果は『乾河道』(1984・3 集英社)、『傍観者』(1988・6 集英社)、『星闌干』(1990・10 集英社)の三冊の詩集に見ることができる。1989(平成1)年9月、新潮社より長篇歴史小説『孔子』を刊行。1991(平成3)年1月29日、急性肺炎のため死去。満83歳。勲一等旭日大綬章が贈られる。同年3月、『すばる』に遺作となった散文詩「病床日誌」が掲載された。
作家逝去の後、藤沢全著『若き日の井上靖研究』(1993・12 三省堂)が刊行され、井上靖の九州帝国大学在学は、実は入学年の10月まで、わずか半年間であったことが判明した。さらに新潮社版『井上靖全集』編集の過程で、文壇デビュー以前の未発表草稿計23点が発見された。その中からユーモア小説「昇給綺談」が、曾根博義の解説と併せて世田谷文学館「井上靖展」(2000・4~6)の図録に掲載され、小説6篇(「昇給綺談」「就職圏外」「復讐」「黒い流れ」「白薔薇は語る」「文永日本」)と戯曲1篇(「夜霧」)が、高木伸幸編『井上靖未発表初期短篇集』(2019・3 七月社)として刊行された。
代表作
代表作:既存全集



 ュー
ュー パッシブ。*猟銃〔1949〕〈
パッシブ。*猟銃〔1949〕〈