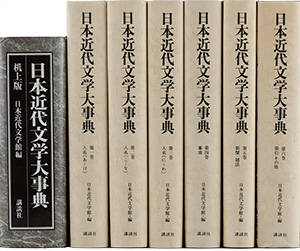1783年,フランス東部の都市グルノーブルに生まれた。家は代々の法曹家で,父は同市高等法院所属の弁護士,母の実家は医家で,ともに裕福なブルジョワである。少年アンリの精神生活はかなり特異なものだった。彼は母を熱愛し,父を憎悪した。父親は,やや視野は狭いものの,きまじめな堅物であったにすぎない。が,少年は,熱愛する母,音楽好きで
13歳でグルノーブル中央学校に入学。これは大革命後の新しい教育理念に沿ってその年創設された学校だが,ここで彼が発見した情熱は数学だった。「二つの仇敵(きゆうてき),偽善と曖昧を許さぬもの」として彼が熱愛した数学は,大嫌いな故郷から彼をパリへ連れ出してくれた。卒業試験で数学の首席をとったため,理工科学校(ポリテクニツク)受験の機会に恵まれたのである。しかし上京した少年の本心は「モリエールのような劇作家になる」こと,「女優を恋人にする」こと,すなわち,〈書き〉〈愛する〉ことにあった。結局,受験は放棄される。のみならず,山出しの16歳の少年は,大都会の孤独に耐えきれずノイローゼ状態に陥ってしまう。救いの手を差し伸べてくれたのは親戚(しんせき)の陸軍高官ダリュで,その斡旋(あつせん)によりアンリはナポレオンのイタリア遠征軍に加わることになり,竜騎兵少尉としてアルプスを越え,17歳の春,初めてイタリアの土を踏んだ。灰色の年月ののちに,ついに訪れた解放としてのイタリア経験は,彼にとって決定的だった。彼はここで自由を知り,愛と快楽を,美と音楽を知り,イタリア人の生き方を知る。以来,イタリアは,ことにミラーノは,彼の精神的故郷となった。
まもなく軍職を去り,1802年に再びパリへ出た青年ベールは,以降数年間,劇作家を志して文学修業に精進する。彼は劇作の前提として人間研究の深化を自らに課し,その基礎を
1804年末,女優メラニーを知ったベールはまもなく恋におちる。この事件は人間観察家に絶好の機会を提供した。当時の日記はメラニーとの交渉の記述に埋め尽くされている。ひとかどの誘惑者を気取る青年は,実際行動においては不器用きわまる臆病(おくびよう)者でしかない。その一方,日記の中で以上の事情を冷静に分析するもう一人の彼がいる。この両者の関係は,後年の小説における主人公と作者の関係になんと酷似していることか。ある評家が,この時代のスタンダールの日記を〈無意識的小説〉と呼んだのも故ないことではない。メラニーとの恋は,彼女の出演先のマルセイユで同棲(どうせい)生活を送るところまで進展するが,破局は意外に早く訪れ,1年ほどで2人は別れた。
1806年から14年の帝政崩壊まで,ベールは,軍属として,また官僚として,さまざまの役職に就き,ヨーロッパ各地を転々とした。文学よりも,社会的地位を築くことに野心を燃やした時期と言ってよい。生活は派手になり,女性遍歴も多彩である。一時はオペラ・ブッファの歌姫を囲って豪奢(ごうしや)な生活を送ったこともあり,知事職や爵位を夢みたことすらあった。
1814年「ナポレオンと共に失脚」。失意のベールは今や精神的故郷イタリアへ赴くことを熱望する。その前に,小遣い稼ぎの意味もあって書きとばしたのが,処女作『ハイドン・モーツァルト・メタスタージョ伝』Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase(1815)である。大部分は他人の著作からの剽窃(ひようせつ)だが,最愛の作曲家
ミラーノ時代の彼にとって最大の事件は,18年から21年へかけてのメチルド(本名マティルデ・デンボウスキ)への不幸な恋である。この多感な魂をもつ美貌(びぼう)の人妻へスタンダールが寄せた思慕は,その生涯において最も純粋かつ熱烈なものだった。この体験をふまえて書かれた『恋愛論』(22,解説後出)は,単に恋愛に関する〈イデオロジー〉的分析の書ではなく,メチルドへの私的告白の様相をも呈している。メチルドは求愛を拒み続け,彼は何度も死を思うほど絶望に陥った。加えて,著作の不穏当な字句や自由主義者との交際などからオーストリア官憲ににらまれるという事態も生じ,21年6月,やむなく彼はミラーノを去った。再会の機はついになく,メチルドは25年に病没する。しかし,スタンダールはとうに自身の墓碑銘を選んでいた——「アッリゴ・ベーレ,ミラーノ人……」。
ミラーノ人ベーレは,祖国にあって異邦人でしかない。絶望をおし隠すため,彼は努めて陽気を装い,辛辣(しんらつ)な才気で人々を煙に巻く。定職もなく,
長い不遇ののち,30年の七月革命は彼に領事職をもたらした。前後して出版した『赤と黒』(30,解説後出)は長編小説の第2作であり,彼の代表作と目されるが,当時は
1831年からその死に至るまで,スタンダールはローマの外港チヴィタヴェッキア駐在のフランス領事の職にとどまった。領事は職務にはなはだ不熱心だった。折さえあればローマの社交界に顔を出し,狩猟や遺跡発掘,あるいはイタリア語古文書の蒐集(しゆうしゆう)などに鬱屈(うつくつ)を紛らわす。が,最大の慰めは,やはり〈書く〉ことにあった。すでに五十の坂にさしかかったベールは自問する。自分は何ものか? 何ものであったか? こうして彼は自伝の筆を執る。われわれに遺(のこ)されたものは,21年ごろのパリ生活を回顧した『エゴチスムの回想』Souvenirs d'égotisme(32執筆,1892没後刊),幼少年期を語った『アンリ・ブリュラールの生涯』(35−36執筆,1890没後刊,解説後出)である。いずれも未完の草稿だが,スタンダールという人物を知るための鍵となる証言を多々含む貴重な資料である。この2つの自伝に挟まれて未完の長編『リュシヤン・ルーヴェン』(34−35執筆,1894没後刊,解説後出)が位置する。これは旧知の某夫人の『中尉』Le Lieutenantと題する小説原稿がヒントになって書かれた作品で,詳しくは〈解説〉に譲るが,槍騎兵(そうきへい)少尉リュシヤンも,『赤と黒』のジュリヤン,『パルムの僧院』のファブリスと同様,作者の分身であることに変わりはない。しかし,さまざまな事情が重なって,この作品は結局未完に終わった。
領事は再び鬱屈する。「太陽はもうたっぷり見た!」。今や彼にとって必要なのは,「汽船に石炭が必要なように,日に3,4立方フィートの新しい思想(イデー)」なのである。36年,庇護(ひご)者,外相モレの好意により,スタンダールは実に3年もの長期休暇を得てパリに帰る。このフランス滞在は,滋味あふれるフランス漫遊記『ある旅行者の手記』Mémoires d'un touriste(38)を副産物として生むことになるが,この時期,小説の創作はそれにも増して多産だった。37~39年にかけて,スタンダールは,後年『イタリア年代記』(解説後出)の総称を与えられる短編群を続々と発表しているが,いずれも往古のイタリア人の精力(エネルジー)を称(たた)える激しい物語である。この作品群の延長線上に,生涯の傑作『パルムの僧院』(39,解説後出)が位する。古文書『ファルネーゼ家隆盛の起源』をもとに短編を書く計画が突如変更されてこの長編が生まれたのは,われわれの幸福と言わねばなるまい。のちに教皇パウルス3世となる青年アレッサンドロ・ファルネーゼの物語は,19世紀初頭のイタリア貴族の息子ファブリス・デル・ドンゴの物語に換骨奪胎される。ナポレオンにあこがれるファブリスは,スタンダールの生んだ〈息子たち〉のうちの末子である。作者はそれにふさわしい愛情を主人公に注いだ。魂の故郷イタリアという枠を得て,彼の想像力はかつてない昂揚(こうよう)をみせ,この長編はわずか50余日の口述筆記によって成った。
1839年,チヴィタヴェッキアに帰任したのちも創作欲は衰えず,長編『ラミエル』Lamiel(1889没後刊)に着手する。従来とはやや作風を変えた一編をものしようとの意図をもっていたようだが,他の長編と違って〈下敷き〉がなかったせいか,スタンダールの筆は思うように伸びず,結局この〈スカートをはいたジュリヤン・ソレル〉の物語は未完に終わった。
このころから,スタンダールの健康は急速に悪化する。若いころの放蕩がたたったものか,激しい偏頭痛に悩まされたり,一時的に失語症に陥ったりしている。〈愛する〉男スタンダールにとって,40年に彼の心をとらえたアーライン(おそらくチーニ伯爵夫人の偽名)は,老境にかいま見た最後の恋の幻影だったろう。
任地で病苦と倦怠(けんたい)に悩まされている老領事にとって大きな慰めは,40年バルザックが雑誌に発表した『パルムの僧院』への賛辞だった。「各ページに崇高が輝く」という絶賛は,スタンダールが生前に受けた最大の,そしてほとんど唯一の称賛と言っていい。41年3月,最初の脳卒中の発作。「虚無と襟首をつかみ合いました」と,後日友人に書き送る。それでも,同年11月,3度目の,そして最後の賜暇を得て,パリへ帰った。静養ののち,翌年3月には『ラミエル』の草稿に手を入れたり,『イタリア年代記』のうちの1編に着手するなど,〈書く〉意欲は依然衰えをみせていないが,健康はもはや完全に蝕(むしば)まれていた。3月22日の夕方,パリの街頭で,脳出血の発作に襲われて昏倒(こんとう),意識を回復せぬまま翌未明没した。
小説家スタンダールの功績は,近代小説における
ところで,小説中の特権的なレンズにほかならぬ主人公たちを,彼はどのように設定したか。言うまでもなく,自己の分身としてである。その意味では,スタンダールの主人公たちはいずれも作者と等身大の存在であり,互いによく似通った人物たちである。スタンダールは生涯にただ一種類の小説を書いた作家だ,と言われることがあるが,たしかに彼の三大長編小説は,いずれも青年主人公(ジュリヤン,リュシヤン,ファブリス)の社会への登場とその教育の物語であるという意味で軌を一にしているし,優れた資質をうけた純潔な青年が,世間の麈(ちり)にまみれつつも,結局は外界と同化し得ない自己の本性を苦渋のうちに再確認するという基本構造においても,また,主人公をめぐる2人の,そして2種類の女性(レナール夫人とマチルド,シャストレール夫人とグランデ夫人,クレリアとサンセヴェリーナ夫人),あるいは,青年主人公を,ときに皮肉にときにひそかな愛情をこめて見守る年配の保護者(ラ・モール侯爵,父ルーヴェン,モスカ伯爵)という人物配置においても,同一のパターンが踏襲されていると言っていい。性的不能者オクターヴや,ジュリヤンの女性版を目指したかに見えるラミエルの場合には,かなりの留保が必要だろうが,それでも若き主人公の挫折というテーマについては一貫している。
スタンダールの主人公たちは作者の理想化された姿だ,というのもかなり流布した説であるが,これには多少の検討を加える要があろう。たしかに,主人公の才能や肉体的美点については〈理想化〉を云々できようが,ひるがえって彼らの内面の葛藤(かつとう)なり,行動の軌跡なりを検討してみるに,作者自身の内面の矛盾や,常に冷静と明敏を志しながら感性の発作に足をすくわれるという失敗のパターンは,作中人物においてなんら緩和されてはいない。むしろ筋の進行は,多く主人公の失敗に原動力を負うているとすら言える。作者は,主人公の失敗を通じて,かつての自己の失敗を分析することに皮肉な快楽を味わういっぽうで,失敗せざるを得なかった自己の本性を確認し,また容認する契機をも見いだす。理想化されたのは,実は自己認識のための視点にほかならない。不惑の年を越えた作者が青年主人公のうちに投影された自己を分析する——作品中におけるこの作者の奇妙な二重生活こそ,スタンダールの多くの小説に共通する構成の秘密である。作者が〈若き主人公の社会へのデビュー〉というテーマを飽かず繰り返したゆえんであろう。主人公への揶揄(やゆ)ないしは注釈という形で頻用される〈作者介入〉の技法,前言した内的独白の多用,人物の〈驚き〉をなぞるように鋭角的な屈折を重ねる跳躍的文体,原因ぬきに結果を述べ,あるいは逆に結果を全く言い落とす,しかし心理的には極めてリアルな叙述法。スタンダールは実にさまざまの〈非連続〉によってその小説を構築してゆく。
発想と手法の斬新(ざんしん)さによって生前多くの理解は得られなかったが,まさにその故に,自ら予言したとおり,死後50年,100年を経て,彼の作品はますます多くの読者を獲得していった。