1. 宇津保物語
世界大百科事典
平安中期(10世紀末)の作り物語。作者は古来の源順(みなもとのしたごう)説が有力。〈うつほ〉には〈洞〉〈空穂〉をあてることがある。初巻に見える樹の空洞に基づくも ...
2. うつほものがたり【宇津保物語】
デジタル大辞泉
《「うつぼものがたり」とも》平安中期の物語。20巻。作者未詳。源順(みなもとのしたごう)とする説もある。村上天皇のころから円融天皇のころに成立か。4代にわたる琴 ...
3. うつほものがたり【宇津保物語】
国史大辞典
活字本では『宇津保物語―本文と索引―』(前田家本の翻刻)、『角川文庫』(浜田本を底本に校注)、『校注古典叢書』(前田家本を底本に校注)のものがよい。 [参考文献 ...
4. うつぼものがたり【宇津保物語】
日本国語大辞典
(「うつほものがたり」とも。「うつほ」は空洞の意で仲忠母子が杉の空洞にひそんでいたことにちなむ)平安中期の物語。二〇巻。作者未詳。源順作とする説などがある。十世 ...
5. うつぼものがたり【宇津保物語】
全文全訳古語辞典
[書名]平安中期の物語。作者未詳。一説に源順が作者とも。俊蔭・俊蔭の娘・仲忠・犬宮の四代にわたる琴の名手の家系を中心とした長編物語。『竹取物語』的な伝奇的・空想 ...
6. うつほ物語
日本大百科全書
平安時代の物語。題名は首巻の「俊蔭(としかげ)」の巻で、主人公の仲忠(なかただ)が母と杉の洞穴(うつほ)で生活したことによる。従来「宇津保(うつぼ)」と書かれて ...
7. あい‐いたわ・る[あひいたはる]【相労】
日本国語大辞典
(「あい」は接頭語)【一】〔他ラ四〕目を掛けてやる。ねぎらう。*宇津保物語〔970〜999頃〕沖つ白浪「一日おとどにとり申ししかば『あひいたはらんと思ふ心やある ...
8. あい‐ぎょう[‥ギャウ]【愛敬】
日本国語大辞典
顔かたちが、にこやかでかわいらしいこと。愛らしく、優しい感じがすること。魅力があること。*宇津保物語〔970〜999頃〕楼上上「見奉り給へば、大将の児(ちご)な ...
9. あいぎょう こぼる
日本国語大辞典
顔つき、姿、言動などに愛らしい魅力があふれる。たいへん愛らしく慕わしい。*宇津保物語〔970〜999頃〕楼上上「いとうれしとおぼして笑み給へる、いと花やかに見ま ...
10. あい‐さだ・める[あひ‥]【相定】
日本国語大辞典
あひさだ・む〔他マ下二〕(「あい」は接頭語)(1)互いに相談して決める。相談し合う。*宇津保物語〔970〜999頃〕国譲下「臣下ども御あなすゑにて、やんごとなく ...
11. あい‐し【愛子】
日本国語大辞典
愛子

」*
宇津保物語〔970〜999頃〕俊蔭「父母があいしとして、一生にひとり子なり」*保元物語〔1220頃か〕
...12. あい‐つ・ぐ[あひ‥]【相次・相継】
日本国語大辞典
追う。あいつづく。*観智院本三宝絵〔984〕中「其寺いまにあひつきてさかゆる事いまにたえず」*宇津保物語〔970〜999頃〕国譲下「二人は大殿大臣のむすめなり。 ...
13. あいな‐だのめ【─頼】
日本国語大辞典
)むだな期待を人に抱かせること。あてにならないことを頼みにさせること。また、法外な期待。*宇津保物語〔970〜999頃〕国譲上「この三条といふ所は、又きゃうにも ...
14. あい‐ぬすびと[あひ‥]【相盗人】
日本国語大辞典
〔名〕共謀した盗賊同士。ひそかに密事を示し合わせている仲間。*宇津保物語〔970〜999頃〕内侍督「『あはれ、ならはぬ御心ちもおもほさるらん。それをなむ、ただい ...
15. あい‐むか・う[あひむかふ]【相向】
日本国語大辞典
〔自ハ四〕(「あい」は接頭語)互いに向かい合っている。向かい合う。*宇津保物語〔970〜999頃〕俊蔭「汝不孝の子ならば、親にながき嘆きあらせよ。孝の子ならば、 ...
16. あう‐て
日本国語大辞典
〔名〕「あいて(相手)」に同じ。*宇津保物語〔970〜999頃〕内侍督「いで、なにかは、あふてにしなし給はば」 ...
17. あえ なむ
日本国語大辞典
未然形「な」と、推量の助動詞「む」の付いた語)がまんできるだろう。差しつかえないだろう。*宇津保物語〔970〜999頃〕蔵開下「あしかるべくは、よかれと思ふとも ...
18. あえ‐もの[あへ‥]【和物】
日本国語大辞典
反 訓安不一云阿倍毛乃〉擣薑蒜以醋和之」*宇津保物語〔970〜999頃〕あて宮「よきくだ物、酒殿の大御酒など召して、〈略〉あへものにとてなどのた ...
19. あえ‐もの【肖物】
日本国語大辞典
〈略〉わが昔よりようずるを、あえものに、けふばかりつけよと、おほせられてたまへりしかば」*宇津保物語〔970〜999頃〕あて宮「いとうらやましげなる人々にあへも ...
20. あお[アヲ]【襖】
日本国語大辞典
が」(2)(狩襖(かりあお)ともいったため、「狩」が省略されて)狩衣(かりぎぬ)のこと。*宇津保物語〔970〜999頃〕国譲下「中納言は赤色の織物のあを、にびの ...
21. あお・い[あをい]【青】
日本国語大辞典
置きてそ歎く〈額田王〉」*彌勒上生経賛平安初期点〔850頃〕「瑠璃といふは、碧(アヲキ)色なり」*宇津保物語〔970〜999頃〕俊蔭「鳥、けだものだに見えぬ渚に ...
22. あおい‐かつら[あふひ‥]【葵鬘・葵桂】
日本国語大辞典
葵が二葉なので、諸葉草ともいう。雷の災いを免れるまじないともした(日次紀事{1685})。《季・夏》*宇津保物語〔970〜999頃〕楼上下「四月まつりの日、あふ ...
23. あおいろ の 上(うえ)の衣(きぬ)
日本国語大辞典
「あおいろ(青色)の袍(ほう)」に同じ。*宇津保物語〔970〜999頃〕菊の宴「わらは四人あをいろのうへのきぬ、やなぎがさねきたり」*源氏物語〔1001〜14頃 ...
24. あお‐がみ[あを‥]【青紙】
日本国語大辞典
〔名〕(1)薄青に染めた紙。*宇津保物語〔970〜999頃〕あて宮「あをきすきばこにみちのく紙、あをがみなどつみていだし給へり」*内局柱礎抄〔1496〜98〕上 ...
25. あお‐くさ[あを‥]【青草】
日本国語大辞典
訓)「素戔嗚尊、青草(アヲクサ)を結(ゆ)ひ束(つか)ねて、笠(かさ)蓑(みの)と為て」*宇津保物語〔970〜999頃〕国譲下「北方は、あをくさの色になりて、〈 ...
26. あお‐くちば[あを‥]【青朽葉】
日本国語大辞典
また、表は黄みのある薄萠葱(うすもえぎ)、裏は黒みのある青丹(あおに)ともいう(雁衣抄)。*宇津保物語〔970〜999頃〕祭の使「あなたの北の方よりはじめたてま ...
27. あお‐し[アヲ‥]【襖子】
日本国語大辞典
乎之〉」(2)童女の着る汗衫(かざみ)に似た服。狩襖(かりあお)より転じたものであろう。*宇津保物語〔970〜999頃〕春日詣「よき童四人、あをし、あはせの袴、 ...
28. あお‐じ[あを‥]【青瓷】
日本国語大辞典
〔名〕(1)銅を呈色剤とした緑色の釉(うわぐすり)を表面にかけた陶器。緑釉陶器。*宇津保物語〔970〜999頃〕楼上上「檜皮(ひはだ)をばふかで、あをじの濃き薄 ...
29. あお‐つづら[あを‥]【青葛】
日本国語大辞典
かづら〈和名鈔〉予州、あをつづら つづらかづら つづらふぢ」(2)植物「つづらふじ(葛藤)」の異名。*宇津保物語〔970〜999頃〕俊蔭「あおつづらを大なる籠に ...
30. あお‐つゆくさ[あを‥]【青露草】
日本国語大辞典
〔名〕露草のこと。*宇津保物語〔970〜999頃〕国譲下「雑色六人、装束、白きろうのさしぬき、あを露くさしてらうずりに摺りて、白きあやの袿(うちき)」 ...
31. あお‐に[あを‥]【青丹】
日本国語大辞典
表裏ともに、濃い青に黄を加えた色のもの。または、表は赤みの多い茶色で、裏は薄い青色のもの。*宇津保物語〔970〜999頃〕春日詣「装束は、大人は青色の唐衣、〈略 ...
32. あお‐にび[あを‥]【青鈍】
日本国語大辞典
〈花田濃色也。尼など用色と云〉」(2)襲(かさね)の色目の名。表裏ともに、濃いはなだ色。*宇津保物語〔970〜999頃〕蔵開上「四の宮、赤らかなる綾掻練(あやか ...
33. あお‐ばえ[あをばへ]【青蠅】
日本国語大辞典
からだが青黒く、腹に光沢のある大形のものの総称。あおばい。くろばえ。くろるりばえ。《季・夏》*宇津保物語〔970〜999頃〕国譲下「恋ひ悲しび、待ち居て、あをば ...
34. あおみ‐ずり[あをみ‥]【青味摺】
日本国語大辞典
〔名〕衣服の染色の一種。山藍(やまあい)で模様を摺って染めたもの。青く摺り染めにした衣料にもいう。*宇津保物語〔970〜999頃〕菊の宴「御供の人、青丹に柳がさ ...
35. あおみ‐や・す[あをみ‥]【青痩】
日本国語大辞典
〔自サ下二〕顔色などが青くなって、やせ衰える。憔悴(しょうすい)する。青みおとろう。*宇津保物語〔970〜999頃〕祭の使「尻切れの尻の破(や)れたる穿きて、け ...
36. あお・む[あをむ]【青】
日本国語大辞典
アヲ)める玻璃のうつはより初秋きたりきりぎりす鳴く」(2)顔色が青ざめる。血の気が引く。*宇津保物語〔970〜999頃〕蔵開上「すこしあをみ給へれど、いとあてに ...
37. あか・い【赤】
日本国語大辞典
杉天外〉二「二人とも顔を赧(アカ)くしてるのに気が着くと」(2)赤みを帯びた茶色である。*宇津保物語〔970〜999頃〕吹上上「少将にくろかげのむま、たけななき ...
38. あか‐いろ【赤色】
日本国語大辞典
宮記等〕。経は蘇芳(すおう)、緯は紫〔服飾管見等〕。経は紫、緯は赤〔胡曹抄・装束抄等〕。*宇津保物語〔970〜999頃〕国譲下「中納言は、あかいろの織物の襖(あ ...
39. あかき 粥(かゆ)
日本国語大辞典
「あか(赤)の粥(かゆ)」に同じ。*宇津保物語〔970〜999頃〕蔵開上「白き御粥一桶、あかき御かゆ一桶」*御湯殿上日記‐天正九年〔1581〕一一月一八日「なか ...
40. 明石(源氏物語) 235ページ
日本古典文学全集
。良清が以前報告したとおりに。→若紫[1]二〇三ページ。入道の豪勢な生活ぶりは、先例たる『宇津保物語』吹上上巻の神南備種松に比すれば、はるかにつつましく現実的で ...
41. あかし‐か・ねる【明兼】
日本国語大辞典
公鳥(ほととぎす)来鳴く五月の短夜もひとりしぬれば明不得(あかしかねつ)も〈作者未詳〉」*宇津保物語〔970〜999頃〕蔵開下「ちかくてもみぬまもおほくありしか ...
42. あか‐ば・む【赤─】
日本国語大辞典
〔自マ五(四)〕赤みを帯びる。赤らむ。*宇津保物語〔970〜999頃〕蔵開中「柑子を見給へば、あかばみたる色紙に、書きて入れたり」*西洋道中膝栗毛〔1870〜7 ...
43. あか・む【赤】
日本国語大辞典
また、赤茶ける。*日本書紀〔720〕皇極元年五月(図書寮本訓)「熟(アカメル)稲始めて見ゆ」*宇津保物語〔970〜999頃〕嵯峨院「九の君、おもてはあかみて、う ...
44. あから‐か【赤─】
日本国語大辞典
平安初期点〔850頃〕「世尊の唇の色は、光り潤ひ丹(アカラカ)に暉れること頻婆菓の如し」*宇津保物語〔970〜999頃〕国譲下「あからかなる綾かいねりのひとかさ ...
45. あから‐さま
日本国語大辞典
「あからさまにも」の下に打消の語を伴って、「かりそめにも…しない。全く…しない」の意となることもある。*宇津保物語〔970〜999頃〕俊蔭「あからさまの御ともに ...
46. あから

し
日本国語大辞典
懇(アカラシキ)かな、我が大師聊かに何か過失有りて、此の賊難を蒙る〈国会図書館本訓釈 懇 アカラシキ〉」*宇津保物語〔970〜999頃〕吹上下「おもひいづるなん ...
47. あから‐め
日本国語大辞典
(「あからめもせず」の形で用いることが多い)ふと目をほかへそらすこと。わき見をすること。*宇津保物語〔970〜999頃〕蔵開中「宮の御うしろにさぶらふほどに、御 ...
48. あか・る【散・別】
日本国語大辞典
日記〔974頃〕下・天祿三年「『火しめりぬめり』とてあかれぬれば、いりてうちふすほどに」*宇津保物語〔970〜999頃〕俊蔭「いとまたびて、みな十、二十人とあか ...
49. あ‐が‐きみ【吾君】
日本国語大辞典
*万葉集〔8C後〕一九・四一六九「松柏(まつかへ)の 栄えいまさね 尊き安我吉美(アガキミ)〈大伴家持〉」*宇津保物語〔970〜999頃〕菊の宴「あなゆゆしや。 ...
50. あ‐が・く【足掻】
日本国語大辞典
やれといふと心得て、五六町こそあがかせたれ」(2)手足をじたばたする。また、手足を動かしてもがく。*宇津保物語〔970〜999頃〕国譲上「思すやうに、平かにてと ...

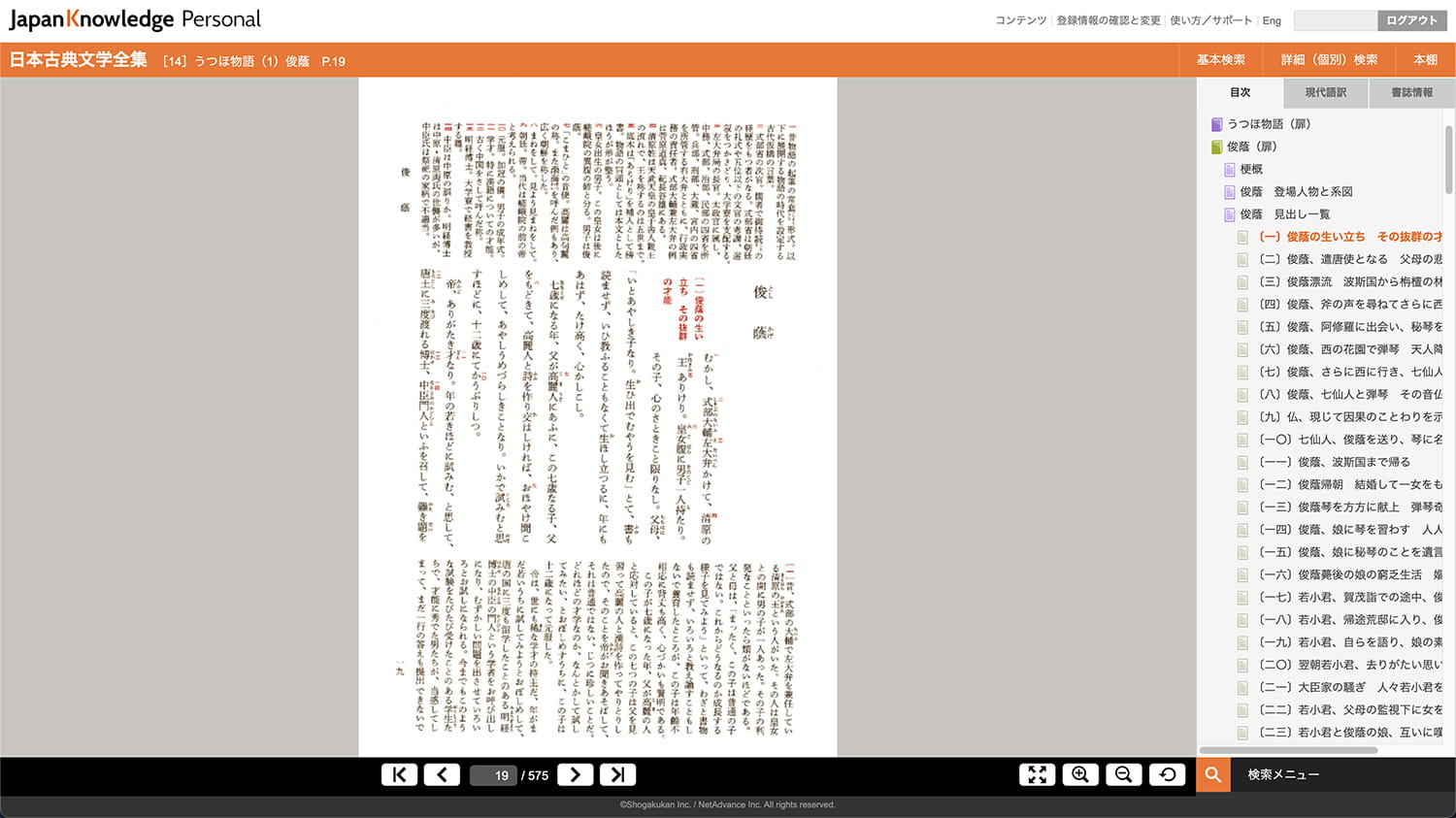
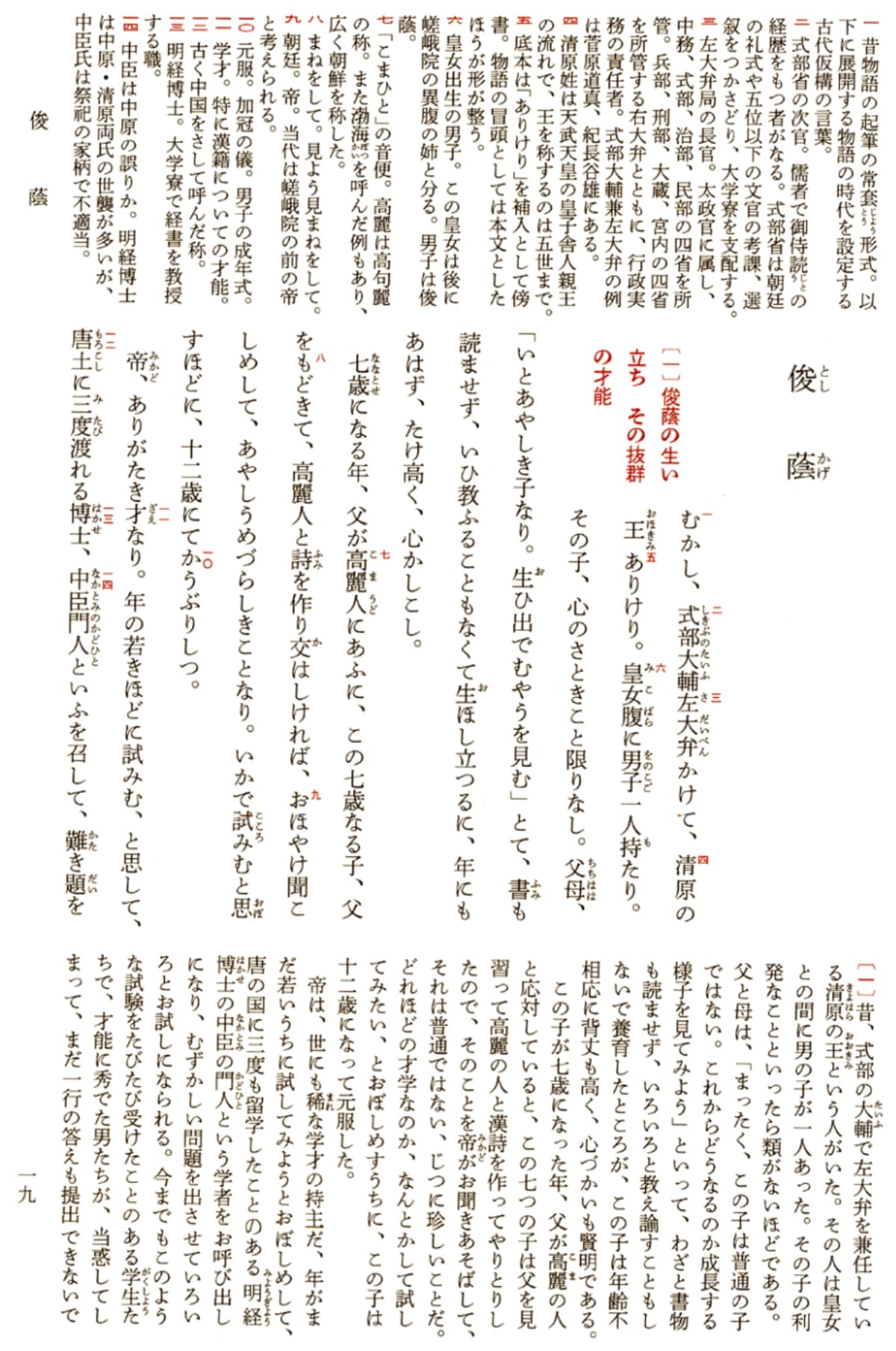


 」*宇津保物語〔970〜999頃〕俊蔭「父母があいしとして、一生にひとり子なり」*保元物語〔1220頃か〕 ...
」*宇津保物語〔970〜999頃〕俊蔭「父母があいしとして、一生にひとり子なり」*保元物語〔1220頃か〕 ... し
し








