俳人目安帖
俳人・中村裕氏による連載エッセイ。毎回、著名な俳人がその作品中で多用した単語、特に好んだ言葉や場面などを取り上げ、俳句の鑑賞を通じて作者の心中や性向を探ります。
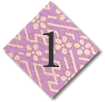 子規、柿喰らう~正岡子規~
子規、柿喰らう~正岡子規~
子規の随筆はどれも面白いが、病床についてからの『墨汁一滴』や『病床六尺』が最も一般に知られたものだろう。これらを「日本」紙上に発表していた頃、同時進行のかたちで、公開するつもりのない『仰臥漫録』という日録も書き継いでいた。「仰臥」とは仰向けの状態でということで、その不自由な姿勢で、綴じた半紙に毛筆で記した。内容は日々の出来事や俳句、気ままに描いた水彩画などだが、なんといっても異様なのは、めんめんと綴られた毎日の食事の献立。たとえば明治三十四年九月三十日の冒頭には次のようにある。
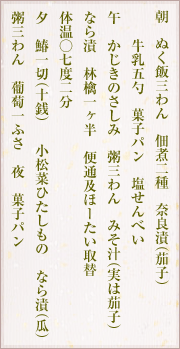
このような記述がほぼ例外なく、毎日続く。その頃の子規の状態はというと、「穴が凡てゞ八つも開いて腰のあたりが蜘蛛の巣のやうになる。其穴の口が爛れて皮がとれる。胃がわるくなつて食物がまづくなる。肛門の筋肉がいふ事をきかぬ。頭がもやもやする。歯が折れる。齦〈はぐき〉が化膿をする。眼が痛くなる。満足なのは頭の毛と踵の皮といふやうになつて」(河東碧梧桐)といったありさまで、結核性カリエスによって全身ボロボロになっていたのである。当然、食べれば悶絶の苦しみを味わうことになる。結核は食事が大切な養生法であるにしても、重病人にしてこの食欲は常軌を逸している。前日の29日には「死ぬるまでにもう一度本膳で御馳走が食ふてみたいなどといふて見たところで今では誰も取りあはないから困つてしまう もしこれでもう半年の命といふことにでもなつたら足のだるいときには十分按摩してもらふて食ひたいときには本膳でも何でも望み通りに食はせてもらふて〈略〉何でも彼でも言ふほどの者が畳の縁から湧いて出るといふやうにしてもらふ事が出来るかも知れない」と書く。このとどまることを知らないあさましいといってもいいほどの食欲は、いったいどこからくるのだろうか。
明治28年、子規は周囲の反対を押し切って、日清戦争に記者として従軍する。しかしはかばかしい成果は得られず、おまけに帰国の船中で喀血。そのため神戸、須磨で療養してから、松山に帰郷し、漱石の下宿に移る。そこで二ヶ月ほど滞在してから帰京するのであるが、その途中、大阪、奈良に遊んで、彼の句としては最も知られた次の句をつくるのである。
- 柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺
「法隆寺の茶店に憩ひて」と前書があるが、この鐘は実際には東大寺のもので、法隆寺としたのはあくまで子規の演出である。しかしこの演出は見事に決まった。あまりにも人口に膾炙してしまったので、今では凡庸とさえ感じさせる句だが、改めて冷静に読めばやはり非凡といわざるを得ない名句である。
- 柿落ちて犬吠ゆる奈良の横町かな
- 渋柿やあら壁つづく奈良の町
これらも同時につくられた句で、奈良や法隆寺と柿との取合せは、よほど本人も気に入ったらしい。「柿などというものは従来詩人にも歌よみにも見離されておるもので、殊に奈良に柿を配合するというような事は思いもよらなかった事である。余はこの新たらしい配合を見つけ出して非常に嬉しかった」(「御所柿を食いし事」)と書いているように、柿は用材や貴重な甘味として用途の多い木(や実)のわりには卑近なものと考えられ、和歌などに取り上げられることは稀だった。柿渋で染めた衣服は、身分の低い人々、社会の底辺に生きる人々によく着られたというのも、その反映だろう。そのような存在を俳句の対象になし得たことに手放しに子規は喜んでいるのである。そんな子規にとって、この古寺の鐘の音は俳句の神様からのご褒美の鐘の音のように聞こえたかもしれない。
旧弊な美意識を脱した新しい時代の俳句に、短い生涯を捧げた子規にとって、この「柿くへば」の句は、案外に重い意味を持っているのである。その尋常ではない食欲が肉体的存在としての自己への果敢な挑戦だとすれば、俳句革新を掲げ、旧弊な俳句に挑みかかっていくその姿勢も尋常でないといえば尋常ではない。この二つのベクトルの幸福な一致点に立つのが、この句といえるのではないだろうか。
二年後に「三千の俳句を閲〈けみ〉し柿二つ」、明治34年に「柿くふも今年ばかりと思ひけり」をつくり、その翌年、柿が出まわるにはまだ少し早い9月19日に不帰の客となるのである。
2004-10-12 公開



