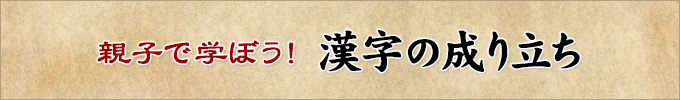
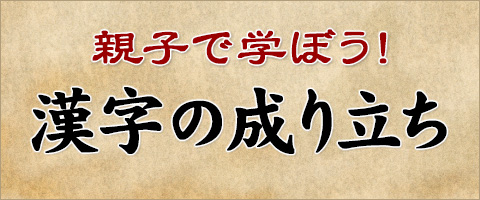
第5回  (さい)(載書(さいしょ))について(1)
(さい)(載書(さいしょ))について(1)
 (さい)
(さい)「口(こう)」のつく漢字は、日本で一番大きな漢和辞典である『大漢和辞典』(大修館書店)の「口」の部に1,447字あります。しかし、この中には「くち」という意味だけでは字の成り立ちが説明できなかったり、矛盾が生まれるものが多いことが知られていました。
例えば、教科書や漢和辞典が基にしてきた、今からおよそ1,900年前にできた許慎(きょしん)の『説文解字(せつもんかいじ)』では、「告(こく)」は「牛が人に何かを訴えるために口をすり寄せているのである」とされ、「名」は「夕べになると暗いので口で名のる形である」と説明されています。しかし、牛は口で人に訴えるというようなことはしませんし、名のるときには顔が見えなくなる夕べだけでなく、明るい日中でも口で名のるのです。この説明がおかしいのはすぐにわかることでしょう。
この問題に終止符を打ったのが、白川静先生による「
 」(さい)の発見でした。これまで単に「くち」として解釈していたものの多くは、実は「祝詞(のりと:人が神に願いごとをするために書いた文)を入れる器の形」であることを解明したのです。この発見により、疑問が持たれていた多くの漢字の成り立ちや新しい文字の系列が明らかになりました。それだけでなく、漢字を生む背景になった3千年以上も前の中国古代の人々の生活・習俗・文化までが、私たちの目の前に姿を現してきたのです。今からおよそ3千300年前の漢字が生まれたころ、人々は自然に対して今よりもっともっと畏(おそ)れと感謝の気持ちを抱いて生活をしていました。大自然の前では人は無力で、為(うなが)す術(すべ)もありませんでした。そのようなときに、自然界のあらゆるものには神が宿っていると信じたのは当然のことでしょう。
」(さい)の発見でした。これまで単に「くち」として解釈していたものの多くは、実は「祝詞(のりと:人が神に願いごとをするために書いた文)を入れる器の形」であることを解明したのです。この発見により、疑問が持たれていた多くの漢字の成り立ちや新しい文字の系列が明らかになりました。それだけでなく、漢字を生む背景になった3千年以上も前の中国古代の人々の生活・習俗・文化までが、私たちの目の前に姿を現してきたのです。今からおよそ3千300年前の漢字が生まれたころ、人々は自然に対して今よりもっともっと畏(おそ)れと感謝の気持ちを抱いて生活をしていました。大自然の前では人は無力で、為(うなが)す術(すべ)もありませんでした。そのようなときに、自然界のあらゆるものには神が宿っていると信じたのは当然のことでしょう。「神(しん)」という字の最初の形は「申(しん)」で、稲光が走る形を写している字であることがそれを証明しています。当時の人々は稲光を神の姿とみたのです。そして、このような自然をつかさどる神にお伺(うかが)いをたてて自分の行動を決定していたのです。すなわち、そのように漢字は、神と人間が交流する神聖な祀(まつ)りの場で生まれたことや、その重要な祀りの器として「
 」が使われたことがわかったのです。これはまさに文字学における偉大な発見と言えます。口を含む漢字の古・可・史・召・右・各・吉・向・名・君・吾・告・呈・言・舎・命・和・害・啓・問・善などは、その口を口(くち)と解釈したのでは字の成り立ちや意味を解くことはできません。口を
」が使われたことがわかったのです。これはまさに文字学における偉大な発見と言えます。口を含む漢字の古・可・史・召・右・各・吉・向・名・君・吾・告・呈・言・舎・命・和・害・啓・問・善などは、その口を口(くち)と解釈したのでは字の成り立ちや意味を解くことはできません。口を (祝詞を入れる器の形)と解釈することによってはじめてそれぞれの文字の成り立ちと意味を、無理なく、また体系だって明らかにすることができるのです。そして『説文解字』の説明の誤りも正しく改めました。
(祝詞を入れる器の形)と解釈することによってはじめてそれぞれの文字の成り立ちと意味を、無理なく、また体系だって明らかにすることができるのです。そして『説文解字』の説明の誤りも正しく改めました。では、「
 」をどうして「サイ」と読むのでしょうか。それは誓いの文書を古い時代に載書(さいしょ)といったので、その文書を入れる器である
」をどうして「サイ」と読むのでしょうか。それは誓いの文書を古い時代に載書(さいしょ)といったので、その文書を入れる器である を「サイ」と読むのです。
を「サイ」と読むのです。● 日本文字文化機構文字文化研究所 認定教本より
ここで紹介している日本文字文化機構文字文化研究所編集の教本は、最高峰の漢字辞典『字通』に結実した白川静文字研究の成果をもとに、漢字の成り立ちをわかりやすく解説した学習コラムです。白川静『字通』のオンライン検索サービスは、基本検索ならびに詳細(個別)検索でご利用いただけます。
コンテンツの概要については以下をご覧ください。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。
日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。
(2024年5月時点)
- 第6回 載書について(2)
- 第7回 載書について(3)
- 第8回 載書について(4)
- 第9回 載書について(5)
- 第10回 人の形から生まれた文字〔1〕
人を横から見た形(1) - 第11回 人の形から生まれた文字〔1〕
人を横から見た形(2) - 第12回 人の形から生まれた文字〔1〕
人を横から見た形(3) - 第13回 人の形から生まれた文字〔1〕
人を横から見た形(4) - 第14回 人の形から生まれた文字〔2〕
人を前から見た形 - 第15回 人の形から生まれた文字〔3〕
体の部分~顔を中心に(1) - 第16回 人の形から生まれた文字〔3〕
体の部分~顔を中心に(2) - 第17回 人の形から生まれた文字〔4〕
体の部分~手と足(1) - 第18回 人の形から生まれた文字〔4〕
体の部分~手と足(2) - 第19回 人の形から生まれた文字〔4〕
体の部分~手と足(3) - 第20回 人の形から生まれた文字〔5〕
女の人の姿(1) - 第21回 人の形から生まれた文字〔5〕
女の人の姿(2) - 第22回 人の形から生まれた文字〔5〕
女の人の姿(3)
▼ すべて表示する


