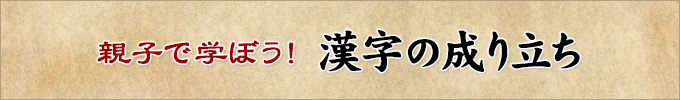
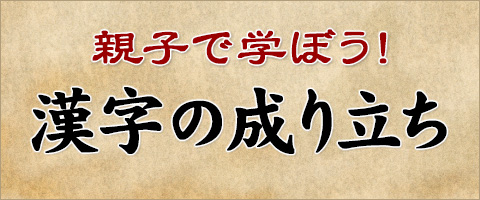
第9回  (さい)(載書(さいしょ))について(5)
(さい)(載書(さいしょ))について(5)
可・哥・歌
『可』
5画(カ・よし・ゆるす)
- 甲骨文字

- 金文


- 篆文

(会意) 口(こう)と (か)とを組み合わせた形。
(か)とを組み合わせた形。
説明 (か)は木の枝の形です。口のもとの形は
(か)は木の枝の形です。口のもとの形は (さい)で、祝詞(のりと:神への祈りの文)を入れる器の形です。神に祝詞をささげて祈り、木の枝で
(さい)で、祝詞(のりと:神への祈りの文)を入れる器の形です。神に祝詞をささげて祈り、木の枝で を殴(う)ちながら願いごとをぜひ実現してほしいと神に訴え、神を責めるのが可の意味です。これにたいして神が願いごとをききいれて、「よし」と許すので、可には「よし、ゆるす(神が許可する)」という意味があります。
を殴(う)ちながら願いごとをぜひ実現してほしいと神に訴え、神を責めるのが可の意味です。これにたいして神が願いごとをききいれて、「よし」と許すので、可には「よし、ゆるす(神が許可する)」という意味があります。
神に強く訴えるときに出す声を、可を重ねて哥(か)といいます。哥は歌(か)のもとの形ですから、歌はもともとは神様に訴える声、祈る声をいうのです。
神に強く訴えるときに出す声を、可を重ねて哥(か)といいます。哥は歌(か)のもとの形ですから、歌はもともとは神様に訴える声、祈る声をいうのです。
用例「可否」(よしあし)・「許可」(許すこと)。
解説白川先生の文字学は、神と人々との密接な関わりをもとに漢字を解読していきます。「可」は祈りを収めた を木の枝で殴ち、大きな声を出しながら祈ることの実現を要求する意味です。
を木の枝で殴ち、大きな声を出しながら祈ることの実現を要求する意味です。 (祝詞)で神様にものをお願いするけれど、なかなか簡単なことでは願い事を叶えてくださらないので、木の枝で
(祝詞)で神様にものをお願いするけれど、なかなか簡単なことでは願い事を叶えてくださらないので、木の枝で (祝詞)を殴って、私の言うこと、願い事を聞け!と叫ぶのです。その時、大体は祈るような節をつけて、自分の願いを許可せよ、実現せよというようにやっているわけで、そこから実現の可能性も生まれてくるわけです。その
(祝詞)を殴って、私の言うこと、願い事を聞け!と叫ぶのです。その時、大体は祈るような節をつけて、自分の願いを許可せよ、実現せよというようにやっているわけで、そこから実現の可能性も生まれてくるわけです。その (可)を重ねると哥となります。これが歌という字のもとの字で、歌というのは楽しんで歌っているのでなく、必死になって神へ向かって「こうせい、こうせい」といってお祈りしているときの声が歌なのです。のちに口を開けて歌っている人の形の欠(けん)(
(可)を重ねると哥となります。これが歌という字のもとの字で、歌というのは楽しんで歌っているのでなく、必死になって神へ向かって「こうせい、こうせい」といってお祈りしているときの声が歌なのです。のちに口を開けて歌っている人の形の欠(けん)( )をつけ加えました。これがいまの歌(うた)という字です。
)をつけ加えました。これがいまの歌(うた)という字です。
『哥』
10画(カ・うた)
- 篆文

(会意)可(か)を上下に組み合わせた形。
説明可(か)は神に祈るとき、その祈りの文を入れた器( )を木の枝で殴(う)ち、願いごとが実現することを責め求める字で、そのとき出す声を哥(か)といいます。哥は神に訴(うっ)たえる声で、歌(か)のもとの形です。
)を木の枝で殴(う)ち、願いごとが実現することを責め求める字で、そのとき出す声を哥(か)といいます。哥は神に訴(うっ)たえる声で、歌(か)のもとの形です。
解説「可」の解説をご参照ください。
『歌』
14画(カ・うたう・うた)小学2年
- 篆文

(形声)音符は哥(か)。
説明哥(か)が歌(か)のもとの形です。哥に、口を開いて立つ人を横から見た形の欠(けん)を加えた字が歌です。歌とは神への祈りの文を入れた器の を木の枝で殴(う)って、祈りの実現を訴えるときに出す声です。
を木の枝で殴(う)って、祈りの実現を訴えるときに出す声です。
用例「歌曲」(かきょく:うた)・「歌舞」(かぶ:うたと舞)。
解説日本語の歌(うた)は、「拍(う)つ、訴(うった)う」と関係があるようです。詠歌(えいか)の詠は、声を長く引く歌いかた、歌は強くせまるような歌いかた、唱(しょう)はみんなで勢いよく合唱する歌いかたです。
● 日本文字文化機構文字文化研究所 認定教本より
ここで紹介している日本文字文化機構文字文化研究所編集の教本は、最高峰の漢字辞典『字通』に結実した白川静文字研究の成果をもとに、漢字の成り立ちをわかりやすく解説した学習コラムです。白川静『字通』のオンライン検索サービスは、基本検索ならびに詳細(個別)検索でご利用いただけます。
コンテンツの概要については以下をご覧ください。

ジャパンナレッジは約1900冊以上(総額850万円)の膨大な辞書・事典などが使い放題のインターネット辞書・事典サイト。
日本国内のみならず、海外の有名大学から図書館まで、多くの機関で利用されています。
(2024年5月時点)
- 第6回 載書について(2)
- 第7回 載書について(3)
- 第8回 載書について(4)
- 第9回 載書について(5)
- 第10回 人の形から生まれた文字〔1〕
人を横から見た形(1) - 第11回 人の形から生まれた文字〔1〕
人を横から見た形(2) - 第12回 人の形から生まれた文字〔1〕
人を横から見た形(3) - 第13回 人の形から生まれた文字〔1〕
人を横から見た形(4) - 第14回 人の形から生まれた文字〔2〕
人を前から見た形 - 第15回 人の形から生まれた文字〔3〕
体の部分~顔を中心に(1) - 第16回 人の形から生まれた文字〔3〕
体の部分~顔を中心に(2) - 第17回 人の形から生まれた文字〔4〕
体の部分~手と足(1) - 第18回 人の形から生まれた文字〔4〕
体の部分~手と足(2) - 第19回 人の形から生まれた文字〔4〕
体の部分~手と足(3) - 第20回 人の形から生まれた文字〔5〕
女の人の姿(1) - 第21回 人の形から生まれた文字〔5〕
女の人の姿(2) - 第22回 人の形から生まれた文字〔5〕
女の人の姿(3)
▼ すべて表示する


