人物に関連するサンプルページ一覧
オンライン辞書・事典サービス「ジャパンナレッジ」で閲覧することの出来る「人物」に関連するページの一部になります。
ジャパンナレッジは日本最大級のオンライン辞書・事典サービスです。
「国史大辞典」「日本古典文学全集」「日本国語大辞典」「世界大百科事典」「日本大百科全書」など80種類以上の辞書・事典をパソコン、タブレット、スマートフォンで利用できます。
「国史大辞典」「日本古典文学全集」「日本国語大辞典」「世界大百科事典」「日本大百科全書」など80種類以上の辞書・事典をパソコン、タブレット、スマートフォンで利用できます。

小泉八雲(日本近代文学大事典・日本大百科全書・世界大百科事典)
本文:既存随筆家、批評家。イギリス人。のち帰化。ギリシア、アイオニアのリュカディア島生れ。島の名にちなんで命名された。父チャールスはアイルランド系の軍医、母はギリシア人ローザ゠カシマティ。生後一年半、父の西印度諸島赴任によりダブリンへ帰ったが

拾遺往生伝(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)
大江匡房の『続本朝往生伝』のあとをついで、慶滋保胤の『日本往生極楽記』をふくめ、それまでに遺漏のあった異相往生人の行業を集め、後人への結縁・勧進のために三善為康が撰述した往生伝。『日本拾遺往生伝』ともいう。三巻。巻中・下の序によると、はじめは一巻の

三遊亭円朝(日本架空伝承人名事典・日本近代文学大事典・日本大百科全書)
幕末・明治の落語家。本名出淵(いづぶち)次郎吉。父は落語家橘家円太郎。七歳で小円太を名のり初高座。一時、画工を志し歌川国芳に浮世絵を学ぶものの、再び落語家に戻り、二〇歳で三遊亭円朝となる。画技を生かした道具入り正本芝居咄で人気を博したが、師匠二代目

国定忠次(日本架空伝承人名事典・国史大辞典・世界大百科事典)
江戸後期の博徒。忠次(治)郎ともいう。上野国佐位郡国定村の出身。中農以上に属する長岡与五左衛門の長男。二一歳のとき博徒の縄張を譲られて以来博徒の親分となり、一八三四年(天保五)縄張争いから同じ博徒の島村の伊三郎を殺害し、有名となる。四二年賭場の最中に

岸信介(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)
一八九六-昭和時代の政治家。明治二十九年(一八九六)十一月十三日、山口県熊毛郡田布施村の酒造家佐藤秀助の次男として生まれ、のち父の生家(秀助は養子)岸家を継いだ。佐藤栄作は実弟である。大正九年(一九二〇)東京帝国大学法学部を卒業、農商務省に入り
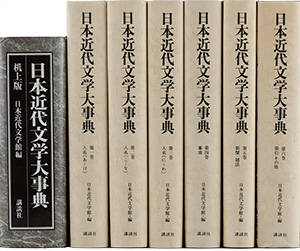
向田 邦子(日本近代文学大事典・日本大百科全書)
本文:新規脚本家・エッセイスト・小説家。東京府荏原郡世田ヶ谷生れ。第一徴兵保険株式会社に勤める父向田敏雄と、母せいの長女として出生。敏雄は仕事柄転勤が多く、家族を伴っての転居を繰り返した(東京、宇都宮、鹿児島、高松、東京、仙台、東京)。1939

紀伊国屋文左衛門(国史大辞典・世界大百科事典)
?-一七三四江戸時代中期の江戸の豪商。略して紀文ともいう。その伝記は詳らかでないが、没年六十六歳といわれるので、寛文九年(一六六九)の生まれか。現在の和歌山県有田郡湯浅町別所の生まれと推定され、はじめ紀州のみかんを江戸に廻漕し、江戸から塩鮭を上方にも

江戸川乱歩(日本大百科全書・世界大百科事典・日本近代文学大事典)
推理作家。本名平井太郎。明治27年10月21日、三重県名張市に生まれる。早稲田(わせだ)大学政経学部卒業。中学生のころに黒岩涙香(るいこう)の『幽霊塔』などの作品に熱中して以来、欧米のミステリーを耽読(たんどく)。ペンネームは彼が傾倒したエドガー

葛飾北斎(日本架空伝承人名事典・世界大百科事典)
江戸後期の浮世絵師。葛飾派の祖。江戸本所割下水(現、東京都墨田区)で生まれた。幼少の頃より好んで絵を描き、版画の技術を学び、勝川春草の門に入って写実的な役者絵、黄表紙などの挿絵を描いた。狩野派を学んだために勝川派から追放され、以後は土佐派・琳派

喜多川歌麿(日本架空伝承人名事典・世界大百科事典)
江戸中・後期の浮世絵師。本姓は北川。生国には諸説がある。幼名は市太郎、のち勇助(勇記とも)。江戸に出て、狩野派の絵師である鳥山石燕に師事し、のちに浮世絵の第一人者となった。初めは北尾重政・鳥居清長ら先輩の作風を学び、修業を重ねた。歌麿の号は

東洲斎写楽(日本架空伝承人名事典・新版 歌舞伎事典・国史大辞典)
江戸時代の浮世絵師。生没年不詳。一七九四年(寛政六)五月から翌九五年一月までの正味一〇カ月間(途中閏月がはさまる)を活躍時期として、役者絵、相撲絵の版画一四〇余図という多くを発表。当時おおいに人気を得たらしいが、その後は浮世絵界との交渉をまったく

二葉亭四迷(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)
一八六四-一九〇九明治時代の小説家。本名長谷川辰之助。元治元年(一八六四)二月二十八日(文久二年(一八六二)十月八日説、元治元年二月三日説もある)、江戸市ヶ谷の尾張藩上屋敷(東京都新宿区、現在陸上自衛隊市谷駐屯地)に生まれた。父は尾張藩士長谷川吉数

ガリレイ(Galileo Galilei)(岩波 世界人名大辞典・デジタル版 集英社世界文学大事典・世界大百科事典・日本大百科全書)
イタリアの物理学者,天文学者.ピサに生まれる.ピサ[1589]およびパドヴァ[92-1616]の各大学数学教授.ピサの聖堂の吊灯を見て振子の等時性を発見した[1583].ピサの斜塔で落体の実験を行い,アリストテレスの自然学の誤りを正し,近代的力学成立
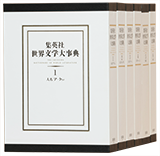
シェークスピア(デジタル版 集英社世界文学大事典・日本大百科全書・世界大百科事典)
イギリスの劇作家,詩人。中部イングランド,ウォリックシャーの小さな町ストラトフォード=アポン=エイヴォンに生まれた。誕生日は4月23日とされるが,それは記録に残る受洗日の4月26日から逆算して,後世がそのように定めたものである。父親ジョンは,近隣の

ジャンヌ・ダルク(日本大百科全書・世界大百科事典・岩波 世界人名大辞典)
15世紀前半、イギリスのランカスター王家が仕掛けてきた戦争(後期百年戦争)の最中、神の命令を受けたと称して現れ、フランスのバロア王家を支援したロレーヌ出身の女。2年後、異端として殺された。今日われわれのみるジャンヌ・ダルクは、国民国家意識の高揚した

始皇帝(世界大百科事典・岩波 世界人名大辞典・日本大百科全書)
中国,秦31代の王(在位,前247-前222),中国最初の皇帝(在位,前222-前210)。姓は嬴(えい),名は政。荘襄王の子。一説では実父は陽翟の大賈である呂不韋とする。荘襄王が人質となって趙に寄寓していたおりに呂不韋は自分の姫妾を荘襄王に献上した

孔子(国史大辞典・岩波 世界人名大辞典・世界大百科事典)
前五五二-四七九中国、春秋時代の学者。儒教の祖。諱は丘、字は仲尼。魯の襄公二十一年(前五五二、または同二十二年ともいう)十月庚子(二十一日)、魯国昌平郷陬邑(すうゆう)に生まれた。父は孔(こつ)、字を叔梁といい、勇士として知られ、母は顔氏の女で徴在と

スターリン(日本大百科全書・世界大百科事典)
本名ジュガシビリДжугашвили/Dzhugashvili。ソ連の政治家。12月21日ジョージア(グルジア)のゴリという町の靴屋の子に生まれる。チフリス(現、ジョージア・トビリシ市)の神学校在学中にマルクス主義の洗礼を受け、職業革命家の道に入った

川端康成(日本大百科全書・世界大百科事典)
小説家。明治32年6月14日、大阪に生まれる。医師の父栄吉、母ゲンの長男。1901年(明治34)父、翌年母が亡くなり、大阪府三島郡豊川村大字宿久庄(しゅくのしょう)(現茨木(いばらき)市宿久庄)で祖父母に育てられた。小学校入学の年祖母、4年のとき姉

上総介広常(日本大百科全書・国史大辞典)
平安末期の武将。平忠常(ただつね)の子孫、常澄(つねずみ)の子。上総権介(ごんのすけ)に任じ、介八郎(すけのはちろう)と称す。その所領は上総国(千葉県中部)から下総(しもうさ)国(千葉県北部)に及び、この地方最大の勢力を誇った。保元(ほうげん)

静御前(日本大百科全書・世界大百科事典・日本架空伝承人名事典)
生没年不詳。源義経(よしつね)の妾(しょう)。磯禅師(いそのぜんじ)の女(むすめ)で、もと京都の白拍子(しらびょうし)であった。義経が京都堀川第(ほりかわだい)で兄頼朝(よりとも)の刺客土佐房昌俊(とさぼうしょうしゅん)に襲われたとき、機転によって

プーチン(岩波 世界人名大辞典)
ロシアの政治家.レニングラード生まれ.祖父はレーニン家など要人の料理人を務めた.レニングラード大学法学部卒業[1975].国家保安委員会(KGB)職員として東ドイツのドレスデンに勤務[80-].その後,サンクトペテルブルク市で大学の恩師ソプチャーク市

菅原道真(日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典)
平安前期の律令(りつりょう)官人。政治家、文人、学者として名が高い。是善(これよし)の子で母は伴(とも)氏。本名は三、幼名を阿呼(あこ)といい、後世菅公(かんこう)と尊称された。従(じゅ)二位右大臣に至る。承和(じょうわ)12年6月25日、父祖三代の

梶原景時(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)
?-一二〇〇 鎌倉時代前期の武将。相模国住人五郎景清の子。通称平三。源頼朝挙兵の時、大庭景親に属したが、石橋山にいき、頼朝の危急を救い、のち頼朝に従って、源義仲追討をはじめ、平家追討に功があった。文治元年(一一八五)屋島攻撃の際、源義経と逆櫓の策を争い

源義仲(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)
一一五四-八四 平安時代後期の武将。木曾義仲・木曾冠者・旭将軍と称される。久寿元年(一一五四)に生まれる。父は春宮帯刀長源義賢、母は遊女と伝える。寿永二年(一一八三)の入洛以前は根本資料を欠き、延慶本・盛衰記・長門本など語り系の『平家物語』によらざるを

源頼家(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典・日本架空伝承人名事典)
一一八二-一二〇四 鎌倉幕府の第二代将軍。一二〇二―〇三在職。源頼朝の長男。母は北条政子。寿永元年(一一八二)鎌倉の比企能員邸に生まれる。幼名は万寿(または十万)。能員妻・河越重頼妻(能員の妹)・梶原景時妻らが乳母となる。頼家の安産を祈って源頼朝は

北条義時(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)
一一六三-一二二四 鎌倉時代前期の第二代執権(一二〇五―二四)。相模守・陸奥守・右京権大夫を歴任、また駿河・伊豆・若狭・越後・大隅・信濃の守護となる。長寛元年(一一六三)北条時政の第二子として生まれる。母は伊東入道女。幼名は江馬四郎・江馬小四郎

平賀源内(日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典)
江戸時代の本草学者(ほんぞうがくしゃ)、戯作者(げさくしゃ)。讃岐(さぬき)の志度浦(香川県さぬき市)の生まれ。幼名を四万吉(よもきち)。伝次郎、嘉次郎といい、名は国倫(くにとも)または国棟(くにむね)。源内(または元内)は通称。字(あざな)は子彝

与謝蕪村(国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典)
一七一六-八三江戸時代中期の俳人・画家。本姓谷口氏。与謝氏(「よざ」とも)を称するのは丹後からの帰洛後。俳号ははじめ宰町・宰鳥、蕪村号は寛保四年(延享元、一七四四)の『歳旦帖』から。代表的画号は宝暦十年(一七六〇)ころから謝長庚・謝春星、安永七年

一茶(日本大百科全書・世界大百科事典)
江戸時代の文化・文政期(1804~30)に活躍した俳諧師(はいかいし)。本名は小林弥太郎。北信濃(きたしなの)の柏原(かしわばら)(北国(ほっこく)街道の宿場町。長野県信濃町)に生まれる。15歳(数え年)で江戸に出たが、晩年は生地に帰住した。父の


