季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
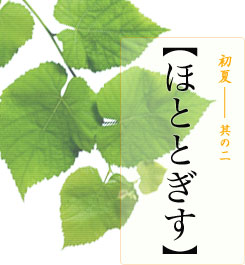
古来、詩歌に詠われてきた代表的な題といえば、雪(冬)、月(秋)、花(春)そしてほととぎす(夏)。最近の都市化で、その声を聞くことはまれになったが、初夏の鶯、秋の雁をしのぐ日本を代表する鳥とされてきた。伝統俳句の牙城である「ホトトギス」がその誌名としたのも故なしとしない。ところが近年はあまりパッとしない。接する機会が減ったというのがいちばんの理由だろうが、日本人の季節感の変化あるいは衰退ということも、その背後にあるように思われる。
ほととぎすは「杜鵑」「時鳥」「子規」「郭公」「不如帰」「杜魂」「蜀魂」などと書かれるほか、あやめ鳥、いもせ鳥、うない鳥、さなえ鳥、しでの田おさ、たちばな鳥、たま迎え鳥、夕かげ鳥などなどたいへん多くの異名がある。それだけ日本人と多面的な付き合いをしてきた複雑な存在だということを、このことはものがたっている。
ほととぎすといえば、まずその鳴き声である。「テッペンカケタカ」「ホンゾンカケタカ」「特許許可局」「あちゃとてた(あちらへ飛んで行った)」などとと聞こえるとされる鳴き声は、かなり忙しげで「帛(はく)を裂くが如し」と言われている。その間にピチピチという地鳴きをはさむが、雌の声はこの地鳴きだけである。夜間に鳴き渡ることも多く、その場合は短くキョッ、キョッと鳴きながら飛びすぎるので、気がつかない人も多いようだ。初音、初声ということばで、その鳴き声を待たれるのは鶯とほととぎすだけ。ともに春と夏の到来を告げる鳥として、その初音を今か今かと昔の日本人は待ったわけである。渡り鳥であるほととぎすが渡来する5月初めはちょうど田植え時。そのため田植えを促す勧農の鳥とされた。
「いくばくの田を作ればか時鳥しでの田長(たをさ)を朝な朝な鳴く」(藤原敏行『古今集』)という歌は、田植えの監督者である長老の田長に、田植えを早くするようにと、ほととぎすが呼びたてていくという意味である。「しで」はよくわからない。「賎(しず)」の転訛とも、山の名とも言われている。「しでの田おさ」はほととぎすの異名にもなるが、問題はこの「しで」が同音の「死出」のほうに連想が働き、暗いイメージが定着していくことだ。ひとつには夜にも鳴く鳥、姿も見せずに鳴く鳥というところから、冥土に通う鳥とされていた点。もうひとつには「杜魂」「蜀魂」という名の由来になった中国の故事のイメージである。蜀の望帝は、退位後、復位しようとしたが果たせず、死してほととぎすと化し、春月の間に昼夜分かたず悲しみ鳴いたという。これらのことも重なって、ほととぎすの一面でもある暗い陰鬱なイメージができていったと思われる。鳴き声をまねると厠に血を吐くなどの凶事があるとか、床に臥して初音を聞くと、その年は病気になるとかのいろいろな不吉な言い伝えがある。
子規一二の橋の夜明かな 其角
うす墨を流した空や時鳥 一茶
ほととぎすすでに遺児めく二人子よ 石田波郷
2001-06-18 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



