季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
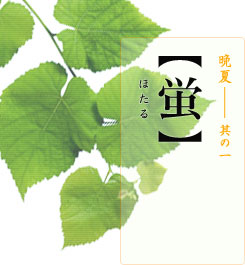
自然環境の変化、特に河川の改修や汚染、農薬散布、餌になるカタツムリや貝の減少で、すっかり数は減ったとはいえ、蛍は日本の夏にはなくてはならない風物詩のひとつである。欧米では日本のように蛍をめでる風習はなく、単に"光るウジ"と呼ばれる気持ち悪いだけの存在のようだ。
近年は農薬規制や環境保護の影響で、多少、回復傾向にあるようで、人工増殖の試みも各地でさかんだ。東京都内でも新たに再生された蛍の里が3、40ヵ所もある。しかしむかしながらの自然状態で見ることのできる蛍はごくごく少なく、多摩丘陵からのわき水などでほそぼそと生きているだけである。
蛍は広く世界に分布し、およそ2000種が知られている。日本にはそのうち40種がいる。一般に蛍は光るものと思われているが、光らない種も多く、日本にいるもので光るのは10種ほどである。その光はほとんど熱を伴わない、いわゆる冷光といわれるもので、その機能は主に恋愛のシグナルで、まれには威嚇の場合もある。その光り方、交信のパターンは複雑で、種ごと、地域ごとの発光パターンをもつ。日本の代表的な種であるゲンジボタルでは、東日本のものは4秒間隔、西日本のものは2秒間隔で点滅するという。そして雄が2回発光して、雌が応答する種がいれば、3回の発光に雌が応答するものもいる。アメリカには、雌が他の種と似た光を出して雄をおびき出し、食べてしまうという種までいるそうである。
その光が恋愛のシグナルであるせいか、平安のむかしから歌や物語の恋愛の場に蛍はしばしば登場する。袖の袂にたくさんの蛍を包み、恋人の前でそれを放つ、その顔を照らし見るという場面が「伊勢物語」「宇津保物語」「源氏物語」などに登場する。また「もの思へば沢の蛍もわが身よりあくがれ出づる魂かとぞ見る」(和泉式部)や「明けたてば蝉のをりはへ泣きくらし夜は蛍の燃えこそわたれ」(よみ人しらず)のように、蛍を身体から遊離した魂に見立てたり、燃える恋の思いに喩えたりして和歌に歌われることも多い。
非業の死を遂げた人の怨霊が蛍に化したという伝説も多い。陰暦5月26日は宇治川の戦いに敗れた源頼政の命日だが、彼の怨霊が蛍となって弔い合戦を挑むというのが「蛍合戦」の伝説である。山梨県ではお盆近くなると、「蛍提灯」というものが売られる。この中には蝋燭(ろうそく)ではなく、蛍を入れ、その光りをたよりにお墓参りをするのだという。先祖の御霊が蛍と化して、子孫に会いに来たと言い伝えている。お墓参りが終われば、蛍を放し、あの世に帰っていただくわけである。
音もせで思ひにもゆる蛍こそ
鳴く虫よりもあはれなりけれ 源重之
てのひらのくぼみにかこふ草蛍
移さんとしてひかりをこぼす 高嶋健一
移す手に光る蛍や指のまた 炭 太祇
さびしさや一尺消えてゆく蛍 立花北枝
大蛍ゆらりゆらりと通りけり 小林一茶
馬独り忽と戻りぬ飛ぶ蛍 河東碧梧桐
人殺す吾かも知らず飛ぶ蛍 前田普羅
蛍火や疾風のごとき母の脈 石田波郷
蛍籠昏ければ揺り炎えたたす 橋本多佳子
ゆるやかに着てひとと逢ふほたるの夜 桂信子
子の寝顔這う蛍火よ食へざる詩 佐藤鬼房
じゃんけんに負けて蛍に生まれたの 池田澄子
2002-07-08 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



