季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
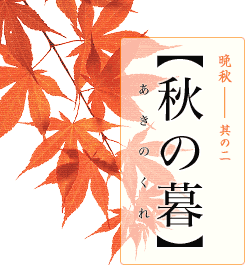
春は桜、秋の深まりとともに、日の暮れるのもどんどん早くなっていく。東京に例をとると、一年中で最も日の永い夏至では、日没の時刻が最も遅く午後七時。それが秋分(九月二十二、三日ころ)には午後五時四十分である。わずか九十日の間に一時間二十分も早くなる。 また日没の時刻が早くなるばかりでなく、日が没してから暗くなるまでの時間も短くなる。すとんと日の暮れる感じ。まさに「秋の日のつるべ落とし」である。これは日が地平線下に没しても、なお地上に明るさが残る薄明(トワイライト)の現象が少ないためである。大気中に水蒸気や塵が多いと、それに太陽光線が散乱され、日没後も明るさが残るわけである。秋は春のように黄砂もなく、地表も冷えて湿っているので、空気の対流現象がさかんでなく、ほこりも立ちにくい。また大陸から乾燥した高気圧がやってくるので、水蒸気も少ない。そんなわけで薄明の時間が短くなるのである。
「百方に借あるごとし秋の暮」(石塚友二)という俳句がいうように、気になっている借金の返済日も秋の日のように、どんどん短くなって迫ってくるような気がするのが秋の暮。前借のさらに前借をする人もいるかもしれない。「前借のまた前借や秋の暮」(加藤郁乎)。 秋はなにかと行事も多く気ぜわしく、時間が駆け足で去っていくような気がする。人の世の淋しさ、あわれさをしみじみ感じさせる季語の代表格が「秋の暮」である。
「秋は夕暮、夕日のさして山の端いと近うなりたるに、烏の寝所へ行くとて、三つ四つ二つ三つなど、飛び急ぐさへあはれなり」。ご存知『枕草子』第一段だが、この「夕暮」が「秋の暮」の前身である。和歌における七音の「秋の夕暮」が、俳句の五音に短縮されて「秋の暮」となったわけである。和歌にも「秋の暮」は使われているが、その数は極端に少なく、しかも暮秋つまり秋という季節の暮の意味で用いられている。
「秋の夕暮」ではなんといっても『新古今集』の「三夕(さんせき)」の歌が有名である。
さびしさはその色としもなかりけりまき立つ山の秋の夕暮(寂蓮)
心なき身にもあはれはしられけり鴫立つ沢の秋の夕暮(西行)
見わたせば花ももみぢもなかりけり浦の苫屋の秋の夕ぐれ(定家)
「秋の暮」はこれらの歌が固定した意味と語感を引継ぎ、高浜虚子なども秋の夕暮の意味に限定しているのだが、俳句では早くから暮秋の意味でも用いられてきた。そこには評論家の仁平勝さんがその名もずばり『秋の暮』(沖積舎)で述べているように、混同という問題には収まらない俳句が成立してきた本質的な問題が横たわっているのだが、それはできれば以下に紹介する俳句を鑑賞することで考えていただきたい。
此道や行く人なしに秋の暮 松尾芭蕉
立出てうしろ歩や秋のくれ 服部嵐雪
日のくれと子供が言ひて秋の暮 高浜虚子
秋の暮まだ目が見えて鴉飛ぶ 山口誓子
マンホールの底より声す秋の暮 加藤楸邨
秋の暮大魚の骨を海が引く 西東三鬼
あやまちはくりかへします秋の暮 三橋敏雄
2001-10-22 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



