季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
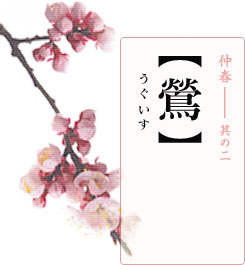
日本人に最も親しまれている春の鳥といえば鶯ということになるだろう。鳴禽(めいきん)つまり鳴く鳥としての人気も高い。
鶯の初鳴き日というのがあって、春の訪れを告げる指標になっている。鶯の別名を春告鳥、報春鳥というのもそんなところからきている。その現在の平均日は早いところで2月20日ころ、北海道では4月30日ころである。これはだいたい梅の開花している時期と重なり、「梅に鶯」(「鶯宿梅」)という取り合わせが古来、詩歌や絵画によく使われてきたのにも理由がある。しかしどうも鶯は梅をそれほど好きというわけではないらしい。初鳴きのころ咲いている花といえば梅ぐらいしかないというのが実情のようだ。鶯は梅につく蛾の幼虫を食べにくるので、別にほかの木でもかまわないわけである。げんに「梅に鶯」以前には「竹に鶯」という取り合わせの方が普通だった。
鶯色という色名があるが、実際にはあまり鮮やかな色ではなく、やや褐色を帯びた緑褐色である。雌雄同色なので、雄と雌は脚の太さで見分ける。かつてナイチンゲールのことを鶯と翻訳していたことがあったが、ナイチンゲールは鶫(つぐみ)に似た鶯よりやや大きな別の鳥。また中国の黄鳥を鶯と考えてきたが、これもまったく別の鳥である。
カラフトや北海道にも分布する鶯は海を渡る渡り鳥だが、本州以南では高いところと低いところを行き来する漂鳥である。暖かい時期は三千メートル級の高山にも棲むが、秋の終わりには人里近くに下りてきて冬を越す。この間は藪の間などでチャッチャッと人間が舌つづみを打つように鳴いている(地鳴き)。これは「笹鳴き」(「藪鶯」)といって冬の季語にもなっている。この「笹」は声が小さいという意味の「ささ」の当て字で、笹の中で鳴く意味ではない。
笹鳴きの鶯を「笹子」ともいうが、子供の鶯だけではないのになぜ「子」なのかというと、鳴き方、囀り方を習っていると解しての命名なのである。実際、鶯の鳴き声は季節を通して一定したものではなく、ホーホケキョと美しく整った囀りを聞かせてくれるのは三月に入ってからで、早春の囀りはまだどこかぎこちない。鶯の春の囀りは基本的には求愛行動だから、四月ごろ適当な配偶者を得れば、山へ帰り、巣を作り卵を生む。したがって人里で、その声を聞くことはなくなるが、実際は山に入ってからのほうが鳴き声は激しくなる。それは縄張り宣言としての囀りで、百瀬浩という研究者によると、最も激しく囀るのは五月で、早朝四時すぎから日暮れまで一日十六時間近くを縄張りのパトロールに費やし、その間、三千回ぐらいの囀りを繰り返すという。ケキョケキョケキョと続けざまに鳴く「鶯の谷渡り」として知られる鳴き方も、敵の注意を引きつけながら、抱卵、育雛している雌に危険を知らせるための行為であることがわかってきた。夏の鶯を「老鶯」とか「残鶯」と言ったりするが、老いても残っているわけでもないのである。
東京の鶯谷はその名のとおり鶯の名所だったことからの命名だが、どうして名所になったかというと、上野東叡宮にいた上野宮公弁法親王はだいの鶯好きだったが、どうも上野の森に集まってくる鶯の囀りが気に入らない。そこで京都から声のよい鶯を集めてきて放したところ、上野の鶯もその声をまねて、だんだんいい声になったということである。
鶯の身をさかさまに初音かな 宝井其角
鶯や下駄の歯につく小田の土 野沢凡兆
鶯のあちこちとするや小家がち 与謝野蕪村
うぐひすや水を打擲する子等に 西東三鬼
鶯や製茶会社のホツチキス 渡邊白泉
2002-03-11 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



