季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
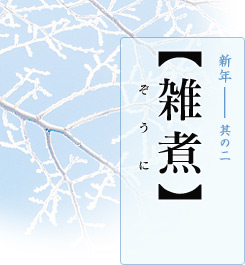
元日が日本の年中行事において、きわめて重要だったのは、その日にともかく年神を迎えることができなければ一年が始まらなかったからである。昔の日本人の時間感覚では、日没をもって一日が終わったので、大晦日の夜は「年の夜」といって、新しい年のはじまりだった。その夜、年神を迎えるための供え物が「節供(せちく)」。「節」とは神祭りの日のことで、元日が一年中で最も大切な節の日であるために、その日、年神に供える料理を「節供料理」というようになり、さらに縮まって「おせち」となったわけである。
現在のおせち料理は煮しめが主体だが、もとは節供料理と考えれば、広義には雑煮もこの中に含まれる。それに雑煮にはハレの食物の代表格である餅も入る。年の夜、年の神に供えた雑煮やおせちのお下がりをいただく直会(なおらい)が、元日を雑煮やおせちで祝う風習のはじまりである。正月に雑煮をいただくことや雑煮そのものをナオライ、オノーライ、オノーレ、ノーレ、ノーリャと称する言い方が地方にいくつも残っているのはその名残とみられる。
雑煮は文字どおり雑多に具を入れて煮こむもので、山海の百味に延命の力を感じたのだろう。餅のほかに青菜を加えることも多い。「名をあげる」に通じるからである。かつてはさまざまな特徴をもつ伝統料理が各地に残っていたわけだが、しだいに廃れ、日本料理の画一化がすすむ中で、雑煮は現在も各地の特色を最も残している料理だろう。焼いた切り餅を澄し汁にする関東風。丸餅を焼かずに味噌仕立てにする関西風。そのほかにも多様な雑煮が各地に残っている。
おせちは「三つ肴」といって、三つのものがちゃんと入っていなければならないとされた。関東では黒豆、数の子、五万米(ごまめ)、関西では黒豆、数の子、たたき牛蒡である。黒豆の黒は道教では魔除けの色として大切な色、また語路合せの好きな日本人の「まめ」に暮らせるようにという願いも込められている。また赤い甘露子(ちょろぎ)という唇形科の多年草の根を砂糖漬けにしたものが入っている。これは韓国語でミミズのことをいうチーロンイが訛ったもので、たくさんの節がある形が似ているのでその名になったもので、その形が米俵に似ているので黒豆の中に入れるのである。数の子は鰊の子で、鰊はカドといわれたので、カドの子が数の子になったのである。その数の多さが子孫繁栄の象徴となり、縁起物としておせちの中に入ったのである。五万米は、干した片口鰯を炒って、甘辛く煮たもの。「田作り」ともいわれるのは肥料にしたところ、五万俵も収穫できたからだという。たたき牛蒡がおせちに入る理由は、黒豆と同じくその黒い色のためだろう。
元日やされば野川の水の音 森川許六
しんしんとすまし雑煮や二人住 小林一茶
何の菜のつぼみなるらん雑煮汁 室生犀星
2002-01-15 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



