季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
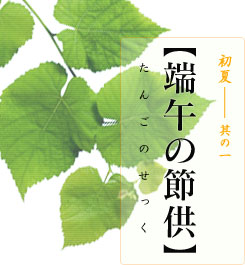
5月5日は「子供の日」、かつては「端午の節供」と呼ばれていた日である。この日が「子供の日」と定められたのは昭和23年7月。従来の皇室儀礼中心の祝祭日を国民中心のものにしようという趣旨で定められた祝日法で、この日は「こどもの人格を重んじてこどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日」とされた。
後段の「母に感謝する日」という部分は案外、知られていないが、5月の第2日曜日ではなくて、法律的にはこの日は日本の「母の日」でもある。推測だが、現在行なわれている母の日はアメリカ合衆国ウェストバージニア州のメソジスト教会から広まり、日本でも大正2年以来、一般に行なわれている。日本古来の母の日がないということから、戦後になって、このアメリカ由来の母の日に近い子供の日に吸収してしまったのではないだろうか。あるいはもともとこの日が日本の民間では、まさしく母(女)の日であったことを、この法律の制定者が知っていた可能性もある。
陰暦5月は皐月(さつき)と呼ばれるが、これは早苗月(さなえつき)の略といわれている。つまり田植えが始まる月である。農家にとって田植えは一年中で最も大切な仕事。そのため田の神を迎えるに際し、女性は巫女となり、軒に菖蒲をさし、菖蒲湯をたいて、身を清め、おこもりをしたのが5月5日だったのである。そのことを「女の家」「女の天下」、その前夜を「女の夜」といった。近松門左衛門の「女殺油地獄」に「三界に家ない女ながら、五月五日の一夜さを女の家といふぞかし」という一節がある。5月5日は子供の日というより、もとは母の日、女の日だったのである。
女の日だったものがどうして子供の日になったかというと、中国の習俗が渡来し、宮廷の行事に入り、さらに武家の世になり武士の行事化していくとともに男の子のためのものになっていったのである。端午の「端」は初めの意、「午」はうまで、端午は最初の午の日のことで、この日は中国では悪い日とされていたので、菖蒲や蓬を使って病気や災厄を祓う行事が古くから行なわれていた。これが宮廷行事の5月の節会でも行なわれるようになり、鎌倉時代になると、菖蒲が「勝負」や「尚武」につうじるというわけで、男の子中心の行事になっていく。3月3日が雛祭りとして女の子の節供になっていくとともに、5月5日は男の子の節供として定着していったのである。
端午は季節の変わり目の節日の名だから、季語として俳句に使われることは少なく、替わりに「鯉幟」「菖蒲葺く」「菖蒲引く」「武者人形」「粽」などが詠まれることが多い。
端午とて厳島の鷹の声すなり 水原秋櫻子
雨がちに端午ちかづく父子かな 石田波郷
風吹けば来るや隣の鯉幟 高浜虚子
鯉幟風に折れ又風に伸ぶ 山口誓子
子守唄いつかきこえず鯉幟 阿部みどり女
飾りたる兜の緒こそ太かりき 後藤夜半
出る時の傘に落ちたる菖蒲かな 正岡子規
2002-04-22 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



