季節のことば
日本の生活や文化に密着した季語の中から代表的なものを選び、その文化的な由来や文学の中での使われ方などを解説する、読んで楽しく役に立つ連載エッセイです。
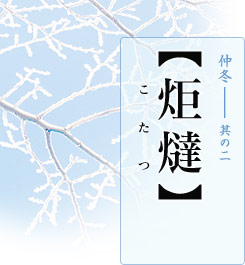
最近の暖房は石油ストーブやエアーコンディショナー、あるいは床暖房といったように多様化して、炬燵の出番はすっかり減ってしまった。しかし相変わらず使い続けている家庭も多く、案外、根強い人気を保っているようだ。
炬燵や火燵は宛字で、「火榻子(かとうし)」の唐宋音に由来するという説が有力である。「榻(しじ)」というのは牛車の乗り降りの際に使う踏み台のことで、その形が炬燵櫓(こたつやぐら)に似ていることからの命名だという(「子」は椅子などと同じく道具や物の名につく接尾語)。室町時代ころから、囲炉裏(いろり)に櫓をかけて暖をとるようになったのが炬燵のはじまりのようだ。囲炉裏に炭火を置く部分だけを開け、すのこを載せ、その上に櫓を載せた掘り炬燵(切り炬燵)、熱源(炭火)を床下に設け、床上に櫓を載せ、床面(畳)に座る腰掛け炬燵、櫓の底に板を張り、そこに火入(最近では電熱器)をつけて使う置き炬燵の三つの形式がある。
茶道の炉開きの日(陰暦十月の初旬の亥の日)に倣って、新暦十一月初旬の亥の日を炬燵開きの日とする習慣もあった。亥は十二支のいちばん最後で、陰陽道では最も陰の極まる動物とされているところから、火事を防ぐという意味もあったと思われる。
炬燵は冬の室内の暖房としては、最も日本人に親しまれてきたものだろう。またそれだけの理由もあった。隙間の多い日本家屋では室内全体を暖めるのは非常に効率が悪い。それに普通の暖房では、温まった空気は上昇するから、どうしても上半身にくらべ下半身が冷えがちである。そこにいくと炬燵は、足の方から暖めるから頭寒足熱で、体に触れる蒲団も心地よく温まっていて、たいへんに効率がいいのである。
日本人の生活にしっかり溶け込んできた炬燵なので、俳句などにもよく詠まれてきた。「当りもす春の炬燵をうとみつつ」「炬燵出ずもてなす心ありながら」という高浜虚子の二句などは、日本人にとっての炬燵のありかたをよく伝えている。歌舞伎にもよく登場する。「矢の根」という市川家十八番の演目で、曽我五郎が炬燵櫓に腰掛けるところや、「天網島時雨炬燵(てんのあみじましぐれのこたつ)」で紙屋治兵衛が炬燵にごろりと横になるところなどは名場面として知られてきた。最後に諺を二つ。「炬燵俳諧、夏将棋」は、冬は炬燵で俳諧を詠み、夏は露台で将棋をすること、季節に応じての趣味嗜好をいうが、嗜好の長続きしないことも喩えている。「炬燵で河豚汁」は、休養し大事をとりながら、一方で危険なことをする、つまり矛盾したことをする喩えである。
つくづくともののはじまる火燵哉 上島鬼貫
住みつかぬ旅の心や置炬燵 松尾芭蕉
腰ぬけの妻うつくしき炬燵かな 与謝蕪村
手枕の敷居へかかる炬燵かな 西沢魚日
ずぶ濡れの大名を見る巨燵かな 小林一茶
三人になつてさびしき炬燵かな 山本梅史
炬燵居に大往生の例もあり 富安風生
炬燵出づ恋を捨てたる如くなり 杉本禾人
2001-12-17 公開
目次
- 1. 風薫る
- 2. ほととぎす
- 3. 梅雨と五月雨
- 4. 祭
- 5. 花火
- 6. 蝉
- 7. 天の川と七夕
- 8. 渡り鳥
- 9. 月
- 10. 紅葉
- 11. 秋の暮
- 12. 木枯し
- 13. 大根
- 14. 雪
- 15. 炬燵(こたつ)
- 16. 元日(がんじつ)
- 17. 雑煮(ぞうに)
- 18. 猫の恋(ねこのこい)
- 19. 春一番
- 20. 雛祭り(ひなまつり)
- 21. 鶯(うぐいす)
- 22. 桜(さくら)
- 23. 蛙(かえる)
- 24. 端午の節供(たんごのせっく)
- 25. 若葉 青葉(わかば あおば)
- 26. 鮎(あゆ)
- 27. 田植え(たうえ)
- 28. 短夜(みじかよ
- 29. 蛍(ほたる)
- 30. 浴衣(ゆかた)
- 31. 踊り(おどり)
- 32. 蜻蛉(とんぼ)
- 33. 露(つゆ)
- 34. 菊(きく)
- 35. 柿(かき)
- 36. 薄(すすき)
- 37. 時雨(しぐれ)
- 38. 布団(ふとん)
- 39. 蜜柑
- 40. 年の暮
- 41. 歌留多
- 42. 大寒
- 43. ぶらんこ
- 44. けいちつ
- 45. 菜の花
- 46. 蝶(ちょう)



